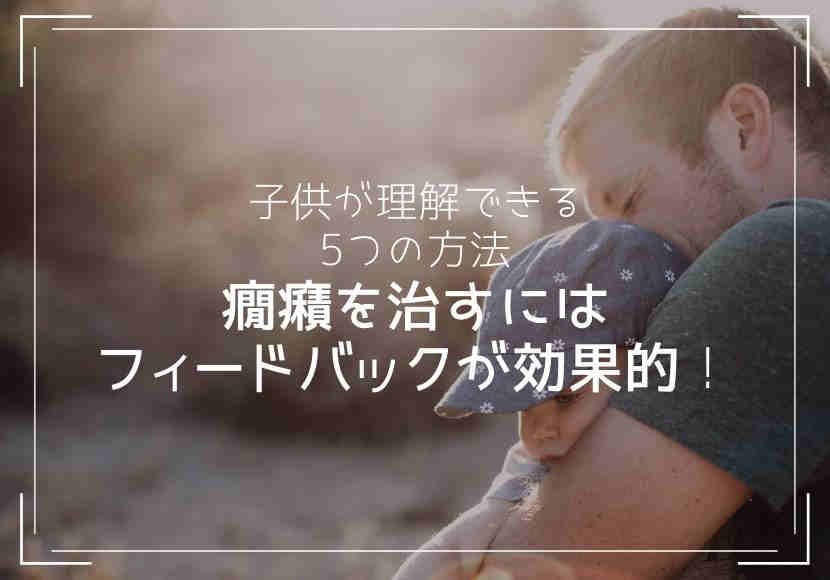子供の癇癪の対応は、思っている以上に大変です。
いつまでつづくんだろう?と不安に思っている方も多いでしょう。最終的には癇癪を起こさなくても感情を表現できるようになることが必須です。
そのために、癇癪が起きてしまったことを正しく理解することが必要でしょう。
今回は、地名の癇癪対応のために私がやっていたことをお話しします。
癇癪を直すなら感情を正しく表現することを教える

子供が自分の癇癪を受け入れ、癇癪という方法ではなく、別の方法で感情を表現する練習をしていきます。
ある程度、会話ができる幼児くらいからの対応方法になります。会話ができない1・2歳児でも、できればチャレンジしていきたいですね。
ここで注意点が1つ。
- それはあなたのせいじゃない
- 自業自得よ
- こうすればよかったのに
という類のことは一切言わない。これを忘れずに進めていきましょう。
癇癪を起した記憶があるかを確認する
癇癪を起こした後、ある程度落ち着いたら、癇癪をおこした時の話を聞いてみましょう。
まずは記憶があるかどうかを確認します。最初はあまりしつこく聞いても答えないかもしれないので、記憶があるかないかだけでOK。
癇癪を起してしまってどんな気持ちになったのか感想を聞く
次に癇癪になってしまってどんな気持ちだったのかを聞いてみましょう。泣き叫んでいるとき、どんな気持ちだった?というような感じで。
大抵は「よくわからない」と答えると思いますがわからなくても大丈夫。初めから答えが見つかるとは思っていません。
徐々に回数を重ねていくごとに、複雑だった気持ちの糸が、1つずつほぐれてくると思います。
どんな気持ちでもいい。どんなにネガティブな気持ちでもいい。気持ちを聞いたら「そっか」と答えればOKです。
やめた方がいい行動だと認識しているか確認
また癇癪になってしまってもいいかどうかを確認してみましょう。
次にまた癇癪を起してまで何を訴えたかったのか。
本当は癇癪で一番辛いのは本人だと思うのです。だからできれば癇癪は避けたいというのが本心だと思います。
原因と解決法を提示
癇癪の原因を認識しているか確認→解決の方向へ向かいましょう。
癇癪の原因はどこにあったのか、何が原因なのかをわかっているのか、どうすれば癇癪をおこさずに済むのかを一緒に考える、そして実行します。
何が原因で癇癪になってしまったのか、話せる場合は聞いてみましょう。話せない場合は親が推測するか、今はわからなくても大丈夫。
- なんとなくの原因
- 次にまた癇癪になりそうになったらどうするか
を話し合っておきましょう。
またこの時に、次回、癇癪を起してしまったときには、親はどうすればいいのかを確認しておきましょう。
- 部屋を出てほしい
- 手を握っていてほしい
- そばにいてほしい
という要望があれば、次回はその要望に応えてください。うまく話し合えない場合は、親が解決法を提示します。
例えば、
- 「買ってちょうだい、と言ってみようか」
- 「貸して、と言ってみようか」
- 「ブランコに乗るのは時間を決めようか」
など。こうしてくれたら良かったのに、ということを提示すればいいと思います。
癇癪はネガティブ要素なので、ネガティブ要素を重ねると地上にあがってこれなくなってしまいます。
マイナスにプラスを足していって、0地点より上に出ていけるように少しずつ経験を積みましょう。
次回の癇癪の時にはおそらくこのフィードバックは忘れているか思い出せないと思います。
でも回数を重ねることに、必ず癇癪とフィードバックが関連付いて、癇癪中に思い出すことが出てくるかもしれない。そうなったら先が見えてきますよ。
繰り返し癇癪を起こす→癇癪の予兆を感じたら声掛け
癇癪がおきる度に、親の対応→子供へのフィードバックを繰りします。
「このままだと癇癪がおきそうですが、気持ちの切り替えできますか?」このような感じで声を掛けてみましょう。
癇癪の予兆の前に声掛けをして事前に癇癪を防ぐことで、子供が「また癇癪をおこしてしまった」を防いでいきます。
始めはうまくいきませんが、癇癪を起してしまうとコミュニケーションが取れなくなってしまうので、できれば癇癪の予兆があるときに一旦声を掛けます。
このままだと癇癪になりそうだよ、フィードバックの時にこうしてみようって話したこと覚えてる?というように、癇癪とフィードバックの関連を付けて、正しい表現に結びつけていきましょう。
毎回うまくいかなくてもいいんです。10回の癇癪のうち、1回でもフィードバック対応ができればいい。その半分の0.5回分でもいい。思いだすだけでもいい。

私なんて声掛けたのに、追いつめてしまって結局癇癪突入したことあるし。
簡単じゃないけど、確実に減っていく方向へは向かえると思います。
その小さな積み重ねは必ず成果を生むと思っています。また、今は行動につながらなくても、知識として記憶に残ります。
目に見える結果だけが成果ではないので、焦らずに向き合っていきましょう。
子供の癇癪につきあう親のメンタル維持に要注意

最後に、子供の癇癪対応で一番心配なのは、親のメンタル維持です。
慣れたくないけど慣れてくれば、癇癪だけではなく、急なパニックにも対応できるようになりますし、対処をしていく、ということがわかってきます。
そこにたどり着くまでの間、意識的に冷静を保つための意識をどう持ち続けるのか。
よく子供に怒鳴ってしまった後に後悔して反省するパターンがありますが、後悔して反省してもまた怒鳴ったら同じこと。
育てにくい子の子育ては、要領よく立ち回らないと自分が崩れてしまうので気を付けた方がいい。本当に意識してメンタルを崩さないようにした方がいいです。
そうじゃないと家族総崩れになってしまう危険性があります。
だから癇癪対応を1回やったらアロママッサージをするとか、特別にとっておいた入浴剤でお風呂に入るとか、自分の都合だけで自分に出来る何かを用意しておくといいと思います。
振り返り|癇癪を直すのは地道なフィードバック

子育てになれてくると、いちいち細かく説明しなくても子供が理解しているような錯覚に陥ります。
特に、言葉が流暢に話せて、語彙もたくさん知っていて、よく喋るタイプの子供だと、親子の「あ・うん」の呼吸で理解できているような勘違いもおきます。
大人でも自分の感情をうまく相手に伝えるのはいろいろと複雑ですよね。子供ならなおさらでしょう。
フィードバックは、共通認識を確認できるので、多少面倒でも本気で子供と関わった方がいいと思います。
地道なフィードバックで自己認識をすることは、癇癪に限らず必要なことです。自分をよく知ることから始めていきましょう。
いずれ、表現のバリエーションが増え、語彙力があがれば、子供は癇癪を起こす必要がなくなります。
その時がくるまで、人として正しい出力方法を1つずつ教えていきましょう。