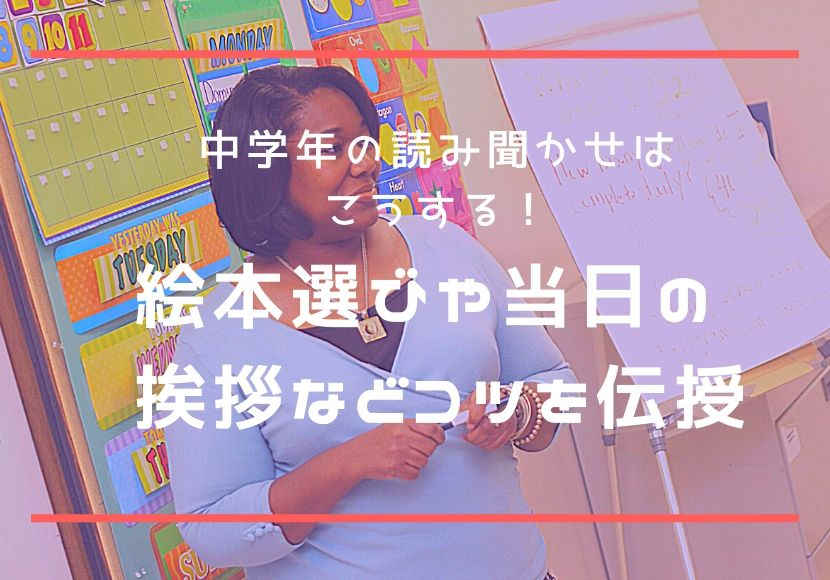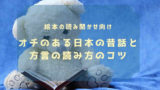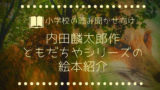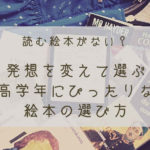小学校で読み聞かせの担当になった方へ、中学年向きの絵本選びや読み方のコツをお話しします。
一般的な読み聞かせの固定観念は忘れ、ある程度自由に読んだ方が読み手も聞き手である子供も楽しいものです。
具体的な当日の流れとして挨拶なども紹介していますので、担当に決まった方はぜひ参考にしてみてくださいね。
テーマを持つと絵本選びがラク!中学年の読み聞かせに合う選び方

絵本選びに悩む理由って、あまりにも多くのジャンルの絵本があるからだと思います。昔話しかなければそれしか読まないもの。悩みませんよね。
たくさんの絵本があるということ。だから何を読んだらいいのかわからないということが起きてしまいます。
それなら、読み聞かせをやるにあたって、自分は何か子供に伝えたいことはあるのかな?と考えてみましょう。
ジャンルはたくさんありますから、自分の気持ち優先で考えて大丈夫。必ずヒットする絵本があります。
読み聞かせ当日までの工程
- 読み聞かせの時間構成を決める
- 絵本選び
- 挨拶などの確認
- 読みの練習
- リハーサル
- 読み聞かせ当日
このような流れで論理的に決めていくと、当日までの時間がなくてもスムーズに読み聞かせができますよ。
読み聞かせの時間構成を決める
学校から割り振られている読み聞かせの時間は何分ですか?
朝の読み聞かせが大半だと思いますので、通常10分~15分でしょう。多くても20分くらいだと思われます。
この時間内に読む絵本の時間構成をなんとなく決めておきます。実際は、絵本を選びながら、話の長さと調整するので、この段階ではなんとなくでOK。
- 1冊読もう
- 2冊読もう
- 詩を入れよう
- ママ友と2人で読もう
などの大枠を決めておきます。
ここが変わると、その後の作業全部がやり直しになりますので、サブ候補も考えつつ大枠を決めましょう。
読み聞かせでやりたいことを決める(テーマを持つ)
中学年の読み聞かせをするにあたり、何をやりたいのか、テーマを決めておきましょう。
具体的には、
- テーマ:伝えたいことは何か
- チャレンジ:読み聞かせでやってみたいことはないか
の2点です。
テーマを持たずに読みたい絵本を読む
ただ、自分が面白いと思った絵本、子供の頃に読んで思い出に残っている絵本、口コミで人気のある絵本、家にある絵本、そんな絵本を普通に読む。
普通というのは、あなたが家で自分の子供に読み聞かせるなら、こうやって読むなという読み方のこと。一般的な普通ではなく(極意になってしまうから)あなたにとっての普通。
一番簡単で、明日にでも読み聞かせに行けますね。
伝えたいテーマを絞って読む
私が絵本を選ぶ基準にしているテーマをのせておきます。絵本を決められない場合は、テーマを絞るとかなりラクになりますよ。
2年生・・・地球
3年生・・・自分や他人などの人
4年生・・・命
5年生・・・共存共栄
6年生・・・古典、差別、自然破壊、学術、文学、将来につながる内容
※むかしばなしは学年に関係なく読めるものだと思うので選んでいません。
こんな風にテーマがあると、その中から自分の思いにヒットする絵本を探せばよいのでとてもラクです。
探すのはネットで「テーマ+絵本」と入力すればあっという間に絵本のタイトル候補が出てきますよ。
絵本選びに迷ったら絵本ナビを使う
絵本選びも、絵本探しも、まずは絵本ナビを使っています。
無料登録をすれば、以下のメリットがあります。
- 絵本の試し読みができる
- 探したい絵本が細かいカテゴリごとに分かれている
私は、探したい絵本のカテゴリ、テーマなどでタグを絞り、試し読みをしています。全部が読めるわけではありませんが、読めるものだけでもかなり参考になります。
年齢ごとのタグもあるので、選べなかったら年齢で区切ってその中から口コミの評価が高い絵本を選べば間違いなし、といった感じですね。
読み聞かせ担当者の強い味方だと言えます。フルで活用しましょう。
山場のある絵本・起承転結がはっきりしている絵本が読みやすい
いわゆる「オチ」がある話ってことですね。最初から最後まで同じトーンが繰り返される絵本もありますし、主人公の思いだけで終わってしまう話もあります。
1人で読む、親が子に読んであげるなら、そんな世界もステキなのですが、30人近くいる子供の前で読むのであれば、何かしらの山場があった方が圧倒的に読みやすいです。
「チャンチャン」とか、「めでたしめでたし」というような、ちょっとスッキリしたり、納得がいったりした方が、読み聞かせてもらった感がでるんじゃないかという私なりの考えです。
ですので、
- スピード感いっぱいの速さで読む・・・掛け合いのセリフ、戦う、追いかけられる、感動的な場面の前など
- ゆっくりと言葉を伝えるように読む・・・解決する、はなしの始め、新たな展開になったときなど
ということを組み合わせて1つのおはなしを読んでいます。
ということは、絵本が決まったらある程度練習して、どこが山場なのか、どんな背景なのか、登場人物はどんな気持ちなのかなど、国語の授業さながらに予習した方がいいということですね。
山場のある絵本選びに迷ったら「ともだちやシリーズ」がおすすめ
山場のあるおはなしなんてわからない、という方は、「ともだちや」シリーズを読みましょう。
ほぼ山場がありますし、感動もあるので読み聞かせで困る事はないです。
2冊以上読む場合は違うテーマから選ぶ
- 昔話+物語
- 科学絵本+物語
- 絵本+紙芝居
一例ですが、違うテーマの絵本にすると子供が飽きません。
- あとがきで絵本の内容の補足を抜粋して読んで理解を深める
- 絵本の内容にでてくる言葉を実際の絵や写真で確認
補足説明も中学年の子供には効果的です。

絵や写真を使う場合は、著作権に気を付けましょう。
読む練習と読み聞かせ当日の流れ
読み聞かせの時間は長くても20分くらいでしょう。短いと10分ですし、朝の時間なら15分くらい。全てを時間内に終わらせる練習をしましょう。
- あいさつ(○○の母です。読み聞かせにきました)
- 1冊目の絵本は○○です→読む→○○というおはなしでした。
- 2冊目の絵本は○○です→読む→○○というおはなしでした。
- これで今日の読み聞かせをおわります。ありがとうございました。
段取りはこの4パターンでいけるでしょう。
本が1冊なら1冊だけ、複数ある場合はタイトル紹介→読む→読んだタイトルを繰り返せば良いだけです。
時間内で読めるように何度も練習
あとは実践のみ。回数を重ねるごとにコツがわかってきて、自分流ができあがりますよ。
読み聞かせの基本的な読み方としては、
です。
横向きで絵本を読むのはかなり読みづらいので、何回か練習した方がいいと思います。読み手が何回も詰まって読むと、話自体がわからなくなってしまうので。
時間内に終わらせるコツはこちら。
【参考】一般的な読み聞かせの方法
- ゆっくりと聞きやすい声で読む
- 抑揚や感情をつけずに淡々と読む
- 読み手の固定観念を押し付けない
- 読み聞かせは絵本との出会いの場であること理解する
こちらでやってみようという方は、この極意を胸に読み聞かせの使命を全うしましょう。
一般的な読み手の極意には何か納得がいかないぞ、という方は花緒流を参考にしてみてください。その後、自分流ができていくと思います。
読み方のスピードについてはこちらを参考にしてください。
一般論から外れた読み聞かせ方法をやっている理由
ちょっと話はそれますが、私がなぜ、一般論から外れた方法で読み聞かせをしているのか、その理由おはなししましょう。
発達障害の長男が飽きないようにに自由な読み方を実験
- 子供は絵本を読むものだ
- 1人でも読めるものだ
そんな固定観念に私が縛られていた頃、長男が自分で絵本を読み始めるであろう年頃になるまで、いろんな絵本を読んであげたい。と、図書館で借りた本を毎日読んでいました。
ADHDだし普通に読んでも飽きてしまう長男でしたので、
- 飽きないように役になりきる
- 効果音をつける(何かを叩く、音の鳴るおもちゃを鳴らす)
- 早口で読む
- ゆっくり読む
とにかく単調にならないように読み続けた結果、長男は自分で絵本や物語を読むことはできませんが、本の世界、絵本の世界、漫画の世界、活字を読むということ自体は苦手意識は持ちませんでした。
苦手なんじゃなかったの?と思うくらい、読みたい気持ちが強く、結局頼まれて私が読むうちに、今では1時間クラスの本を読んであげることもあります。
夏休みの宿題に必ずと言っていいほどある読書、そして読書感想文。6年生の頃は「250ページ以上のものがたり」が宿題でした。
一般的な読み方ではうまく想像できない子供もいるという現実
学習障害を含めた発達障害の子供のように、脳回路や脳機能に特性がある子供が、クラスの中には何人かいるですよね。
子供だからみんながみんな、絵本が読めるということではなく、子供だから想像できるとは限らない。
だから刺激して鍛えるのでは?言われてしまいますが、普通の読み方ではその神経がうまくつながらない子供だっているわけです。
どんな脳の特性にも伝わる読み方をした結果
文字や文章から、映像として想像することが難しい長男。
ゆっくりとした口調で淡々と読み聞かせても、初めての言葉の意味や表現はとても伝わりにくく、話の内容を理解しづらくなってしまうのです。
そんな思いがあって、私は自分で絵本を読む場合、一般的な読み聞かせの固定観念は忘れ、自分の頭の中で映像化され、面白くなっている部分がきちんと子供達に伝わるような読み方をしていいます。
そのおかげなのかはわかりませんが、長男は、学習障害でも本が嫌いではありません。
振り返り|読み聞かせのテーマから選ぶと中学年にピッタリの絵本が選べる
小学校での読み聞かせをやるとなると、いろんな不安が頭をよぎるでしょう。
- おもしろいと思ってもらえるのかな
- ちゃんと読めるかな
- 何を読んだらいいのかな
- 嫌がられたりしないかな
- 緊張しないかな
大丈夫です。
何がおきても、読み聞かせは時間がたてば終わります。
あれこれ心配していても、子供の反応は当日にならないとわかりませんし、反応を気にするために読み聞かせをするわけではありませんよね。
自分で「こうだ!」と思う絵本を好きなように読んできてください。