突然ですが、「育てにくい子供」について徹底的に考えていこうと思い立ちまして、「育てにくい子供」についていろいろな角度から考えてみました。
こんにちは!小2あたりまで長男のことをかわいいと思えなかった花緒です。
長男の子育てが大変すぎて、なんでだろう?なんでこんなに大変なんだろう?とずっと疑問でした。
今回は、そんな子育てが大変すぎて悩んでいる方へ、なんで育てにくいと感じてしまうのか、ということについてお話ししていきます。
子供が育てにくいと感じている方の参考になればうれしいです。

科学的根拠は全くない、私の考えです。ご了承ください。
育てにくい子供とは?具体的にどういう子供のこと?

「育てにくい子供」って一体、何なのでしょう?
私は、長男のことを育てにくい子供だと思っていましたし、育児が大変すぎて、子供をかわいく思えない自分をおかしいと思っていましたし、母親失格だと思っていました。
精神的にもかなり参っていて、心療内科で落ち着くような薬をもらって飲んだこともありました。
「育てにくい」とは子供の問題ではなく親が感じるものなのではないか?
子供 にしてみれば、「育てにくい」なんて言われたら傷ついてしまうかもしれませんが、私は「育てにくい子供 」「育てやすい子供 」は確実にいると思っています。
「育てにくさ」は子供をこと(対処法含め)を知らないことが原因かもしれない
小6になった長男の子育てを「育てにくい」と感じているかというと、全く感じていません。
そうかと言って「育てやすい子供 」でもありませんが、今は気にならなくなりました。理由としては、
- 今は長男の特性も対処法もわかるようになった
- どうすればいいのかわからなくても大丈夫だったという経験を積んだ
- 育てやすいか育てにくいかが問題ではなくなった
ふと、長男が2・3歳の頃を思い出すと、あまりにも大変だった育児に振り回されていた自分が思い出され、今ならアドバイスできるのに、今ならこんな対処で乗り切れるのに、と思いつくんですよね。
例えば今、タイムマシンで長男2・3歳の頃に戻って、その頃の私と交代できたら、たぶん「育てにくい」とは感じていないと思います。
ということは、「育てにくい」=知らない(子供のことを)、という図式ができ上がるのではないかと思ったのです。
「育てにくい子供=発達障害の子供」そういうことではないと思う理由
ネットで情報を調べていると、「育てにくい」と「発達障害」という言葉はまるでセットになっているかのように一緒に表示されます。また、「育てにくい子供」は「発達障害かも?」というタイトルも表示されますよね。
正直言って、「育てにくい子供」は発達障害やHSCを含め、私は、何かあるとは思っています。だた「育てやすい子供」にもHSCを含めた何かがあると思っています。
要するにどっちも当てはまるわけで、発達障害だから育てにくいわけではなく、育てにくいから発達障害でもないと思っています。
育てやすさは親と子供の相性の問題ではないかという仮説
親や関わる大人との相性も関係あるでしょうし、親の特性や気質も大きく影響してくるでしょうね。同じ子どもでも、神経質な親と真逆な親であれば、育てにくいと感じるかどうかの差が出るのは当然のことだと思います。
子どもに対する親の理想像が「育てにくい子供」を作り上げているのではないかという仮説
これって、よく考えてみたらある種の理想像なんじゃないかと思い始めました。
誰しも、妊娠・出産を経て、無事に赤ちゃんが生まれたら、大変かもしれないけどこんなことをしてみたいな、あんなことを子どもにやってあげたいな。という理想を持ちますよね。
【親が想定している子供との生活案】
- お風呂担当になって、子供とたくさん遊ぶパパになりたい
- 子供と一緒にお菓子作りをしたり、仲良しのママ友を作って公園デビューしたい
- ベビーカーに乗せて、ショッピングやお散歩を楽しみたい
そんな理想のパパママ像はいつも笑顔で、子どもを注意したらちょっと泣いちゃうけど、すぐに謝って抱きついてくるような、そんな理想の子どもを想像したりしますよね。
【育てにくいと感じてしまう子供の事例】
- 子供が自分と手をつながない
- 出かけなきゃいけないのに着替えもしないでおもちゃで遊び続けている
- 一度泣いたら何をしても泣き止まない
- 一生懸命作った離乳食を食べない
- 夜になっても寝ない
実際に子育てをしてみると、自分が想定していた子供との生活とかなり違うことが起きた時、想定外の子供の行動に理解が追い付かなくなってしまうのでしょう。
だって、自分の予測では、子どもは自分の理想のように動くと予測していたから。想定外が起きてしまったのです。
自分が理想のパパママ像になれないのは、理想としていた子供像とは違う子供だから。こんなはずじゃなかったのに、なんでうちの子はこんなに「育てにくいんだろう」と思ってしまう。
育てにくい子供は、こんな風に生まれているのではないでしょうか。
子育ての固定観念と親の理想が「育てにくい子供」を生み出し親を苦しめる
人間、誰しも理想を持っていると思います。自分への理想は自分のことなので何とかコントロールできるでしょう。
しかし、自分とは別人格である子供に、自分の理想をスキャンするように見てしまうことで、子供には「育てやすさ」という親の判定が付くようになります。
- 親の理想と比べて本を読まない
- 親の理想と比べて手先が不器用
- 親の理想と比べて運動能力なし
育てにくい子供ができあがる過程を解説
【育てにくい子供の事例】
- 本を読む子になるように絵本を借りに行こうと図書館に連れて行ったら、子どもが大きな声で楽しそうに走り回りだして、何度注意してもやめなくて、居づらくなって図書館を出た。
- 理想は図書館で本を借りて、本を読む子になるような教育をしたいのに、現実は本を借りるさえできなかった。
- ならばアマゾンで絵本を数冊買って、家で読み聞かせをしてみたら、子どもが次々とページをめくっていくので、全く読み聞かせができなかった。
- 理想は絵本に興味を持っておとなしく聞いてほしかったのに、現実はページをめくって終わってしまった。
【親の理想】
- 理想:本を読む子供になってほしい(勉強や将来の進学に関わるから)
- 理想を叶えるための目的:親が子供に絵本を読み聞かせをする
- 子供に読み聞かせをするための行動:図書館で絵本を借りる、アマゾンで絵本を買う
- 目的を叶えるために子供に望まれる行動:図書館に同行(館内では静かに)、絵本の読み聞かせをだまって聞く
【育てにくい子供の行動】
- 行動:図書館で走り回る、絵本をペラペラめくる
- 心理:いつもとは違う場所が面白くて走り回る、ペラペラめくる紙の感覚が楽しい
事例を分析してまとめるとこのような感じになりますね。
- 親の理想通りに動く子供→育てやすい子供、お利口さん、いい子
- 親の理想通りに動かない子供→育てにくい子供、悪い子、ダメな子
要するに、親の理想通りに子供が動かないので、育てにくい子供だな、と思ってしまうということになります。
親の理想が叶えられないストレス×大人の生活環境要因で育てにくい子供が現れる
先程の事例は私の例ですが、親の理想が叶えられない例×日常生活でうまくいかない様々なストレス=理想とは違う現実、を過ごす事になり、1日でかなりのストレスが溜まってしまいます。
さらに、
- 溜まったストレスをうまく発散できない
- ワンオペ育児になっている
- 周りに子育ての大変さを理解してくれる人がいない
などの大人側の環境要因が重なって、「育てにくいかもしれない」と感じていた気持ちが「育てにくい子供」を現実のものとして作ってしまうのではないでしょうか?
育てにくい子供は親の理想が生みだしている感覚(妄想)ではないか?

どんなに育てにくいと感じていても、毎日子供と過ごしていくわけです。育てにくいと感じているのは自分。それなら、自分(親)の理想を持ってはいけないの?と思うかもしれませんが、そういうことではないのです。
育てにくい子供と生きる親にできる基本の考え方
育てにくい子供について私がたどりついた考えは、
ということ。だから子供を怒っても解決しないという結論に達しました。
育てにくいのは親が悪いの?「育てにくい」と思う自分の感情は否定しない
では、育てにくいと感じてしまう親が悪いということなのでしょうか?
私はそれも違うな、と思うのです。良い・悪いの問題ではない。
私達親が「育てにくい」と感じるのは、自分の感情です。感情は自分の過去の経験や知識やさまざまなことから生み出されてくるもの。
自分の感情は否定するものではないですね。だってそう思うのですから。我思う、故に我あり、ですから。自分も他人も「育てにくい」と感じてしまう親の感情を否定するものではありません。
育てにくい=自分の理想を子供に叶えさせようとしているサインだと考えてみる
育てにくいと思うのは、自分の理想の子供像ではないから。ここで「あれ?」と立ち止まってみましょう。
子供は、親の理想を叶えていくためのお人形ではありませんよね。私達親も、自分の親の願いを叶えるために、今、生きているわけではありません。
ということは、育てにくいな、と感じた時は、自分の理想を子供に叶えさせようとしていたんだな、ということに気づける自分からのサインだと思ってみましょう。
そうすると、親の理想を叶えさせるのではなく、目の前にいる子供を見る事ができるのではないでしょうか?
改めて育てにくい子供と向き合うための基本の対処法
気持ちを改めてみると、子供の行動や言動、様子を冷静に見て判断することができるようになる、思い込みや固定観念がない状態になると思います。
育てにくいと思っていた子供のそのままを知ることで育てにくさが変化する
育てにくい子供の対処法として私が常日頃から考えていることは、
早い話が子どもを観察して→実験と検証を繰り返し→試行錯誤をするということです。
まるで理科の実験みたいと思うかもしれませんが、困っているということは、解決したいということですからね。
まずは現状を把握するところから始めてみましょう。
さらに、自分が理想としていた子供像を書き出してみましょう。親としての自分の理想も一緒に書き出してみるといいと思います。
理想の子育てを叶えたいのは親であるという事実を受け入れる方法
理想と現実の差に落ち込む必要はありません。
理想は、あくまで今思いつく理想ですから、現実と違っていて当然です(理想と現実が一緒なら現実だから)。
- 理想を書き出す
- 現状を書き出す
- 叶えなくても死なない理想にチェックマークをつける
- チェック以外の理想と現実の差を埋めるプロセスを考える
- 叶えてみたい理想にチェックをつける
叶えてみたい理想のチェックは、一番最後にしてくださいね。そうじゃないと、叶えてみたいが叶えなければいけない理想に変わってしまうので。
理想はあくまで理想なので、チェックしてみると特別叶えなくても死なないな、と思いませんか?
それなら、今、子供に自分の理想を重ねてまで「育てにくい子供」を作りださなくても大丈夫だという結果になりますね。
理想の子供像を持っている親だからこそ気づける子供の生きづらさ
育てにくい子供だと思っていた子供が、自分の理想を重ねあわせていただけだとわかったとしても、いきなり自分の理想という色眼鏡を通さずに子供を見るのは難しいです。
長い期間をかけた意識や練習が必要です。そうやって、子育て経験を積んでいくのですから、今すぐできなくて良いのです。親だってはじめは誰でも初心者ですから。
子供が成長するように親として成長していけばいいですよね。
私達の子育ての理想は、社会を通して何代も受け継がれてきているものです。一般常識や固定概念と同じく、社会の人々と時代が作りだしてきたもの。
育てにくい子供は確かに親の理想像を重ねあわせた幻の姿ではありますが、親の理想像と違う子供というのは、少数派になり得る「何か」がある可能性もあります。
自分の気持ちや感情を言葉でうまく話せない子供ですから、その子特有の感覚の過敏さ、わからなさ、不器用さなどは見た目ではわかりません。
親の持つ理想像や社会の一般論が、子供の生きづらさに気づくきっかけになる場合もあるということを覚えておきましょう。
子育ての悩みや子供の発達が不安なら第三者に相談する
親が子供について「気になること」は相談先を探して、第三者の専門的な意見を聞き、必要なら検査をしてもいいと思います。
熱はないけど溶連菌っぽいな、みたいな感覚で病院に行くようなものです。
何でもなければそれでよし。親の勘がきっかけでHSCや発達障害に気づき、早めの配慮をすることで、子供と一緒に生きる人生がより前向きに変わっていけたらいいですよね。
振り返り|【衝撃!!】育てにくい子供と感じてしまう理由は自分にあった

結局、自分の思いが、育てにくい子どもを作ってしまっているの??と自分でも驚いたわけです。
もしかしたら私たちは、妊娠したその日から、自分の理想の赤ちゃん、理想の子どもを作り上げてしまっていて、目に見えるところしか見ていないのかもしれません。

私だけかもしれませんが。
とは言え、育てにくいと思うお子さんを育てている親にしてみたら、そんな定義はどうでも良く、「とにかく育てにくすぎてもう無理」と思っているかもしれないですよね。
子どもを知ることも観察することも何もかも、親にも気持ちの余裕がないと難しいと思います。理想論にしか聞こえない。今日、明日、使える対処法がないとやり切れない。
私を含め、たくさんの先輩ママたちが情報を発信していると思います。先輩ママたちも試行錯誤しながら今日まで生きてきました。
体験談から学べるもの、本や知識を参考にするなど、方法はたくさんあるでしょう。
大切なのは、人の情報を自分で理解した後、自分と子供に合うか合わないかを判断することです。私の考え方も方法も、私という親と子供の組み合わせから生まれているものです。
同じ方法がみんなにも合うとは限りません。だって、始めから「育てにくい」という少数派だからです。ただし、あなたとお子さんに合う方法は必ずあります。
残念ながら私がその方法を見つけることはできませんが、1つの体験を紹介し、参考にしてもらうことができます。ヒントのようなものや、ある種類の道しるべになることができます。
ちょっと先に行って、壁にぶつかってきます。そして乗り越えられるよう努力してみます。
育てにくい子供との生活は、はっきりいって「大変」なんて軽い言葉では語れません。
だからこそ、その要因となる考え方や物の見方を変えることで、少しでも育てにくさが減っていくきっかけになれるような情報を発信してみました。
自分の頭で考えるからこそ、本質が見えてくると思います。不安かもしれませんが、怖いかもしれませんが、自分と子供のそのままを見てみましょう。
その後、どうすればいいのかは、その後考えればいいですよ。




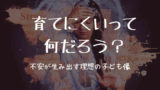





コメント