私達親は、どうして子供を怒ってしまうのでしょう?悪いことをしたから、危険なことをやろうとしていたから、勉強しないから、片づけないから。怒ってしまう理由はいろいろありますよね。
幼少期であれば、いい悪いの区別もついていませんし、知識も少ないため怒る機会が多くなりますが、成長したところで怒る機会はさほど減らないもの。一体、どうしてなのでしょう?
今回は、親が子供を怒る原因を根本から考え、解明しました。
毎日怒ってばかりで疲れてしまった、いくら怒っても子供はまったく変わらずに困っているという方の参考になればうれしいです。
親が子供を怒る理由とは?|子供を自分の思い通りにしたいから(理想の子供像)

私達親は、
- 子供が自分(親)の思い通りに動かない
- 親が子供に言ったことをすぐにやらない
- 親に見えるように子供が動かない
このようなことで怒ります。
自分の理想の子供像に近づけようと毎日必死です。
シャツが出ているとか、ズボンが後ろ前逆とか、忘れ物はないのかとか、集金袋を出していないとか、帰りの時間が過ぎているのに帰って来ないとか、下の子を泣かせたとか。
- 親の目に見えるところで勉強していれば=勉強していると判断
- 目に見えるところをで勉強していなければ=勉強していないと判断
こうやって考えてみると、親って結構勝手です。でも、別に怒る必要はないのかもしれないのに、なぜ怒ってしまうのでしょう?
先人や親と同じ失敗をさせてくないから|親の愛その1
これまで、人類はたくさんの失敗を重ねてきています。中には命を落とした人もいて、その経験は知識として本などを始め、データとして残っています。
私達は学校などでその辺りの先人の知恵を学び、命の危険があるものは対策を取れるようになっています。
先人が失敗しているのにもかかわらず、知識量や経験量が足りない子供は、また同じ失敗をしようとしているわけですね。
- それは先人の○○が経験して、うまくいかなかった方法だ
- 失敗したら命を落とした先人がいた
こんな感じで科学がいろんなデータをもとに、実験や検証を重ねて人間は現代まで生き延びているわけです。
親は子供に、危ないこと、過去に失敗した人がいる人(親含め)、自分も経験上うまくいかないことが予想されること、そんな事を子供に伝えたいだけなんです。
だから、こうした方がいいよ、ということを伝えたいだけ。
でも子供はそんな親の思いなんて知らないし、まだ経験していないことがたくさんあり過ぎて、親の意見はまだ取り入れられないのです(大人は経験からわかってしまっているが、子供はまだわかっていない)
だから親の言うことを聞かずに、自分のやり方を押し通そうとする。
これが、育てにくい子のきっかけでもあり、親が怒るきっかけでもあるのでしょう。
親は、そんな子供をなんとしても阻止したい。できればうまくいく方法で試してほしい。親心ってヤツなのですが、子供は気づかないでしょうね。
悲しい思い・挫折・苦労している姿を見たくないから|親の愛その2
先程の話と似ていますが、先人達の失敗に、同じ方法で挑もうとする子供の、悲しい思いや挫折、苦労して大変そうにしている姿を、親はできるだけ見たくありません。
自分のお腹から出てきた我が子の悲しみや苦労は、自分の身を切り裂かれているように感じる人もいるでしょう。
そんな自分(親)をストレス(子供が悲しみ苦労する姿を見ること)から守るために、子供を自分の思い通りに動かそうとし、その手段の1つとして怒るのではないでしょうか。
さらに子供には順風満帆な人生を歩んでほしいという願いから、できるだけ苦労しないように、大変な思いをしないように、できるだけ危ないことは避けてあげたいわけです。
転ばぬ先の杖、過干渉とも言えますが、一重に親の愛情でしょう。
でも子供はよくわからないので言うことを聞かず、親は思いをうまく伝えられず、結果衝突してしまうんですね。
怒らないと今の子供の状態が続くと思っているから|親の愛その3
子供が生まれるとよく聞く話ですが、親も周りの大人も含め、今○○ができるとその子の人生においてずっと続くと思ってしまう現象。
例えば、
- 1歳の子供がボールを投げたらすごい勢いで飛んでいった→野球選手になれるんじゃないか→野球チームに入れないと
- 1歳の子供がピアノのおもちゃをバシバシ楽しそうに叩いた→ピアニストになるくらい才能があるんじゃないか→リトミックに行かないと
- 1歳の子供がたまたま流れていたセサミストリートのテレビに反応して何かを喋ろうとしていた→バイリンガルとして世界で活躍するんじゃないか→英語を習わせないと
みたいなやつですね。
おじいさんおばあさんがこの手の話を良くしますし、現実的に育児にあまり関わっていないお父さんや親戚の人、近所のおばさん達が言うはなし。
育児に疲れ切っているお母さんがこの手の話を真に受けて、子供の才能を伸ばさないと、子供の興味関心を確認することなく習い事に通わせてしまいます。
子供の才能を幻想や妄想で先回りして空回りする育児疲れ
早期教育をさせて、子供ができない、他の子と同じ態度じゃない、うちの子だけ違う、なぜなんだ???なんでうちの子だけできなんだ???と子供を怒ってしまう。
ちょっと落ち着いて考えれば、それは誰かの幻想であり妄想だったわけですよ。
今、大人が目で見た子供の行動1つから、想像力を働かせて将来の仕事につなげたい。そして安心したいわけですね。この子は大丈夫だと思いたいのです。
なぜなら、大人は子供のよりも先に死にゆく身ですから。
かわいい孫や子供が、一人で生計を立てていけるという安心感があれば、安心して大人は死ねるわけです。そういう自己満足の1種類です。
結局、習い事などがうまくいけば問題はありませんが、ほぼこの手の話はいずれ親子のどちらかに支障がでてきてぶつかります。
親の空回りなので、子供にとっては甚だ迷惑な話なのですが、この親と大人の空回りで子供はだいぶ怒られているかもしれませんね。
親の妄想で子供にできないレッテル張りをする育児疲れ
逆の話も考えられます。
今、目の前にいる子供が片づけをしない場合、今この片づけないクセをなんとかしないと、この子は一生片づけられない子になってしまう。
女の子ならお嫁に行ったら恥ずかしい思いをさせてしまうのではないか、男の子なら会社の重要書類を失くしてしまうのではないか、だから今、片づけさせないと。
みたいな感じです。
これが、3歳とか4歳の子供に課せられてしまう課題であり、親の育児疲れの原因でもあると思っています。
親が希望するタイミングで子供が動かないと一生続くと思い込んでしまう育児疲れ
ちょっと冷静に考えてみると、片づけるにはカテゴリに分けられる知識が必要で、時間の把握や物の分別、効率よく片づけるには物事の効率と最適化を考えられるだけの情報量がベースになければいけません。
すでに子供から大人に成長してしまった私達は、過去の事は覚えていませんね。
自分が3・4歳だった時、今、親である自分が子供に課している片づけの方法ができていたのか、そう考えたところで覚えているはずがありません。
自分ができなかったかもしれないことを、結構な勢いで子供に求めてしまうことは、親のあるあるでしょう。
意外と自分の子供が何をどう理解していて、どういう片付けが向いているのかなんて、考えたこともないと思います。
- 親が片づけてほしいタイミング
- 親の頭で考えられる方法
- 親が最終ゴールとしている片づけ後の部屋にする
これができないと子供を怒る。それが私達親です。
できないのではなく、やらない理由があるのかもしれないし、やりにくい何かがあるのかもしれない。
やらなくてもいい環境だからやらないのかもしれない
さらに言えば、成長と共に必要であれば片づけるのではないでしょうか?いやいや、うちの子は一生やらないよ、と思うかもしれませんが、それは現時点での妄想ですよね。
可能性はあるかもしれませんが、ないかもしれません。そのくらい、子供の将来は不確定なものです。
何が何でも片づけなければ死んでしまうのであれば、きっと片づけるはずです。
お嫁に行ったら自分が片づけないと生活していけないし、会社に入ったら重要書類の扱いは自分でなんとかするでしょう。
やるかやらないかは子供次第|親の問題ではない
そこは親の責任とは少し違います。本人の問題ですよね。
3・4歳の子供から大人になるまでの間、子供は成長する中でいろんな体験をして経験を積んでいきます。3・4歳の状態で大人になるわけではないのです。
だから、今の状態がずっと続くとは限らないのですね。要は親がどう考えて子供を動かすのか、ではなく、子供がどう考えて、どう動くのか。
そこが解決しない限り、親がいくら子供を怒っても暖簾に腕押し、馬の耳に念仏。
親の怒りも言葉も右から左へ流れるだけになってしまいます。
子供を怒る前に親にできる3つのこと

要するに、子供への愛情の裏返しってヤツが子供を怒ってしまう正体なわけですね。
じゃあ、結局親はどうすればいいのか?親にできることは3つあるのではないかと考えてみました。
同じ轍を踏んでもらう覚悟をする|子供が納得(失敗や成功)するまで見守る
危険なことは怒ってでも止めていいと思いますので、その他のことに関しては、子供が失敗や成功の体験に納得するまで、同じ轍を踏んでもらうしかありませんね。
いいか悪いかは発達や子供の特性・気質などに合わせていただくとして、情報としての知識は前もって伝えておけるかもしれません。
しかし、実際に体験し、考えて改善して行動に移し経験を積んでいくのは子供自身です。ここを変わってあげることはできませんね。
結局、子育てに正解なんてないのでしょう。ならば、覚悟をして、親の見えているところでたくさん失敗や成功をして大人になってほしいと思います。
失敗しても戻れる場所になる|はなし相手になる
失敗した後やうまくいかないことが続くスランプなど、明らかに前進できていないことが出てきます。
そんな時、失敗しても何をしても、帰る場所があるというのは、とてもありがたいものです。親は、どんなに失敗しても、戻れる場所になりましょう。
たくさん話を聞いて、より安心できるような環境を整えてあげましょう。
傾聴するだけでOK|求められていないアドバイスは不要
子供の話は聞いてあげるだけでOKです。
「こうした方がよかったんじゃないの?」とか「それは○○ちゃんの判断が甘かったんじゃないの?」「それ意味なくない?」みたいなアドバイスは不要です。
2度と話そうという気にならなくなるので、「そうなんだ」「大変だね」「頑張ったね」的な感じでいいと思います。
アドバイスしたい時は子供に聞いてみる
前置きなしにアドバイスされると、そういうことを聞きたいんじゃなくてただ言いたかっただけ、ということもありますよね。
さらに子供は話しながら情報を整理して、自己理解をしていくことも考えられます。
できるだけアドバイス的なことはしない方が、子供のひらめきとか想像力とかが鍛えられたり、言葉や経験とのつながりが増えると思うのですが、もしアドバイスをしておいた方が良さそうだなと思った場合は、一言聞いてみるといいと思います。
「いいこと思いついたんだけど、聞きたい?」「1個アドバイスがあるけど教えた方がいい?」みたいな感じで聞いて、子供が受け入れてくれたら話せばいいし、いらないと言われたら次回に先送りしましょう。
子供のペースで情報処理をしてもらった方が、後々のためにもなると思いますので。
子供のレベルに合わせて通訳し根気強く教え続ける
できるなら、子供を怒るのではなく、子供のレベルに合わせて親が通訳できればいいわけですよね。
先人たちの失敗や知恵、親の失敗やうまくいった方法などを怒ることなく伝えたい。
もう怒りたくない親がいて、当然怒られたくない子供がいるわけですから、違う方法を試してみましょう。
方法は2つ。
- 目の前の子供のレベルを知る
- 子供のレベルに合わせて通訳する
親にできることはここまでなんじゃないかな、と思います。その後の事は子供が自分で判断し、やるかやらないかを決めればいいことでしょう。
さらに追加するとすれば、子供の発達を知っておくといいと思います。
発達障害やHSCなどの配慮するべき特性がある、なしにかかわらず、すべての子供の発達を知っておくことで、自分が子供に求めていることをそもそも理解できないかもしれない、ということがわかります。
脳のしくみや発達のパターンなどを知ること、さらに発達心理学や児童心理学のような本もサラッと読んでおくと怒る回数はかなり減ってくると思いますよ。
子供の発達のことがとてもよくわかる本があるので、1冊紹介しておきますね。
学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす|中山芳一
これからの時代は、テストの点数が良ければいい時代ではなくなり、点数では測れない非認知能力が大きく関わってくると言われています。
STEAM教育実現のために、日本を含めた世界の教育が変わり始めているんですね。
それに伴い、子育てにも変化が求められる時代になるような気がしています。AIの進歩と共に、すでに親である自分達の子供時代と同じ子育ては使えない。環境があまりにも違い過ぎるからです。
子供の発達を含めたこれからの時代の子育てには何が必要なのか、ということが書かれている本です。何よりも発達面の説明がわかりやすくて、1回読んだだけで「そうなのか」とすんなり理解できました。
文体がやわらかく、作者の考えなどの押しつけもなく、でもこういうことが必要なんじゃないのかなということを、作者の活動などから教えてくれます。
発達障害の子供に対する取り組みも触れていますので、発達障害の子育てに対する考え方の参考にもなる本です。割とすぐに読めてしまう字の大きさと量なので、機会があったら読んでみてください。
子供の見え方も大きく変わると思います。
振り返り|親が子供を怒るのは親の愛の裏返し~怒らなくても愛は伝わる~

親が子供を怒る理由は、子供に辛い思いをさせないようにちょっと先回りした親の愛情が原因だと私は考えました。
「親の心子知らず」とはよく言ったもので、本当に子供は親の心なんて全く関係なく成長しますよね。そして、大人になって、子供を産んで育て、初めて自分の親が言っていたことが身に染みてわかる。
そこまでこないと、親の思いはわからない。親子の仲が悪ければ、最悪永遠にわからないままになってしまうこともあるわけです。
別に親の思いを子にわかってほしいわけではないと思っているかもしれませんが、わかってほしいから怒るんじゃないかな、とも思うんです。
なら、伝えたい事は怒らずに別の方法にしてみましょう、というお話しでした。
子供の事を理解し、受け入れることができ、子供が安心して親と接することができれば、子供を親を理解する準備ができ、親の言葉はすんなりと入っていくかもしれませんね。

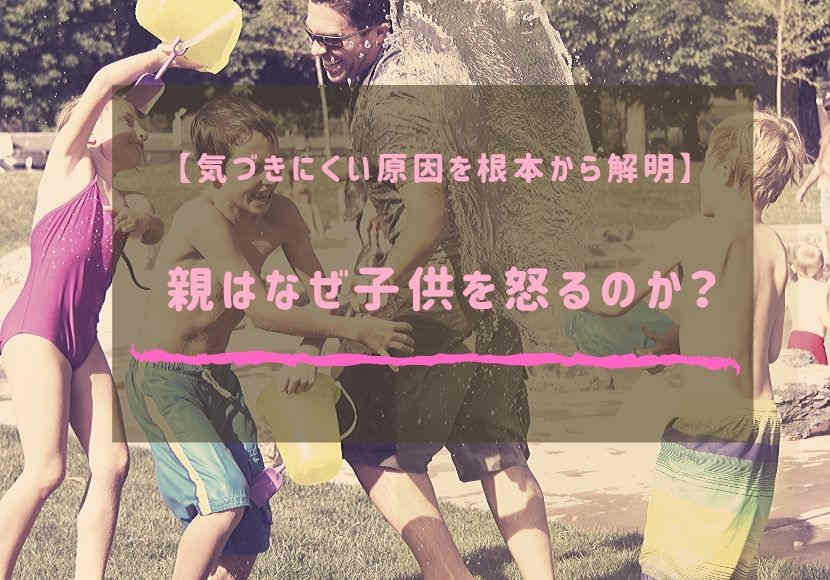


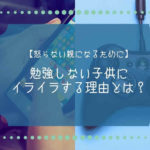
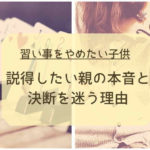
コメント