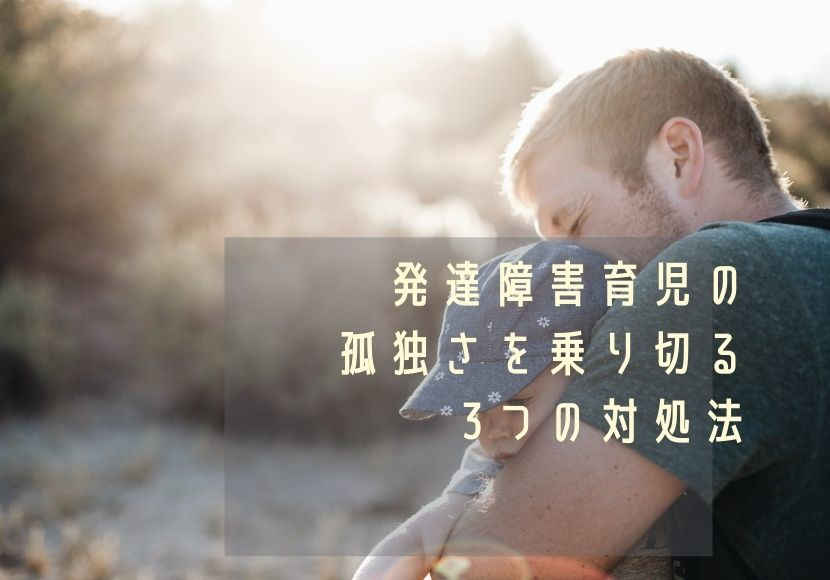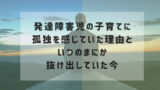発達障害の子供の育児は、ときにモーレツな孤独を感じ、辛くなってしまいます。そんなときは、とりあえずの対処をしてみるといいでしょう。
今回は、私が孤独感で辛すぎたときにやってきた対処法をお話していきます。合わせて、孤独感につぶされないよう、気を付けておいた方がいいことも載せておきますので、参考にしてくださいね。
発達障害育児の孤独さを感じつつできる3つの対処法

対処はあくまで現状を悪化させないための方法です。
孤独が辛すぎてもうダメだ→孤独を感じているだけだ、と、現状を認識できるようになったら、対処は終了。
その後は、対策などを考え、最終的には孤独を味方につけられるようにしていくためにも、まずは対処をやっていきます。
とにかく何でもいいのですべて紙に書き出す
今、感じている孤独感をすべて紙に書き出すことをおすすめします。
実際に、書き出してみるとわかるのですが、
- 書いた文字を目で見る
- 可視化されることで客観的に捉えられる
- 人ごとのように現状把握ができる
- なぜか解決策まで思いつく
頭の中だけで考えていると、何かモヤモヤしたまま、心が苦しくなったり、痛くなったりしてしまいがち。
書き出すことで、自分の外に出て、自分から切り離すことができるわけです。
書き出したから忘れないし、目で見て客観的に捉えたことで、なんとなくこうしたらいいのかも、という案も浮かんでいる。
1つでも2つでも、辛いことや問題だと思っていることを自分の外に出すことで、頭にその分のスペースが空くので、少しだけ、荷が降りた感じがするんですよね。
わからず、モヤモヤしていたものが、何だったのかわかったような感じがして。
気分的なものかもしれませんが、スッキリする可能性はあると思います。
別の五感を使う
五感には視覚、味覚、触覚、聴覚、臭覚がありますね。
今、孤独を感じていて辛い、という感情を「ごまかす」というと表現が悪いですが、五感をあえて使うことで、「孤独が辛い」に100%を使わずに済むようになるんですね。
例えば、お風呂の湯船につかり歯を磨く、で考えてみましょう。
- 触覚:お湯の感触にあたたかさを感じる
- 臭覚:入浴剤の香りがする
- 聴覚:水の音が聞こえる
- 味覚:歯磨き粉の味がする
- 視覚:今感じているものを見て認識する
これを言葉にしてみます。
- あたたかいな
- いい香りだな
- 自然の音がするな
- ミントの歯磨き粉だったな
- あー、お風呂で歯磨きしてるな
この感覚からくる情報を思考している間は、孤独が辛いです、を思考することは難しい。
孤独が辛い感覚は、残像として残ってはいても、それは今、感じているものじゃないですからね。
お風呂で歯磨きをしながら、孤独は辛いな、と考えることもできますが、他の感覚も使用中のため、孤独感に使われる割合が減るはずなのですよ。
おすすめは、空気を変えること。
- 室内なら外へでる。
- 外なら建物内に入る。
- 街なら自然の中へ。
- 歩いているなら走ったり乗物に乗って。
こんな感じで、辛い孤独感を感じている空気を変えることで、五感が変わります。
本格的に出かけなくても、部屋の窓を開けるだけでいいし、雨が降っていたら傘の外に手を出して雨を感じるだけでいい。
今、出来る、ちょっとしたことが、きっかけになって、全力で孤独感を感じずに済むと思います。
別の行動に置き換える
先程と同じ理由で、別の作業を割り込ませる方法です。
理屈は別の五感を使うと同じ。無理に孤独感を忘れようとか、孤独感を感じてはいけない、などとは考えなくて大丈夫。
今の状態、今の作業だと孤独を感じて辛くなってしまうのですから、全く別の作業に変えてみる。それだけです。
家の中なら、家事をやるとはかどります。1つでも2つでも、作業を前倒しにすることで、未来の自分の時間にほんの少しのゆとりが生まれますからね。
外にいたとしても、その場で立ったりしゃがんだり。目線を変えてみてもいいですし、突然瞑想するのもいいでしょう。
- 何かを食べる
- 出かける
- 映画を観る
- 草花に水をあげる
- ペットと過ごす
などなど。やれることは意外と無限大にあるものです。
療育でも使われている方法ですので、孤独感が辛すぎる場合は、ちょっとしたことでいいので、別の行動に置き換えてみるといいと思います。
発達障害育児に孤独を感じたら気をつけておきたい3つのこと

日々の育児に疲れ果て、さらに孤独に辛さを感じていると、孤独自体をストレスに感じ、どうしてもメンタルが悪化してしまいます。
メンタルが悪化して、最悪、うつ病になってしまうようなリスクをさけるために、気をつけておきたいことをお話ししたいと思います。
孤独を感じることに集中しない
自分の心に、ポッカリどころかドーンと穴が空いたように感じる孤独感。
ずっとこの辛い孤独感を持ったまま、この先も暮らしていくのかもしれない、というお先真っ暗感に浸りたくなってしまうこともあるでしょう。
どうせ私は、どうせうちの子は、みたいなことを考え始めると、孤独を感じている状態が迷宮入りしたかのように思えたりもします。
あ、孤独を感じているんだな、という事実がわかったら、それ以上、孤独であることをマイナスに捉える必要はありませんよね。
私は孤独、私は孤独、、、と集中しすぎて自己暗示をかけてしまわないよう、意識して気をつけた方がいいでしょう。
寝る前に孤独について考えない
寝る前に考えごとを始めてしまい、眠れなくなった経験はありませんか?
イベントを控えた前日の夜に、ワクワクしたり緊張したりして、眠れなくなってしまうのと似ていますよね。
孤独についても同じで、寝る前に考え始めてしまうと、不安まで抱いてしまうでしょう。
安心して脳が休めなくなってしまうので、寝る前の考えごとは、意識して避けた方が良さそうです。
誰も何も否定しない
誰も、というのは、
- 自分
- 子供
- 配偶者
- 親、義父母、他親戚
- 友達
- 先生
- 仕事や環境
- 他関わる人、物の全て
です。
自分の接し方が悪い、育て方が悪い、旦那や先生、関わる人のせいで、自分の環境のせいで、今、自分は孤独に苦しんでいる。
というように考えてしまうと、キリがないんですね。
孤独は、ある種の感情のようなものですから、自分か生み出しているようなもの。
それなら、孤独を感じる自分のせいなのでは?と思いたくなる気持ちはわかりますが、自分や周りを否定しても孤独はなくならないんですね。
孤独を感じている、ことはあくまでも事実だと受け止めて、対処し、予防として対策をした方が前に進めそうな気がしませんか。
振り返り:発達障害育児の孤独を突破する第一歩はまず「対処」から

孤独は本当に辛いですよね。
誰もわかってくれない、独りぼっち、みたいな感覚は、できればあまり感じたくないものです。
しかし、今、孤独感を感じてしまっているなら、無理にやめようとする必要はありません。孤独を感じてはいけない、みたいに考えてしまうと、自分の感情をも否定することになってしまいますからね。
孤独を感じていることは、あくまでもそういう心の状態であって、疎外感というか、孤立感というか、そんなことを感じているんだな、とわかればよいだけ。
今すぐに孤独を感じなくなるわけではないので、孤独を自分の隣におきつつ対処することは、自分の孤独とも少しずつ向き合っていくことになるでしょう。
お話した注意点に気を付けていただきつつ、紙に感情のすべてを書き出し、孤独を感じる以外の五感を使い、孤独と共存しつつ別の行動に置き換える。
そうやって、少しずつ孤独の対策を立てて実行していくことで、孤独ともうまく付き合っていけるようになると思いますよ。