今年の運動会の徒競走は、少しでも走る練習をして望んでみませんか?かけっこが苦手だと思っているのは、実は走り方を知らないだけかもしれません。
今回は、走る事が苦手な子供の問題点を根本から改善できる練習法を提案します。本格的にガッツリとした陸上練習ではなく、走るための神経がつながっていない状態である現状にスイッチを入れるためのきっかけを作る、そんな練習法です。
速く走れる走り方を見ても、運動神経のつながりがうまくいかずに、自分は走れないと思い込んでしまっている発達障害の子供や、頑張って走る練習をしてみたけれど、さっぱり速くならないという方の参考になればうれしいです。
かけっこが苦手な子供が走る練習をする前にやっておく重要なこと

かけっこが苦手な子供は、走り方がわからないだけかもしれません。ほとんどの子供が走り方を教わっていない状態で、幼稚園や学校の運動会で徒競走に参加しているだけで、そもそも「走れない」わけではないのです。
この考え方には3パターンの解釈があると思っています。
- 走れないという思い込みにハマっているだけ
- 走り方がわからない結果が走れていないだけ
- 神経と筋肉の発達、運動神経の連携がうまくいっていないだけ
速く走れないことへの思い込みに気づくこと
極端な例で説明しますと
小学1年生の子が、保育園の2歳時と一緒に走って「速く走れない」という思いは抱かないと思うのです。
さらに、たまたま一緒に走った友達が学年でもトップ集団だったとしたら、「速く走れない」と思ってしまうだけかもしれないのです。
本当に走れないかどうかは、また別の問題であって、誰かと比べた状態での「走れない」は、ただの思い込みであることに、まずは親子で気づきましょう。
思い切り走れたかどうか?!目標は自分の理想の走りを追求すること
よくやってしまいがちな目標設定が、「運動会で1位を取ること」。
これは、一緒に走る友達がベースになっているので、人ありきの目標です。
先程の極端な話で言えば、タイムレースで真ん中くらいの速さで走れる子が、一番遅い組で走れば当然1位を取れますよね。
逆に、タイムレースで真ん中くらいの速さで走れる子が、一番速い組で走ればビリになってしまいます。これでは、1位を取ることを目標にしようとすると、「走れない」と思ってしまうのも無理はありません。
神経や発達・運動神経の連携がうまくいっていないなら走ってみてから判断
もしかしたら、神経がうまくつながっていないだけかもしれませんので、体を実際に動かしてみてから判断してみましょう。
その際、こうやって走るんだよ、と見本を見せるよりは、足や腕を実際につかみ、ゆっくりと動かして見せることで、体が動きを覚えていきます。
自閉傾向がある場合は、見て真似をすることは難しいので、作業療法のように手足を直接、説明している動きと同じように、動かしてあげてみてください。
そして、子供自身が意識して、同じ動きができればOK。できなければ、神経がうまくつながっていなかったことになるので、毎日数回ずつ動かして、新たに神経をつなげていきましょう。
かけっこが苦手!速く走れない!を改善する5つの基本練習

では早速実践です。練習する時は、動きやすい洋服と靴がおすすめです。
動きやすい洋服とは、できればジャージのようなものにしましょう。格好だけ本格的にするのも・・と思うかもしれませんが、本格的っぽいジャージを着ると、速く走れるような気がするものです。
次男は西松屋のジャージやアディダスが多いです。
くつはこちらでおすすめしていますので、参考にしてください。
ゲーム感覚でスターターに素早く反応する練習法
かけっこ練習と言えば、とにかく走ることに意識が向きがちですが、基本的に小学生は短距離走。スタートでほぼ決まってしまいます。
スタートが遅ければ、そこから挽回するのは本当に速く走れる子供だけ。
スタートは、できるだけ雷管と同時に体が反応して走り始めた方がいいことは説明するまでもない感じです。
音に反応する訓練|手拍子練習法
大人が手を叩いた瞬間に子供が手を叩くという単純な練習です。音に反応できるか訓練、のような感じです。
ランダムに手を叩いたり、ヨーイ・・・・・・・・・・パン!のように間を開けてみたり、いろんな間で訓練してみましょう。
音に反応して体を動かす訓練|ビーチフラッグ練習法
本当にビーチフラッグをやってもいいのですが、要はスタートと同時に体が走り出せばOKです。
できるなら、次のパターンで訓練してみることをおすすめします。
- 腕立て伏せから
- 仰向け寝から
- うつ伏せ寝から
この状態から、ヨーイ、ドンとスタート練習をしましょう。実際に旗を設定してもいいですし、スタートのみでも構いません。
どれもほぼ寝ている状態から身体を起こす時に、真上に体を起こすのでなく、飛行機の離陸のように斜め上に上半身が起きていく感覚、こうやってスタートするよという感覚を体が覚えてくれたらいいな、という期待も込めています。
ヨーイ、ドンで真上に飛び上がってしまうと、前に走る加速が付きにくいので、前に倒れて転びそうになるくらいから身体を起こす練習を兼ねて、加速もつけていこうということです。
日常のケガ防止にもつながる足首をやわらかく動かす練習法
できれば一度、走っている足の動きをスローモーションで見ていただいたり、動画などを参考に観察していただきたいのですが、地面を蹴る時に意外と足首が動いているのです。
地面を蹴り上げる動作なので後ろ足なのですが、足首が固定されたまま地面から離れてしまうと、地面を蹴らないので加速、馬力と表現した方がわかりやすいでしょうか、グイっと前に進んでいかず、その場で宙に浮くだけになってしまうのです。
ちょっと理屈っぽい考え方ではありますが、スタートで加速をつけた後、一歩一歩の馬力(足首での蹴り上げ力)×ゴールまでの歩数があるのとないのとでは、歩幅に差が出てくると思うのです。
当然ですが、歩幅1つの差×歩数は、短い距離でゴールについた方が早く走れているということ。
なのですが、足首が固定されている子が存在していることは確かです。→長男
やる時間はいつでもOK|足首を動かす訓練
まずは、足首を前後に動かしてみてもらいましょう。十分に動いている場合はいいのですが、指先だけ動かして足首から動いていない場合があります。
このような時は、足首自体が固い場合が多いので、足首を前後左右に動かし、毎日マッサージして下さい。ぐるぐる回してやわらかくなるまで、寝る前などにマッサージをすればだいぶよくなります。
マッサージの最後には、自分で足を前後に動かしてもらいます。自分で意識的に前後できるようになったら、地面を蹴る練習をします。
地面を蹴って前にジャンプする練習
とにかく後ろ足で地面を蹴って前にジャンプしてみます。できれば動画を撮って、ちゃんと足首が動いているか、地面を蹴っているかをチェックするといいでしょう。
細かくあれもこれも練習するのではなく、足首を使って地面を蹴り上げる。これのみに集中して練習しましょう。
膝を持ち上げる筋肉と神経にスイッチを入れるもも上げ練習法
陸上部っぽい練習をしましょう。
大人が子供の足の付け根あたり、骨盤あたりに手のひらを下向きに広げ、子供がもも上げ練習をします。
ほぼ100%手のひらにひざがつけばOK。足の付け根以上足をあげる必要はありませんので(上に飛びたいのではなく、前に進みたいので)高くあげることにこだわるのではなく、その後、もも上げのスピードあを上げていけるように、100%手のひらに膝をつけていきましょう。
できるようになったら、足の動きを早めて練習します。
これができれば一気に速くなる!膝下(スネ)を前に動かす練習法
足が遅かった長男と足が速い次男の差は、スネ部分が一番大きいポイントでした。
次男は、足が120度近く開いているのに対し、長男はほぼ90度ちょっと。その差30度。
30度×ゴールまでの歩数差は、結構な差になると思いましたし、実際にここが肝でした。
本当はもも上げよりもスネ部分を前に出す方が確実に速く走れるようになりますが、何分、ちょっと難しい。さらに言えば、ももが足の付け根まで上がっていないと、スネ部分が前に出にくくなってしまうため、結局ももあげも最低限は必要になるのです。
でも、ももを上げた後、膝下がグッと前に出れば、あとは加速やその時のスピードが底上げをしてくれて、気が付いたら風を切って走っていたということも起こります。
片足ずつ膝下スネ部分を前に動かせるかどうか練習
片足ずつ、ひざを足の付け根あたりまで上げ、そのまま120度くらいまでスネ部分を前に出せるかどうか、やってみましょう。
もし、この説明をして足が前に出なければ、神経がつながってないと判断し、足を持って動かしてあげましょう。
毎日少しずつ、足を持って動かし、意識的に動かしてもらい、ということを繰り返します。
止まっている状態でスネ部分を前に動かせるのに、実際に走るとスネ部分が前に出ていないようであれば、ゆっくり走りながら意識してスネを前に出して走る練習をしてみましょう。
体の状態は起き上がったままでも大丈夫です。実際にトップスピードで走っている時は、前傾姿勢ではなく上半身は起き上がっていますので。
できるだけ、1回の走りごとに動画を撮り、微調整していくことが望ましいです。
メトロノームを使って体全体で走るをサポート!足の回転数を上げて走り抜ける練習方法
さらに陸上部っぽい練習になりますが、足をできるだけ早く動かす練習です。
もも上げではないので、足を上にあげなくても良いです。とにかく最速で小走りをするイメージで足を動かす訓練をします。
メトロノームを100くらいにセットし、カッ、カッ、カッ、カッ、と鳴るごとに、左右の足踏みをします。
ポイントは、足全体をベタッとつくのではなく、つま先だけでやること。
カッ、カッ、カッ、カッ、で タタ タタ タタ タタ という感じです。
200くらいまで速度を上げられたら結構すごいかなと思います。
速く足を動かせる、ということを認識すればいいだけの練習です。メトロノームだと数字で判断できるので、できるようになったことが見えやすい(数字で)というだけです。
やりすぎると、太ももの筋肉が痛くなるので気をつけましょう。
さらなるレベルアップを目指すなら!よりスピードアップできる応用練習

ゴール地点は最速タイムを測る場所|ゴール走り抜ける体力をつける
運動会を見ていると、ゴールテープの少し手前でスピードが落ちている子は本当に多いです。ゴールはただの線であり、一つの目印なだけ。
ゴールが最速タイムである必要があります。
そして、ゴール前でスピードが落ちる子供が多いのであれば、最後の最後で追い抜く可能性もあるわけですね。
大事な事なのでもう一度念を押しますが、ゴール地点が最速タイムです。ということは、ゴールの最低でも30メートル先までは走りぬけないと。ゴール前で止まったら走り切った事にならなくなります。
ゴールの先まで走り抜きましょう。そして、余裕で走り抜けられるだけの体力をつけてください。
徒競走の長さが50走メートルなら、毎回100メートル走る。80メートル走なら160メートル。100メートルなら20メートル、全速力で駆け抜けられるだけの体力作りをしてください。
お尻に足裏が付くまで蹴り上げろ!|1回の速度を究極まで上げる
最後に、立ったまま足の裏をお尻に付ける練習をします。1回の速度を究極まで上げるために、足裏をお尻に付けてハムストリングスという筋肉を動かしていきます。
立った状態で、跳ねながらかかとをおしりに付けていきます。今まで一度もやったことがない動きですので、出来ない子は全く足が動きません。
できそうになければ、足を持って教えてみましょう。この筋肉は、蹴り上げた足を前に誘導させる役割がありますので、足の回転や馬力などに直接関わってくる筋肉です。
振り返り|苦手を乗り越えて思い切り走れ!自分の意志で体を動かすことの楽しさ

今回ご紹介した練習は、足が遅い長男用に実践した方法です。直線を走る練習もしていましたが、足首の固さを取り、スネ部分を前に出す練習をした後、急激に速くなり運動会の徒競走で1位を取りました。
「できない」の大半は、やり方を見直すことで、思い込みを消し去り、前へ進むこと解決します。走ることも同じです。
地道に練習を積むことでできるようになることがあります。それがと徒競走につながってくれたらうれしいです。

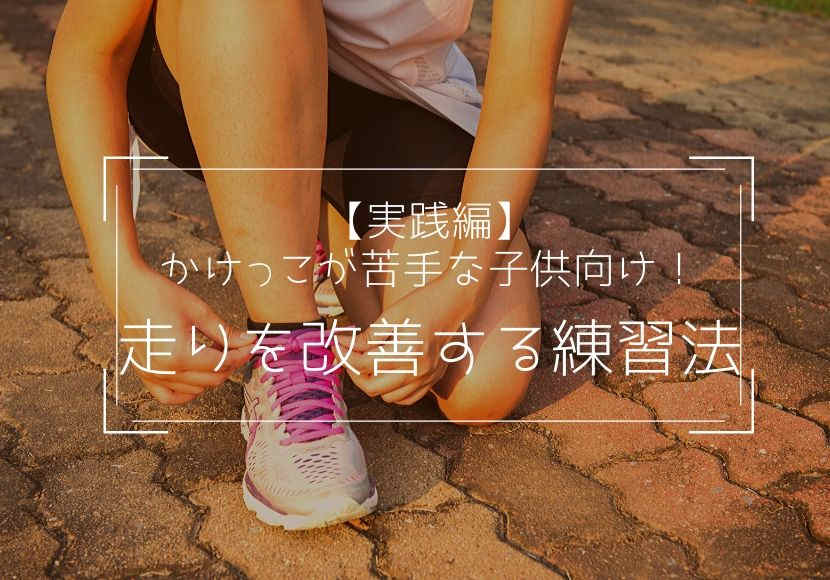
![[アンダーアーマー] 二ット トラックスーツ(トレーニング) 1347743 ボーイズ](https://m.media-amazon.com/images/I/412wPghIZGL._SL160_.jpg)





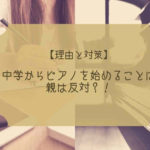

コメント