育てにくい子ってどんな子どものこと?もしかしたら子どもが「育てにくい子」かもしれない、と不安に思っている方へ、私なりの「育てにくい子」の定義を考えてみました。
いいとか悪いとか、そういう話ではありません。あくまでもこういう子が「育てにくい子」と呼ばれているのでは?というお話しです。
育てにくい子どもと育てやすい子どもの定義(私流)

私流ではありますが、育てにくい子どもとはこういう子どものことなんじゃないかな、という定義をある程度考えておきたいと思います。
注意:科学的根拠はありません。あくまでも私流の考え方です。
育てやすい子どもの定義
- 意志の疎通がうまくいく
- よく寝る
- 何でもよく食べる
- 親の思う通りに動く(想定外の行動があまりない)
- 大人がわがままだと思うようなことを言わない
- 1人で遊ぶ
- 素直
- 適度におとなしく適度に活発
- 友達とのトラブルがない
育てにくい子どもの定義
- 意志の疎通がうまくいかない(できない)
- 寝ない
- 偏食が多いor食べない
- 親の思う通りに動かない(想定外の行動が多い)
- 大人がわがままだと思うようなことを言う
- 頑固すぎる・こだわりが強すぎる
- 起きている間中動いている
- 友達とのトラブルが多い(すぐ叩くなど)
- 不安行動がある(奇声・チック・どもり・緘黙など親が不安に感じる行動)
子どもの将来の姿の定義~親の理想~
- 大きなケガ・病気がなく健康に大人になる
- 挨拶やマナーをちゃんと守れる
- 生活習慣に問題がない
- 保育園・幼稚園・学校に行く
- 読み書き計算に支障がない
- 一通りの運動ができる
- 一芸がある(習い事など)
- ある程度のレベルの学校へ進学する
- 協調性がある(人と仲良くできる)
- 大人の言うことを聞ける
- 目標に向かってコツコツ努力できる
- 本をたくさん読む
- 人を気遣えるだけのやさしさがある
- お手伝いをする
- 言われなくても自分から行動する
- 夢を持つ
- 大学を卒業したら職に就く
- 結婚して家庭をもつ(孫が生まれる)
- 夫婦円満
育てにくい子どもだと思っていることが勘違いだとしたらどうなる?

育てやすい子どもの定義、育てにくい子どもの定義、理想像について3つの定義を簡単に挙げてみました。細かく言えば、もっともっとあると思いますが、とりあえずはこの辺りでお話を進めていきたいと思います。
子どもを育てるということ
みなさんいろんな思いや考えがあるとは思いますが、子どもを育てるということは、子どもが大人になって1人で生活していけることを念頭において育てていきますよね。
ざっくり言えば、自分で働いて生活していくために必要なこと、社会で必要なスキルを、家や学校で勉強していくので、人と暮らしていく上での様々なルールを、子どもの頃から少しずつ教えていくわけです。
子どもは家族という安心できる人達の中で、認められて、愛されて、共感されて・・・
様々な感情や愛情、技術や知識を一番身近にいる親が教えていくのですが、そこには少なからず親の理想像が関係していますよね。
【礼儀・社会的なルールやマナー】
- 相手の話を聞く
- 挨拶や返事をする
- 悪いことをしたら謝るなど
【親の理想】
- このままじゃ、進学できない
- このままじゃ、就職できない
- このままじゃ、結婚して幸せになれないなど
という種類のものですね。親であればなんとなくこの種の焦りを感じたことがあるのではないでしょうか?
この焦りが苛立ちに代わり、思うように子どもが育っていかないのではないかと不安を感じてしまうのは、あるかもしれないですよね。

私は完全にこの思考回路だったわ。
どこまでも追加されていく仕事と同じ現象が見えてきた
まず、最低限、食べて・寝て・トイレにいく。これができていれば良いわけで、これに付加的な能力が追加されていくわけです。
寝返り、お座りのようなものから、聞く話す、読み書き計算、1人で着替え、自転車に乗る・・・・などなど。
生まれたばかりの赤ちゃんの時は、ひたすら泣いて寝ているだけだったのに、できる事が1つ増えると、次はこれ、次はこれ、とどんどん期待が追加されていく。望まれることが増えていく。
仕事でもルーティンで処理している仕事がうまく回るようになると、新たに担当を増やされて、なんとか頑張ってそれもルーティン化出来てくると、また新しい仕事が追加される。
営業マンのノルマのように、達成しても達成しても終わりがないノルマと似たような現象が子育てでも見え隠れしているような気がしてきたのでした。
今は、このルーティンのまま、しばらく過ごしていきたい時期だってある。一旦、他のことに目を向けていきたい時期も出てくるじゃないですか。
その辺のことを考えないで、親の理想の子ども像と同じじゃない、このままだとなれないかもしれない、って言われても、ロボットじゃないんだからそんなに器用に、順番通りに、期待通りに動けないんですよって子どもは思っているかもしれない。
そう考えたら、じゃあ、育てにくい子どもっていうのは、どとのつまり、育てにくいのではなくって、親の期待通りに「理想の子ども像にならない子ども」ってことになりますね。

ややこしい・・・・
逆に実親に理想の親像を求められたらその通りの親になるのかという仮説
まだ発達中で一人前とは言えない「子ども」と、もう生活的に自立している「親」を比べるのはいささか違うのでは??という疑問も若干ありますが。そこはちょっと強引に考えてみるとして。
例えば、自分の親に「あなたはこういう親になりなさいね」って言われたとして、しかもどんどん理想が追加され続けていったとしたら、あなたはその通りの親を目指して日々を過ごすのだろうか?という仮説です。
心に余裕があるときにふと実親に言われたことを思い出して、「確かにな」とか、「それはないな」なんて判断して、実行するかしないかを決めていくと思います。
それに、自分にだって考えがあるし、理想もあるし、興味があることだってある。それって親と同じとは限らないし、親の描いている世界と同じであるとは考えにくいじゃない。
だって「私」という人間の過去経験から思い描ける今や未来と、親であっても違う人間である人が思い描ける今や未来って違うしね。
それって、たった何年かしか生きていない子どもにだって、その世界や思いや考えはあると思うのですよ。
親の敷いたレールの上を、親が用意した乗り物に乗って、親に押してもらっているだけ。ちゃんと自分で歩いてみたことあるのかな。って感じになっちゃうと思いませんか?
そういうことを感じて考えられて思える人間を「考える人間」って呼ぶんじゃないかな、と思うのと、学校は、同年代の人と一緒に、いろんな「考える人間」に会える機会を与える場所なんじゃないかなと思うのです。
そのために必要な語学スキルであって、間違っても覚えてテストに受かるためのものじゃないですよね。考えるための情報整理の道具であり、人との意思疎通のための手段のための勉強だと思うし。
知的好奇心を形にしたり、感情を形にしたり、人の情報を参考にして新しいことを考えたり。そういう生きていくっていうことの根本を便利に快適にしていくために、共通ルールを覚えておく必要が人間にはあったわけで、それは親が持つ、「理想の子ども像」の姿とはちょっと違うなと気づいたわけです。
子どもの将来の姿が、結果「理想の子ども像」の姿になったとしても、スタートが「理想の子ども像」なのかな、という疑問は、育てにくい子どもを育てる上での重要な鍵になる部分な気がします。
育てにくい子どもを育てる親の役割って何だろう?

話しがどんどんややこしくなっていますが。
育てにくい子どもは、頑張って自己主張をしているのではないかという仮説
育てにくい子どもって、結局、自分の意志や感受性がちゃんとあるって一生懸命主張していると思います。
それが、他の人とは違う感覚があるから、なかなかわかってもらえない。人間、自分に置き換えられなければ本人の気持ちや思いなんてわからないものだと思いませんか?
でも、違うからこそレアになるんだし、違うからこそたくさんのことに気づくんだし、とってもすごく価値があることだと思うんだけど、日本社会は出る杭は打っちゃうからね。もったいないなって思います。
そんなわけだから、育てにくい子どもたちに必要なのは、まずは環境かなって思います。親という居場所、家族という居場所、学校という居場所、友達という居場所。得意なことを思い切りやれる環境は、大人がお金と経験でいくらでも解決できるし、提案できるでしょ。
子どもにできなくて大人にできることの大きな違いは、考えたこと、思いついたこと、やってみようとおもったことを現実に変える(買える)力があるということ。
子どもは外国に行きたいと思っても行けないけど、大人なら連れていくことができる。様々な体験も、ジオラマ作りも昆虫採集もドールハウスでもプリンセスになる夢でも(ドレス買って着せるだけとかね)、大人の移動力と情報収集力と資金力と現実化できる可能性力は、絶対に子どもには真似できないですよね。
それが大人なんだし。
ならば徹底的に環境をそろえてみたらいいんじゃないかと私は考えたわけです。
雨風に負けない倒れない根っこを張る木のために親ができることは環境づくり
子どもにだって同じような気持ちや思いや考えはあると思うんです。うまくまとめて話せないとか、相手に伝わるような話し方を知らないとか、子どものうちの支障は多々あるにしろ、個人としての考えはあると私は思っています。
そこを、しっかりと聞いてあげる。1人の人間として聞く。聞いた上で、子どもが大人になっていくまでの間に必要なこと、社会で働いていくために必要なこと、生きていくということなどを順に教えていけたら、きっと育てにくくは感じない気がするんですよね。
いや、やっぱり頑固だったり素直に聞かなかったりするとは思うので、育てにくいのは変わらないかもしれないけど、折り合える部分というのは探せると思うんです。
その、折り合う部分というのをお互いに探して、分かり合っていくことって、社会で生きていく上で必要なスキルですよね。自分の子どもの最大の理解者が親であることって、子どもの人生にとって最高に心強い人生の根っこだと思うんですよ。
土のような親の上に根っこをしっかりと張って、その木が自分で納得のいく育ち方をして生き生きとしていたら、親としては最高にうれしいと思います。
そのために土(親)にできることは、根を伸ばそうとしている木(子ども)の根をしっかりと受け入れること。時にやわらかく、時にしっかりと固めて。
土である親が栄養をたくさんとって、木である子どもに栄養を分け与えるために、どういう木なのかを理解しておきたいですし、万が一、背の高い木になっても大丈夫なようにしておきたいですし、雨風で倒れてしまわないようにしっかりと根を張れるような栄養のある土にしておきたいですよね。
いろいろと考えを巡らせた結果、子どもに理想を求める前に、自分をなんとかした方がいいのか。という結論に至ったわけです。
育てにくい子どもを理解するって何だろう?
理解するって難しいです。頭で知識をわかるってこととは違いますよね。足し算を勉強しても、実社会で使えなければ本当に理解しているとは言えないのと同じ。
子どもを理解するのも、見えるところだけを知ることじゃないような気がします。見えるところ、聞こえてくるもの、から得た情報から、今まで育ててきた子どもの過去データと照らし合わせて未来を予測する。
予測した上で、今、親にやれることは何だろう。通訳になることなのか、子どもと周りの人の通訳になることなのか、子どもの力を最大限に発揮するための環境を整えることなのか。
など、いろんな方向から考え、想定して行動を起こしていく。子どもを変えるのではなく、まずは自分にできることをやっていく。子どものためにどんどん動いてみる。試行錯誤をしてみる。
そこからわかる様々なことを子どもにフィードバックして、先の未来につなげていくことが、「理解すること」かなと私は思っています。
結構大げさかもしれないけど、正直なところ、動いておいて損はないです。「育てにくい子ども」でも、最初のイメージとはちょっと違う「育てにくい子ども」に感じてくるかもしれません。たまらなく愛らしい「育てにくい子ども」とかね。
こうなってくるとストレスに感じることはだいぶ減っているはずです。自分の思い通りに動かなくても、何で動かないのかの理由をわかっているから。過去の対処法でうまくいかなければ、違う対処法を試していくと思うので、それはストレスではなく、新しい試み。親にとっても新しいチャレンジです。
チャレンジし続ける人生に不満足は少ないと思うという仮説
正直、親の歳になって新しいことにチャレンジしていくって、あんまりないと思いませんか?
いろんなことが面倒になってきて、いろんな刺激に慣れてしまって、テレビを見過ごして、誰かの影口を言って、時間が過ぎていったりしませんか?
私は長男が発達障害、次男がHSCで、子育てが大変過ぎて、2人とも育てにくくて、もうこれ以上子どもはいらないと本気で思っていますが、現在でも2人の子どものためにチャレンジし続けているので結構充実しています。
日々、実験&検証の連続で、情報収集のための読書量もかなり多いです。長男が発達障害じゃなかったら、子育てでチャレンジし続ける人生にはならなかったと思っています。仕事ばかりしてて、子どものことに興味がない親になっていたかも。
でも、意外と突き詰めて考えることは好きなんだなと、新たな自分に気が付いたり、私は何もできないおバカだと思っていたけれど、できることも1個はあるなと思えるようになりました。
振り返り~育てにくい子どもの定義~

育てにくい子どもを2人育ててみて、子どもと向き合っているな、という感覚があります。
発達的に今は難しい場合や、そもそも「できる」方向へ向かわないもの(神経のつながりが違うとか)は、代替手段を考えて道具を使えばいいし、先生に相談したり交渉したりすればいいし、と理由と原因と対策を順序立てて考えられれば、子育てでイラつく事の半分は消せると思う。
今、親の理想の子ども像に近づけることよりも、今、子どもが何を見て何を感じているのかを知ることの方が今後の生産性を考えても確実に前向きだと思います。
昨日が今日になって今日が明日になるわけだから、今日やらないことは明日もきっとやらないし。どこかで意を決しなければいけない時もあるだろうし、今は好きなだけ好きなことに没頭する時期かもしれないし。
そういうことを親が知ることが、子どもを理解することの第一歩になるのかな、と思います。
「育てにくい子ども」って、いろんな才能を持った子どもが多いように見えるのは私だけかもしれませんが、私には才能の塊に見える。長男も次男も、種類の違う天才に見えるときがある。
そうやってどの子にもみんな違う才能があるんじゃないかなと思うんです。「育てにくい子ども」の子育ても、まんざらでもないかな。

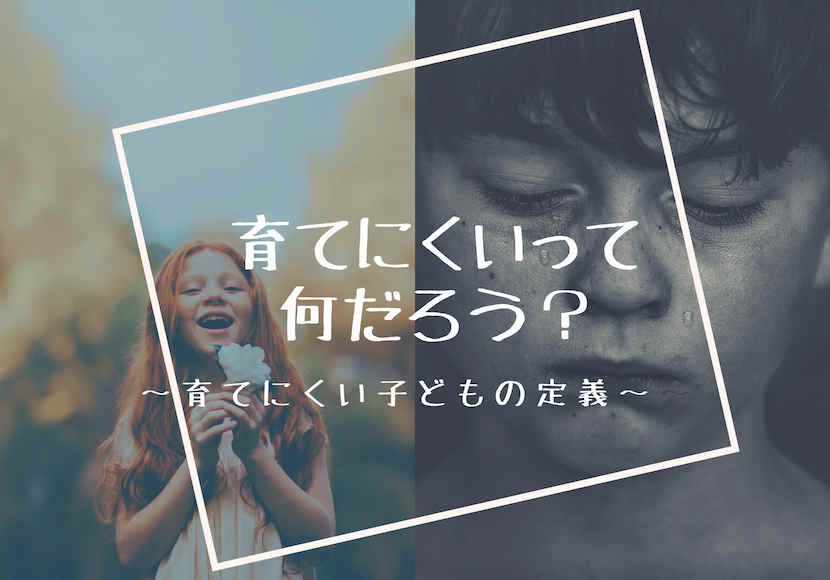





















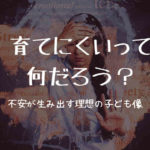
コメント