こんにちは!長男が1年の頃の担任は授業の半分は席に座らない授業にしていたことを思い出した花緒です。多動の子供にとって座り続けることは大変みたい。お尻がムズムズ病になるらしいです。今回はそんな長男用に私がやっていた対応と対策をご紹介します。
今日の質問|担任の先生から、子供が授業中立ち歩いて迷惑になっていると何度も指摘されます。何度注意しても治らないのですが親としてどうすればいいのでしょう?

いきなりで申し訳ないのですが、私の理想をお話しします。まず先生は立ち歩く子供を怒らないでほしいんですよね。あくまでも私の予想なのですが、たぶん、授業に飽きているんだと思うんです。
私は先生ではないので実際に実験できないところがかなり残念なのですが、立ち歩いてしまう子供はやることがないんだと思うのです。
正確な表現で言うと、授業なのでやることは決まっていますね。
- 椅子に座る
- 先生の話を聞く
- 言われた作業をやる
「やることがない」と私が言ったのは、立ち歩いてしまう子供にとっては、本人的にやることがなくなっている状態なんじゃないかなと考えています。
例えば、先生の授業が面白くない、説明がわからない、作業が終わってしまった、作業がうまくできない、などの理由でやることがなくなったので、立ち歩くという行動に出ているのではないか、と考えています。
たぶん、先生の授業が面白ければ、立ち歩く必要がなくなるので、歩かなくなるんじゃないかな。とか、立ち歩いても関係ない授業にすればいいんじゃないかな、とか、何か工夫をすることで、授業中の立ち歩きはなくなるんじゃないかな、と思っています。

ただの親の憶測的な発想ばかりでごめんなさいね。
ADHDの子供に起きる学校での悪循環
結局、頭の回転が速いADHDの子供には、先生の話し方はゆっくり過ぎるのかもしれないし、今授業でやっているテーマはもうわかってしまったのかもしれない(子供の本人の脳的には)。
実際にできるかできないかは別として、わかってしまった内容にはもう興味はなくて、ADHDの子供は次の興味に移りたいのに、先生はまだ同じ話をしていて、さらにまた同じような作業をさせようとしているのかもしれない。
何か他に面白いものはないかなと探すために、
- キョロキョロして→怒られる
- ちょっと立ち歩いて探してみる→怒られる
- 動くと怒られるので喋る→怒られる
結局、他に面白いものを探すと→怒られる、という図式がADHDの子供には起きてしまうのではないかと思っています。
そして、私の中ではあまりよくない悪循環だと思っているのですが、
この図式がADHDの子供の中に出来上がってしまうと、興味を示せなくなってしまうというよくないことが起きる気がしています。
ただ、ADHDの子供の興味って、それこそ多種多様で多方面にあると思っていて、突然思いつく、目につく、思い出す、ひらめく、などいろんなことがきっかけで突然動くような気がするんです。
だから、当然だけど、ものすごく、あぶない。
だから怒られちゃう。
ADHDの子供が興味を持ったから怒られるんじゃなくて、大抵の場合、とてもあぶなくて怒られるんですよ。最初はね。
興味を持つと怒られるという悪循環【長男のパターン】
でも、最初はあぶないから怒られていたのに、何度も怒られているうちに、怒っている方も子供が何をしても怒ってしまうという現象がおこります。
私もそうだったのですが、長男がやろうとすること全て、親としてやってほしくないことばかりだったんです。
- 高いところから飛び降りる
- 水たまりの中をジャンプしまくる
- つかんだものはとりあえず投げる
- 洋服をハサミで切ってみる
- 壁にクレヨンで絵を描く
- お米をバラまく
- 風呂の栓を抜く
- 玄関を出たらとにかくダッシュ(400mはくらいはまず走る)
- その他諸々・・・・
高い所から飛び降りる以外、今ならやってみればって思いますが、当時(長男2・3歳ころ)はとてもじゃないけどいいとは思えなかった。
後々、命の危険に関わること以外はやらせてあげようという方針が私の中にできましたが、初めての子供だし、そんな考え方があるなんて知らずにガンガン怒ってまして。
長男には申し訳ないですが、これでは興味を持つと→怒られるという図式になってしまいますよね。
それこそ自閉傾向の強かった長男に、コミュニケーションというものは存在していませんでしたし、親からの一方的なコミュニケーションはほぼ押し付けに等しかったかもしれません。
待ち時間・空き時間を作らない長男の先生の対応方法
席を立ち歩く事件はADHDで多動が気になる子供には、ある意味普通に起きることです。長男はお尻がムズムズするからとりあえず立つ、椅子をガタガタ揺らす(そして後ろにひっくり返るのはお約束)、なんなら廊下に出てみる、ということをやっていました。
長男の担任は、この立ち歩きに関しては一切長男にも私にも注意もしないし、怒ることもありませんでした。その代わり、授業の半分は椅子に座らないような授業方針をやっていました。
要するに、全員が移動するんですね。授業中に。
細かく言うと、
- 前に出て発表する
- グループにするために席の配置を変える
- 終わった人から教卓の所に並んで先生に丸付けをしてもらう
- クラスメイトと意見交換をするために自由に移動させる
- 国語の時間のたけのこ読み(自分で読むと決めた一文を読む音読法)
- 進捗度合によって待ち時間がないように調整されている
普通の授業じゃん!って言われそうですが、なんかね、やれる人はやりましょう、やれない人はこれをやりましょう、終わった人はこれをやりましょう、みたいな感じで、何かしらやることがあったし、並んでいる時間とかはほぼ自由時間だったので解放されていたみたいです。
あと、授業中につい喋ってしまうADHDの子供の意見を、「よく言ってくれた!」「よく気づいてくれたね」「先生も気が付かなかった」って授業の1つとして先生が吸い上げてしまうんです。
だからADHDの子供の喋りが迷惑になるのではなく、授業の1つの意見になっていく。たぶん、長男の担任は別格でそういうのがうまい先生だったみたいで、クラスメイト1人1人に役割が与えられていたんですよ。
子供同士でできないことを笑ったりバカにすると、「でも○○君はこんなところがすごいのよ。あなたできるの?」と切り替えしていました。
つい笑ったりバカにしてしまった子を怒るのではなく、そっち(できないこと)じゃなくて、こっち(できること)を見てごらん、という指導法だったので、先生も生徒を良く見ていて、いちいち気づいてあげて、これでもかっていうくらい、フィードバックしていました。
そして、クラスみんなの前では怒らないし、だから恥に感じるようなこともなく、通常級にいるのに通級で過ごしているように私は感じていました。
だから、長男のADHDは目立ちにくかったですし、他にも何人かいましたが、別段問題になることはありませんでした。(クラス替えになって担任が変わったら大変なことになりましたけどね)
ADHDの子供が迷惑をかけてしまう行動とは?3つの行動を我流で分析!

長男以外にもADHDの子供の行動が授業の迷惑になっているなと思うことは多々あります。実際は私にとって迷惑なのではなく、授業を真面目に受けたい生徒にとって、迷惑になっているという表現が正しいのかな。
ちなみに迷惑の定義を再確認。
ある行為がもとで、他の人が不利益を受けたり、不快を感じたりすること。また、そのさま。「人に迷惑をかける」「迷惑な話」「一人のために全員が迷惑する」
goo辞書/ めい‐わく【迷惑】の意味
ただし、迷惑か迷惑じゃないかは人それぞれってところもありますね。
興味が向いたらすぐ動く
基本的にADHDの特性は頭の回転が速い+忙しいと思っていて、いろんなことが頭の中をかけめぐっているのではないかと思っています。
当事者ではない私にはわからないのですが、次から次へと思い浮かんで疲れる人もいるみたいです。あと話がまとまらないとか、何を思ったのか覚えていないとか、大変なことも結構あるみたい。
長男は、何かに引き寄せられるように興味が向いた物の方へ動いていきますが、授業中に興味ベースでどこかに動かれたら、逆に動いた子が他のみんなの目に入ってしまいますよね。
特に、一生懸命授業を聞いて、先生の話を理解しようとしている子や、作業に集中しようとしている子にとっては、集中が途切れる原因になってしまいます。
気になるものを触る
動くのと同じで、気になるものを授業中だろうと何だろうと触る子もいますね。授業で使う道具だったり、友達の持ち物だったり、教室に置いてある物の何かであったり。
目の前からなくなれば、とりあえずは触らないのでしょうが、また別の物にターゲットが移るだけなので、基本的にはイタチごっこでしょうね。
見えなくなれば一番いいと思いますが、授業にはいろんな物を使いますので、あまり現実的ではないでしょう。
おそらく、授業に関係している物を触りたいのであれば、その子に担当にしてもらう(持っていてもらう、動かしてもらうという助っ人的な役割を与える)、授業に関係ないものであれば、布などで覆って見えなくするか、どこかの棚の中にしまうのがいいかな。
それでも別の物を探しそうですが、とりあえず教室内に何だろう?触ってみたい!と思うものがなければいいのかな。それが、触りたいと思って興味を持ったものを勉強するという全く関係ない授業に変更するとか。
かなり現実的ではないですが、そうしたら、きっと興味は完結するので、それ以上その物には触らない。次にターゲットが移るとは思いますけどね。
TPO関係なく大声で話す・奇声をあげる
気になることところ構わず話すのは2種類あると思っています。
- 動く・触ると同じで、興味関心がある内容を声に出して喋るパターン
- 動くと怒られ、触ると怒られるのでストレスがたまってわざと大声を出すパターン
奇声をあげているのも、やっぱり何か押さえつけられている感を吐き出しているのかなと思っています。学校公開とかで大声を出してる子や奇声を上げている子はそんな感じがしてならない。
それで隣の席の子に「うるさい!」って文句を言われたり、席を立つと「座って!」ってクラスメイトに怒られたり。
じゃあ、どうしろっていうんだよ!って怒りたくなるのも分かる気がする。
座ってられないし、興味があるのも脳の問題だし。問題行動なんじゃなくて、勉強方法が合ってないだけなんじゃないのかな、って思います。
ADHDの子供の切ない悪循環。って思っているのは私だけかな。
【子供が迷惑にならないために】ADHDの子供に親ができる対応と対策

先生から「お宅のお子さんが授業中に立ち歩いて他の生徒の迷惑になっています」と連絡がきたら、とりあえず1回「すみません」と謝るだけ謝って、心の中では、「あなたの授業が面白くないんです」とつぶやきましょう。
子供は面白ければ、興味があれば、勝手に動かないと思うのですが、先生はそれを知らないのでしょう。そして、自分のこと(子供に興味を持たせることができないこと)を棚に上げて、他の生徒の迷惑になっていると言ってくる先生の言うことはひとまず横に置いておきましょう。
お子さんにしてみれば、面白くない授業を聞かされ、先生の思い通りに動かないと怒られ、挙句の果てに親に連絡をしてきて、親が今度は子供を怒ればいいのですか?って話しなんですよ。
例えば、その他大勢の9割に合わせた授業をして、1割の子には合わない授業をしているのに、1割の子供の態度が悪いと連絡してくる意味、よく考えてみませんか?
それに親は現場を見ていないでしょう。子供にも理由があるのかもしれないし、先生の力が足りないだけかもしれないし、他の子の迷惑かどうかは、クラスメイトに聞いてみなきゃわからないじゃないですか。(大抵隣の子とかには迷惑になってますけどね)
とにかく、カッとならずに、かといってペコペコ謝らずに、対応をして対策をすれば良し。先生の言う現状をそのまま受け止め、なぜ子供が授業中に立ち歩くのか、原因を探り、先生にフィードバックしましょう。
「迷惑」という言葉に惑わされない
まず、迷惑という言葉は一般的な言葉であり、人様に迷惑をかけるなと言われて私たち日本人は育ちますが、そもそも論で「迷惑」は他人がしたことで不利益になったり不快を感じること。
不利益は大人の解釈だとして、不快を感じるあたりはいじめと一緒ですね。
要は相手がどう思っているかによって、いかようにでも解釈がかわるもの。ハラスメントとかも同じ。迷惑も似たようなものだと思っています。
接する人が迷惑と感じるかどうか。おそらく今回の事で迷惑を感じているのは、対応しなければいけない先生とクラスの友達でしょう。
先生が迷惑だと感じるとしたら、それは先生の問題なので私たち親が介入することではありません。すみやかに撤収しましょう。
友達には迷惑を掛けあって成長していくと思うのですが、おそらく迷惑の度合いが過度になってしまうんでしょうね。
この点は、子供にも教えていきたいところ。自分の行動で、相手が不快に感じることがある。こういうことをすると相手の感情にも関わってくる、ということを知り、どうすれば不快じゃないのか、どうすれば良かったのかを一緒に考えていきます。
親も自分探しの旅状態です。自分のスタンス、信念を貫きましょう。
子供が本当にやろうとしていることを知る
では、本質に入りましょう。
子供はなぜ、授業中に席を立ち歩いてしまうのか、または授業中に何かを触ってしまったり、話始めてしまうのか。
直接子供に聞かないとわからないことなので、子供に直接聞きますが、1回でわからないことが多いと思っておいた方がいいです。
その際、子供が何を言ったとしても、例え、常識から外れていても、マナー的に良くないことでも何でも、子供が喋ったことに関しては全て良しとしてください。
子供の感情や思い、そう思って行動したこと自体をまずは否定しないように気を付けましょう。
そして、少しずつ話してくれればいいと思っておきましょう。突然尋問をして、いきなり喋るわけがない。
だって、今までは怒られてきたから。たくさん怒られてきたから、学校でも友達や先生からたくさん怒られ、家でもまたいつも通り怒られる、誰も自分のことなんてわかってくれないんだ、くらいに思っているかもしれませんからね。
子供がやろうとしていることをサポートする
次に、子供が何をしたくて席を立ち歩いているのか、それが叶えられる方向へサポートしていきましょう。
何か見てみたいものを発見したら、放課後にでも親と一緒に見に行きましょう。お仕事をされているお母さんでしたら、連絡帳に書いて先生に知らせましょう。休み時間に見てもらえばいいですね。
子供がやろうとしていることを、固定観念や一般常識で押さえつけず、どこまで「できる」に近づけていけるのか、大人の力量にかかっています。
もちろん、学校ですからできないことの方が多いのかもしれません。でも、始めから「それはダメだよ」「ここは学校だから無理」などと否定しない方がいいと思います。
できないなら何ができないのかを、子供が納得するまで先生があの手この手で説得すればいい。
子供の「なんで?」を「なんでも」と答えてしまうのは最悪。学校内で特に先生はやめていただきたい発言です。
子供がやろうとしていることを子供に伝える
思考の神経が速すぎて、ADHDの特性を持つ本人も認識していないことが結構あると思っています。不思議なところなんですけどね。
子供から聞いた情報を、子供に再度伝えて確認をすることで、子供本人も自分のできるところ・できないところなど、客観的に考えられる脳に変えていくと思っています。
なぜ今できないのかを考える
例えば、授業中、なぜ今立ち歩くとダメなのか、私たちの住む世界にはTPOがあり、TPOをわきまえて生きていく必要があることを子供本人に教えましょう。
「そんなことわかってる」と言い返されても、良く考えてみましょうね。
TPOをわきまえられたら、学校から連絡来ないんですよね。何かあるんです。今できない理由が何かある。
それをきちんと知識として教えてあげましょう。
どうすればできるのかを考える
一番問題なのは、授業中に子供が興味をもったこと、やろうとしていることをどうすればできるのか。ここが一番の難関です。
すぐにできるものならいいんですけどね。お絵描きしたいとか、実は本を読みたいとか。
でもサッカーしたいとかはさすがに難しい。ならばどうする??1冊専用のノートを買って、サッカーの情報をたくさん書いて、自分用のサッカー辞典を作るとか。
虫捕りに行きたいとか、外でやるものは基本難しいでしょう。体育とかは動いているから大丈夫ですよね。席に座っていること、何も触らないこと、大声で話さないこと。
この辺りが可能になるものは何があるだろう。どうすればできるだろう。
そこをしっかりと考えてみましょう。何よりも、目的に向かって自分にできることをやるのは、生きる上で必要なスキルだと思います。
一緒にいて、教えてあげられるうちに、生きる上で一番大事なんじゃないかとも言える、「目的に向かって自分にできることをやる」を子供と一緒にやりましょう。
そんな親の姿をお手本にして、あきらめずに、人のせいにせずに対応すれば、子供も親を見て育つと思いますよ。
授業中だけ別の課題をやらせてもらう
先生はいい顔をしないと思いますが、これが終わったらこれをやる、という何か別の課題があると、うまくいくかもしれません。
公文式の勉強方法が合う子であれば、先取りでレベルを上げた問題のプリントをやってもらえばいいのですが、合わない子は難しいでしょう。
本当は授業に関係のないことをやってほしくないとは思いますが、終わったら本を読んでいてもらうとか、謎解きっぽいクイズをやってもらうとか、ぬり絵的なものをやっているとか。
まずは席に座ってほしいなら、席で座ってやれる興味があるような楽しいもの。制作造形的なものになると他の子もやりたくなるだろうし、ハマり過ぎたら戻ってこないかもしれないけど、それで席を立ち歩かなくなるなら、大声を出さなくなるなら良しとすればいいんじゃないかな。
そんな発想は私だけかもしれませんが、長男は興味がない授業の時はひたすら練消し作りに精を出し、次男は遅れている漢字や計算ドリルをやっています。
一時期は将棋の本を読んだこともありました。それもこれも、先生の理解があったらからできたことですが、他の子の迷惑にはなっていないことは確かです。
何事も1つずつ。段階を追っていけばいいんじゃないかな。小6になった長男は、席で過ごす方法を自分で身につけているので、参加するときは参加する、聞いていない時は席に座ったまま、授業に支障がでない程度に(作業はやる)自由に過ごしているみたいです。
幼稚園・学校・習い事などにフィードバック・配慮依頼
わかったことは小さなことでも先生にフィードバックしておくことをおすすめします。
何のために?それは子供のためにです。子供が本当に悪いことをして怒られる以外で怒られないようにするためです。
もちろん、ADHDの特性があるから、特性を大目にみてちょうだい、ということではありません。本人の意志とは無関係に動いてしまう部分は怒っても仕方がないわけですから、別の対策をしないとね、ということなんですよね。
学校など現場でも試してもらう
できれば学校の先生にも、家で実験したことを試してみてほしいですね。うまくいけば先生のスキルにもなりますし、ADHDの子供のパターンをひとつ理解することにつながります。
理解のある先生なら、やってみてもらえるかもしれませんが、先生にも先生のやり方やポリシーなどがあると思うので、あくまでも提案程度にとどめておきましょうね。
それこそ、やるかやらないかは先生のことですので、こちらが口出しすることではないと思うので。
振り返り|ADHDの子供は迷惑じゃない/発想や思考の速さをうまく使えたら

もし、ADHDの子供の発想を形にすることができる世界があったら、いろんな面白い発見があるんじゃないかなと思います。
頭ごなしに子供を怒るのではなく、子供が何をやろうとしているのかを知り、できる限りのサポートをしてあげているうちに、成長が追い付いてくるでしょう。
小4辺りになれば落ち着いてきますから、それまではなんとか対策で乗り切れるからな。といった感じです。
できるだけ先生と一緒に対策をして、いい方向へ向けばいいですね。


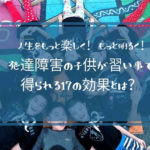

コメント