早期療育が良いといわれる昨今ですが、発達障害の診断は受けるか受けないかはその人たち次第ですよね。
風邪を引いたから病院に行くか行かないかは本人と親の判断。目が悪くなったからメガネをかけるかどうかは本人と親次第。
例えそれがケガであっても風邪であっても重度の障害であっても、医師の診断を受け、その後をどう生きていくのかは、本人とその家族次第だと思うのです。
今回は、発達障害の診断を受けるとどうなるのか、ということを私なりに考えてみました。お子さんなどの診断を受けるかどうか迷っている方の参考になればうれしいです。
発達障害の診断を受けること・受けないことの違いとは

最近では、発達障害も早期療育をした方が良い、などと言われていますが、まず診断を受けるとどうなるのか、受けないとどうなるのか、というところはあまり知られていませんね。
私の見解になりますので、他の方の意見や情報を参考にしつつ、ご自分で判断していただくための参考にしていただければと思います。
【診断を受ける】「発達障害」という診断がつく可能性があるということ
そのままですが。
「風邪」とか「喘息」とか「じんましん」とか。病院で医師の診察を受ければ、診断名がつきますね。
児童精神科で診察を受ければ、「ADHD不注意優勢」、「自閉症スペクトラム」「学習障害」というような発達障害の診断がつきます。
または、発達障害ではないという診断ですね。
診断を受けることでわかることは、ある種の「型」がわかります。「型」というとイメージがわきにくいかもしれませんが、何かしらのパターンですね。
目に見える症状、目に見えない症状、発達障害の場合は成育歴、困りごとの現状などから、医師がどのパターンに属するのかを判断し、診断名をつけます。
医師も人間なので、医師によって診断名が違う場合があるのは、どの病気も大体同じ。インフルエンザのような検査キットで答えがでるもの以外の診断は、医師の判断で診断されますね。
診断名がわかることで、学校の特別支援教室への入級や、療育を受ける判断、療育手帳の発行などに使われます。
また、薬の処方などは医師にしかできませんので、ADHDなどで薬の処方を希望している場合は医師の診断が必要です。
【診断を受けない】「発達障害」という配慮は社会から受けられないということ
社会的な配慮とは、学校の特別支援教室への入級や、療育を受ける判断、療育手帳の発行などを指します。
発達障害でなければ特に問題ではないのですが、発達障害で配慮が必要な子供であれば、公的な配慮(通級に入れない)がない状態で学校生活を過ごすことになりますね。
発達障害の診断がないので、療育センターなどの療育は受けられませんので、心理や作業療法、言語療法などの療育が必要な場合は、受けられないでしょう。
【違い】公的に療育などのバックアップがあるかないか・薬の処方が違う
発達障害の診断を受けるか受けないかの違いは、
- 「発達障害です」って医師に言ってもらうかもらわないか
- 通級に行けるか行けないか
- 療育をやれるかやれないか
- 薬の処方をしてもらえるかどうか
個人レベルでは、その人に合わせた配慮を望み、相手が受けいれてくれるなら配慮はしてもらえるでしょう。
結局、診断があろうがなかろうが、本人は特性を持ち、周りはそれを知りつつ共に生きていくわけですからね。ただ、診断をした方がわかりやすい人もいると思います。
接する人達は、本人の特性や感覚などはわかりませんから、診断があった方がより接し方がわかりやすくなる場合や薬を使用したい場合、医師の診断は有効でしょう。
【花緒論】 診断は第3者に配慮をお願いしたいときにも使える
幼稚園や学校に子供の困りごとについて配慮を求めたいのであれば、親の思い込みや勘違いではないことの証明として医師の診断を受ければ良いと思います。
同じように習い事やベビーシッター、学童などにも使えます。
私が長男の発達障害の診断を受ける2つの理由
- 通級に通いたいから
- 私が特性を知ることで長男を理解でき受け入れられるから
中学も通級に通いたいと長男本人が言っているので、そのために診断を受けます。
そして私が長男と一緒に暮らしていくために、
- 長男の特性を理解したい
- 先を生きてきた方達の方法や対処法を教えてもらい、これからの長男の未来に活かしたい
この2つの理由から私は診断を受ける派です。
【一番の重要ポイント】診断にこだわる前に現状の困り感の度合いが重要

それじゃ、受けても受けなくてもどっちでもいいの?っていう話になってしまうのですが、一番重要だと思うのは、診断を受ける・受けないじゃないと思うのです。そんなお話しをします。
困り感の度合い
まず、現状、何か困っているのでしょうか?別に何も困っていないのでしょうか?
学校で担任の先生から「発達障害の診断を受けた方がいいのでは?」と言われてどうしよう・・・と思っているかもしれませんね。
親子で困っている
親子で困っているのであれば、私は診断に行けばいいのではないかと思います。困っている自覚があるわけですからね。
別に診断に行って仮に「発達障害です」と言われたからといって、明日から生きていけないわけではないんです。
診断を受けた途端、突然高熱が出たりするわけでもないし、倒れたまま動けなくなるわけじゃない。診断するってそういうことじゃない。
よくあるパターンが、「発達障害です」と診断されたら、
- 進学に影響が出るのではないか
- 就職が不利になるのではないか
- いじめの対象にされるのではないか
と心配して診断に行かないパターン。
夫婦のどちらかがこの考えを持っていて、診断に行けずにいる。でも行った方がいい気もして悩んでしまうのでしょう。
親だけ困っている
もし困っていることに対処していきたいと考えているのであれば、相談先を見つけて相談にいきましょう。診断を受ける・受けないを含めて、専門家に相談にのってもらうといいと思います。
子供だけ困っている
親が「子供なんてそんなもの」と思っているが、実は子供は困っているパターンです。
学校の先生から子供が困っている話をされたら、親の固定観念で「そんなもの」とはねのけないで、一度先生の話を聞いてみましょう。
すぐに納得のいくことではないかもしれませんが、子供が困っているということは現実です。子供から直接聞いてもいいですし、先生から聞いてもいいと思います。
その話に納得がいかなければ、スクールカウンセラーのところへ相談にいきましょう。学校での様子を見に行ってくれますので、より親にわかりやすく説明してくれると思います。
先生だけ困っている
先生だけ困っていて親子で困っていない。学校の先生に「発達障害の診断を受けに行った方がいいのでは?」と言われたけど、「なんで??」と受けに行かない。けど先生は何かに気づいているパターン。
親子が困っていないから、診断を受けるモチベーションが見つかりませんね。
早期療育がすすめられる理由と診断を受ける・受けないの影響
100歩譲って、困っているのが親だけならいいんです。先生などの大人だけが困るなら100歩譲っていいとしよう。
でも子供の場合はどうなのでしょうか。
- 困っているのに困っていることに気づいていない子供
- 困っているのに何て言ったらいいのかわからずに止まっている子供
- 困っているのに声をかけられなくて周りを見ながら必死に合わせようとしてるけど合わない子供
これは全部長男のことなのですが、幼稚園や学校の教室で、自分の子供がこんな様子だったら、親として何を思い、何を感じるのでしょうか。
今の困りごとが子供の未来に影響するかしないかは、診断を受けるか・受けないかではなく、今、困り感に対処するか・しないかの差だと思います。
これが早期療育が必要だと言われる理由かなと思っています。

早期にこだわる必要はなく、高学年でも中高生でも大人でも、気づいたとき、やろうと思ったときにどう対処していくのか、ということでしょうね。
結局どうしたいのかをはっきりさせる
結局のところ、困りごとに対処していきたいのか、今はそのままでもいいと思っているのか、そこの目標設定によっ診断を受ける・受けないが決まってくると思います。
そして、どう生きていきたいのかは、親子と家族の問題であり、おせっかいに口を出すことでもないかなとも思っています。
どこで?どうやって?発達障害の診断を受ける手順
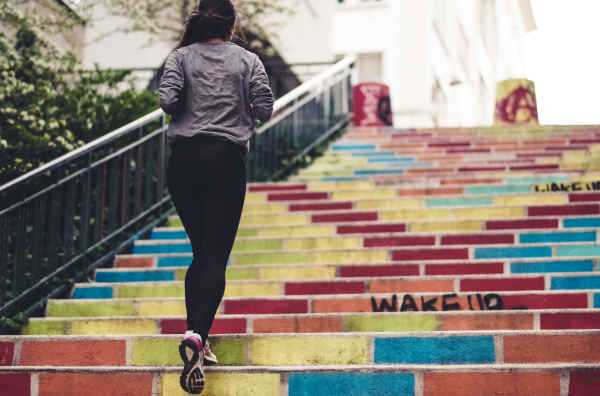
では、実際に発達障害の診断を受けるとしたら、どのような手順で受けるのか、いくつかのパターンをお話しします。
あと診断書をもらう場合は(就学相談などで使う)別途診断書作成料金がかかります。さらに診断書はすぐにはできないので、後日引き取りに行くか、郵送になる場合が多いです。
学校に相談→病院へ予約→診断
担任の先生に相談してみましょう。診断を受けたいと相談すれば、その後誰に相談すればいいのかを教えてくれます。
病院への予約はおそらく自分でやると思うのですが(ごめんなさい、私はこのパターンじゃないのですが、一番オーソドックスなパターンです)、あとは各学校や担当の先生により、違いがあると思うので、先生に相談してみてください。
相談機関→相談→病院へ予約→診断
保健センター、教育センター、などの相談機関に相談します。相談員の方が、病院のリストや候補を絞ってくれるので、行く病院を決めて自分で予約します。
その際、相談期間からの紹介状をもらうことができるので、紹介状を持って診断にいきます。予約から診断までは病院によって違いますが、うちは半年くらい待ちました。
直接病院へ予約→診断
おそらく、どこかしらの紹介状が必要になると思うのですが、もしかしたら直接病院に予約できるかもしれません。
発達障害の外来がある場所でしたら、予約のみで受けられるかもしれませんので、問い合わせてみましょう。
ただし、病院の情報を自分で集める必要があるので、心配であれば相談機関へ相談してから病院予約をした方が安心です。
かかりつけ小児科→紹介状をもらって予約→診断
かかりつけの小児科に育児相談をして紹介状をもらう方法です。また、提携の病院がありますので、そのまま紹介してもらうこともできます。
受けないパターンの対応と手順

では発達障害の診断を受けない場合はどう対応していくのかを考えてみます。
困ごとへの対処はしない→その後はわからない
特に必要性を感じていない場合は、診断も受けず、対応もしないという判断もありますね。そういう選択もあると思います。
困りごとに対処する
診断を受けなくても困りごとに対処していくことはできます。泣いている→抱っこするみたいに。
第3者に相談する→相談先からアドバイスをもらって対処
相談に診断は必要ありません。スクールカウンセラーや教育相談など、お住まいの地域で利用できる相談先に相談してみましょう。
そして、アドバイスをもらいながら、できる対処をしてみましょう。
対処をするしないは置いておいたとしても、困っていることを相談できる人がいる、というのは心強いものですよ。
自分でなんとかする→本やワークをフル活用→様子をみる
何が何でも絶対に自分でなんとかしたいのだ!という方は、次の手順で進めてみてはいかがでしょうか?
- 困りごとを親と子供で分けて書き出す
- その中で1番困っていることの対処法を調べ、実践
- 実践している期間に困りごとが書かれてある対処法を本やネットで勉強する
- 勉強した対処法を少しずつ実践(2つくらいずつがおすすめ)
- 様子をみて試行錯誤
通級とかに通わせるつもりがないのであれば、正直、診断がなくてもできることはたくさんあります。
【注意するポイント】
困りごとの対処をしていても、うまくいかない事があると思います。でも、夜泣きの対処や癇癪の対処に困っている親も、同じように試行錯誤しているのです。
どうしても診断を受けたくないが、困っているから対処はしたい、というのであれば、ガッツリと本やワークブックを、ネットの情報をフル活用してみてください。
それでも困りごとの対処がわからない場合は、今一度、診断を受けるかどうかを考え直せばいいのです。人生、柔軟に考えて、臨機応変に対応していけばいいと思います。
発達障害の対応がわかる本3冊と超優秀なワークブック3冊
自分で頑張る人を応援する本とワークブックを載せておきます。
【本】俺ルール!自閉は急に止まれない/ニキリンコ
ASD傾向の対応におすすめ。自閉症の世界は生きづらさがある反面、才能の塊だとこの本を読んで思います。
【本】「ズバ抜けた問題児」の伸ばし方/松永暢史
ADHD傾向の対応におすすめ。いわゆる困ったことに対応するというよりは、ADHDのいい方面に気づくといった内容。発達障害ってマイナスばかりじゃない、逆にプラス部分が大きいなと思います。
【本】ケース別発達障害のある子へのサポート実例集(小学校編) 発達障害を考える・心をつなぐ/上野一彦
実例集は支援するたくさんのヒントが載っています。子供のケースと全く同じパターンはないかもしれませんが、応用できるたくさんの例が載っているので、参考にしてみましょう。
大切なことは、この実例集を例と考え、いかに子供用にカスタマイズするかです。
【ワーク】実行機能力ステップアップワークシート 自立に向けてのアイテム10/NPOフトゥーロLD発達相談センター
いろんなワークを探してきましたが、びっくりする程使えると思ったワークブックです。使えると思ったポイントは、生活に密着した課題を実際にやってみること。
例えば、自宅から最寄の駅まで歩いて何分かかると思いますか?という問いの予想を立て、実際に歩いてみるんです。
何が分かるかっていうと、自分の予想と実際の時間の違い。
思っていたことと違うことが起きるとパニックを起こす自閉傾向がある子供や、そもそも考えるより実行しているうちに寄り道をしてしまうADHD、そもそも論で予想を立てる意味がわからない、といったわりと広めの困りごとを解決していく訓練ができます。
超優秀なワークブックですが、難点は2つ。
- 小学校高学年以上じゃないと、実践できない内容になっている(以上、大人まで使えます)
- 1つの課題が終わるまでに時間がかかる(全部ではありません。)
先程の駅まで歩くパターンは、1ページの課題の1問。他にもありますので、そうすると1時間くらいかかる場合もあるし、5分で終わるものもある。
実際にやらないと時間がわからないという難点を考えても、いずれ、このワークをやった方がいい日は必ずやってくると思います。
【ワーク】SSTワークシート(自己認知・コミュニケーションスキル)あたまと心で考えよう/LD発達相談センターかながわ
たぶん、療育の心理とか、通級とか、道徳の授業とかで使われているかもしれない雰囲気があるワークブック。
大人も答えに迷うような深い問題もあります。字がよめて文章が理解できれば、子供一人でもできるので、家庭で一番使いやすいSSTの教材かなと思います。
何が正解なのかをはっきりさせるというより、子供の物の見方や考え方、思考を理解するためにも私は使っています。
目的別に他にもあります。
漢字の基礎を育てる形・音・意味ワークシート(1(空間認知編)) 点つなぎ・図形模/発達支援ルームまなび
漢字が苦手な子供用。まずは空間認知訓練のための、点つなぎ。
これができたら、字が書けてカタカナが書けて漢字が書けます。たかが点つなぎ、されど点つなぎ。漢字を書くってそういう事なのかと思った1冊。
続きもあります。
振り返り:診断のメリット・デメリットを知り発達障害を受け入れる

一般的には発達障害の診断は、できるだけ早く受けて、早期療育をやるべき、という流になっている気がしますが、人それぞれの選択で決めていけばいいだけのこと。
親子の困り感に合わせて、必要になった時に診断を受ければいいのではないでしょうか。
大切なことは、診断するしないということではなく、困りごとにどう対処するかですからね。
通級や療育を受けたいなら診断する選択をし、特に公的な療育を受ける予定がないのであれば診断をうける必要ないでしょう。
ただ、発達障害なのか違うのか、診断した方がいいのかしない方がいいのか、など、悩んでいる時間が長くなってしまっているなら、私はサクッと診断しますね。時間がもったいない。
事実を知っている方が動きやすいこともあるでしょうし、その結果からまた、いくらでも自分の望む方向に、人生を仕切り直せますから。

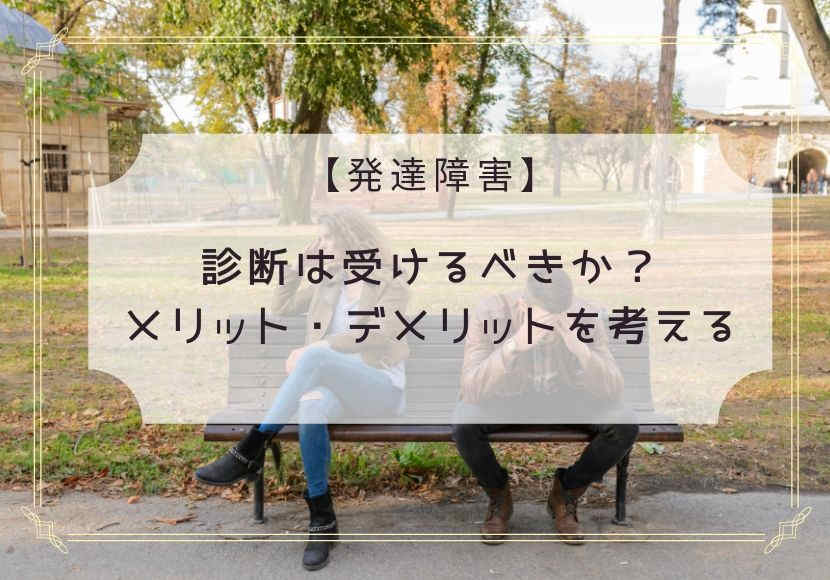





















コメント