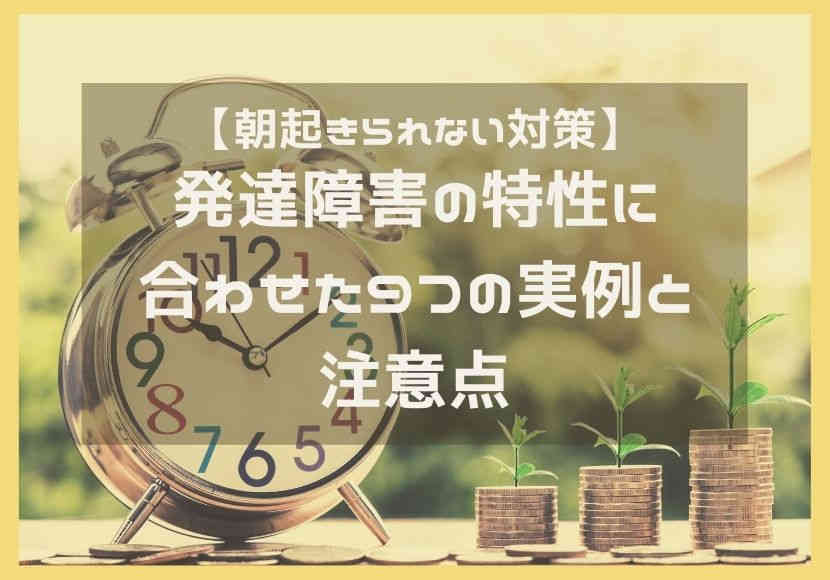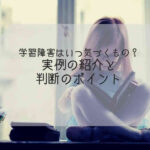発達障害の長男は、朝起きられないことが多々ありました。
長男の場合は、夜寝ないから→朝起きられないというパターン。
これから紹介する実例は、発達障害で寝なくて起きなかった長男のために、実際に私が試した対策です。
うまくいったものもうまくいかなかったものもありますが、中2になった現在では、ほぼ困っていないレベルになりました。
発達障害の子供が、朝起きられない、と困っている方の参考になればうれしいです。
発達障害の特性に合わせた朝起きられない対策実例

朝起きられないことは、発達障害だから起きられないわけではないと思います。
しかし、特性により、夜寝られない、夜中に起きてしまう、など快適な睡眠を取れていない可能性は考えられますよね。
何をやっても慣れてくると効果はなくなるもので、手を変え品を変え、試してみた方法です。(幼稚園くらいから中2まで)
朝はどのように起きたいかを確認
子供は、こんなこと、全く考えないとは思いますが、
- 起こされ方(自分で・親に起こされて)
- 起きる方法(目覚まし時計・親の声・音楽)
- 目覚めた後の時間の過ごし方(すぐ起き上がる・ぼーっとする・本を読む)
など、どんな風な起き方に変えれば、起きられそうか?ということを子供と一緒に考えてみます。

このとき「自分で起きてよね」というスタンスは出さないようにしました。
あくまでも、
そのために、子供が親に頼みたいことがあるなら、サポートするためです。
子供が自分で決めた方法を、実践し、成長や発達により合わなくなったら、別の方法に更新する、というやり方です。
これにより、長男は、
と考えました。前記事で紹介した通り、朝時間をお楽しみ時間に変えることで、起きれないを脱出できました。
寝る環境を徹底的に整える
寝る環境は、家庭の事情により、なかなか私の希望通りにいかなかったのですが、引っ越しを機に実現。
- 人との共有が嫌なので1人用布団にした
- 苦手な肌触りがあるので、シーツ系は綿かフリース
- お腹が弱いので、常に暖められるよう、専用布団乾燥機を購入
- 人の生活リズムに影響されないよう個人部屋にした
- 蛍光灯が苦手なため、本人選択の照明に変えた
以前は、私と長男次男が一部屋で寝ていたので、全てを叶えることはできませんでした。
私や次男は問題ないけど、長男は無理、となると、いろいろとお互いに不都合があったのです。
環境が整ったことも良かったのか、寝る時間も以前に比べて平均すると早くなり、朝起きる時間も圧倒的に早くなりました。
この本を読んで、寝る環境をきっちりと整えることで、日中のパフォーマンスを保てることを改めて感じました。漫画と本と両方ありますが、どちらも読みやすくて2冊持っています。
決めた時間にガジェット類を全ストップ
例えば20時になったら、テレビもスマホもパソコンもすべてやめてみる。
そうすれば、刺激がなくなっていきますから、寝る環境にはなっていきますね。
まあ、なかなかですが、うちはガジェット使用は基本21時まで。
金曜ロードショー観たいとか、ゲームの大会参加したい、などてイレギュラーなこともありつつ、基本は21時でやめることが家族のルールです。
1番守れていないのが、私という・・・
スマホやiPadなどのポータブル系は難しいですが、コンセントから電源を取っている系はタイマー付きコンセントで強制終了もアリですね。
また、ゲームをやめずに困るときは、Wi-Fiを切っちゃいます。それでもやめなければ、パスワードを変更しようと目論んでいます。
生活習慣の見直し
眠れない、起きれない、というのは、生活習慣の一環ですから、困りごとがあるなら見直しが必要です。
食事の内容や日々の運動、お風呂の時間などさまざまなパターンを試してみて、かなり理想に近づいてきたと思います。
見直したことは、以下の4つ。
- おやつを果物に変える
- お風呂は20時過ぎ
- 21時でガジェットストップ
- 22時就寝
食べ物は砂糖を極力少なくするようして、寝る時間にちょうど体温が下がるよう、お風呂は夕飯後に。
21時でガジェットをストップするのは先ほどお話した通りで、22時に就寝。家全体の電気が消えるようにみんなで協力しています。
寝るときに絵本を読んであげる
定番ではありますが、絵本を読んでもらいつつ、自然に寝てくれたら・・・と思い試しましたが、逆に覚醒して何冊も読まされることになったので、止めました。
好奇心が旺盛なADHDタイプの子には難しいかもしれませんが、一般的には絵本を読みつつ寝る子は多いと思いますよ。
ストレッチや瞑想をしてみる
簡単なストレッチや瞑想をすることで、これから寝ます、というルーティンが作れます。
長男はストレッチをあまりやりませんでしたが、瞑想は結構効果がありました。何せ、目をつぶりますからね。時間にして10分。短いようで結構長いです。
私も一緒にやっていましたが、長男はそのまま寝るパターンが多かったです。
これも慣れちゃうと全然寝ないのですが、それでも一定の時間、動かず喋らず座って目を閉じるというのは、ある程度、心が落ち着く時間になってはいたのかなと思います。
さらに次男は、ストレッチも瞑想もどちらもやっていましたね。瞑想は土日の昼間に、ストレッチは寝る前にやっていました。今でも気が向けばやっています。
YouTubeでやっているお気に入りのストレッチを見つけて、一緒にやることで、続けられていました。
寝る前に瞑想をやると、そのまま寝てしまうことがあります。一時期、長男は寝る前の瞑想で寝ていました。
やっぱりなんだかんだ言っても日中動き回っているわけですから、疲れているんですよね。あぐらをかいて目をつぶって、親指と人差し指で印を結ぶだけ。
嫌がる子はダメでしょうが、やれる子はやってみるといいかもしれません。
スーッと寝られる、早い時間帯に寝られると、朝の寝起きは良くなるはず。おそらく。
音楽や照明などをつけて寝てみる
寝る前の音楽や水や波の音、みたいな自然の音ですね、そういう音楽や音をかけつつ、寝てみるのもいいでしょう。
歌ってしまわないのであれば、音楽を聴いて寝てもいいのですが、逆に覚醒してしまう可能性もありますので、インストのようなものがおすすめ。
YouTubeやアプリでもいろいろありますし、Amazonのプライムミュージックにもたくさん寝る系の音楽がありますので、試してみてもいいですね。
プロジェクターを寝る前に使う最大のメリットは、電気を消さないと使えないこと。うちにもありましたが、結構いいものですよ。
ただ、若干、楽しくなってしまう可能性も考えられますので、子供の興味によりけりではあります。
本格的な星座verもありますし、他にもいろんなタイプのプロジェクターがありますので、興味がある方は検索してみてください。
子供と一緒に寝てしまう
私が起きていると寝なかったので、一時期、子供と一緒に寝てしまうようにしてみました。
なんといっても、自分が一番よく眠れるのですよ。
21時22時という時間帯に寝るなんて、大人になってからはほぼ皆無ですからね。
さすがに家が暗くなってしまえば、子供も寝るしかなく、早めに寝られたら早く起きられるという、良き循環に変わっていきます。
【超スパルタ対策】いっそ起こさない(マジで遅刻させる)
恐ろしいかもしれませんが、起きなかったことで本当に遅刻してしまう、という経験をさせました。
長男は2回ですかね、、、。
小学生と中学生で1回ずつだったと記憶しています。
これも時間が経つと忘れてしまうようなのですが、少なくとも起きないと遅刻になる、という経験にはなっています。
配慮を求めるだけではなく、子供本人の意識を変えていくことも、社会で生きていくうえで必要なスキルだと思いました。
【注意点】発達障害の子供の特性を無視した対策は意味がない
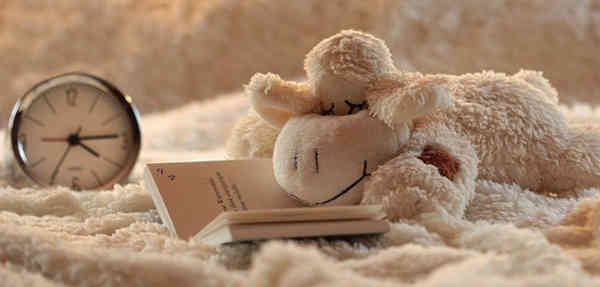
4歳あたりから中2まで、発達障害の長男の子育てで感じたことは、特性に合わせた対策は必須であるということです。
当たり前だと思われるでしょうが、療育がうまくいくと、特性による困り感が減ってきて、そのうち忘れてしまうんですね。
しかし、特性部分がなくなっているわけではないので、忘れていると何かしらの機会に困りごととして出現します。
やっぱり、基本を忘れずに対策を進めた方が、最終的にうまくいくなと思いました。
感覚的に苦手なものは使わない
五感に苦手な感覚がある場合、避けられるものは避けました。
寝る環境ですから、安心第一。感覚的に苦手なものは極力避けていきます。
必ず事前に予告してから対策を始める
誰でも同じだと思いますが、予告された方が安心ですよね。
発達障害の人との接し方としては定番でもある「予告」。基本、長男への対応や対策には必ず予告と声掛けがセットになっています。
起立性調節障害の可能性も考えてみる
長男はまだなったことがありませんが、朝起きられない場合、「起立性調節障害」の可能性がありますので、あまりにも起きなくておかしいな、と感じた場合は病院を受診した方がいいと思います。
小児科や児童精神科、心療内科など、子供の年齢に合わせて受信する、もしくは学校の先生方に相談すると病院の紹介や対応などの相談にのってくれると思います。
「失敗させない」だけが支援ではない
早めの療育、家でも学校でも配慮され、支援されることが当たり前だと、失敗することが少なくなっていく気がしました。
特性により、うまくいかないことばかりになると、自己肯定感が下がってしまいますが、人間、失敗からしか学べないこともあるわけですね。
親側が、特性に合わせた対策や配慮を一生懸命やっても、子供に全然響かないな、と感じた場合は、親が一緒にいられるうちに失敗させることも体験の一つとなるでしょう。
長男の場合は、朝、どうしても起きなかった場合はそのまま寝かせておき、遅刻させました。一応、予告はしておきますが、やっぱりドンと失敗すると、意識が変わりますので効果はあります。
ただ、寝坊したからもう行かない、というタイプの子の場合は、逆効果になるかもしれません。
成長や発達によって変わっていくこともあるかもしれない
長男の場合だけかもしれませんが、幼少期は特に、成長や発達によって、寝ることも寝起きも、違いがあるような気がしました。
安定しているときは夜も割りと寝て、寝起きも良いのですが、切り替えの時は寝たり寝なかったり、起きたり起きなかったり、ということが頻繁にあったと記憶しています。
王遅延に入る前までくらいは、4か月~半年くらいで何かが変わっていた気がしました。
朝を怒られる時間にしない
朝から怒られてしまうと、一日が憂鬱になってしまうので、朝の時間ができるだけスムーズにいくように改善を重ねました。
その効果もあり、朝から私がイラつくことはほぼなく過ごせています。
幼少期は大変だったな、、と思い出しますね。本当に大変だった。怒ってばかりでした・・・。
怒る前にできることがあると思いますので、今、子供が起きないことで困っている方は、日常を見直してみるといいかもしれませんね。
振り返り:発達障害の特性に合わせた対策で朝起きない状態を卒業できる!

朝起きられない子供に対する対策と注意点について、発達障害の長男に実際に行ってきたものをご紹介しました。
いろいろな本を読み、長男の特性に合わせた勉強から考えた対策。地味に頑張ってきた結果、現在は、朝起きないという状態ではなくなりました。
発達障害の特性に合わせた対策をすることで、朝起きられる確率は上がっていくと思います。
また、子供が朝時間の過ごし方に納得することで、すんなり起きられるようになるのかもしれません。
長男のパターンではありますが、何かお役に立てたらうれしいです。