こんにちは!子育ての試行錯誤をしていくうちに、論理思考が身についた花緒です。子育て中のイライラ、気力の低下、子どもがかわいいと感じない、うつ病になりそうなどのストレスも、論理的に考えていくと解消方法がみつかるかもしれません。今まで考えたことがなかった方は、一緒に考えてみましょう。
今日の質問:子どもに振り回されて自分の時間が取れません。どうやって自分の時間を作っていますか?

私も疑問でした。一体、何をどうすれば自分の時間が取れるのか、さっぱりわからなかった。
子どもが小さいと、一つ一つの対処と家事に時間を取られているうちに、夜になっちゃうってことがとても多かった気がします。
自分の時間を取りたくて、少しでもちょっとでもいいから「リラックス」というものをしてみたかったけど全然うまくいかなくて、結局、あきらめたときに時間ができました。
何をあきらめたのかというと、
- 子どもを寝かしつけなかったこと。
- こちらの都合でご飯やお風呂など、無理に子どもを動かそうとしなかったこと。
- 家事も必要最低限にしたこと。

え??って感じですよね。それで大丈夫なの??ってなりますよね。
結果、全然大丈夫だったのですが、私もあきらめがなかなかつけられなくて、「まあ、いいや。」と思う度に先行きが不安に感じて超心配になりました。
長男3歳、次男1歳の頃です。
こだわりが強くて、朝起きたときからブロックを積み続ける日々で、ご飯や外遊びやお風呂や買い物で、いちいち切り替えがきかない長男と、まだ歩き始めたばかりの次男を抱え、日々奮闘していました。
何かが違うと感じていた長男の育児について、発達障害の相談に行く前あたりは、とにかく次の行動に移ろうとする度に長男とバトルになり、私も精神的に追い詰められていました。
そんな時、なんか全てがバカバカしくなってきて、「もういいや。」って思ったんです。でも母親をやめて、子どもを置いて出て行くなんてできないし、そんなことをしたいんじゃない。
朝起きたら着替えをして、ご飯を食べて、公園で遊んで、お昼寝をして、おやつをたべて、絵本を読んだりちょっと遊んだり、買い物に行ったり、お風呂に入ってご飯を食べて、夜になったら寝て欲しかった。子どもが寝た後、ネイルをしながらドラマを観たりしたかった。
ただそれだけ。私が思い描いていた子育て生活は、特に変わったことを望んでいたわけでもなく、普通だと思っていたことができないなんて考えもしていなかったから、この普通の生活が全部うまくいかないなんて予想もしていなくて。
あまりに予想外なのに、なんとかこの思い描いていた子育て生活をやろうと思っていて。だってこれが子どもがいる生活だと思っていたし、最低限ご飯の時間にご飯は食べたいし、お風呂にも入りたかったし、洗濯とか掃除とか料理とかも、要領は悪いけどそれなりにできると思っていたのです。
ぜーんぶうまくいかないから、何をやってみてもうまくいかないから、「もうどうでもいいや」と思ったのでした。
- お腹がすいたらご飯を食べるだろう。
- 眠くなったら寝るだろう。
- 服も着替えなくても死なないか。
- 公園も行かなくていいや。
- 掃除も洗濯もできるだけでいいや。
超なげやり。生活習慣をつけるとか、ご飯のマナーとか、おしゃれな服をきてお出かけしている雑誌の中の親子とか、ちゃんと手をつないで散歩をしている親子とか。もうそんなのどうでもいい。

今日、生きてればいいや。今日、死ななきゃいいや。って思ってました。
そしたらね、なんか不思議なくらいに力が抜けて、長男も私も自由で、ゆっくりできたんです。ネイルもできたし、ご飯も食べれたし、お風呂も入れたし、意外と洗濯も掃除もできました。ちょこっとだけだけど。
時間を決めて、何がなんでも親の都合で動かそうとすると、テコでも動かなかった長男が、自分で行動を選択するだけであっさり動いてくれました。
もちろん、寝る時間もご飯の量も時間も不規則になるし、兄弟がいると影響を受けてしまうから、あまり良くないのかもしれません。
ただ、もういいやって思えなかったら、私は間違いなく精神的におかしくなっていっただろうし、子どもにもいい影響はなかったと思います。
「母親が笑っていないと」「子育てを楽しまないと」「もっと気楽に」みたいな表現を軽々しく言われても、誰でも気楽に笑って楽しい子育てができるとは限らないんですよね。余計プレッシャーかかるから、そんな助言、マジでいらない。って何度思ったことか。
もちろんそれは、私の性格や気質の問題もあるでしょう。周りの人達からの様々な言葉や、世間体のようなものも影響しているでしょう。子育てに関する固定観念もあるでしょう。
でも、育てにくい子ども育児のストレスを抱えている親がいるってことは確かで、そのストレスをどうにもできなくなっている人がどこかにいるのも確かです。
育てにくい子どもが理解されにくいのと同じで、育てにくい子の親の、子育てストレスも理解されにくいと私は思っています。
要するに、自分自身が最大の味方になるということ。逆に言うと、自分以上の味方はなく、自分でストレスの対処ができればわかってもらえなくても大丈夫なわけですよね。
どうでもいいや時代に偶然出会って、長男の偏食に悩んでいた私を救ってくれた奇跡の1冊。

パンとか牛乳とかあれだこれだと食べなくても、ご飯・味噌汁・魚・漬物でOK。親がいろいろ食べさせようとしなくても、必要な栄養は自分で食べるよ的なことが書いてあって、本当に救われました。
米とみそ汁と魚だけは食べていたけど、パンとかレバーとか牛乳とか一切食べなくて、野菜も食べるものと食べないものとあったんだけど、この本読んでから毎日同じご飯でもいいやと思えるようになりました。
ストレスの感じ方は人それぞれ。だからこそ、自分でストレスの本質にたどり着くことが解消の糸口かもしれません。そんな人たちに、ヒントになる考え方をお話ししていきたいと思います。
本質にたどり着く力をつける
_本質.jpg)
前置きが長くなってしまいましたが、本題に入ります。
まずは子育てストレスの原因を考えてみましたので、参考にしてみてください。
原因がわかったら、子育ての何にストレスを感じているのかをしっかりと見極めていきましょう。
- イライラする
- やる気がおきない
- 子どもがかわいいと感じない
- うつ病になりそうな気がする
このような症状は、ストレスの表面に見えているものであって、本質ではないですよね。根本の原因を知り、対策をすることで表面に見えるものが変わってくると思います。
人の情報に流されず自分で判断し決めて行動する力をつける
ネットで調べた情報、人から聞いた情報、本で調べた情報を使う場合は、そのまま試してみるのではなく、まずは自分と子どもの場合ならどうなるのかな、と考えてみましょう。
「カスタマイズをする」と言った方がわかりやすいでしょうか?
自分や子どもに当てはまるのか、当てはまらないのか、少し変えてみればうまくいきそうなのか、など自分流に変換してみましょう。もちろんそのまま使えそうなものがあれば、そのまま試してみても大丈夫です。
なぜこんな面倒なことを提案しているのかというと、自分の情報ではない他人の情報をそのまま試してみてうまくいかなかった場合、ネットの情報が悪かった、聞いた情報が悪かった、やっぱり自分にはうまく出来ないのかもしれない、など人や物のせいにしたり、自己肯定感を落としてしまう可能性があるからです。
そして、人の情報を鵜呑みにしてしまうと、情報に流されてしまうこともあるからです。自分の行動は自分で判断し、考え、自分で決めてみましょう。
体調不良になる前に!子育てストレス解消のための理想論
_人形.jpg)
子育てストレスは、子どもをうまくコントロールできないことが原因となっているかもしれないというのが私の考えです。ということは、コントロールしなければ子育てストレスは解消するのかもしれませんよね。
完全にコントロールしないことは現実的ではありませんが、まずは理想論から考えてみたいと思います。
理想の子ども像を捨てる
まず、私たち親が持っている理想の子ども像を捨てましょう。これから先の学校生活、社会人生活など、子どもの未来について理想の通りの姿にしようと、今、焦るのをやめ、今の子どもの姿に注目してみましょう。
子どもが何を見て、どんな事を考え、行動を取っているのか、よく見てみてみましょう。
未来への不安を捨てる
理想の子ども像を捨てたら、未来の不安も捨てましょう。正直、今、子どもの未来に不安を持っていたとしても、たぶん親にはどうすることもできません。もし、親の不安を解消するために、今、子どもを叱咤激怒するのであれば、それは子どもの問題ではなく、親の問題ですよね。
ただ、とても不安ですよね。常に子どもの未来を考えて、今、何をさせるべきなのかを考えてしまいますが、一旦お休みしましょう。メンタルが安定すればいくらでも健全な未来を夢見ることができると思います。
これまでの子育て固定観念を捨てる
- 子どもは○○しなければいけない。
- 親は○○じゃなければいけない。
この類のことを考えることは一旦やめましょう。子育てに関する固定観念は四方八方から飛んできます。一度全て忘れてしまいましょう。
子どもをコントロールしない
理想論なんでね、子どもをコントロールしないつもりで考えてみましょう。とはいえ、コントロールしないなんて無理なのでは?と思うかもしれませんね。
「コントロール」というのは、どちらかが指示をだして、どちらかが従うという関係性にありますが、「共生」というような感じにイメージを変えてみてはいかがでしょうか?
例えば、夜泣きで泣いている赤ちゃんをどうにかして泣きやませようとしてもこちらの思い通りに泣き止んでくれるわけではありませんよね。泣き止んで欲しいと望んで、泣き止むであろうと期待してこちらが動いてしまうと、思い通りにコントロールできなかったことでストレスを感じてしまいます。
でも、どこか痛いのかな?音が気になるのかな?肌寒いかな?お化けが見えているのかな?何か不安なのかな?と泣き止んでくれることを望むというよりも 原因を探ることで、 泣いている原因の本質がわかることがあります。
子どもも親もお互いに上辺に見えているところで翻弄されるのではなく、本質をしっかりと見て行動してみようとするだけで、いつもと違うものがわかってくるかもしれません。
買い物や食べ物でごまかさない!子育てストレス解消法(実践編)
_食べ物.jpg)
ストレスが溜まってしまうと、どうしても衝動買いをしてしまったり、ストレス食いに走ってしまうこともありますよね。私もお腹いっぱいになるまでグミを食べ続けたことがありました。
後から後悔してしまうこの種のストレス解消は、結局、根本が改善されないので本当の意味でのストレス解消にならないわけです。
そこで、徹底的に原因を探り、仮説を立て、実験&検証をすることで、次の改善へつなげていくことで、この種のストレス解消をしなくてもよくなりました。
子どもを知る事ができ、現状を把握することができ、親の自分に何ができるのかがわかるため、子どもを理解し、一緒に問題解決をすることができます。意外にも自分の思い過ごしだった、なんてこともあるかもしれません。
そうは言っても結構面倒なのでは?と思うかもしれないですね。
その通りです。とても面倒な上に結構大変です。時間も取られます。必要であれば多少の費用もかかるでしょう。
一緒にいる時間にやることなので、お仕事をされていてももちろんできます。もし、お子さんに振り回されていて嫌だと感じていたり、育てにくくて本当に困っていると感じているのであれば、いずれかのタイミングで同じようなことをやらなければいけない日がきますので、一度はチャレンジしてみることをおすすめします。
無駄なストレスを感じなくても良くなることは確かです。一番の子育てストレス解消法だと思います。しかも本質からしっかりと対応するので、人からの情報に振り回されることもありません。時代の流れも関係ありません。
子どもの才能に気づくこともできますし、ストレス解消にもなるので、体調不良になってしまう前に一度参考にしてみてくださいね。
子どもを観察(統計を取る)
育てにくい子どもシリーズのストレス対策でも書きましたが、まずは現状把握からです。
あれこれと言う前に、子どもがいつ、何をしているのか、何を見ているのかを観察していきます。
2.場所
3.行動
4.付属情報(対策と結果など)
私は子どもが行動を切り替える様子を見ていました。何で遊んで次に何をしているのか。親の姿を見ているのかなど、自分流の記録をしていきました。
フォーマットは何でもいいのです。大体、こんな行動をしているとか、こんな動きをしているとか、意外と細かいところを見ているとか、割と気づきはあると思います。また、言わなくてもやっていることもあると思います。単に親が先に声を掛けてしまっていたんだと気づくこともあるかもしれません。
最低2日位の記録があれば、仮説を立てることができると思いますよ。
仮説を立てる
観察した記録をもとに仮説を立てます。仮説は、年齢や困りごとによって変わってくるとは思いますが、例えば『親が声を掛けなくても生活できるのか?』とか、逆に『親が声を掛けたら生活がうまく回るのか?』など、お子さんに合わせて考えてみてくださいね。
注意:危ないことは避けてくださいね。(外出先での実験など年齢によってはとても危ない場合があるのでやめましょう)
・起こしてから起きるまでの時間
・着替えをするのかしないのか
・声を掛けたらすぐにご飯を食べるのか
・声を掛けたら外出できるのか
・言わなくても宿題をやるのか
他
・強制しなくても挨拶、返事はするのか
・会話はどのくらい理解しているのか(年齢に応じて変えてください)
・困っているときにヘルプを出せているか
他
気づくことで、さらに改善する方へ気持ちと行動が向けばOKということです。何回でもやり直せばいいんです。
情報を集める(正しい知識をつける)
認知行動療法とかと同じ種類のヤツですね。子どもの様子から何か知っておいた方が良さそうであれば情報を集めましょう。発達障害やHSC、その他子育て関連の本をたくさん読んでみてもいいでしょう。
海外の子育て、児童心理学なども見てみると結構面白いですよ。

私はフィンランド式が好きだな~

大切なことは、情報に流されないこと。
この癖をつけるだけでも、いろいろと違うものが見えてきて、わかってくると思います。
本人に予告
今まで親がいろいろ指示してくれていたのに、ある日突然何もなくなると子どももビックリしてしまいます。(しない子の方が多いかもしれませんが、HSCの子達は気づいて気を遣ってしまう子もいるので)
何かを始める場合は必ず子どもに予告をしましょう。
私の場合は毎回こんな感じで予告をしています。
どんなに小さい子どもでも、突然禁止されるより、予告をしておいた方が注意も入りやすくなると思います。買い物の前に「○○を買ったら帰ります」とか、「お菓子は買いません」とか、「お店の中は歩きます。」など。
急な予定変更が苦手な自閉傾向がある子どもにも予告は有効です。普段から予告をしておくといいですよ。
実験をする&検証をする
実際に実行します。この期間は、子どもの様子の何を見てもぐっと我慢をして様子をみましょう。但し、危ないことに関しては即注意したり、即ストップして仮説から立てなおしてくださいね。
また、検証しながら実験をしていく方法もあります。試しながら仮説との違いを良き方向へ修正してみるということです。
別に論文を発表するわけではないので、自分の都合のいいように変更してしまって大丈夫です。最低限、ここは押さえておこうというポイントは決めておきましょうね。
改善をする
検証まで終わったら、結果から今後どうしていくのか、何を重点に置いていきたいのかを考え直してみます。
もしかしたら今の生活に必要がないこともあるかもしれませんし、逆に今からやっておいた方があるかもしれません。
要は考え方なんです。子どもの様子をしっかりと見て、都度判断して柔軟に改善していければいいだけなのですが、どうしても過去の固定観念や周りの情報に流されがちなので、本来の子どもの姿をそのまま知るにはこの方法が一番いいと私は思っています。
そのときに親の理想像に合わせて改善案を考えるのはやめましょう。お子さんの様子を見たら、おそらく理想の子ども像に近づけるより、子どもの素質に合わせた方がいいと親の方も気づいているはずです。気づいてなければ気づきましょうね。
本人にフィードバック
結果は本人にフィードバックした方が、より改善に近づくと思います。コミュニケーションが取れる年齢しかできませんけどね。
2歳前くらいから話が通じるようになりますので、フィードバックもある程度は効果があると思います。実験に協力してくれたことにお礼を言ってくださいね。
関係者に協力を仰ぐ
関係者、というと固いイメージがありますが、子どもと接する大人の方へ情報を共有しましょう。もし、関係者の方たちが、理解のない方たちであれば、情報の共有は必要ありません。
保育園・幼稚園・学校の先生方へはお話ししてみてもいいと思いますよ。
振り返り

結局は、子どもと真正面から向き合いましょうっていうことですね。そして、親の都合で子どもを動かそうとするのは止めましょう、ということです。
そんなんで子どもの将来は大丈夫なの?という声も聞こえてきそうですが、意外と現代の親は、子どもの才能に気づいていなくて、逆につぶしてるかもしれないことに気づいてないな、と思うことがあります。
上辺の行動だけ見て、子どもの本心、本質を見てないなってヤツです。その言葉の裏には、行動の裏には、どんな欲求があるんだろう、親に何をわかってもらいたいんだろう、ってイチイチ考えてみた方がいいです。
親が勉強していないのに子どもに勉強しなさいっていうのは矛盾している気がしますし、努力が足りないと子どもに言う前に、親が努力している姿を見せましょうってことです。
子育てストレスは、ある意味、子育てって何だろう?ということを考えるきっかけになっているのかもしれませんね。




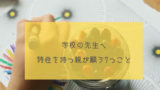

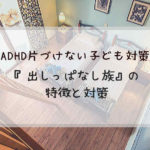
コメント