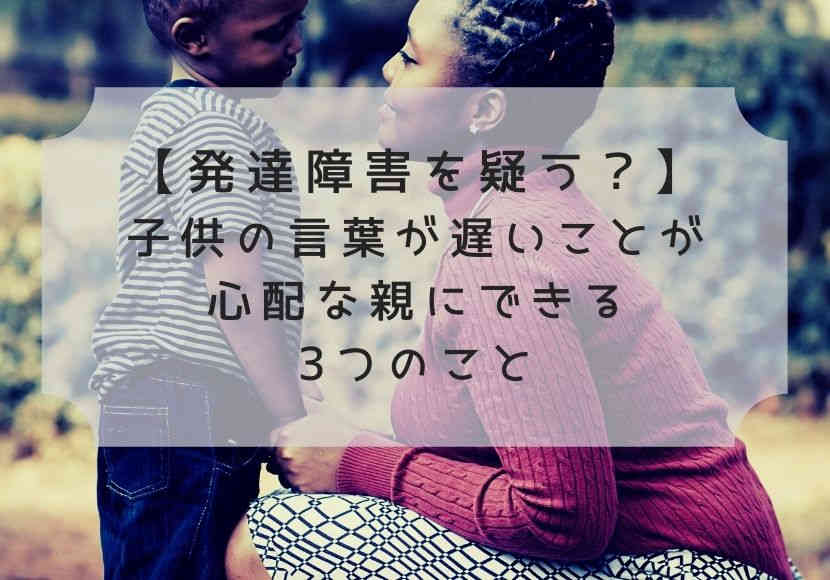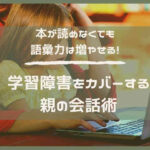うちの子は言葉が遅いのでは?と不安になったことはありませんか?
子供が2歳を過ぎたのに、周りの子供と同じように喋らないとモーレツに心配になってしまいますよね。
特に保育園に行っている場合は、同じ年の子はなんだかたくさん喋っているような気がいて、さらに不安は倍増。
今回は、2歳すぎあたりのお子さんの言葉が遅いことについてお話していきたいと思います。
子供の言葉が遅いことを心配し、発達障害かも?!と思っている方の参考になればうれしいです。
親にできる3つのこと

子育てをしていると、つい友達や周りにいる子と我が子を比べてしまい、発達が遅れなどを心配してしまいがちです。
もしかしたら、うちの子は発達が遅れているんじゃないかしら?発達障害なのかもしれない・・と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
とはいえ、不安になったり心配していても解決するわけではないので、親にできることと言えば、今できることを1つずつ行動に移していくしかありません。
- 事実を明らかにしていく
- 日常生活は今まで通り
- 徹底的に知識をつける
この3つの行動で不安にさらされるだけの日々からは抜けられます。
今わかるところだけでも事実を明確にしていく
つまり、子供を観察して、記録をとるということです。
日記やブログなどに記録を残してもいいでしょう。
わかる事実とは、
- 今、喋っている言葉は単語?
- 返事は?
- 挨拶は?
など、現状子供が喋っている言葉を記録しておきます。
また、親側から話しかけたときに応えるか(オウム返しになっていないか)なども見ておくといいと思います。
ポイントは「共感」できているか、ですかね。
言葉を覚えるとかではなく、同じものを見て一緒にうれしいとか楽しいとか、そういう共感があるかどうかは、発達障害かどうかを見極める上で一つのヒントになるかもしれません。
ただ、若干2歳ですので、そもそも共感が親子ともにわからないというのもあります。
感覚的なことですので、人それぞれだとは思うのですが、もう少し大きくなってくると、この辺の共感が感じられないな、ということが、会話が成り立たないな、と感じることにつながる気がしています。
日常は普通に子育てをする
言葉が遅いと感じているからと言って、あえて言葉を教え込む必要はないでしょう、
年齢的に「気にしすぎ」ということも考えられますので、日常生活はいつも通りでいいと思います。
- 読み聞かせ
- 会話などのコミュニケーションをとる
- 日常の生活や良し悪しなどはきちんと教える
この辺りは押さえておくといいでしょう。
テレビやスマホに子守をさせる時間があっても構いませんが、動画やゲームの日常は言葉が遅くなる原因にもなりかねません。
目を見てコミュニケーションをとり、共感することの喜びを感じられる時間を過ごすことで、「伝えたい!」という思いをはぐぐむきっかけになると思います。
徹底的に知識をつける
なんとなく周りの子を見て、自分の子と比べる、というのも発達や成長を知る上で一つの方法だと思いますが、子供の成長や発達についての知識をつけておくと安心します。
- 子供は何歳からしゃべり始めるのか?
- 言葉を喋らないと感じた場合、どうすればいいのか?
- 発達障害やHSCなど特性や気質の基礎知識と対応方法
- 聴覚障害や知的障害について
わからないから不安になるので、知識をつけておけば多少の不安はなくなります。また、勉強すればするほど、何かしらの障害に気づくこともあるでしょう。
その場合は、早期療育につなげていくことで、将来の困り感を減らすきっかけを作ることができます。
なんとなく、「もしかしたら」という不安にただ押しつぶされそうになるのではなく、親としてわからないことを積極的に取りに行く、という感じで過ごすだけでも、かなり前向きに過ごせますよ。
振り返り

私も長男が2歳代の頃に同じような経験をしましたが、ただただ不安に感じていただけでした。
長男も3歳前まではほとんどカタコトしか喋りませんでしたし、今思えば、会話、というものになっていなかったと思います。
当時保育園に行っていたので、同じ年の子はみんな、親と会話していました。自分の子との差を目の当たりにしたとき、本心から焦りましたね。
自分の子がとても赤ちゃんに見えました。
2歳という年齢で言えば、発達や成長に大きな差がある年齢。焦る必要なんてこれっぽっちもないのですが、長男は初めての子供でしたのでそんな余裕はゼロ。
明らかに自分の子が他の子と違うな、感じ始めたきっかけでもありました。
だからこそ、3歳前のお子さんがいる方の焦り感、もしかしたらうちの子は言葉が遅いんじゃないか、もしかしたら発達障害なんじゃないか、と焦る気持ち、とてもわかります。
ただ、現時点ではまだ2歳。ここからどう成長していくかは、子供次第なんですよね。
いつ喋りだすのか、もしかしたら喋らないのかは、未来にならないとわからないのです。
中2の長男は今、かなり雄弁です。はやりの若者言葉もお友達と一緒になってガンガン話しています。
幼少期の言葉の遅れを悩んでいた時期は、何かの悪夢だったかのよう。
子供は成長します。発達の遅れがある発達障害の子供でも成長していきます。
ですので、今不安に思うことについて、片っ端から調べ、知識をつけ、必要であれば早期療育をしていけばいい。
そうやって親も子も、成長していくのだと今なら思えます。
障害があろうとなかろうと、今できることをやるしか、親にやれることはありません。複雑な思いもあるとは思いますが、腹をくくって動いていきましょう。