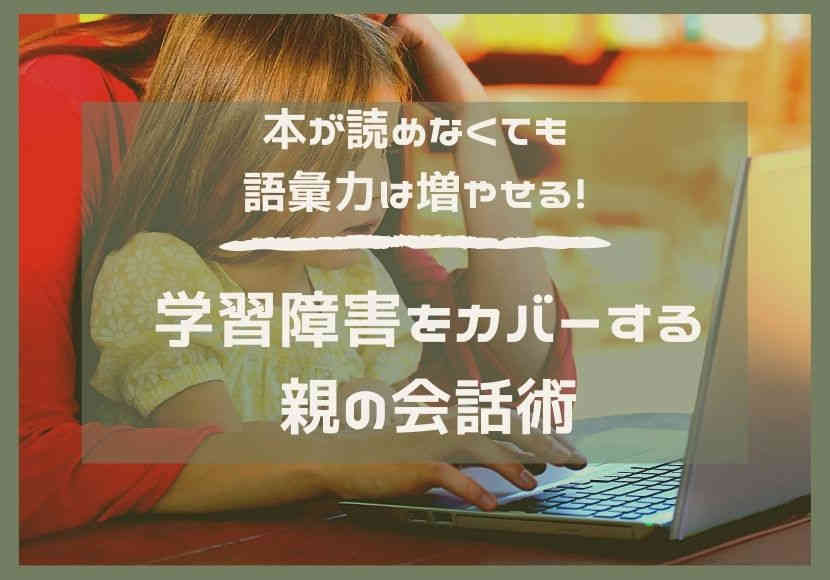発達障害の長男は、小3の時に学習障害と診断されました。
文字の認識はできるし、1文なら文章も読めるのですが、内容が理解できない読字障害に加え、字を思い出せない書字障害の方がひどいと言われていました。
結果として本が読めない長男に対する対応として、医師から言われたことは、「学年が上がるごとに圧倒的に語彙が少なくなっていくから、いろんな手段を使って語彙力をつけること」でした。
本人が本を読むことなく語彙を増やすために、親にできることをいろいろ考えた結果、いつでもすぐに取り組める「普段の会話」を工夫してみました。
今回は長男が小5あたりから現在でも進行中の「親の会話術」をご紹介します。学習障害のお子さんの、語彙が増えずに困っている方の参考になればうれしいです。
学習障害と語彙が少なくなる理由と想定される困りごと

学習障害と語彙が少なくなる理由
語彙は、基本的に「聞く・読む」などののインプット、「話す・書く」などのアウトプットで力がついていきますよね。
幼少期の頃から言葉の発達に遅れがみられる場合、同じ年の子と比べると語彙が少なくなることはあるでしょう。
さらに、絵本や学校での勉強で習得していく語彙についても、学習障害によってうまく理解していけない場合は、語彙力に差がついていくのは何となく想像がつきますよね。
学習障害で語彙が少ないと想定される困りごととは?
語彙が増えることで何ができるようになるかというと、円滑なコミュニケーションと自己表現だと私は思っています。
- 自分が伝えたいこと
- 相手が伝えたいこと
- 文字や文章からの理解
言葉でも文字でも何でもいいので、できるだけ正しく伝え、正しく理解することは社会で生きていくための基本。
親が生きている間に、できるだけの語彙力をつけてあげること、または代替手段を持たせておけると安心です。
本が読めなくても親の会話術で語彙力をカバーできる3つの方法

長男が学習障害の診断を受けたのは小学3年の頃。
当時私が観ていた「信長コンチェルト」のドラマのセリフを私が真似して会話で使っていたところ、子供達も真似するようになり、割と正しいタイミングで使っていたことにヒントを得て実践し始めました。
始めるまえに
家庭で療育的なことを始める場合は、「これから~やります」的な宣言をいつもするのですが、今回は宣言はなし。
いきなり実践し始めましたが、これまで疑問が出るわけではなく、いつの間にかそうなった感じになっています。
学習障害の対応について調べてはいたものの、興味のないものごとへの取り組みは特性的に難しいですからね。
小3くらいから対応可能(幼少期には向かない)
今回ご紹介する方法を実際に試し始めたのは、長男が小3あたりです。聞かれた単語をまず漢字で回答するため、漢字のパーツとなるある程度の漢字を知っていることが前提だから。
- 聞かれた言葉は漢字で回答する
- 漢字から意味を連想する(私が)
- 本当の意味を伝える(あれば豆知識も)
- 現実で使われている例を2つくらい伝える(あれば口語と文語で)
気を付けたことは、長くダラダラしゃべらないようにすること。
何とか意味をわかってもらおうと、つい長めに話してしまいそうになるので、意識して考えてから口に出すようにしています。
知らない場合はその場で調べて回答する
基本的に、知っていることを知っている範囲で答えれば良いと思います。
日常で使われている表現をそのまま伝えればよいので、知らない言葉は「知らない」と正直に答え、その場で調べるといいです。
読み書きが苦手という意識があるうちは、一緒に調べる過程を子供にやらせようとしないように気を付けました。
聞かれた言葉を漢字で表現
子供と生活していると、いろんなことを聞かれますよね。
この、聞かれた1回で、できるだけ印象に残るように漢字にして答えます。
学習障害で漢字が思い出せなくても、思い出す「きっかけ」、みたいなものを作ってみようと思ったわけですね。
漢字では「こう書く」と説明
例えば、「じんせいって何?」と聞かれた場合、
「漢字で人が生きるって書くんだけど」とまずは漢字を伝えます。
漢字から意味を連想できると説明
次に「人」が「生きる」って書くから、「生きること」とか「生きる時間」を指しているのかもね。と漢字から連想できることを説明します。
実際の意味を説明
先ほどの説明がなんとなく合っているなら、あえて辞書などで調べた正しい説明を伝える必要はないと思います。
知らない単語や先ほどの表現であやふやな場合は、調べてから正しい意味を教えた方がいいですね。
「こんな風に使う」という参考例を説明
よく使われる文面が思いつくなら、合わせて伝えておくとより実践で使えると思います。特に口語の場合は、みんなはこんな風に使うかな、というサンプルをいくつか伝えておくといいでしょう。
- 人生バラ色
- 人生は短い
とかいうよね、という感じで、自分が聞いたことがあるもの、使ったことがあるサンプルを伝えてみるといいと思います。
漢字で説明するための参考本
言葉を漢字で説明する=ある程度、自分の知識が必要になります。
大人であっても語彙力には差があると思いますので、子供向けの絵本などを参考にすると、わかりやすいでしょう。
さらに、時代の移り変わりなどで、自分が覚えてきたものとは認識が変わっているなどあるかもしれませんので、参考までに最新の絵本を参考にするといいと思います。
◎学研ことばえじてん
言葉の辞典が絵で表現されているもの。わかりやすいイラストになっているので、イメージでも覚えやすい。子供への伝え方の参考にもなるので家に1冊あると重宝します。
◎こころのふしぎ なぜ?どうして?
子供に聞かれても、どう答えていいのかわからない質問にどう答えるのか?ということが載っています。
専門家の方たちが全力で子供の質問に答えている内容が載っているので、読み物として読んでおくと実際に聞かれたときの参考になります。
◎いのちのおはなし(日野原重明)
医師が「いのち」について子供向けに書いた絵本。いのちとは、その人にある「じかん」のこと。ということを実際の授業で子供に教えたそうです。子供にはこういう風に伝えるとわかりやすいなと感じましたね。
何よりも、「いのち」を生きるか死ぬかだけでとらえてしまいそうになる概念を、哲学風でもなく、医学風でもなく、本当に誰にでもわかるように表現されているんですね。私も子供にこんな風に通訳していきたいと参考にしました。
お願いするときは敬語を使う
2つめの方法は、日常会話の中で「敬語」というカテゴリの語彙をふやしていく方法です。
親子の関係で子供に敬語を使うのはちょっと・・・と抵抗のある方はスルーしてください。
社会に出たことを想定する
いずれ、子供が社会に出たとき、意外と使えないのが敬語です。
丁寧語、レベルは使えるかもしれませんが、尊敬語、謙譲語などの使い分けはとても難しいですよね。
こればかりは、紙面でのテストがどうのではなく、実際に使っていかないと身につかないものだと私は思っているので、日常で人に物をお願いするときだけでも敬語を意識できればいいのでは?と思ったわけです。
参考例
- 頼むときは→~していただけますか?
- 褒められたら→恐れ入ります
- 落としたりこぼしたら→失礼しました
最低限、この3つくらいを日常会話に入れ込みます。
少なくても、毎回同じような場面で同じような敬語を親が話していると、使えるようになるものなのですね。
1年もしないうちに、長男も次男もお願いごとをするときは敬語を使いだしました。
「ママ、ゲームの課金をしていただけませんか?」
いちいち説明しなくても、親が使っている言葉や表現は、子供の語彙力を高めるなと確信しました。
言葉の調べ方を教えておく
最後に、自分でも知らないことをサラっと調べられるよう、方法を教えておくといいでしょう。
学習障害の子供に、辞書を使って言葉を調べさせることは、必須ではない気がしているのですが、一応、こんな方法もありますよ程度に、言葉の調べ方を教えておいてもいいと思います。
インターネットで
知識の検索に一番使えますので、最低限インターネットでの調べものの極意は伝えておきましょう。
私は、知りたい単語を優先順位の高い順にスペースを空けて入力し、エンターを押す、という風に教えています。
さらに、検索結果の広告以下の情報を見て、1ページ目に知りたい情報がなかったら検索ワードを変えるよう、教えています。
だいたい、2ページ目以降からは知りたい内容から遠ざかっていくと思うので、1ページ目で見切りをつけて、違う観点から調べるさせるようにしています。
スマホやiPadのアプリで


単語を調べるだけなら、便利なアプリが簡単です。
読めない漢字などは漢字検索でさっさと調べてもらいましょう。指で字を書くタイプのものは、ストレスにならない程度で使用し、親が目の前でサクッと調べてしまってもいいですね。
電子辞書で
子供自身が単語を調べる場合、スマホなどを使わせたくない場合や、学校でも使いたい場合は電子辞書が便利です。
子供自身が単語を調べる場合、スマホなどを使わせたくない場合や、学校でも使いたい場合は電子辞書が便利です。
学校で使用する場合は、担任の先生や学校によって医師の文面などが必要なこともあるかもしれません。
療育などで通っている病院の医師に頼めば、文面にしてくれるとは思いますが(おそらく有料です)、私なら面倒なので、学校の先生を説得する、もしくはスクールカウンセラーに相談した後、校長に直談判しますね。
※長男は自分だけ別の物を使用することを嫌がっていたので、電子辞書は使っていません。
◎小学生向け:カシオ エクスワード
◎小学高学年~中学生向け:カシオ エクスワード
◎高校生用:カシオ エクスワード
ワーク的なものがあるものもありますので、使い道にあわせて検討してみるといいですね。
使えるなら辞書で
学習障害の特性がある場合、辞書が使えない子が多いと思いますが、もし辞書が使えるのであれば、辞書を使って自分で調べてもらうのも一つの方法ですね。
◎新レインボー小学国語辞典
◎旺文社国語辞典
振り返り:学習障害の特性があっても語彙力を高めておいて損はない

語彙力があれば、物事を考えたり整理したりするときにも使えますので、結論から言うと語彙力を高めておいたところで損はないと思います。
本が読めるかどうかに左右されることなく、親の会話だけで語彙が増やせるのであれば、それに越したことはないでしょう。
実際、自分で実践してみて思ったことは、日常的に使えた方が語彙は増えやすい、と感じました。
語彙力があることで、
- 理解力が高まる
- 表現力が上がる
最低限、この2つは賄われるわけですから、コミュニケーションや伝えたいことを文面などで伝えられることになるわけです。
勉強することに何かしらの困難があったとしても、語彙力があることでベースはカバーできていることになるかなと思います。
本が読めなくても、漫画が読める、雑誌なら読める、と別の手段から語彙力を上げてもいいですし、ドラマや映画などの動画・テレビ系からも語彙を増やすことはできます。
机に向かって読み書きを頑張って、できない、を増やしてしまうのではなく、できるだけ日常で触れられるもので語彙力を高められるといいですね。