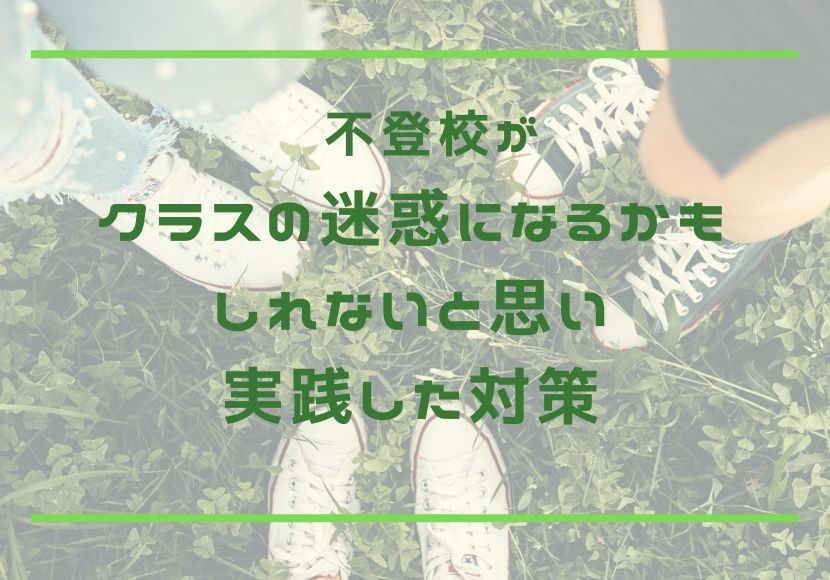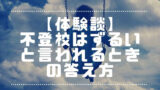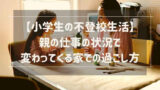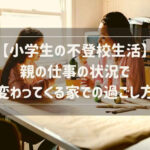次男が不登校になったことで、クラスメイトには何かしらの迷惑がかかるであろうことを想定し、不登校当初から対策を取っていたことがあります。
本来であれば、子供の不登校対応に集中した方がよく、迷惑になる・ならない、を気にすることは考え過ぎの類いのことでしょう。
しかし、実際に不定期であれ定期であれ、不登校により迷惑さを感じる人がいることは事実。
できれば、クラスメイトの学校生活に極力迷惑にならないよう、できることはやっておこう、そんな感じです。不登校は迷惑、というお話ではないのでお間違えの無いようお願いします。
今回は、次男の不登校に関することで、迷惑にならない対策としてやってきたことをお話したいと思います。
不登校になることで迷惑になるのでは?と不安に思ったこと

小3から不登校になった次男は、以下のスタイルで不登校生活を送っています。
- 小3の1年間・・・1日2時間だけ授業に参加
- 小4から現在小5は・・・週1休み他フル登校
理解ある学校とクラスメイトに恵まれ、実際は、次男は一度も不登校であることを迷惑だ、と言われたことはありません。
しかし、係や委員会など、役割があるものやグループでの授業などでは、少なからず次男が休むことで迷惑を感じる子はいるだろうと、当時の私は予測していました。
- 係活動
- グループでの授業
- 隣の人との活動
- 委員会
- 学校行事での役割
- 他役割を振られたもの
小3~小4の間は、主にクラス内でのグループ作業や係活動ですね。小5の今年は、委員会も始まったので、こちらの対策も考えました。
(小3)席替えの席は固定:廊下側一番後ろ
遅刻と早退を繰り返していた小3。
席替えは、廊下側の一番後ろに固定していただきました。担任の提案でしたが、いつ、出入りしたとしても、クラスメイトの目にはあまり触れないあたりがとても良いと思いました。
必ず当番として回ってくる日直ですが、3人席でしたので、たとえ次男がいない時間であっても、お友達が一人にならないあたりも良かったです。
係活動は人数が要るものを選ぶ
係活動が2人のものはほぼないらしいのですが、次男は、
- 配り係
- 窓閉め係(電気付けなど)
この辺りを選んでいるようです。
一応、担任にも、人数のいる係になるように配慮してもらっていますが、現時点では、次男が自分で選んだ係活動ができているようです。
グループ作業系は基本休まない
社会などの授業によっては、一年間、同じグループで活動することがあると思います。
そのような場合は、基本、グループ作業は休まないようにしていました。理由としては、やはり同じグループ内での担当割などで困ることがあるからです。
次男がいないことで、次男の担当をどうすればいいのか、基本的にグループ内で決めることが多くなってしまうんですね。
そうなると、同じグループのお友達が、学校に来ない次男に対し、少なからず気を遣って割り振りを決めなければいけない。それは申し訳ないなと、私が思っていました。
もちろん、無理に参加することはさせませんでしたが、次男にもこの辺の話をして、基本的にはグループ系の授業は休まないようにしました。
委員会は基本休まない
同じような理由ですが、委員会の日は基本的には休まないようにしました。
委員会は小5から。委員会の日は木曜日で、次男が休むのは基本月曜日ですので、委員会の日にはかぶらないいことが基本です。
しかし、単発的に木曜日に休みたくなった場合でも、委員会のある日は休まずに行くようにしています。
担任の先生は、代わりの人がいるのだからそこまで気にしなくても大丈夫だと言ってくれているので、委員会の日に休むこともありましたが、基本や休まない方針です。
初めての委員会は代表委員会に立候補した
委員会を決める前、事前に次男とも相談しました。
- どの委員会にも学校内での役割があること
- 自由に休んでいい仕事はないこと
週1(主に月曜日)休むのだから、休む日に委員会の仕事がないものを選んだ方が良い、と私はアドバイスをしました。
そしたらなんと、学年の代表委員会に立候補し、決定したとのこと。正直、「えー?」と思いましたね。
委員の役割はみな同じ的なアドバイスをしておきながらなんですが、代表委員会は一番大変だろうと思ってたので避けた方が良いかと思っていたのですよね。
責任やら、クラスの意見のとりまとめやら、人前での発表やら、次男が避けてきたことのオンパレードがメインの仕事なんですけど、と思いまして。
そんな私の心配は不要だったようで、
- 代表委員会はなり手がいないので、立候補すれば希望通りの委員になれること
- 仕事はある程度決められていて、最終判断は基本6年生がやること
このあたりが自分の性格に合っている、と思ったようでした。
春から始まった委員会活動。コロナ禍で、過去に比べると仕事は少なくなったようですが、秋の時点までは問題なく参加しているようです。
学校行事も基本休まない
すべて似たような理由になりますが、学校行事も基本休まないようにしています。理由は前と同じで、役割が決まっているから。
劇のように代役があるもの以外(次男の小学校の劇では基本代役はない)、休んでいません。
一つだけ、運動会の演技種目には出ませんでしたが、はじめから出ない予定で練習から参加していませんでしたので、学校としてもあまり問題にはなりませんでした。(当日の演技種目時間は親と一緒に過ごしました)
小5になったら代表的な役をバンバン引き受けるようになった
小5になった現在、週1休みで他フル登校なのですが、何かしらの役割として代表的なものに立候補する機会が多くなりました。
- 宿泊学習の班長
- 授業などのグループ活動の班長
- 集会で発表する学年代表
なぜかはわからないのですが、「やってくれる人~」という先生の声に立候補しているようで、実際にちゃんと務めていると担任から報告がありました。
代表的な役割を引き受けているからと言って、メンタルが落ちることもなく、余計な不安を抱えることもなく(もちろん家でサポートしていますが)、なんか順調でちょっとコワイくらいです。
休む日の手紙は基本届けてもらわない
小学校は、学校からくる手紙が結構ありますよね。
小3の頃は、日中いる2時間の間に、その日に配る予定の手紙をもらっていました。
小4の頃は、近所のお友達が手紙を届けてくれていましたが、基本は緊急のもの以外、届けてもらわないことになっていました。
小5になってからは、手紙類は届けてもらうことはなく、緊急のものは私が直接学校に取りに行くことにしています。
そもそも緊急のものなどほぼなく、先生が電話で伝えてくれること、メールなどを活用してもらうことで、十分間に合っています。
「不登校がクラスの迷惑」ということについて(善悪の話ではなく)

- 子供が不登校になると先生やクラスの友達に迷惑をかけてしまうのではないか
- クラスに不登校の子がいると迷惑だ
不登校と迷惑、という言葉は、ネガティブな言葉のセットとして使われていると思います。
私も次男が不登校になった際、クラスメイトに迷惑をかけないようにしたい。親の気持ちではありますが、真っ先にそう思いました。
当時、私が「次男の不登校」と「迷惑」について、結構本気で考えたことをお話します。
「迷惑」の言葉の意味
まず、「迷惑」という単語の意味を確認しました。
1 ある行為がもとで、他の人が不利益を受けたり、不快を感じたりすること。また、そのさま。「人に―をかける」「―な話」「一人のために全員が―する」
2 どうしてよいか迷うこと。とまどうこと。
出典:めい‐わく【迷惑】 の解説/goo国語辞書
迷惑とは、基本的に他人が迷惑だと感じるかどうか、ということ、なんですね。
不登校を迷惑だと感じるのは他の人の問題
「迷惑」を感じるのは、他人の感情です。ということは、不登校になっている本人や、その親、先生にはどうすることもできないカテゴリになるわけですね。
それを踏まえた上で、話を進めていきましょう。
- ある行為→不登校で休むこと
- 他の人が不利益を感じたり→不登校で休んだ人の役割をこなさなければいけなくなること
このように考えてみたんですね。
不登校児である次男が休むことで、同じ係の人に負担がかかり、迷惑だ、と感じる、という流れで考えていきました。
不登校を迷惑であると感じる人は一定数いるものだと仮定する
「迷惑」というのは、人の感じ方によるものであることは、先ほど確認したとおり。
ということは、不登校当事者である子供や親には、どうすることもできない、ということをまずは理解しました。
要するに、私が「迷惑をかけたくない」といくら思って、対策を立て、実行したとしても、他の人が、「いやいや、次男君が学校を休んだら迷惑ですよ」と感じることは止められない、ということになります。
人がどう感じるかはこちら側ではコントロールできない
例えばですが、次男が休むことで、「ずるい」とか「困る」といった感情を抱く子は一定数いるだろうな、と仮定しておいた方がいいと思ったのです。
人がどう思うかは、こちら側からはコントロールできませんし、そもそもコントロールするものでもないですからね。
そういう意味でも、次男が不登校になり学校を休むことで、ある程度迷惑だと思われることは覚悟しておくことにしました。
不登校児の回りの人が不利益を感じなければ迷惑にはならないのでは?
例えば、次男の回りで過ごす友達やクラスメイトが、次男が休んだとしても何の不利益も感じなければ「迷惑だ」とは感じないわけですよね。
逆に、次男が休むことで、グループ活動がうまくいかない、係活動が進まない、というような不利益を、誰かが感じたとしたら、次男の不登校=迷惑、という図式が成り立つ、ということです。
ならば、
このように考えた結果、先ほどお話した対策を実行しているわけです。
どうしても避けられなかったのは、小3不登校時代の日直。
3人席ではありましたが、次男が登校するまで、次男が早退した後は、2人で日直をやるんですよね。通常2人なので問題ないのでは?と大人は思うのですが、まだ若干8・9歳の子供には「ずるい」という気持ちを持たせるきっかけにはなってしまいます。
それを、次男のHSC気質を理解してね、というのも少し違うと思っていました。ですので、ひたすら、平謝りです。「ごめんね、いつもありがとう」と言って、登校し、帰る。そうしていました。
不登校で迷惑をかけたくないという思いをチャンスだと変換してみた

自分の子供が不登校になり、クラスメイトや学校、担任に迷惑をかけてしまうのではないか、と親である私は考えてしまいました。
ですから、子供の不登校に対処することと同時に、学校の先生やクラスメイトに対しても対策を立てた方がいいな、と思ったわけです。
対策を取った理由は次男が非難される姿を見たくなかったという私の主観
それは、「次男の不登校は迷惑だ」とクラスメイトから、次男が言われる姿を、私が見たくなかったから。完全なる主観です。
- 迷惑とかそんなことを言う子はいないよ
- 学校に来れないならゆっくり休めばいいと思うよ
という優しい言葉をかけてくれるママ友や先生方。でも、正直に当時の気持ちを暴露しますと、本心ではどう思っているかなんてわからない、って思ってました。ひねくれてますよね。私。
「不登校で学校を休むから=学校の役割をこなさなくていい」ではないと思った
だいぶ理屈っぽいですが、不登校になったことは次男の問題。それと、学校に在籍することで振られる役割をこなすことは別問題だと思うのです。
大人の発想であることは100も承知の上ですが、学校に行く行かないに関わらず、振られた役割に対して、できることは参加した方が良いと思ったのも事実。
仕事じゃないんだから、まずはゆっくり休ませて、復帰できそうならちょっとずつ復帰すればいいか、と、もっとラクに不登校に対処する道があることは知っていました。
うまくいかないことがあったときの対処を一緒に経験できると思った
何かうまくいかないことがあったとき、できることがあるなら対処する、という機会、少なくとも小学校時代の不登校に関しては、もうないかもしれない、とも思いました。
次男の人生にはこの先、いろんなうまくいかないことが起きるでしょう。そのときに、
- 全休しして復活を待つ
- 休みつつできることはやる
- 休まずに復活できる術を実行する
ゲームのように自分で道を選んでいきますよね。
次男の不登校は、困難にぶつかったときの対処法を次男と一緒に考え、次男の行動をサポートできるチャンスでもあると私は思ったのです。これが、次男の不登校をポジティブにとらえるきっかけとなりました。
一般的ではない選択をし、学校を休む生活をした次男。ならば、私も一般的ではない親として、やれることは何だろう、といった感じです。
HSCが原因で不登校になったからできたことでもある
友達関係が悪くなって不登校になったわけではなかったので、次男はできることに参加しつつ不登校になる、ということができた、というのも、迷惑にならない対策が実行できたポイントだと思っています。
不登校の理由は人それぞれ違いますからね。
振り返り:子供の不登校が迷惑になるかもと不安になるならできる対策を実行してみると良い
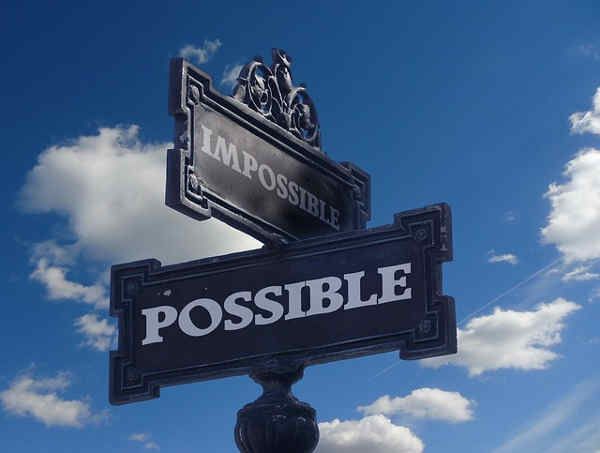
HSCが原因で子供が不登校になっている場合、親もHSPの可能性は大きいと思います。
- 不登校になったからって迷惑だなんて思ってないよ
- 迷惑とか気にしなくてもいいよ
という言葉をかけていただくと、正直、本当に救われます。
ただでさえ、「不登校」という普通とは違うことが目の前にあって、どうすればいいのかわからない、と焦ってしまってさえいるメンタルですからね。真面目にうれしいんです。
でも、でも、本当に申し訳ないのですが、自分の脳のデフォルト機能として、「迷惑かも」という思いを消すことは難しい。たぶん、できない。これもまた事実なのです。
ということで、対策を考え、実行してきました、というお話をしてきました。
迷惑だ、と言われても、やれることはやりました、と言える伏線を張って過ごしている、ということになりますね。保険になっていないけど、似たようなことをやっているともいえるでしょう。
こんな私の体験談ですが、同じような不登校タイプに悩み、同じように子供の不登校は迷惑なのではないか?と不安になってしまっている方の参考になればうれしいです。