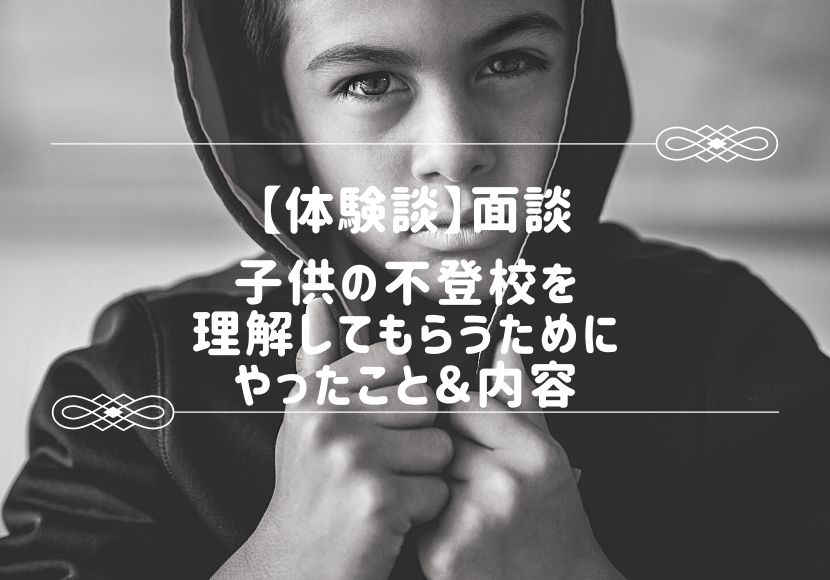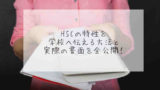次男が小3春に不登校になったとき、学校側には次男の不登校について正しく理解してもらいたいと思い、面談を行いました。
今回は、面談の時期や目的、内容や用意したものなど、次男の不登校と面談に関することをまとめてみました。
不登校のお子さんがいる方で、面談について不安や悩みがある方の参考になればうれしいです。
不登校の面談の時期&目的を明確にした

次男が不登校になったのは、小3の5月初め頃。はっきりとした日にちは覚えていませんが、運動会の練習が始まり、リレーなど、学年を超えた競技の練習が始まった頃でした。
面談の時期と面談の人数
面談は、自分から希望しました。
面談の時期
時期は以下のとおり。
- 小3・・・不登校になって割とすぐ
- 小4・・・やらなかった(電話で挨拶程度にすませた)
- 小5・・・春。新学期が始まって2週間後あたり
小4で面談をやらなかったのは、コロナ禍だったのと、小3の先生が面談で使った資料を引き継いでくれたから。挨拶がてら、電話で軽く済ませました。
小5のときは、それまで次男を知っていた先生がほぼ移動でいなくなる、という事態がおきたので、面談を希望。
小4の先生が、次男の面談資料を引き継いでくれなかったので、最新に更新して渡しつつ説明しました。
面談の人数
面談の人数は私以外、先生方の人数です。
- 小3・・・3人(担任、専科音楽、専科図工)
- 小4・・・0人(コロナ禍で面談系はほぼなし)
- 小5・・・1人(担任)
小3の面談の人数が多いのは、小3の担任がいろいろスルーするタイプの先生であることを知っていたから。証人として自分から頼んだところ、快く引き受けてくださいました。(もちろん、担任には内緒です)
過去に長男の担任でもあった先生で、実はそのときも結構意見の食い違いがあったのですよね。長男の特性を、面談して1から時間をかけて説明して、配慮をお願いしても、理解してもらえなかったのです。
配慮って、お願いしてもどうにもならない先生がいるんだ、ということをその時学習したんです。
そんな過去があり、他の先生にサポートしてもらおうと考え、特別支援的な窓口になっている担当の先生(学校に誰かいるはず)に同席してもらおうと計画を立て、実践。
それが、専科の先生2人でした。長男のサポートで、何年も相談にのってもらっている先生でしたので、話は早かったです。
次男の不登校にあたり、専科の授業をどうするか、ということを担任含め相談する、という体裁にしました。(実際その話は必要でした)
面談の目的を明確にして学校と共有する
単に、「子供が不登校になりました。先生、どうしましょう」ということを話すことは時間の無駄だと思いました。
先生、どうしましょう。と言えば、少しでも学校にくることを勧められることはわかっていました。だって学校ですからね。
特に、次男小3のときの担任が、そのタイプの先生でした。(給食あるから、学校においでよ、、など)
ですので、面談では、
- 次男のメンタル悪化を防ぐこと
- 登校方法や勉強方法をどうするか(学校と家でどう役割分担をするか)
この2点を達成するために、次男に関わる大人は何をすればいいのか。ということを面談の目的としました。
面談の冒頭では、毎回、この2点を話し、このために私は面談にきています、と伝えてから先生方とお話をするようにしています。
不登校の面談で話した内容
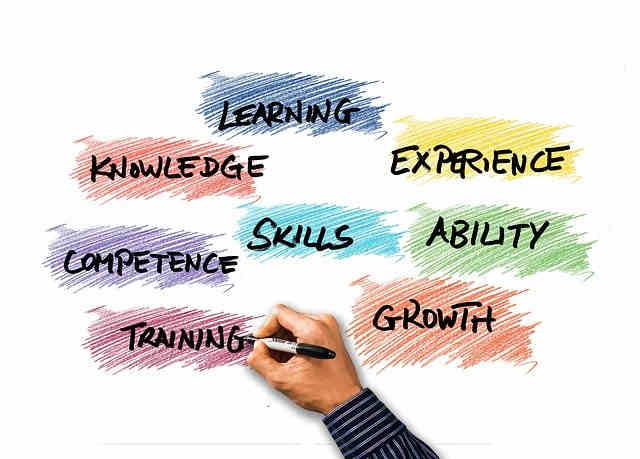
面談するにあたり、事前に話す項目を決め、先生方が理解しやすいような順序にして、最終的には家庭と学校で連携できる形にしたい、と依頼しようと思いました。
- 次男のHSC気質を理解してもらうこと
- 今後の過ごし方
実際に話した内容はこんな感じでした。
次男のHSC気質を理解してもらうこと
まずはhscを理解してもらうために、資料を作成しました。特にHSCって何?という先生がほとんどでしたから、まずは自分が読んだ本を持って、次男の資料を作成し、説明することにしました。
作成した資料の詳細
資料には、
- 自分で作成した次男の特徴とHSCの資料
- 本の巻末をコピーした参考資料
資料の内容は、
- HSCの特徴と合っている次男の特徴とサンプル例
- 対処方法や声かけ、外から見える様子と本人の気持ちの違い
- 学校にお願いしたいこと
大体こんな感じです。
資料の詳細については、別記事で内容をそのまま公開していますので参考にしていただければと思います。
最後に、HSCの子育てハッピーアドバイス HSC=ひといちばい敏感な子という本の巻末にある、「学校の先生のために」という教育者向けに書かれている章をコピーして、参考資料にしました。
このときの面談は、担任+専科の先生2人の計3人と面談する予定でしたので、3部作成し、セットで先生方に渡しました。
面談では、資料を見ていただきつつ、こんな感じなんです、と様子を説明しました。
次男の幼少期の様子や幼稚園での対応
幼稚園でも困りごとはありましたので、そのあたりの話をしました。
次男の幼稚園は、幼稚園のしくみとして、先生方の目がとても行き届いていましたので、いろいろありながらも、最終的にはとても楽しい経験がたくさんできたみたいです。
次男のこういう様子から、先生はこういう対応をしていた、という感じで、軽く触れる感じにしました。
小1~2までの様子と先生の対応
低学年は、2年間同じ先生が担任で、現在も在籍されている先生ですので、1・2年の様子はその先生に聞いてください、という感じにしました。
親として、1・2年 のときには、こういう困りごとがあって、先生に相談してこういう風にしてもらいました、ということは簡単に触れる程度で話したような気がします。
次男家庭での様子
家庭環境や兄との様子、宿題の取り組みや、習い事など、家ではどんな風に過ごしているのかを軽く話しました。
小3のときの担任は、長男が小3のときも担任でしたので、どういう兄がいるのか、ということは知っていますから、話は早かったですね。
ただ、発達障害で、そもそも困りごとのオンパレードだった兄と、見た目上は真逆なので、そのあたりの違いや、声掛けのタイミングなど、家庭での様子を話しました。
今後の過ごし方について
不登校当時ですので、次男のメンタル回復を最優先にして、
- 1日2時間だけ登校してみる(私が送迎する)
- 無理なときは休む
- 他はすべて都度相談
ということにしました。
毎日、学校でも過ごしつつ、都度方向性を微調整していきましょう、というのが一番良いかなと思ったんですね。
あれこれと決めごとが多くなると、チャレンジしたいことがあっても自由に動けないと思いましたし、完全に不登校になる可能性もありましたし。
決めてもできない、ということは避けたかったという気持ちもありました。
まずは様子を見る、そして、毎日短時間であっても、一応登校するので、どんどん相談していこう、ということにしました。
都度相談の内容は主に事務的なこと
先生方には他の生徒もいますし、当然、授業も学校の仕事もありますから、親の私の不安的なことを話すことはやめ、事務的なことの方向性をどうするか、ということを都度話し合いました。
例えば、
- 掲示的なもの(クラスの壁に貼ってあったり、棚に飾っているもの)
- 給食や掃除当番への参加
- 課外授業への参加(社会科見学や遠足など)
- 学期を通して参加できなかった授業の評価について
- 学校行事への参加と練習や担当の割り振り、活動授業への参加について
- 宿題などの方法
おそらくこんな感じだったと思います。
勉強と宿題のこと
不登校当時、私もかなり気になったことは、やはり勉強ですね。勉強、どうしよう、と思いました。
しかし、面談の目的でも話した通り、まずは次男が「学校に行きたくない」というヘルプサインを出していることをしっかり受け止めようと思いましたので、勉強のことは後回し。
宿題は、やってもやらなくてもどちらでもいい、ということにしてもらいました。宿題を提出すことより、2時間授業に参加すること、こちらが優先。
何かしらの原因で、本能的に休もうとしているのに、「やらねば」がたくさんあって休めない。
先生にも、ゆるーく見守ってもらうことをお願いしました。
不登校で評価ができない教科の通知表の表示は斜線になる
豆知識になりますが、不登校で授業に参加していない場合、教科としての評価ができないため、通知表には斜線が引かれます。
次男は小学生ですので、特に通知表の評価はどうでも良いと思っていましたが、中学生になると内申点などの進学への影響がありそうですね。
次男は、図工の授業に全く参加しなかったので、斜線になっていました。
他の先生にも話しておいた
- 校長先生
- スクールカウンセラー
- ピアティーチャー
- 保健の先生
日々、次男を送迎していると、誰かしらの先生に会うんですよね。
たいてい、「どうしたの?今来たの?帰るの?」と聞かれるので、「実は、こういう状態で不登校児なんですよ」とありのままを話していました。
特に、ピアティーチャーの先生と通級の先生、保健の先生とは普段から話を聞いてもらっていたので、学校で過ごしている間は、様子を見てくれていたみたいです。
スクールカウンセラーは、長男入学のときからずっと相談し続けていたので、次男のことでもよく対応してもらいましたし、すれ違えば、校長先生とも話をしました。
おかげで、学校で会う先生方が、次男の様子を教えてくれるようになり、2時間しか登校していないのに、たくさんの情報が入るようになりました。
私も、ふと油断すると、孤独を感じてしまいそうなメンタルでしたので、声をかけてもらって、情報を教えてもらい、不登校状態だけどとりあえず大丈夫だな、とホッとした記憶があります。
振り返り:面談をすることで次男の不登校を理解してもらう一歩になった

担任の先生と直接会って面談をすることで、次男の特性といいますか、HSCという気質があって、こういう感じで次男は、ずっと学校にいるときつくなるんだな、ということはわかってもらえんじゃないかなと思います。
特に今回のように、資料や参考本を持って説明したい場合は、面談はとてもよい手段だと思います。
どの先生でも、面談時の反応は大体同じで、HSCのことを知らなかったー、そういうのがあるんだねー、という感じ。
逆に、じゃあこれまでの生徒にも同じような子がいたかも、と思い当たるところもあるようです。
特に専科の先生たちは、なんかわかる、という雰囲気があったので、音楽や美術方面に進む人達には、似たような特性や気質を持つ人がいたのかもしれないな、と思いました。
ということで、次男の不登校時の面談について、体験談をお話してきました。お子さんの不登校について、面談しようか迷っているという方、面談は決まったが何を話せばいいのかわからない、という方などの参考になればうれしいです。