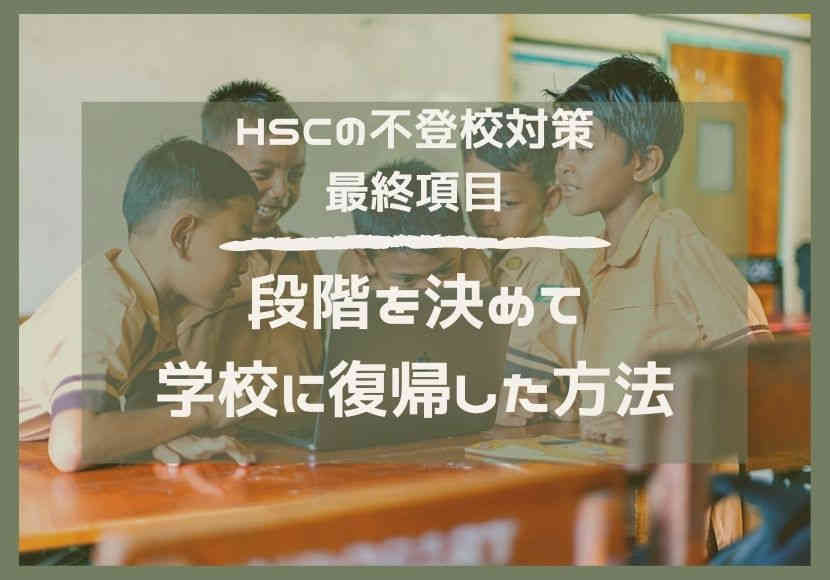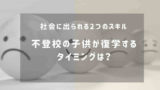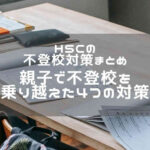小3の5月上旬、次男はHSCの気質が原因と思われる不登校になりました。
1日2時間登校という、変わった不登校のスタイルを貫きつつ、次男のメンタルの様子に合わせて段階を決め、少しずつ学校に復帰。
小4は週1休みでフル登校できるまでになりました(週1休みなので年間で60日近く休んでいますが)。
欠席日数でみると不登校児ですが、メンタル維持のための週1休みなので、「ポジティブ不登校児」ですね。
ではどのようにして、校内に入れないくらいのメンタルから学校に復帰したのか、というお話をしたいと思います。
不登校から学校に復帰するまでの段階をメンタルの様子で決めてみた

- 休息優先期
- 不安定期
- 回復期
- 自立期(復帰期)
休息優先期
不登校になり始めの頃。とにかく休ませることを優先に考えていた時期です。
学校内に入ろうとすると足が止まる、という次男の行動は、ある程度、メンタルに負荷がかかっているわけですから、まずは学校内に入れるようになるまでは、すべてを忘れ休んでいいと思いました。
次男の場合は、ちょうど運動会があったので、ずっと休んでいたわけではないのですが、運動会のリレーの朝練習だけ登校し、早退するの繰り返し。
とにかく次男がゆっくりと過ごせるようにしました。
不安定期
不登校生活にも慣れ、1日2時間だけ登校するという新しいスタイルも学校側にも友達にも理解して受け入れてもらう毎日。
友達や先生と関わる中で、メンタルが安定する日があったり、反動で超荒れたりすることもあった不安定な時期。
調子がいいからと安心することなく、ずっと客観的に様子を観察しつづけることに気を付け、私は接するようにしていた時期です。
次男の行動にイチイチ一喜一憂しないこと。私は私の時間を過ごし、次男は次男の時間を過ごす。一緒の時間は二人でできることに専念する(学校のことは考えない)。
そんな風に過ごしていた時期です。
回復期
認知行動療法の考え方に次男が慣れてきて、少しずつ自分にできる方法があるな、とわかってきた時期。
感情コントロールが成功することで、次男が社会と共存し始めてきたような感覚がありました。
自分と社会を切り離して自分を守る方法もあるけれど、地球の上の社会の中に自分が暮らしていること受け入れ、社会の中に自分の居場所を作っていくことを意識させていた時期でした。
自分ではどうにもならない環境もあるけれど(人や親とかのこと)、自分から変えていける環境もあること(自分の意思を伝えること)を実感し始めて、行動することもありました。
自立期(復帰期)
それまで避けてきていた授業、避けていた発表の場、はっきりしないことが多い子供主体の学校行事などを避けず、あえて参加し、体験を積んだ時期です。
行きたくない理由を聞いて、対処法を考え、必要であれば紙に書いて手に持たせ、登校させました。
もしかしたら、この1回でまた学校に行かなくなるかもしれない、そんな不安もありましたが、それだとしたらまだ回復期だったということ。判断を早まっただけと考え、果敢にチャレンジさせました。
意外にも、行ってみれば平気だった、とケロッと報告をしてくれたので、学校に行って新たな体験をすることへの抵抗も少なくなっていったのだと思います。
段階ごとの具体例

不登校になったばかりの頃は、学校に戻る戻らないを始め、その後の生活のことなど何も考えてはいませんでした。
毎日、朝になると学校に行ってみようと思うらしく、校門までは行くのですが玄関に入れず。そこで家に帰っていました。
始めは休ませるだけ、こんな状態になったら次の段階かな、、と次男の様子を見つつやってきたことを振り返ると、大きく分けて以下の4つの段階があったかな、と思います。
休息優先期
とにかくメンタルを休ませる日々。
親の私からは学校に行く行かないなどの声をかけることはせず、休みたいと言われたら休ませ、行ってみようかなと思ったら付き添い登校をしてみる、という段階です。
この時期、学校には朝の時点での次男の決断、やっぱり行ってみようかと言い出したら行くかもしれない、ということを伝えつつ、基本的には欠席として扱ってもらうようにお願いしていました。
自己肯定感が低く、ぼくにはできない、ということも多々ありましたし、すぐ怒るようなこともまだまだ健在の時期。
学校の校内に入れず、ランドセルを背負ったまま近くの大きな公園の広場で、大の字に寝っ転がったりもしていた時期でした。
たまたま運動会の月だった不登校当初
不登校になり始めたばかりの5月は、運動会実施月でもあり、リレー選手の次男はリレーの練習だけは毎朝行っていたので、欠席扱いにはならなかったんですね。
毎日、朝の練習で直接校庭に行き、練習に参加して帰るという日々でした。
たまに1時間目だけ参加することもありましたが、運動会までは基本的にリレーのみの参加。
ダンスには出ないと始めから決めていたので、体育の授業も出ず、当日の演舞もお休み。
運動会当日は、短距離走と団体競技(綱引き)、リレーに出て、あとは家庭用のテントで過ごしました。
運動会後は1日2時間だけ授業に参加
次男の不登校の原因は、先生がよく怒っていたことや、先生を始めクラスメイトの気持ちを感じ取り過ぎてしまうこと。
気を遣いすぎて自分の意見はほぼしゃべらず、一見、クールを気取っている感じですが、内心ではいろんな葛藤があったようです。
これは幼稚園に入った当初からよく言っていたことなので、ある意味、年中から4年頑張りつづけ、5年目にして疲れた、メンタルの限界がきたのでしょう。
そういうこともありましたので、原因を解決していないのに、学校に戻すことは逆にあぶないな、と思った私は、1日2時間だけ授業に参加することを担任に提案し、受け入れてもらいました。
習い事関連もいったんすべてやめた
メンタルが不安定な状態なので、学校以外のコミュニティも本人の希望で一度すべてやめました。
当時は長男と一緒に将棋に通っていましたが、兄につられて入ったようなものなので、本当に自分が将棋をやりたいのか疑問だったことも、やめるという決断につながりました。
そして1年生からやっていたチャレンジタッチも、日々のノルマ達成が辛くなり、退会。
メンタルが落ち着いてから、必要ならまた再開するか、勉強なら別の手段もあると思っていったんやめました。
放課後は友達と遊んでいた
地域の友達が帰ってきてからは、みんなで外で遊んでいました。
やっぱり、学校、という空間がキツかったみたいですね。遊びに誘われることもありましたし、一人で公園に行き、そこにいる友達と遊ぶことも多々ありました。
または、長男と一緒に虫取りに出かけることも多々ありました。不登校だからと言って家にこもり切りにならなかったことは、いろんな意味で、とてもよかったと思いました。
不安定期
1日2時間登校にも慣れてきて、私も学年の子供達に次男の新しい不登校スタイルについて、読み聞かせの時間を利用して説明したあたりから、次男のメンタルの様子も変わってきました。
認知行動療法で、自分の感情について知る機会をもった次男。
- これまではきっちりと宿題をやらないと
- 先生の言っていることはやらないと
という考えに変化が出たのか、
- 宿題はやれる時だけでいいや
- 忘れ物をしても死なないからいいや
と言う風になってきました。いいのか悪いのか、気を張り続けなくても大丈夫だと思い始めたのでしょう。
勉強は自宅でやっていましたが、学校で教えてもらう方法にイマイチ納得がいかないと、家に帰ってきてから荒れることもしばしば。
先生との相性が合わない、ということもあるのでしょうが、次男も自分にわかるように説明してもらえないという、ある意味自分勝手な思いを持っていたような気がします。
一度荒れると家に帰ってきてからも復帰できず、寝てしまったりずっと機嫌が悪かったり。
メンタルの差が激しい時期でした。
子供の様子で一喜一憂しないことを心がけた時期
次男の様子から、何度も自分の対応が悪いのではないか、と私自身が自分を責めてしまいそうになることがありました。
不登校がひどくなるという心配ではなく、次男のメンタルを安定させることができないことに、です。
しかし、よく考えたら、私はだたの母親で、心理士でもないし児童精神科の医師でもないわけですから、母親としてできる対応をすればいいのだと、何度もリセットしながら過ごしました。
ともすれば、次男の調子に合わせて一喜一憂してしまいそうな不安定な時期。子供と一緒に親まで不安定になってしまわないことが、私の一番の仕事だと思うようにしました。
回復期
親子ともに認知行動療法に慣れてくると、親の方の認知の変化により、子供への接し方が変わってきたように思いました。
なんて表現すればいいのでしょうか、、親の私が、より自分のことをコントロールできるというか、より明確に子供を客観視できるというか、、
私のメンタルがめちゃくちゃ安定していました。
ちょうど自分の糖質制限などもやっていたので、体調も大きく改善され(お菓子とパンの食べすぎでした)たことも関係しているのかもしれません。
安定して子供へ接することができるようになったおかげで、さらに行動心理学みたいなものだったり、栄養学だったり、他の心理学だったり、自分の勉強がはかどりました。
次々に次男によりよい方法を提案できたので、次男のメンタルが一気に安定。ちょっとした感情コントロールのスキルを、次男も身に着けた感じでした。
これも、荒れるだけ荒れたからの結果だと思います。落ちるところまで落ちたというか、結構派手に荒れた時期があったので、回復していると感じることもできたのでしょう。
チックが改善
いつの間にか、チックは改善されていました。
たまに疲れたりすると、目が激しくパチパチしますが、一日中まばたきしていることもなく、口をグルグル回して止まらないと泣くこともなくなりました。
笑顔が増え、バカみたいなくだらないことをしゃべっては笑い転げることも多くなりました。
チックの改善に気づき、次の段階に進めるかな、と思い始めました。
自立期(復帰期)
不登校になってから避けていた授業や学校行事に、あえて参加して体験をする方向で過ごした時期です。
避けていた理由ときちんと向き合うことで、次男の認知を「参加しても大丈夫だった」という経験の上書きにつなげていきました。
- 前もって避けていた理由と原因
- 別の見方はないのか
- 友達の様子はどうなのか
- どうすれば参加できるのか
などの対策を立て、とりあえず1回だけ参加して、その後のことは調整しようということにしていました。
人前の発表とやることがわかりづらいことを避けていた
結局、学校で避けているようなことの大半は、人前で発表することが関わっていたり、やることが中途半端で明確ではないようなこと。縦割り授業とかですね。
参加する意味がわからない、みたいな感じですかね。
参加する意味がわからなくても、先生が明確にしなくても、時間だけ過ごすつもりで参加してみたらどうなるのか、という最低限レベルで参加。
やり過ごす方法を伝授
速い話が、「やり過ごす」方法を教えました。どんな親だよって話ですが。
- 上の空で授業を過ごす方法→外を見る、妄想・空想にふける、帰ってからのことを考える
- 突然興味のない話をガンガンされたときの対処→3回ふーん、と言ったらトイレに立つ
- イラっときたとき→口で言いたくないなら表情でアピール。それもできなければトイレに立つ
こんな感じで、予想できそうなことを一緒に話し合っておき、参加。
「今日はこんなことを考えたよ」と、いかに先生の話を聞いていなかったかを笑顔で話すようになりました。
たぶん、このくらいでちょうどよくなっていると思われます。指示されていることはちゃんとやっていたようなので。
もちろん、担任にも「うわの空」練習中ですので怒らないでね、と根回ししておきました。
発表の目的は人の見た目や反応を気にする場ではないことを知る
発表が苦手なら、原稿をすべて書いておき、読みながら発表する、パーテーションの後ろから発表する、教卓の中から発表するなど、次男からみんなが見えない方法を試したこともありました。
逆にその方が目立つのでは?というツッコミをしたくなることもありましたが、実際に参加してみれば意外と大丈夫だった、という反応も多かったですね。
次男の頭の中だけで勝手にネガティブな方向へ考えすぎていたことで、避けていた授業が多かったことも判明。結局、そんなもんなのですよね。誰だって。
人からの見た目や反応を気にしすぎるあまり、自分の行動を止めてしまっていただけ。
人の反応は人の反応として、好きに反応してもらうことが当たり前。人の感情は自分の望む通りにするものでもないし、自分の湧き上がる感情もすべてその時の事実。
正しいとか、正しくないとかではなく、「こう思った」がその人の事実。以上でも以下でもなく、判定も不要。
だから、うまく発表することが大事なのではなく、自分の考えや思いが、できるだけ自分の思いと同じように伝わる方に意識を注ぐことが、発表などでやることだ、ということに重点を置きました。
学校復帰で気を付けた4つの注意点
次男が学校に復帰するにしても、しないにしても、私の中でここだけは押さえておこうと決めていたことがありました。
いつやめてもいいというバックアップがあること
- 学校に行くという選択肢
- 学校に行かないという選択肢
どちらを選択したとしても、いつでもやめて別の選択肢に変えられる柔軟性を持つように意識しました。
一度決めたんだからやり通す。これも一理ありますよね。
やり続けなければわからないこともありますから。でも、不登校の段階ではこの理は不要かなと。
それよりも、とにかくいろんなパターンを試し、いろんな体験を経験に変えることが優先だと思い、いつでもどんな選択にでも切り替えられるようにしていました。
情報収集がすべての始まりだと思う説
具体的に何をしていたのかというと、情報収集ですね。
常に、フリースクールやホームスクールの情報収集をしておき、また自分ならこうしてみようかと趣味レーションをしていました。
N高やN中は、行く気配がない頃から説明会に参加していて、オンラインスクールというものがどういうものなのか、先生方や学校の雰囲気などをリモートで見たり。
フリースクールは結局、通わなくてはいけないので、人との関わりがキツイ次男の場合は、在籍校かオンラインスクーの2択。
コロナ禍でオンラインスクールが増えたとは思いますが、次男が小3の時は小学生用のオンラインスクールはなかったですね。
収集した情報を次男と共有
でも、中学はN中があるから大丈夫だな、と予防線を張れるというか、在籍とN中と両方をかけ持つこともできるしな、とか他の道を次男に提案できる。
全く違う特性の学校が2つあれば、より自分に合う方を選べますし、どちらもダメならそれでもいい。
今やれることを知り、選択して行動する。
これを大人の行動力でやり続けることで、ポジティブ不登校であってもある程度アクティブに活動していけるかなと思ったので、まずは私が率先して行動し、情報を次男に教えていました。
次男も、在籍がきつくなったらN中があるな、と思っているので、今のところは学校に行くことにも割と前向きに思えているみたいです。
充分すぎるくらいの休息をとること
HSCもタイプによるかもしれませんが、たぶん、昼寝とかした方がいいと思いますし、夜も早く寝た方がいいと思います。
結構、次男は平日の放課後、昼寝しているみたいです。(私は仕事中で知らない)
自動的にスキャン状態になる情報収集量が多いHSCの気質は、記憶として脳が処理する情報も多いということ。
寝ている間の脳の処理能力が倍以上の速さでない限り、寝ないと処理が追い付かないでしょう。
また、リラックスできている時間が少なければさらに、メンタルが休めず体にも力が入りっぱなしになってしまいますね。
次男は、夜の歯ぎしりがひどく、チックになっていたり、爪かみをしていたり。
何か表に見える形でストレスの様子が出ているなら、充分すぎるなと思うくらい休ませた方がいいと思いました。
一番休息が取れる方法はいい意味で放っておくこと
一番いいと思った休息の取らせ方は、家に帰ってきたら別段声をかけないこと。
- 宿題しなさい
- 明日の準備は?
- お風呂に入ったの?
- いつまでゲームやってるの?
などなど。何も言わない。親の方がトレーニングされているみたいですが、頑張りどころです。
声は掛けます。でも2回くらい事前に声をかけたらあとは何も言わない。
宿題忘れてた、忘れ物をしてしまった、などを子供が話してきても、「そうなの、大変ね」で終わり。
いいとか悪いとかを絶対に言わない。次男の行動に評価をつけない。いい意味で放っておく。
私なら、この方法が一番休めるので、次男にも確認しつつ、この方法を実践しています。
そのおかげで、怒らなくてもいいから私は疲れないし、やらなかったことは自業自得だと次男も自覚できるので結果オーライ、ということです。
体験(経験)のために最低1回は参加すること
学校に行くとか行かない選択を、いつでも変更できることは、裏を返せば体験できないことはいつまでもできないままで終わるということ。
これではいつまでたっても、避けたい体験が本当に避けるべき体験なのかの体験ができないのですね。
ですから、次男には、最低でも1回は参加してみることをすすめました。そのうえで、次から行かないというのであれば、それで良しとしています。
1度参加して、トラウマ的にいやになったものに関しては、逆に行かなくていいのですが、そもそも、その学年になってから体験していないものに関しては参加してから決めるようにしています。
すでに体験があって→嫌な思いと連動してしまっているものは→認知行動療法などのアプローチが終わってから再チャレンジしてもいいし、しなくてもいいと思っています。
結構この考え方が効果的で、行ってみたら別に何ともなかった、と思えてくるみたいです。
これは、年齢的なものや、過去に初参加してみて大丈夫だった、という経験の積み重ねからくるものかなと思っています。
最初の1回目ですね、ちゃんと事前に、起こりそうな嫌なことなどの対策を話し合い、必要であれば紙に書いて手に持たせるようにしました。
振り返ること(どんな反応でも受け入れること=傾聴)
学校に行くことに対しても、行かないことに対しても、たまに振り返ること。これは結構大切かなと思います。
今日、今、自分がいる場所。ここから明日以降、自分はどっちの方向に進みたいんだろう、ということを常に確認しながら進むことで、迷わず学校に迎えるから。
休んでいるときは、その場で休憩しているので、その先の方向などを決める必要はありませんが、いざ、進んでみると決めたなら、こっちにいってみようという方向が必要。
そして、その方向に一歩足を踏み出した結果、どうなったのか?何を感じ何を思ったのか?
これを聞いただけなんですけど。
何を言っても、「そうなんだ」とひたすら聞くようにしました。次男の話が先生の悪口しかなくても、友達の悪口しか言わなくても、学校なんて行きたくないといっても、全部「そうなんだ」。
振り返りは私が振り返るのではないのです。次男が自分の行動を振り返る、気持ちの整理をつけるために、言葉で話してもらう、という方法です。
うちは長男も次男も、とにかく何でも私に話してくれるので(だぶん何も否定されないから、話しやすいのだと思います)私はひたすら傾聴に専念できましたが、あまり話さないタイプの子の場合は、紙に書いて捨ててもらってもいいでしょう。
嫌がるならやらなくてもいいかなとは思いますが、どうだった?と声をかけるだけでも、一瞬、頭の中で振り替えると思いますよ。
振り返り:メンタルの段階に合わせて少しずつ学校に復帰したことが不登校を乗り越えられたポイントだったかも

子供の不登校を何とかしたい大人たちは、寄ってたかって学校に戻そうとしますが、その対応はもう昔の話でしょう。
学校に行かない「不登校児=次男」に対し、客観的に分析し、必要な情報を集め、必要な声をかけ、チャレンジする機会を作る。
まるで何かの実験のようで聞こえは悪いかもしれませんが、おかげで私も学校というものが何なのか、子育てとは何なのか、発達障害とはまた別の角度でいろんなことを知ることができました。
次男が学校に行くこと行かないことに対し、「今できること」を積み重ねた結果、次男は4年生から週1休みでフル登校できるでに復帰。
これは、次男と私の日々の選択の先が、学校に復帰するという結果につながっただけだと思います。
子供が不登校になる理由は、ひとそれぞれ、さまざまでしょう。
今回私が、不登校復帰をメンタルの段階に分けて対応してきたことをまとめてみたのですが、これは復帰したから言える結果です。
これはいいな、と思うものがあれば参考にしていただき、うちの子には合わないなと思うものは、こんな人がいるんだな程度に思っていただければと思います。