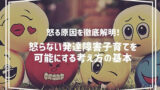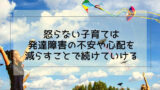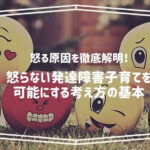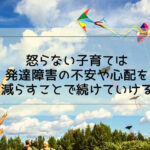怒らない子育てを実践するには、怒りに隠れた感情を、正しく表現することが最初にやることです。そのためには、怒りを伝えたい相手に、正しく自分の感情を伝える必要がありますよね。
ただ、発達障害の子供は、特性によりコミュニケーションがうまくいかない場合が多いと思います。ですので、大人の方が子供の特性に合わせて理解できる伝え方をすることが必須。
ここがうまくいかずに怒られたとしても、子供は何に怒られたのか、何が何なのか理解ができないまま、大人の怒り爆弾をダイレクトに受けることになってしまうのですね。
子供も身を守るために反抗したりパニックになったりするため、さらに子育てが大変になるという負のループにはまってしまいます。
もともとは、怒りに隠れた自分の感情を、自分が正しく表現できていないことが問題の根本ではありますが、ここでは、発達障害のお子さんの特性に合わせた伝え方(声掛け方法)とは何なのか、ということを中心にお話を進めていきます。
怒らない子育てを目指すことはもちろん、声掛け方法がわかれば子育ての困りごとは大きく減ることになりますし、ラクになるでしょう。
いろんな発達障害の情報を参考にしたけど、もうどうにもならないよ、お手上げなんですよという方に、別の切り口として参考になればうれしいです。
※あくまでもただの母親である花緒の体験からくる方法であることを、ご承知おきくださいね。
実践前の事前確認と準備

子供のうちは、知らないことが多いので、一つ一つ教えてあげる必要がありますよね?
なんとなくわかるよね、前も教えたよね、というこどが続くと、だんだんイライラしてしまうのは、仕方がないでしょう。
ただ、何度も教えなくてもわかっていることもある。ならば、その方法を分析して分かっていないことに応用すれば、イライラせずに済むのでは?
ということを改めて考えてみましょう、という提案です。
事前確認
まずは怒らない子育てを実践するために必要な情報を確認し、整理しておきましょう。ここでは、以下の3つを確認していきます。
- 自分が怒ってしまうパターンを把握
- 最終的に望んでいる怒らない子育てのゴールの確認
- 子供の特性を確認
自分が怒るパターンを把握
さて、自分が子育て中に怒るパターンは何でしょうか?
- いつ怒るか?
- 誰に怒るか?
- 何を怒るか?
改めて考えてみると、パターンが見えてくると思います。そのパターンを探しましょう。
年齢や性別、兄弟の有無や同居している人の有無などによって、さまざまあると思いますが、具体的に考えてみた方がいいと思います。
自分の機嫌や人前にいるときなどで、怒る基準が変わるのはアウト。
大人の矛盾には子供は敏感。矛盾を感じると信用を失うので、基準は守った方がいいでしょう。
自分が何に怒るのか、ということについては別記事で詳しい考え方をお話していますので、興味のある方は参考にしてください。
望む改善策ゴールは?
それぞれの怒るにおいて、自分が望んでいることは、何でしょう?
どうなれば、改善したな、と思い、怒る必要がなくなるのか、という基準をある程度はっきりさせておきましょう。
自分が怒らなくなる、ということは、つまり、子供がある程度自分の思う通りに動いてくれるようになっている、ということも含まれるでしょう。
いつも怒っていたことが、片付けならばこんな感じ、宿題ならこんな感じ、というように、なんとなくでいいのでゴールをイメージしておくと対策しやすいと思います。
子供の特性を確認しておく
一般的な概念を確認してもいいのですが、ここでは、
- 怒ってしまう子供の何に困っているのか
- 子供の特性は?
という順で考えてみます。
特性まで確認したときに、自分が過去に怒った方法で、発達障害の特性上、伝わる怒り方だったのか?
そんな観点から特性を確認していくと、自分ではわかっていたつもりなのに、子供の特性に合わせた接し方がうまくできていなくて子供を怒ってしまっていたかもしれない、ということに気づけるんですよ。
特性と確認したら、参考にできそうな接し方も軽くおさらいしておくと、今後の接し方の参考になると思いますよ。
準備
事前確認が終わったら、準備に入ります。おそらく準備に一番時間がかかると思いますので、やれそうなところからどんどん動いていきましょう。
- 怒らなくてもよい環境に調整する
- 怒らない子育てをするための声掛け方法を考える
- 代案を用意する
環境調整:使えるものは使い工夫して怒らなくてもよい環境にする
子供と過ごす環境を調整することで、子供が怒られる行動は減っていくと私は思います。
例えば、
- 子供部屋を作る、子供専用スペースを決めてみる(テントや段ボールハウスなど)
- 触られたくないものは見えないところに置く、または置かない
- 危険が多い場所では遊ばせない
- 兄弟のフォロー
- 協力者を増やす(習いごとや学校の先生、療育やセラピー市町村の施設、ボランティア団体など)
- ヘルパーやベビーシッター、預かり保育、親族などに預ける
- 便利家電を買う(乾燥機付き洗濯、食洗機、自動調理鍋など)
子供がおもちゃを片付けなくて毎日怒ってしまう場合なら、子供部屋を作ってしまうとか。他の部屋におもちゃがあったとしても、全部子供部屋に投げ込んでしまえばいい話。
要は、共有の部屋におもちゃが散らかっていると、大人の目に触れ、片付けない子供が怒られるパターンになるのですが、おもちゃが見えなければ大人も腹が立ちませんよね。
- 片付けを教えることと
- 習慣づけることと
- 片付けない子供を怒ること
これらは、すべて別の話だと思っています。今回は、怒らないをテーマにしているので、怒らない環境にするのであれば、子供部屋を作ってすべてそこに投げ込むことで解決します。
子供部屋以外に散らかっているおもちゃを、子供部屋に投げ込むのを子供にやらせようとしないことで、怒らない子育ては成立しますからね。そんな感じで、新たな発想で、子供を怒らなくても済むような環境を作っていきます。
関係なさそうに見える家事や育児の一部委託は、自分の時間に余裕ができ、自分時間を生み出すことで、怒りを生み出さないようにしています。
お金がない場合は、工夫するしかありませんが、お金で何とかなるものは自己投資だと考えるのも手。子育て以外のタスク効率化を図ることで環境を整え、子育てと自分時間確保に専念することが理想です。
声掛けを見つける:実行方法を考える
ここが一番のポイントなのですが、一般論で言われている発達障害の特性ではなく、目の前の子供の特性をよく観察してみてほしいのです。
子供が生まれてから今まで、本能でできたこと以外は、何らかの方法で子供がそのスキルを取得できているということ。
- 道具の使い方
- 洋服の着方
- 自転車の乗り方
など。どうやってできるようになったのかを思い出しましょう。そして、そのとき、どのような声掛けをしたのかを思い出しましょう。
- うまく伝わるパターン
- うまく伝わらないパターン
- それぞれのタイミング(時間的な、場所的な)
このあたりをキーワードにして、過去の記憶を探ってみるといいかもしれませんね。
イラストや動画の方がわかりやすいのか、言葉がどこまで通じるのか、などを思い出し、声掛けのパターンを作っておきましょう。
代案を用意:うまくいかない想定をしておく
子供相手ですので、1回でうまくいくとは思わない方がいいでしょう。代案をいくつも想定しておくことで、怒る前に対策がヒットするかもしれません。
なんかうまくいってない、と思ったrすぐに次の案に切り替えられるように、代案を用意しておくといいですよ。
タイミング的に時期尚早な場合もありますし、ちょっとずつ変えて調整していくうちに、フィットする方法にたどり着くかもしませんし。
最初からうまくいかないと思っておけば、想定の範囲内ですので、イラつくこともありませんしね。
声掛けで怒らなくなるまで調整する

ここまで考えてきたこと、用意してきたことを使い実践。怒らなくなるまで調整し続けることで、怒らない育児は可能になります。ここからが本番です。
子供には予告してから実践する
実践する前は、必ず子供に予告をします。予告のタイミングは、機嫌のいいときが良いでしょう。
集中して何かをやっているときは避けた方が無難。長男の場合は、ご飯やおやつ、お風呂、それらの直後などのタイミングが比較的、話が入りやすかったですね。
予告は、いつから何をやるのか、ということを短く簡潔に伝えればいいと思います。
例えば、今日から怒らないで過ごしていきたいから、おもちゃで遊ぶときは、このスペースで遊んでもらってもいい?みたいな感じで伝えてみるなど、です。
検証する
実際に実践を始めたら、検証をしていきます。
うまくいっていることには、必ずパターンがありますので、
- なぜうまくいったのか?
- なぜうまくいかなかったのか?
ということを考えてみるといいでしょう。
いろんな方法や情報が、本やネットなどで入手できますが、結局は、自分と子供用にうまく変換し、使っていけなければあまり役には立たないのです。
ある程度の方法だけ参考にしたら、あとはひたすら目の前の子供の様子を観察し、こんな風にしてみればいいのかな、こういう方法もあるんじゃないかな、と試行錯誤していくしかないんですね。
望む改善策ゴールにたどり着くまで工夫し続ける
うまく回り始めると、その方法が日常になり、習慣になっていくので、さほど苦ではなくなるはず。
怒らなくなってきたのに何か辛さがあるなら、別の問題が潜んでいるのかもしれませんね。
すぐに結果が見えなくて、へこむ日もありますが、そうやって親子ともに生きていくのだと思います。
そういえば最近怒ってないかも、という状態になるまで繰り返すことで、怒らない子育てができるというのは、なんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。
怒っちゃダメなんだ、とか、怒ってしまう自分は母親失格だ、とか、極端な思考に向くのではなく、常に現実に起きている事実を正しくはあくていくことで、自分に湧き上がる感情も少しずつ変化するでしょう。
そんな感じで、試行錯誤していく日々が、子育てってことなのかな、と思います。
振り返り:怒らなくなるまで工夫し続けることで発達障害子育てはラクになる

怒らない子育てが可能になったら、今の生活はどうなると思いますか?
私の場合は、「これって怒るった方がいいんだっけ?」と考えた自分に、びっくりしました。
ちなみに、子供の年齢とともに、大きな声で怒る必要はなくなります。
なぜなら、会話でコミュニケーションが取れるようになるからですね。
さらに、命の危険的なものも年齢が上がるとさすがになくなっていきますし、火の扱いとか別の危険があったとしても怒らなくでも話せばんかりますからね。
あとは、子育て中の心配や不安をどう処理していくのかにより、さらに怒らない子育てになっていくと思いますよ。
伏線的な感じにはなりますが、自分の心配や不安を、一度ちゃんと考えてみてもいいかもしれませんね。