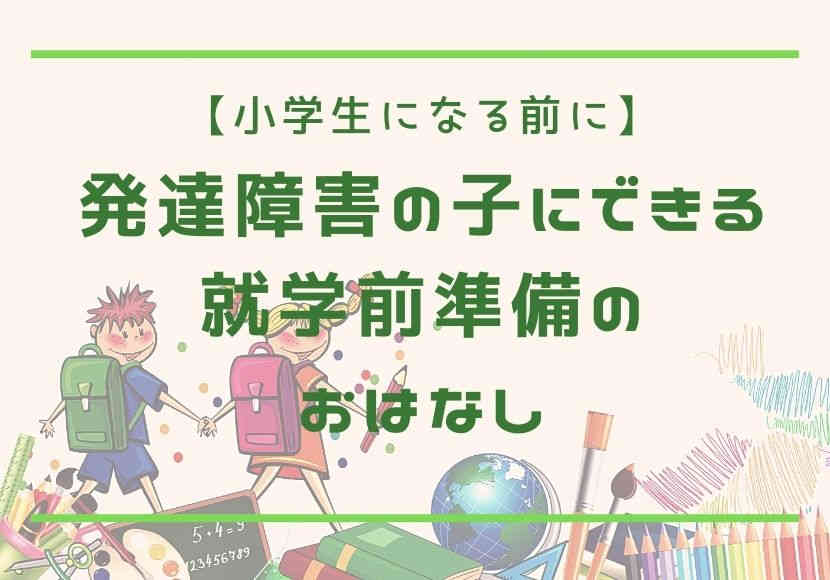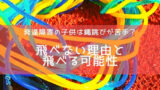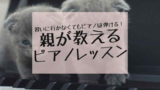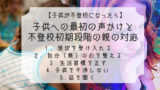発達障害の特性を持つ子供の子育てをする中で、小学校へ入学する、ということは結構な一大イベントですよね。
発達障害の子供に、親として就学前にできることは何があるだろう、という考えを記載しています。
通級に通うかどうか迷っている、今やれることはやっておきたい、という方のお役に立てるとうれしいです。
小学生になる前に発達障害の子にできる就学前準備リスト
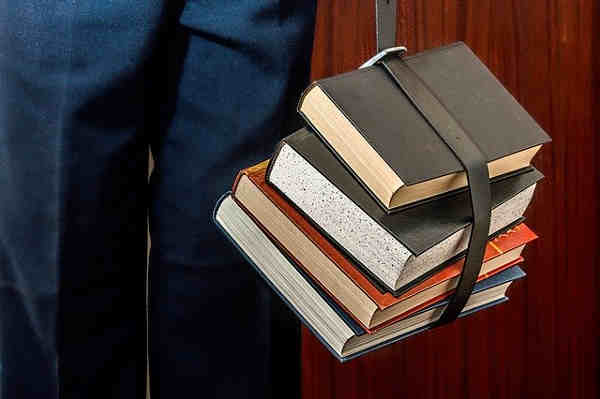
公共機関を利用してできること
- 就学前相談
入学前までにできるだけ教えておきたいこと
- 通学路の確認
- 着替えの練習(体操着・給食着など)
- 折り畳み傘の使い方練習(置き傘)
- 名前を書く練習
- 配膳の練習
- 郊外学習に向けて(リュックやお弁当・レジャーシートの使い方)
- レインコートの使い方
- 毎日少しずつのお勉強
必要に応じてのサポート
- 教科ごとのファイルを用意する
- プリント用のファイルを用意する
- 運動の補佐(なわとび・鉄棒・マット運動など)
- 楽器の練習(鍵盤ハーモニカ・リコーダーなど)
- 音読の練習
- 教科の事前学習(日本地図・九九など)
- 給食の練習(お箸やお椀の持ち方使い方)
- チャレンジタッチなどの家庭学習または宿題を想定したワーク練習
親として考えておいた方がいいこと
- 役員やボランティアに参加するかどうか
- 担任の先生へ伝える内容の準備
- 働いているなら学童の準備
- 不登校に備えてフリースクールなどを調べる
- 学校に行きたくないと言われたときの対処法
【公共機関を利用】就学前相談

小学校に入学後、通級(特別支援教室)に通うことを希望するかどうかの制度のことです。
通級を希望する場合、就学前であれば就学相談への申し込みが必要になります。
説明会
春くらいに就学前相談の説明会があると思います。市区町村によって違うかもしれませんが、説明会などのようなものは何かしらあると思います。
幼稚園や保育園の先生に問いあわせてみるか、市区町村の役所に聞いてみましょう。
申し込み
説明会に出席した場合は、その場で申し込みができると思います。説明会に出ていなくても、管轄の部署に連絡を入れれば申し込みはできるはずです。
入学後、お子さんの通級を希望しているなら、早めに希望しておくといいでしょう。
幼稚園や保育園の先生、わからなければ市や区役所に聞けば、わかると思います。
発達検査と面談
就相談の申し込みが終わると、発達検査や心理士との面談などがあります。特に事前に何かを練習する必要はありません。
今の子供のままを、そのまま検査や面談に活かした方がいいと思います。(結果が変になった方が面倒なので、勉強系などは何もせず、そのままの状態で検査をした方たよい)
この時、親も面談をすることがありますが、その際は以下のようなことを聞かれました。
- 子供の好きな遊び
- 加配は必要か否か
- 通級に通う目的
- 家での過ごし方
- 困りごとや不安など
グループ活動観察(数人の医師が子供の行動を観察)
60分から90分くらいだったと思います。
要するに、学校生活という一定人数が集まる場所で、子供がどのような行動を取るのかを、数人の医師が観察します。
数名の子供が同じ部屋で、遊びの課題などを元に遊びつつコミュニケーションを観察することです。
何が正しくて、こうだと悪くて、ということではなく、あくまで集団の中でどういう行動をしてしまうことにより、困りごとがおきるのか、ということを判断するためのものです。
繰り返しますがいい悪いではないので、家庭で事前にどうこうするものではありません。
判定通知がくる
すべての結果を元に、医師が判断した通級の判定です。
通級が必要、通級は不要、というようなことを判断するわけですね。
これは、市区町村から手紙がきて、その内容として「在籍+通級」のような内容が書かれています。
読んだら、「あぁ、そうですか」と思って、どこかに収納してしまっても大丈夫な書類です。
新学期を待つ
通級判定がきたら、就学前相談としては特にやることはないでしょう。
あとは新学期まで待ちます。
入学前までにできるだけ教えておきたい8つのこと

通学路の確認
地域のお友達同士で確認することがあるかもしれませんが、春休み中に通学路の確認はしっかりとやっておいた方がいいでしょう。
集団登校であれば問題ないとは思いますが、帰り道などは入学当初しか先生は送ってきませんので、一人で学校まで行き来できるようにしておいた方が親も安心ですよね。
着替えの練習(体操着・給食着・水着など)
幼稚園である程度着替えの練習をしているとは思いますが、心配な場合は体操着や給食着などを一人で脱ぎ着できるよう、練習をしておくことをおすすめします。
1年生のうちは担任を始め、サポートの先生が来たりしますので大丈夫だとは思いますが、意外と水着から洋服に着替えるのは大変です。
スイミング教室に通っていない場合は、家庭で事前に練習しておくと子供も安心できると思います。
折り畳み傘の使い方練習(置き傘)
置き傘で折り畳み傘を学校のロッカーに置く場合、またはランドセルに常備させる場合、折り畳み傘の使い方をしっかりと教えておきましょう。
開くことはできるけれど、たたむことはとても難しいです。
できなければ担任の先生がやってくれるとは思いますが、通学路の途中で使う場合やたたむ場合、最低限、ここまでできれば歩けるな、というところまでの使い方は教えておくといいと思います。
名前を書く練習
年長さんになると、幼稚園でも保育園でも、自分の名前を書く練習はすると思いますが、家でも年のため、自分の名前を書く練習をしておくといいと思います。
書けているなら問題はないので、書けていない場合、ちょっとずつでいいので毎日練習しておくことをおすすめします。
入学当初は何かと配り物が多く、自分の名前を書いておきましょう、ということもあり得ます。
サポートに入る6年生がやってくれる場合もありますが、徐々に自分で名前を書いていくようになりますので、名字だけ、名前だけでも書けるようにしておくといいでしょう。
配膳の練習
給食当番は名簿順に割り振られることが多いと思います。
1年生のうちは、6年生がサポートに入りますし、加配の先生方も手伝ってくれるとは思いますが、ごはんをよそう、お味噌汁をわける、といった日常生活に必要なスキルは覚えておいて損はありません。
給食当番のためはもちろん、子供が自分で食べていくスキルとして、配膳はできるようにしておくことをおすすめします。
郊外学習に向けて(リュックやお弁当・レジャーシートの使い方)
幼稚園の時は遠足くらいしかリュックを使わなかったと思いますが、小学校に入ってからは校外学習がありますので、リュック・お弁当・レジャーシート・レインコートはよく使います。
これらの使い方や、リュックのしまい方は練習しておくと、子供が大変な思いをしなくて済むと思います。
レインコートの使い方
雨の日は、傘ではなくレインコートを使う場合、練習しておいた方がいいのがレインコートの着方と片付け方。
家を出るときは、お母さんがレインコートを着せてくれるので問題はないのですが、学校についてからは一人です。
一人でレインコートを脱いで、フックにかけるなり、たたむなりしなければなりません。
そもそも、ランドセルを背負ったままレインコートを脱げない、ということも起こり得ますので、ランドセルを背負ったままレインコートを着せてみて、一人で脱げるかどうか確認してみるといいと思います。
できなくても、先生や6年生、友達など、誰かがやってくれるとは思いますが、できるに越したことはないでしょう。
毎日少しずつのお勉強
これからの時代、宿題が定番のままかどうかはわかりませんが、念のため、毎日宿題をやることを想定して、1日1枚のプリントやワークなど、何かしらのお勉強を習慣づけておくといいと思います。
「ちえ」や「めいろ」、「まちがいさがし」など子供が楽しめるものでいいと思います。
必要に応じてできるの9つのサポート

教科ごとのファイルを用意する
忘れ物をしてしまうADHDタイプの子というよりは、教科書・ノート・ワークのセットがわからないような子におすすめなのが、教科ごとのファイルを作っておくことです。
ADHDタイプの子は、ファイルを作ってあげても、その中に入れませんので意味がないんです。
国語の教科書、ノートが授業で必要なセットだ、と理解できない子の場合は、ファイルを用意するとわかりやすいようです。
授業が終わると、またファイルにしまうだけでいいので子供の方もラクみたいですよ。
プリント用のファイルを用意する
学校からの連絡プリントを入れるファイルですね。低学年のうちは、担任がファイルにしまうように声掛けをしてくれるように頼んでおくとうまくいくと思います。
低学年のうちは学校が許してくれないかもしれませんが、子供が好きなキャラクターのクリアファイルにすると、使いたくてちゃんとプリントを入れて持ち帰ってきますよ。
運動の補佐(なわとび・鉄棒・マット運動など)
出来なくても死にませんが、学校の体育で必ずと言っていいほどやる運動。走ることに始まり、縄跳び、鉄棒、飛び箱、マット運動は必須です。
家でできるとしたら、縄跳びとマット運動は親でも教えられますよね、
子供が嫌がる場合は無理にやらなくてもいいですが、親と一緒に少し触れているだけでも違うものです。
体操教室に入れる必要はありませんので、親子の遊びの中で縄跳びやでんぐり返りができると、体育の授業での「できない」が減ると思います。
楽器の練習(鍵盤ハーモニカ・リコーダーなど)
運動と同じ理由で、音楽の授業は避けられませんので、鍵盤ハーモニカやリコーダーなど、楽器ができるといいでしょう。
特に鍵盤ハーモニカは、吹きながら弾くという、同時に2つの作業をやりますので、何気に難関です。
ピアノを習う必要はありませんし、音符も読めなくていいのですが、おもちゃのキーボードなどで指を動かす練習をしておくといいかもしれませんね。
音読の練習
音読は、声に出して文字を読むだけではなく、少し先を読み、少し予測し、先に読んだものを記憶しつつ、現在読んでいる箇所を口から発するという結構高度なことをやっています。
学校に入ると、教科書を読む、ということが起こります。
学習障害の傾向がある場合、教科書の音読は難関の一つ。
うまく読めないなら読めないなりのサポートが必要になりますので、年長時で絵本の音読ができるかどうかは、知っておいた方がいいと思います。
教科の事前学習(日本地図・九九など)
やらなくても問題はありませんが、生きていく上で覚えておいても損がないものがあります。
日本地図や九九は早めに覚えておいても損はありません。
九九は2年生で、日本地図は4年生で勉強しますので、早めに覚えておくとお得です。
遊びながら知らないうちに覚えているパターンが親もラク。おもちゃで覚えておくと後々苦労しませんよ。
長男も次男も幼稚園の時には日本地図をすべて覚えていました。九九も年中で覚えられていたので、遊びながらできると思いますよ。
給食の練習(お箸やお椀の持ち方使い方)
手先が不器用な子であれば、お箸やフォークの使い方をおさらいしておくといいですね。
担任の先生がうるさく注意するタイプであれば、お椀を持って食べるとか、箸の使い方や食べる速度など、何かと注意されるかもしれません。
苦手な食べ物や牛乳が飲めないなどは、事前に学校側に知らせておくといいでしょう。
チャレンジタッチなどの家庭学習または宿題を想定したワーク練習
家庭の方針によるとは思いますが、家庭学習的なものは何かやっておくといいと思います。
タブレット学習は、ゲームや子供の習性をうまく利用して作られていますので、万が一、不登校になったときでも役に立ちますし、学校の授業替わりにも使えます。
どんどん進める子であれば、予習の代わりになりますし、宿題をやりたくないタイプの子であれば、タブレット学習で勉強はカバーできるでしょう。
無理にやる必要はありませんが、何かやっておくと安心、というレベルです。
なくなりそうなものは予備を用意
鉛筆、消しゴム、定規(三角定規含む)、ノート、下敷きなどの文房具類は、予備があると安心です。筆箱ごと行方不明になることもありますので、全部2つずつ用意しておくといいでしょう。
傘はなくすより壊しますので、こちらも常時2本あると安心。なんで?と思うものですが、紅白帽子は行方不明になりやすい。その他、縄跳びや彫刻刀、うちはリコーダーも2本あります。
100円ショップにもいろいろ売っていますので、予備は安いものでいいのであった方がなくなっても慌てずにすみますね。
親として考えておいた方がいい5つのこと
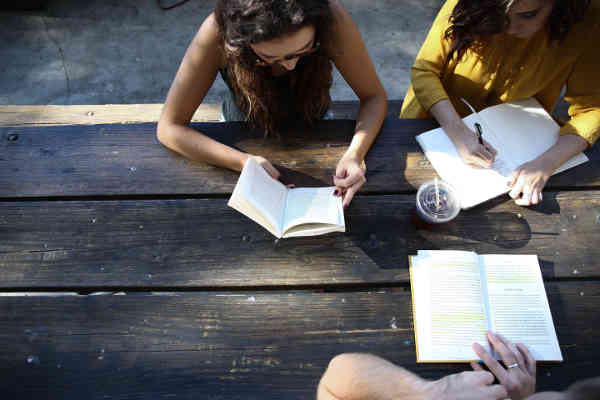
役員やボランティアに参加するかどうか
役員や学校ボランティアへの参加は大変そうだと思うかもしれませんが、学校での子供の様子がわかるので私は積極的に参加しました。
先生方とも会えばお話ができますし、先輩ママ友情報も結構入ってきます。
郊外学習や学校行事のこと、先生や長期休みの宿題案、受験や習い事など、リアルな口コミにはたくさん助けてもらいました。
必要以上に深く付き合うと、人間関係が面倒になるので、サラッと情報収集するつもりで、役員カウントも終わらせてしまってもいいですよね。
担任の先生へ伝える内容の準備
学校に子供の配慮をお願いするなら、就学前相談とは別で担任に依頼したいことをまとめておくといいです。
私は、子供の様子やお願いしたい配慮などをプリントとして用意していましたが、
- 連絡帳に書く
- 手紙を書く
なども有効です。1回作っておくと、毎年必要な個所を修正するだけでずっと使えますし、学童や放課後デイサービス、習い事などさまざまな方面で使えますので、ベースを作っておくことをおすすめします。
働いているなら学童の準備
仕事をされている方の場合、学童は早めに動いておいた方がいいでしょう。役所系のことは何かと面倒になりがちなので、休みの日を利用してサクッと終わらせておくことをおすすめします。
不登校に備えてフリースクールなどを調べる
発達障害の子供を育てるにあたって、不登校になることはある程度覚悟しておきましょう。
不登校になることは、子供自身が自分の命を守ろうとすることだと私は思っていますので、あまり深く深刻に悩まずに、子供にあった環境を考えるいい機会だと思ってみるといいでしょう。
不登校になったからと言って死んでしまうわけではありませんので、通信制の学校やフリースクールなども、あるものすべて利用できるものは使っていきましょう。
そのためには、事前に情報収集をしておくといいと思います。
ネットで調べてもいいですし、市役所区役所でも情報を教えてくれます。保健センターや教育センターなど、お住いの市区町村で使えそうなものは情報収集しておきましょう。
もしくは、ホームスクールという考え方もあります。親が仕事をしていなければホームスクールの方が子供に合っている場合も多分にあります。
大切なことは、子供が育つ環境として、今、選択できるベストは何か、ということです。一般的な固定概念にとらわれることなく、親子で最適な選択をするためにできることの第一歩が情報収取です。
行かなくても知っておくだけで親の心の安定につながりますので、時間が空いたらある程度調べておくことをおすすめします。
学校に行きたくないと言われたときの対処法
家庭の方針によると思いますが、「学校に行きたくない」という言葉を子供が発した場合、親として何をこたえるのかを決めておくといいでしょう。
先に決めておかないと、その時の親の気分や状況で、全く違うことをこたえてしまう可能性があるからです。子供は意外とするどいので、その矛盾にはすぐに気づいてしまうんですよね。
親が一貫性のないことを言っていると、信頼できなくなりますので、事前に考えておきましょう。
ちなみに私の場合、子供が学校に行きたくない、と言ったら、そうですか、と答えます。
そのあと、子供が何を言うかにより、判断するといった感じです。
振り返り:無理のない範囲で発達障害の特性に合わせた就学前の準備をしておくに越したことはない

就学前の子育てだけでも大変なのに、と思われるかもしれませんが、事前に準備や対策を用意しておくことは、その後の学校生活に大きく関わってくると私は思っています。
なんとなく行き当たりばったり必要、でももちろん構いませんが、それでは子供の表面の様子で判断しがちになってしまう可能性が高い。
そうではなく、本当は子供が何を言わんとしているのかに気づけるのが親だと思いますので、時間を見つけてできる限りの情報収集をしておき、必要なタイミングでサッと動けるといいですよね。
ちょっとしたことばかりかもしれませんが、意外とそういうことって大切だと思います。
あとから、「あの時こうやっておけばよかった」と後悔することは簡単です。発達障害の子育てはマイノリティの子育てなのですから、できる限りのことを予測し、親としてできることをやっておけば、後悔は少なくなる。
親も親としてどう生きたいか、というスタンスの問題になってきますが、やれるだけのことをやった結果は、必ず子育てに反映されると思いますよ。