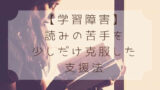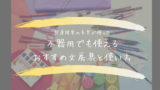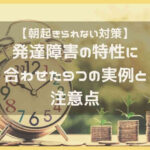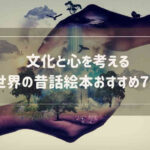本が読めない、漢字が書けない、掛け算が覚えられない、などの学習障害。いつ頃から気づくものなのでしょうか?
長男は、検査では読字も書字もアウトな感じです。中2になった現在では、本人の意地とある程度の頑張りにより、ガジェットを使わずに学校生活を送っています。
幼児期に数字の概念が変だった時期はありましたが、成長とともに問題なくなったので、算数障害についてはご紹介していません。
今回は学習障害の長男を例に、実際に私が学習障害に気づいたきっかけについて実例を紹介していきます。
学習障害に気づくのは年中頃(4・5歳)には傾向が出ているのではないか?

一般的に学習障害き気づくのは、小学生になってから、と言われていますが、私は長男が年中あたりから「何か変だな」と感じていました。
具体的な長男の様子を紹介します。
絵本の読み真似がなかった
絵本の読み聞かせは毎日やっていました。リクエストも多く、何度も読んだり、一度に何冊も読んだりしていました。
ただ、長男が一人で本を開くときはきまって図鑑。無言で黙って見てましたね。
2歳くらいになると(やらない子もいるのかもしれませんが)、普段読んでいる絵本の読み聞かせの真似をするじゃないですか。
「あー、あー、・・・たっ!」みたいなやつ。
今思えば、あの読み真似的なものはなかったですね。

絵本全然見ないのね、って思ってました。
ごくたまに「トーマス」などの単語は発していましたね。
お絵描きに違和感あり
4歳くらい(年少あたり)の頃、キャラクターの絵を描いてほしいと言われ、アンパンマンやトーマス、ウルトラマンなどの絵を描いていたときのこと。
長男に、「自分でも描いてみたら?一緒に描こう」と声をかけたのですが、「こんなに上手く描けないからいい」と断られました。
いやいや、誰だって最初からうまくは描けないのだから、と思ったのですが、その真剣な表情に驚いたことを覚えています。

正直、この子は何を言っているのだろう?と思いましたね。
普通、そんなことは気にせず、無邪気に描くでしょう、と。
自由に描くこと(壁や机に大きな模造紙を貼って自由に描かせていた)は好きだったようですが、キャラを真似て書くことはなかったような気がします。
その後、年長だったかな。納得のいく丸を書くこと40分。当時は、これじゃ、授業が終わっちゃう・・と思いました。
結局、小3くらいの時に、アニメキャラの描き方をスパルタで教えたので、今では結構上手く書けるようになっています。
年長冬でも名前が書けず
年長冬、6歳になったばかりでしたが、自分の名前が書けなかったです。なのに、当時、習っていた将棋の駒のレタリングはやっていました。
このギャップにすごく戸惑ったんですね。今なら認識の種類が違うのかもなーと思えますが、7年前は不安でしかなかったです。
ワーク的なものはずっとやっていたのですが、なぜなのか見ては書けても見本がないと書けず。
とりあえず、名前さえ書ければ何とかなるかと、名前だけ練習しました。
文は一文字ずつしな読めない【年長冬】
長男が年長の冬頃、絵本が読めないことを、私はかなり気にしていました。
文字に触れていない訳でもないし、教えていないわけでもない。
発達障害であることはわかっていましたが、何かおかしいぞ、と本気で思っていました。
知り合いに相談しても、「そういう子もいるって」と言われるし、気にしすぎなのかもしれないけど、何か違う、という自分の直感はあるわけで。
読み聞かせでは、話の内容をちゃんと理解しているのに、長男が自分で読むと誰の話なのかもわからない。
この体験が、長男の学習障害を意識し始めたきっかけになっています。
ノートのマス内に字が入らない
小学生に入ってすぐから始まる宿題。ドリルは本当に大変でした。
とにかく、字がマスに入らないので、国語も算数も何を書いているのかわからなくなることか多かったです。
漢字学習が始まると、同じように字が書けないイラだちから、自分の手の甲や指、壁などを鉛筆で刺し始めるようになりました。
私の中では、長男の学習障害はある程度確定していたのですが、低学年時の学校の先生は宿題の方法を緩めてくれることはありませんでしたね。
地獄絵図、みたいに私の目には長男の姿が写っていました。
音読で文を切る場所が分からない
目の筋肉が弱い関係で、一行の文を読んでいる最中、チラッと目が横にそれてしまう長男。
療育でビジョントレーニングなどの対処はやっていましたが、音読ではつまずき過ぎて読んでいる箇所がわからなくなることがよくありました。
さらに、文をどこで切って読むのかわからず、もうパニックに陥っているわけです。
普通は、低学年の教科書ですと、単語ごとにスペースが空いていますから、何となくそのあたりで区切るのですが、長男にはそれが理解出来ず。
私が読み聞かせをした後、斜線を引いてから読むようにしたらなんとか読めるようになりました。
筆算の桁を揃えられない
先程のマスに書けないのと同じです。
マスの線が邪魔だったみたいで、線ナシノートなら何とか筆算できましたが、2年生くらいの計算は暗算してました。
- 1年生用のノートを使う
- 1ページ1問にする
など情報を減らしたらできるようになりました。
学習障害かどうかわからないときの判断のポイント

私が学習障害の長男と接してきて、判断に迷ったときに基準にした考え方は、次の2つ。
- 経験がないから→理解できないのか
- 経験があっても→理解できないのか
私は、後者の方を学習障害だと判断しています。
経験がないから→理解できないのか
まず、経験がないから→理解できない。のであれば、
- 経験してみる
- 理解できなければ別の方法を試す
それでも理解できなければ別の人にお願いしてみる
理解できない理由を分析し、今、思いつく方法を次々試してみた結果、やっぱり理解できていない場合、学習障害を疑ってもいいと思います。
何か変だな、何か違うな、と感じる直感があるなら、放置しない方がいいでしょう。
乳幼児期からのアナログな遊びはとても大事だと痛感
- 数を数える
- 積み木やブロックで遊ぶ
- 水遊びや粘土などの感覚的な遊び
- 歌うこと、走ること、ボールを使うこと
- 絵本などの読み聞かせやふれあい
いろんな経験を通して、言葉を覚え、やり方があることを知っていく。
目で見て調整して体を動かすことが、後の学習に大きな影響を与えることを、子育てを通じて痛感しました。
子供が小さいうちは、子育てが大変過ぎて、理屈で理解しがちですが、幼児教育という大げさなもので考えずとも、超大事です。
経験があっても→理解できないのか
経験があっても→理解できない、場合(別の方法は試し済みだと考えて)、学習障害だと思って動いた方が良いと思います。
もしかしたら学習障害かも?と思ったら相談・診察を申し込む
何に引っかかっているのかをはっきりさせることで、何かが変だと思い続ける悶々とした日々から抜け出せます。
悶々としているその時間も、子供は成長していますし、何もやらずに考えているだけでは何も変わらないと思うので、私はすぐに診察や検査を申し込んでいました。
長男は、Wiskの検査は就学前検診時に受けていましたので、小3のときにK-ABCⅡを受けました。
検査や診断などの相談についてはこちらの記事を参照ください。
振り返り:早ければ年中くらいから学習障害に気づけるのではないか

長男の学習障害に疑問を持ち始めたのは年中あたりからです。
後から思い返せば、こんなことも兆候としてあったのかな、と思うこともありますが、やはり読み書きができるあたりから何かしらわかってくるものがあると思います。
ただ、家庭での過ごし方や遊び方、大人や友達との接し方や兄弟の有無などによっても、多少違ってくるような気がしますので、少しでも何かひっかかるな、と感じたら、相談先に連絡してみることをおすすめします。
もし、学習障害だとしても、日常にすることでつながっていくものもあると思うので(人によって違うとは思いますが)、学習障害の兆候があるから→ネガティブに考える、のではなく、そのときにできることをやっておくこと。
後々ものすごく困ることになってから、
- やっぱり診断しておけばよかった
- 検査しておけばよかった
- 通級に通わせればよかった
- 療育をお願いするべきだった
と思っても、時間は戻りませんね。
現状、できないことや理解していないものに関しては学習障害だと思って接しておくのも、一つの対策です。