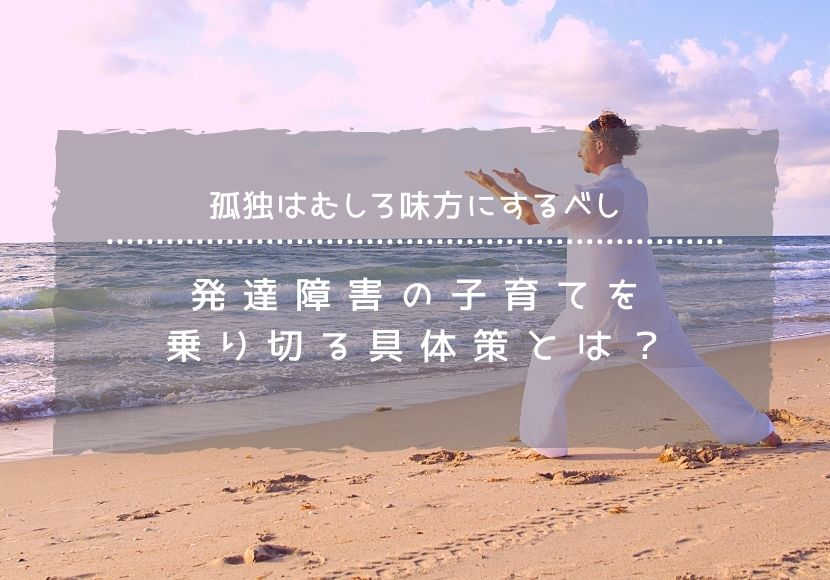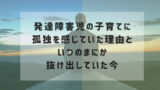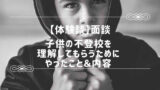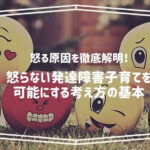発達障害の長男の子育てで、どうにもならないくらいの孤独感を感じていました。
しかし、逆に辛い孤独状態に目をつぶらず、「今の自分にできること」をやり続けたことで、孤独は辛いと感じることはどんどん減っていきました。
むしろ孤独が味方になったことで、発達障害子育ての大変さも、何かわからない疎外感のような孤独も乗り越えられたような気がします。
今回は、どうやって孤独を味方につけたのか、具体的に何をやったことで、対策にしてきたのかについてお話します。
今、発達障害のお子さんの子育てで、孤独感に悩まされている方の参考になればうれしいです。
なぜ発達障害の子育てに孤独を感じる?自分でできるメイン対策

辛い孤独を対処しつつ、この孤独を何とかしたい、できるなら孤独を感じず楽しい子育てライフを過ごしたい、そう思っているのなら、まず自分の孤独について知ることから始めましょう。
「敵を知り、己を知ればナントヤラ」ですね。
孤独であることを良しとする
孤独を感じている状態、というのは、自分が生きているコミュニティに分かり合える人がいない、少ないということですね。
人間は集団の中にいることで安心を得ている
人間は集団で生き延びてきた生き物ですから、本能的に群れを成していた方が安心するそうです。
自分と同じ悩みなどの感覚を、誰かと共有できない場合、これでいいのかな?合っているのかな?極論までいくと、自分や家族の命の安全は保証されているのかな?と本能が察してしまう。
だから不安になり、孤独を避けようと、群れに入ろうと、同じ感覚を探そうとしてしまうのですね。
発達障害の特性を持つ人は少数派、ならば子育ても当然少数派
さて、そう考えると、発達障害の子供は、数的に少数派。となると、発達障害子育ても少数派。なんだ。同じ子育ての悩みを持つ人の人数がそもそも少ないだけか。ということに気づきませんか?
何か、自分のせいで孤独になっている気がしていましたが、実は比率からしても少ない側で当然だったんですね。
まとめると、発達障害の子育て自体少ないわけですから、孤独を感じることも普通のこと。それで良し、というわけです。
孤独の原因と向き合う
発達障害の子育てが少数派であることがわかったところで、では、孤独の何が辛いのかを解明してみましょう。
もちろん、環境や感じ方の違いなどは人それぞれですので、自分ならこうだな、と逐一置き換えて考えて下さいね。
孤独はある種の状態だと考えてみる
孤独を感じて辛い、というのは、ある種の結果のようなもの、だと考えてみます。
こういう状態だから→孤独を感じる
みたいな感じですね。
結果となる行動は認知によって変わる
この、「こういう状態」をどう認知しているかで、その後の感情や行動は変わってきます。
認知→行動
つまり、孤独を感じる「認知」が何なのか。それが分かれば、何となく孤独の正体がぼんやり形取られてきませんか。
どのコミュニティだと孤独だと感じるのか?
次に、自分かどういう状態だと、孤独を感じるのか、振り返ってみます。
基本的に、何かしらのコミュニティ内で孤独を感じるわけですから、そのコミュニティが何なのか、ですよね。
小さいところで家族とか、幼稚園や学校のママ友とか、大きいところで日本の社会とか。
逆に、孤独を感じないコミュニティはあるのかも考えてみましょう。
コミュニティの概念がつかみにくければ、人間関係で考えてみるとわかりやすいかもしれませんね。
どの話題だと孤独を感じるのか探してみる
発達障害の子育てのことを考えると孤独を感じることは、すでにわかっていますので、別の話題も考えてみましょう。
まずは子育て以外。自分の仕事や趣味、関心があることでも孤独を感じるのか。
同じ子育てでも、兄弟のことは?
発達障害の子供でも、勉強、習い事、子供の趣味など、孤独を感じるものと感じないものがあるのではないでしょうか。
もし、何を考えても孤独だと感じるなら、それは発達障害子育てで感じている孤独ではなさそうだな、と判断できますね。
だとすると、孤独対策は、発達障害育子育ての対策ではないものを探すことになります。
思いつくままに紙に書いた方がわかりやすい
このように、視点を変えて考えるだけで、真っ暗闇だと思っていた今の生活に、うっすらと進む方向が見えてくると思います。
対処法でもお話しましたが、出来るだけ紙に書き出した方がわかりやすいです。
- 客観視できる
- モヤモヤが整理される
- たまっていたものが吐き出された感じになる
- 脳のスペースが空く
書き出しているうちに、あれこれと思いつくこともありますし、気がつかなかった思いに出会うこともあります。
対処法で書き出したものがあれば、参考に見直してみてもいいですね。意外なヒントがあるかもしれませんよ。
【体験談】花緒の孤独の原因は「わかってもらいたい」という傲慢さだった
私が孤独を辛いと感じていた原因は、子育て「大変だね」という言葉ではなく、「大変」ということを自分が思っているように理解してほしかったという傲慢さだったと思います。
当時、誰かに相談したところで、自分の知りたいことは返ってこない。私のそのように考えていました。
友達や幼稚園などの先生、旦那や親、スクールカウンセラーや保健センターなどの相談員。たくさんの人達にたくさん相談してみても、孤独に陥っていた過去の私。
実際、人に何かを相談しても、私の考えていることは相手にはわからない。似たような体験や経験や知識から、ヒントになるようなことはあるかもしれないが、本やウェブサイトですでに知っていることが多くてあまり役に立たない。
とはいえ、知らないことはたくさんあったんですけどね。自分のことでいっぱいいっぱいで、盲目だったのでしょう。
だから「誰にも相談しない」という行動を選択したからと言って、孤独からは抜け出せませんでしたね。
知識をつける
孤独の正体がなんとなくつかめてきたら、知識をつけていきます。
- 発達障害のこと
- 孤独とは何なのか
- なぜ孤独を感じるのか
- 他の人は孤独とどう過ごしているのか
- 認知行動療法
- 心理学・哲学
などなど、興味・関心があるものをどんどん勉強してみます。
勉強方法は何でもよく、自分の環境や特性に合わせましょう。
- 本
- ウェブサイト
- セミナー
他にもありますが、私はメインは本です。
製本された本は常に何冊か手元に置いておき、物理的に読めない場合は、電子書籍+オーディオブックを使っています。
怪しくなければ、セミナーに参加することで、専門家からの最新情報を知ることも可能。
また、最近では、オンラインで大学の講義を受けられるものもありますので、心理学や教育関連のことなど、知識はいくらでも手にいれられますよ。
行動・実行する
知識がついてくると、発達障害の子供との接し方など、実際に行動に移せることが増えてくると思います。
また、自分の孤独についてもいろいろわかってくると、対処しながら対策が思いつくこともあるでしょう。
何から始めてみてもいいので、とにかく行動してみます。行動に移さないと現状維持のまま何も変わらないので、すぐに出来そうなものからやってみる。
1つ行動してみることで、「やれた!」という前向きのエンジンがかかると思います。とにかく、1歩だけでいいので、足を前に出してみましょう。
検証と改善を繰り返す
何か行動に移せたら、結果を振り返ります。
結果を「ただの事実」として認識する
こんなことをやってみました→こんな結果になりました。以上。という感じですね。
- 次に出来ることは何だろう
- 目指している方向に近づくには何が必要だろう
すぐに次に向けて考えていきます。
「良い」「悪い」という評価 はやらない
結果の一つ一つに評価を入れてしまうと、
- うまく出来た
- うまく出来なかった
という工程が出来てしまいます。そうなると、うまくやろうとしてしまうんですよね。
今やるべきことは、うまく出来たと感じることではありませんので、意識して評価は入れないようにしましょう。
どんどん次のステップを試していく
どんどんサクサクと次のステップを試していきます。そのうち、現状の困りごとのレベルが、少しずつ変わっていくことに気がつくでしょう。
そうなってきたら、孤独でありつつも、前に進んでる感覚が掴めてくる。
繰り返すうちに改善していくことが楽しくなってきたら、孤独はもやは味方として、自分をアシストしてくれる存在に変わっていきます。
さらに、孤独であることで、人の意見に振り回されることなく過ごしていけるようになるのですよ。
すると、孤独、という言葉はやがて、1人の方がラクとか、1人が好きというような言葉に変わってくると思いますよ。
私がそうだったように、あれ?孤独感はどこへ・・・?という日もくるかもしれませんね。
自分の次は社会の中で!発達障害の子育てで孤独にならないサブ対策

自分でできる対策が、ある程度軌道に乗ってきたら、次は少しずつ社会に出ていきましょう。
人は社会の中で生きていく生き物なので、親子ともに最終的には社会の中で、最良の状態をキープしていきたいですからね。
ただし、孤独が辛い、と感じているうちは、急にフルで社会に出てしまうとまた逆戻りしていしまう可能性も考えておきましょう。
少しずつでいいんです。足だけ出してみて、すぐ戻れる状態を繰り返すうちに、どのレベルで社会と接して暮らしていきたいかを決めていけばいい。
自分たち用に調整しつつ「ちょうどいい感じ」を探していきましょう。
相談というより自分の思いを喋りまくる
誰かに相談したからといって、孤独がなくなるわけではありませんが、相手の反応を一切きにしなければ、ちょっとしたストレス解消にはなるものです。
毎日、幼稚園や学校ではママ友に会うし、近所の人に会っても子供の事はよく聞かれますよね。私も長男の発達障害子育てに悩んでいたことをスルーした世間話が、正直面倒になったんですよね。
話すことを取捨選択して、当たり障りのない情報に加工することが。で、面倒なことはすべてやめて、とりあえず自分の思っていることは何でも喋るようにしてみました。
そのことで、相手がどんな反応をしようと、どんなことを言ってこようと、それは、相手のことであり、私のことではない。そんな風に考えてみたんです。
要するに、バーっと喋ってすっきりする。それでいっか、って。
発達障害のことをわかってもらわなくていいし、理解してもらわなくてもいい、別に受け入れてもらえなくたって、誰かが何かを言っているだけなら、別に自分と長男が死ぬわけじゃないし。だから、ま、いっか、って。
そんなわけで、現在まで、誰に対しても私は思っていることを正しく伝えるようにしています。校長先生だろうと、ママ友だろうと、親だろうと。
まずはこちらから話すことで、社会からの疎外感、みたいなものは少しずつ気にならなくなっていきました。そもそも、自分が勝手に疎外感を感じ、孤独だ、と言っていただけなので。
同じ悩みを持つコミュニティに参加する
発達障害の子育てをしているのですから、同じ子育てをしている仲間と話せば、出てくる悩みも似ています。何ならその孤独感を理解してくれる人もいるでしょう。
- 発達障害の親の会
- 特別支援教室の親の会
- 発達障害の子育て中のママ友
など、知り合いの紹介やインターネットの利用、地域の保健センターなどに聞いてみると登録されている団体を教えてもらたりします。
私は、単発で自閉症協会のセミナーに参加したり、無料で行ってくれている発達障害のセミナーに参加したりしています。
以前は特別支援教室の保護者会に参加しては、ママ友を作り、ママ友経由で発達障害の親の会に参加させてもらったこともあります。
やっぱりね、少数派の子育てを経験している人達だと、悩みごとをわかってもらえるんですよね。
少数派の親として、
- 社会でどう立ち回っていけばいいのか
- 何の支援をすればいいのか
- どこまでを他人に助けてもらえるのか
など、本やインターネット・ウェブサイトなどから得られる情報とは違う、生きた体験談を聞くことができました。
同じ悩みを持つ人達がいる。その事実を知っただけでも心強く、孤独さを感じながらも孤独ではない感覚を持ち始めました。
人間関係があまり面倒ではなさそうなコミュニティがあれば、参加してみるといいかもしれませんね。
配慮を求め続ける
発達障害を知らない人はまだまだたくさんいます。身近に当事者がいなければ、言葉は知っていても現状を知らないことは当たり前のこと。
それば、幼稚園や学校の先生であっても同じことなので、発達障害の子供と関わる人には配慮を求めておいた方がいいと思います。
もちろん、賛否両論ありますし、何なら何も言わない方が良かったと思うこともあるかもしれません。
しかし、現状、発達障害のことで困っている人がいるなら、「困っています」と言うだけでいい、伝えてみましょう。
あ、この人この子は何かに困っているんだな、ということが分かるだけでも、接する側の関わり方が変わります。
発達障害は見た目では判別しにくいものですので、求められる配慮は求めていく姿勢を取るだけでも、子供の環境は変わっていくと思います。
振り返り: 発達障害子育ての孤独に目をつぶらなかったことで道が見えてきた

発達障害の子育ては、少数派のため孤独を感じやすいと思います。
相談したくても相談できる人がいない、理解してもらえない、もうどうすればいいのかわからないと思っている方もいるのではないでしょうか。
そんな孤独に辛さを感じながらも、腹を決めて孤独と向き合うことで、少しずつやるべきことが見え、自分にできることに力を注いでいるうちに、孤独を感じている暇がなくなりました。
自分の孤独について真正面から考え、なぜ孤独に陥ってしまうのか、その原因がわかれば対処も対策も可能。
また次、新たな孤独を感じたとしても、本心から「自分は独りぼっちだ」とは考えないでしょう。なぜなら孤独は、自分の内側にあるものだったから。やろうと思えばいくらでも孤独に陥る思考をすればいいだけだから、ということがわかっているから。
結局、現状を正しく認識し、よりよく過ごすために今できることは何か、ということに意識を向ければ、孤独の辛さは関係なくなります。
今できることに注力すること。発達障害に限らず、子育てにおいても、自分の人生においても、「今」という時間をどう過ごすのか、ということになりますね。
次は何をやっていこうか、という少し先の道が見え、どう過ごしたのか、という道ができる。その繰り返しでできた道を振り返った何年か先にまた、自分が孤独かどうか振り返ってみてはいかがでしょうか。