こんにちは!私がインフルエンザで寝込んだ時、次男が作ってくれたおかゆに感動した花緒です。超おいしくできていてビックリ。さて、自閉症スペクトラムの子供が自立して生活していけるために、子育て中から教えていけることを考えていきます。今回は衣食住の「食」について、何を教えておくように心がけているのかをお話しします。
自閉症スペクトラム自立支援計画その2-1|インスタント・レトルト食品・冷凍食品・缶詰を使えればOK

とにかく、基本は多くを望まないことです。
とりあえず生きていければOK。本当に最低限のことから、1つずつプラスしていく、と考えていきましょう。 成功体験を積ませるように、できた!1人で食べられた!ということを教えてることがゴールです。
【火を使う際に気を付けたい黄金のテーマ】
- 換気扇をつける
- ガスの消し忘れに気を付ける
栄養を考えて、時間配分も考えて、材料を用意して、要領よく料理をする、ということは不可能に近い。よっぽど料理が好きで、積極的にやりたい人以外は、マルチタスク的な料理は難しいと思っています。
ですので、まずはチンッ!とやればご飯が食べれるものを教えていきましょう。

これは1つの方法です。毎日、インスタント食品を食べるというわけではないですよ。あくまでも最低限できたらいいと思うことです。
インスタント食品
インスタント食品の場合、お湯を沸かすということが最低限の作業になります。
そして、簡単だけど意外とややこしい、インスタント食品ごとの作り方の違いを覚えることですね。
カップ麺・カップ焼きそば
気を付けたいのは、ふたを全部開けない事ですよね。事前に作り方の説明を読むようなタイプの子であれば、何の心配もありませんが、何も見ずにすぐ開けちゃう場合は、一から教えておきましょう。
そして、意外とわかりづらいのが、付属のスープ。
液体はフタの上で、温めて、粉上の物はお湯の前に麺の上に入れておく、ということ。そして「かやく」もお湯の前に麺の上に入れておくこと。
それぞれのカップ麺や焼きそばによって、微妙に作り方が違うので、細かくイチイチ教えておきましょう。じゃないと、焼きそばのマヨネーズもお湯の前に入れちゃうかも。そして、水切りしないでソース入れて、もはや焼きそばじゃなくなっちゃうかも。
インスタントラーメン
カップではないので、鍋と食べる器が必要になるインスタントラーメン。1回やれば、作り方自体は覚えられるでしょう。
よくわからなそうな場合は、どこを見ればインスタントラーメンの作り方がわかるのかを教えておけばいいと思います。
ま、袋の裏に書いてあるんでね、読んでねってはなしなんですけどね。
レトルト食品
レトルト食品自体、電子レンジと湯煎と両方の調理法がありますね。
どちらも体験しておき、子供自身はどちらの方法でレトルト食品を調理していきたいのか、ある程度決めておくといいと思いますよ。
できる体験は、できるうちに全部やっておいたお方がいい気がします。
冷凍食品
まさにチンッ!の冷凍食品ですが、中には味付けが合わなかったり、食感が合わないこともあると思います。健康にいい悪いは別として、どんなものでも食べれた方がいいと思います。
その辺りは感覚過敏が関わってくるところ。
また、自分でお弁当を作る際にも、冷凍食品はとても重宝されますよね。この際、栄養面とかは二の次三の次。
別に毎日3食、冷凍食品を食べるわけじゃないんです。こんな方法でご飯を食べられるよ、というイザという時のための知識です。
缶詰
缶切りで開けないタイプの缶詰を買うことが基本ですが、間違って缶切りタイプを買ってしまうことがあるかもしれないし、災害時などは缶きりを使うタイプをもらうかもしれないので、両方使えるように練習しておきましょう。
缶切りは、ある程度器用さを求められる物ですので、練習してもできそうにない場合は、何としても缶切りナシで開けられる缶詰をゲットする術を教えればいいと思います。
といっても、一緒にスーパーに行って、見分け方の違いを教えるだけですけどね。缶ジュースもそうですが、缶は開けられるようにしておいた方がいいですよね。
自閉症スペクトラム自立支援計画その2-2| お米が炊ければOK

「サトウのごはん」でもいいのですが、たぶん、自炊しないとお金が持たないかも。ということで、炊飯器でご飯を炊く、できそうであれば、鍋炊きでご飯を炊く、ということはできると便利です。
炊飯器でご飯を炊く事自体、そんなに難しいことではないので、ご飯の何合とかの数え方と水のメモリの見方とかを教えておけばいいと思います。
基本は炊飯器ですよね。きっと。でも、停電になった時、災害時用に、鍋炊きで炊くご飯の炊き方も教えておくといいと思います。
炊飯器のご飯を保温にしたまま忘れてしまう可能性も大です。忘れたままだとカビが生えて大変なことになりますので、食べきれない場合は冷凍するとか、次の日に食べきれなかったらどうするのかなど、簡単に知識を入れておくといいと思いますよ。
自閉症スペクトラム自立支援計画その2-3 | 焼くことができればOK

調理法としては、他にも、
- 煮る
- 炒める
- 茹でる
- 蒸す
- 揚げる
- 煎る
- ふかす
- 炊く
などありますが、とりあえず焼ければなんとかなるのではないかと思います。
この3つがわかっていれば、最低限大丈夫かなと思います。
油がはねて熱いとか、油に調味料(醤油など汁系の)を入れるとはねるとか、実際にやればわかることがありますので、できれば子供のうちに親と一緒に体験しておきたいですよね。
意外とフライパンとか鍋とかは、持ち手の部分に自分がひっかっかって、フライパンごとひっくり返して大やけどをする、というパターンも考えられるので、体験だけはしておいた方がいいかも。
ちなみに焼ければ「炒める」ことができますし、油を引かなければ「煎る」ことになりますし、油を多めに入れたら「揚げる」ことになりますよね。
火を使う料理の基本なんじゃないかな、と思います。
自閉症スペクトラム自立支援計画その2-4| 包丁が苦手ならキッチンバサミでOK

感覚過敏の人で、まな板と包丁が当たる音がイヤとか、野菜を切った時の包丁の感覚がイヤという方がいます。だから包丁で料理ができない、となってしまう場合、キッチンバサミでいいと思いますよ。
もちろん、包丁の方が使いやすいでしょうし、かぼちゃ、とかは包丁じゃないと切れないと思いますが、ならかぼちゃは切って冷凍してあるものを使えばいいんだし、今は何かと便利になっていますから、便利なもので料理をすればいいと思います。
固定概念に縛られず、柔軟な発想でおいしく食べられればそれでOK。使ってみたくなったら包丁の練習をすれば良いと思いますよ。
振り返り| 自閉症スペクトラム自立支援計画その2|最低限食べれればOK

将来のためとはいえ、今時点でいろいろと求める必要はないですよね。ただ、放っておいても覚えていくこともないでしょう。
普通とはちょっと違う自閉症スペクトラムの子供たちなのですから、生きるに関する衣食住のことは、意識して子供のうちから接しておいた方がいいと思います。
こだわりが強ければ、過集中になっていれば、もはや衣食住の話など、どうてもいいわけですからね。
そうなる前に、毎日の生活で少しでも食に関する意識が高まってくれたらうれしいと思います。
ちなみに、長男も次男も1人で料理をしますが、1歳から野菜洗いの手伝いをしてもらっていました。長男は幼稚園辺りで、料理のメインとも言える炒める系をお願いしてきました。
味付けも、大体の指定をしておいて、後は味見をしながら足していく、という方法をとってもらっています。感覚過敏をフルに活かして、いつも美味しく味付けをしてくれています。
チキンのトマト煮を作ってくれた時は、テレビでみた科学の調理術みたいな方法を早速使って、鳥モモ肉をとてもやわらかく調理してくれました。
お手伝いとして料理を手伝ってもらうなら、下働きみたいな作業よりは、メインとなる部分を任せるところから始めてみるといいですよ。料理っておもしろいな、実験みたいだな、と思ってもらえれば、あとはちょっと声を掛けるだけでうちの子たちは私の代わりにやってくれます。
親の感覚であーだこーだ口出しするのではなく、子供がチャレンジしてみたことを一緒に体験しましょう。びっくりするような発想と味付けもまた、楽しい子育ての思い出になるんじゃないかな、と思います。

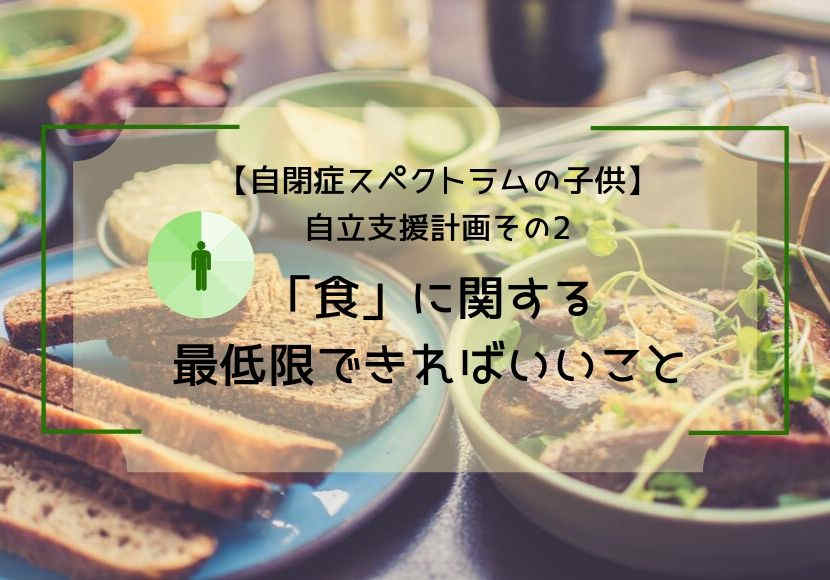


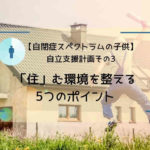
コメント