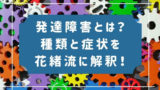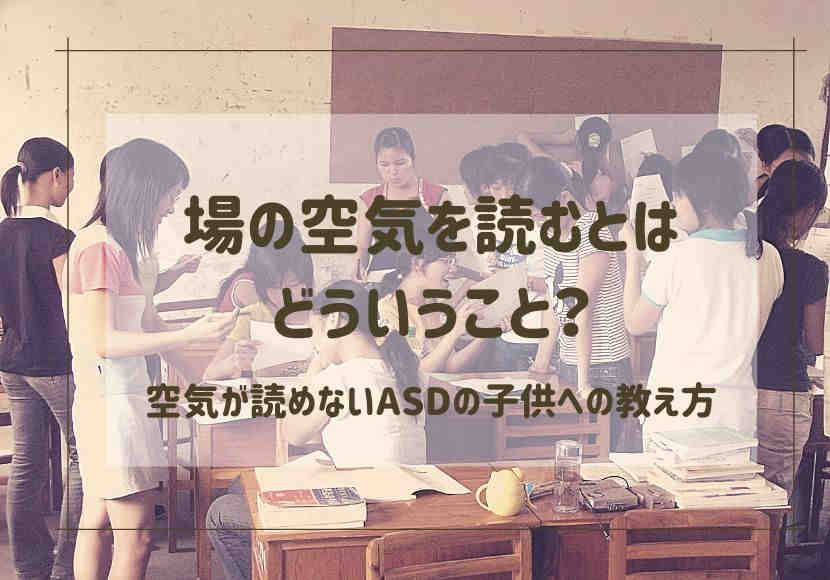「空気を読む」ってどういうこと?
「場の空気」って何?
と子供に聞かれた場合、どのように答えたらいいか迷ってしまいますよね。
年とともに、当たり前のように空気を読んで過ごしている私たちにとって、子供の素朴な疑問「場の空気って何?」「空気を読むってどういうこと?」と聞かれても、すんなりと答えられないでしょう。
特に発達障害の中でもADHD(注意欠陥多動性障害)やASD(自閉症スペクトラム障害)は空気が読めないことが特性として挙げられます。
そんなASDを始めとする発達障害の子供たちに、「空気をよむ」とはどういうことなのか?ということを説明する方法をご紹介します。
ついでに、「場の空気を読む」ってこんな感じだよね、という私の考えも合わせてご紹介していきます。
ASDの子供と接している大人の方、ASDの当事者で空気を読めなくて困っている方の参考になればうれしいです。
場の空気とは?TPOごとの人の気持ちの集まりのこと

子供も小学校4年生くらいになってくると、場の空気を読んだ言動や行動が求められるようになってきます。
「空気読めよ」と言われることもあるでしょうし、「それ言っちゃダメでしょー」と突っ込まれることもあるでしょう。
さらには、何か言った瞬間、周りがシーン・・・・となることにも遭遇するかもしれませんね。
何度かこのような体験をした子供が、家に帰って「空気って何?」と聞いてくるわけです。
明らかに何かイヤな思いでもしてきたんだろうな、と察することできるこの質問に、親として、子供と接する大人として、どのように答えていけばいいのかを考えてみました。
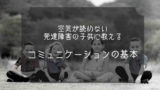
【前提】「場の空気」が目で見えるわけではない
ASDの子供も、「場の空気」が理科の教科書で見る「空気」ではないことくらい、わかっていると思います。
だから、聞かれているのですよね。場の空気って何って。
当然ですが、空気は目には見えません。しかし、人が集まれば、そこには確実に場の空気が存在しますよね。
- 楽しい空気
- 一致団結した空気
- 重い空気
- ピリピリした空気
さまざまな種類の空気が存在しますが、実際に目では見えません。なんとなく感じ取るもの、それが場の空気です。これがまず、前提となります。
【基本】自分以外の人がいれば「場の空気」が発生する
花緒論ではありますが、私は自分以外の人が1人でもいれば、場の空気が発生すると考えています。
自分を含めて2人の場合
自分以外に1人いる場合は、全部で2人ですので、場の空気の半分は自分が発生させていることになりますね。
この場合、2人の時間や会話によって場の空気感は変わっていきますが、自分が当事者ですので空気を感じて何か行動を起こすというよりは、相手との2者間による会話のやり取りや行動がメインになると思います。
自分と相手だけですので、場の空気が何か関係してくることは、あまりないのではないかと思いますがいかがでしょう?
ケンカしている時などは張りつめた空気感が存在すると思いますが、それも結局は相手との関係性によってなんとかなるので、空気を読むというよりは、相手とのコミュニケーションについて考えた方がいいでしょう。
自分を含めて3人以上の場合
自分以外に2人いる場合、場の空気は確実に発生すると考えています。この辺りから空気が読める読めないの問題が出てくるのではないでしょうか。
3人以上~クラス単位くらいまでで行うの日常の会話や学校などのイベント、付き合いなどで場の空気を読むことが求められるようになってきます。
ASDの子供が地雷を踏んでしまって、友達から文句を言われたけどよくわからない、と悩み始めるのも小学校3・4年あたりからでしょう。
もちろん、小学2年生以下でも、大人から見えば「空気読めばいいのに」と思うことがあるかもしれませんが、大抵の場合、当事者である子供本人があまり気にとめていない場合が多い気がします。
【性質】場の空気は人の気持ち(感情)とTPOで変動するもの
完全に持論展開になりますが、「場の空気」というのは、TPOに応じて生じる人の気持ちではないだろうか?と考えています。
例えば、スポーツクラブの試合で負けてしまった場合、チームメイトは全員、負けた悔しさから泣いたりがっかりしたりしますよね。
悔しい、残念、悲しい、など負の感情が集まることで、その場の空気は暗く重くなっていきます。
この時、1人1人の感情はそれぞれ違いがあるにしろ、同じような感情を持っていれば同じ空気感を持つことはできますよね。
自分の感情と一緒にいる人の感情が必ずしも同じになるわけではないことが問題の根本
この例の場合、試合に負けたことは負けたのですが、全員が全く同じ気持ちになるわけではないんですよね。
人それぞれの試合に対する思いや、チームに所属している役割や責任、立ち位置や目的など、みんな違うので、試合1つの結果からみても、みんなが同じ感情になるとは限らないわけです。
ですので、負けたけど別に悔しくないという感情を持つ人と、死ぬ程悔しいという感情を持つ人など、人の感情に差が出てくる。これが、場の空気が読めないことで問題になってくる根本なのではないかな、と考えています。
言葉や態度でアウトプットすることで空気が読めないと言われてしまう
人の感情がそれぞれ違うことは、ある意味、当たり前のことだと考える方が多いのではないでしょうか。
場の空気が読める人と読めない人の差は、同じ場に居合わせている人の感情と、自分の感情が違う時に、どうアウトプットするのか?ここで大きく結果が分かれると私は考えています。
- 自分の感情をそのまま言ってしまう→地雷を踏む・空気が読めないと言われる
- 自分の感情を言わずに態度で出してしまう→空気が読めないと言われる
- 自分の感情を言わない・態度にも出さない→何も言われないor空気が読めないとは思われない
- 自分の感情を押さえて周りに合わせるそぶりをする→空気が読めると言われる・嘘がバレると八方美人と言われる
俗に空気が読める人に属する人達は、3の自分の感情を言わないし、態度にも出さない、が一番多いでしょう。さらに、自分に危険が及ぶと判断した場合は、4の周りに合わせるそぶりをする、を選択します。
「いじめ」とか「長い物に巻かれる」とかが当てはまるでしょうね。
【仮説】場の空気は感覚から生まれる感情の集まりなのではないか?

空気が読める読めないが人の感情に関係しているのかも?という仮説を元にして、感情の違いについてもう少し深く考えてみました。
この違いが、発達障害の脳の違いと関係があると考えていますので、合わせて参考にしてください。
これまでよくわからなかった「場の空気が読める読めない」に関して、何かつながる部分があるかもしれません。

感覚の違いを共有することが空気を読むということ?
ちょっとマニアックな考え方になってしまいますが、あくまでも花緒論であることをご了承ください。
まず、人の感情が生まれるきっかけは、人の「感覚」が原因になっているのではないか?というところから始めます。
例えば、
- 転ぶ→肌の感覚→感情発生(痛い)→アウトプット(泣く・痛そうにする)
- 食べる→味覚→感情発生(おいしい)→アウトプット(笑顔になる・「おいしいね」と言う)
- 頑張ったのにできない→目で結果を認識→感情発生(悔しい)→アウトプット(怒る・泣く)
こんな感じです。
事例に対して、感覚の部分、または結果としての事実の認識があり、この後感情が発生すると思うんですよね。
趣味嗜好による感覚の違いが感情に差を生み出しているのでは?
感覚の感度は人によって違いますよね。
ぶつかったときの「痛い」でも、人によって痛みの感じ方は違うと思いますし、レベルも違うでしょう。
さらに感覚には趣味嗜好も関連してくるのではないか?と考えてみました。
【感覚の種類】(音楽や味、肌触りなどの感覚)
- 好き・得意→良い感情・プラスの感情
- 嫌い・不得意→悪い感情・マイナスの感情
種類やふり幅のレベルは人それぞれ違いますね。
1の好き・得意という受け入れOKな感覚であれば、良い感情になりますが、逆に2の嫌い・不得意という受け入れNGな感覚であれば、悪い感情を持つ可能性が高い、となります。
感覚が同じ=感覚の趣味嗜好による感情が同じということではないか?
感覚が同じということは、要するに感覚における趣味嗜好が同じなので、同じような感情、または似たような感情を持つ事が出来るため(共感)、その後の言動・行動も同じようになる、と私は考えたわけです。
そうすると、「場の空気を読める人」は、そもそも論で感覚による趣味嗜好が同じで、さらに同じような感情を持てるから、同じような行動になることで、場の空気を読んで行動しているような感じがしている、と考えるとつじつまが合いますね。
感覚が違う場合、他人の感覚を想像する必要が出てくるのではないか?
では、感覚が違う場合はどうでしょう。
感覚の趣味嗜好が違っていた場合、相手の感情を想像する、推察するなどして予想するわけですね。
そして自分の感覚に置き換えた後、趣味嗜好→感情→言動・行動とつながってきます。
感覚の分母(他人の感覚と自分の感覚)を置き換えることは脳の特性上難しいのでは?
さてここで、感覚→趣味嗜好の間に「他人の感覚を想像する」、さらには「他人の感覚を自分の感覚に置き換える」という2肯定が割り込みました。
発達障害の脳の特性(特にASD)は、相手のことがよくわかりません。特性上、顔色や表情から気持ちを推察することも、相手の状況も、少し先の未来も、想像することが難しいのです。
そうなると、自分と感覚が違う場合、さらには感覚の趣味嗜好が違う人の場合、この時点で相手の感覚の想像が難しく、さらには自分の感覚を置いておいて、人の感覚に感情を乗せるという器用なことは、離れ業に近いと思った方がいいでしょう。
ということは、感覚が違った時点で、発達障害の特性がある以上、「場の空気を読む」という流れは脳の特性的に考えても難しい、という結論に至ったわけです。
振り返り|違う感覚の共有が難しいことが空気が読めない根本なのかもしれない【花緒論】

「場の空気」とはそこに集まっている人の気持ちや感情の集まりで生まれるものであり、言動や行動は感情の違いによって変わってくる、というお話しでした。
そして、感情は感覚の趣味嗜好による違いが根本となっているので、他人の感覚を想像することが脳の特性上難しい発達障害の子供には「場の空気を読む」こと自体、難しいのかな、と考えています。
空気を読むことでいいこともあれば、読まない方がいいこともあるわけですが、人と暮らしていく以上、場の空気が存在することや、場の空気で人の行動が変わることも知識として知っておいた方がいいでしょう。
少なくとも、社会に出るまでの間にはその辺の知識を身に付け、自分の言動や行動をコントロールする材料にできるといいのではないかと思います。