発達障害の子供の中には、手先が不器用なタイプの子がいます。長男もとても不器用で、消しゴムで字を消すことさえ苦労しました。
文房具は何を使っても差はないだろうと思っていたのですが、より使いやすいものを探したり、工夫して使ってきました。
今回は、そんな不器用な長男が実際に使った文房具を紹介します。
発達障害の長男が助けられた不器用でも使えるおすすめの文房具

手先が不器用なタイプの子供が実際に困るのは、文房具を始めとする道具をうまく使えないことです。
日常的に鉛筆と消しゴムを使いますし、線を引く、長さを測る、角度を測る、コンパスで円を書く、楽器を演奏する、図工では彫刻刀なんかも使いますよね。
道具を使うことのほぼ全てに、何かしらの配慮が必要になったり、個別訓練が必要になったり、より簡単に使えるもの、見えやすいもの、わかりやすいものを探し、「できない」を1つでも減らしてあげたいと思いました。
実際に長男が使った文房具を順に紹介していきます。手先の不器用さが原因で、授業に支障が出ているようでしたら、ぜひ参考にしてみてください。
なわとびはこちらを参照ください。
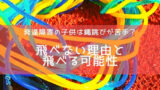
消しゴムを使うと紙がグチャっとなるのなら|電動消しゴム
たぶん絵画用とかなんでしょうけど、長男は普通の消しゴムで字を消せなかったので電動を買ってみました。「電動」「消しゴム」で探すといっぱい出てきます。
同じように消しゴムで消そうとすると、紙がぐちゃっとなってしまうのであれば、家では電動消しゴムを使うだけでストレスが半減すると思います。
子どもが発達障害でしかも不器用な子だと、1つの行動には複数の工程がある事に気付かされます。例えば消しゴムで字を消すなら、
2.左手で消す字の辺りの紙を押さえる
3.右手で消したい字の近くに消しゴムを持っていく
4.消しゴムを動かして字を消す
→紙がグシャっとならない力加減で消す(これが難しい)
→字の周囲1cm辺りを消す(これも難しい)
偶然100均で見つけた電動消しゴムを使い始めたら、上手に消せたんです。これはもう、消しゴム練習をするんじゃなくて、便利な道具を使えばいいやと思って買いました。
ただ、電動なので音がするんですよね。ガーって。だから学校には持っていけません。
なので家だけで使っています。今でも使っています。絵を描いた時は細かいところがキレイに消えて、思った以上に便利です。

不器用でも円がスムーズに書けるコンパス|ソニック くるんパス
発見しました!
指先で回さなくてもきれいな円が書けるコンパス。なんと、上のグリップ部分を握ったまま円を書くように動かすだけで、コンパスが動いてくれるという画期的なコンパス。
もう器用な技術は必要ないです。値段も安いし使いやすいし、これで円が書けないという困りごとはなくなるかも。
シャーペンコンパス
今まで通りのコンパスを使うなら、シャーペンコンパスが主流みたいです。
ただし、手先が不器用な場合、コンパスが使えるようになるまで結構大変です。
長男流コンパスの使い方
例によって不器用な長男君がコンパスという器用な文房具を使いこなせるわけもなく。算数ノートにたくさんの穴を開けて学校から帰ってきました。
正直、コンパスを使えなくったって、全くもって困らないのですが、一応練習しました。
・支点を中心に回すことができない(支点がはずれる)
・鉛筆側(シャーペン側)にコンパスを倒しながら回せない
・なぜか円を書いている途中でコンパスが開いていく現象がおきる
2.シャーペンの芯の長さを調整(芯を長めにする)
3.ゆっくりと駒を回すようにコンパスの持ち手部分を回してみる(下に押し付けない)
4.慣れてきたらコンパスを倒しながら円を描く練習をする
とにかく支点がずれるので、段ボールをノートサイズに切って、針をブスっと指してしまうことにしました。そうすれば支点の針が途中でズレてしまうことがなくなるので。
そして円を描かなきゃ、という意識からか、コンパスを下に押し付けてしまっていたので、軽く描いてもなんとなく円が見えるように、芯の長さを長めにしました。
この方法でなんとかコンパスを使えるようにはなりましたが、根本的にコンパスで半径を合わせることができないという致命的なことが起き、最終的にはコンパスが使えなくても死なないという結論に至りました。
そういいながら6年生になった今、コンパスで円を描くことはできるようになっています。
ただし今度はコンパスを倒しながら描けるようになったので、芯が何回も折れて円にならなくなり、鉛筆型を買うことに。
鉛筆型安全コンパス
基本のコンパスの形です。手先が不器用なのであれば、既存の形で頑張らず、ソニックのくるんパスでスムーズに円を書くことをおすすめします。

数字が大きく見えやすい|定規
定規が使えない意味、わからないですよね。
測る端っこを「0」に合わせるということの意味がわからないようです。
だから、極力、定規に模様とか色とかがなくて、折り畳み式でもなくて、小さい字でもなく、「0」って大きく書いてある透明タイプの定規をおすすめします。
三角定規も分度器も同じことが起こります。実際に見てみないとわからないかもしれないけど、定規系も分度器も、不思議な角度で紙の上に置かれているんですよね。長男が使うと。
始め全然意味がわからなくて、何を教えればいいのかもわからなくて、「0」から測らない意味が私には理解できなくて、結局どうすることもできなかったんです。
苦肉の策でシンプルな定規にしたっていうだけですが、「0」がわかっただけ大きな進歩でした。
数字が大きく見えやすい|三角定規
そんなわけで、見やすいシリーズをおすすめしています。数字が見やすければいいと思います。
ちなみにものすごい勢いでなくなると思うので、文房具類は全てスペアを用意しておくといいと思います。うちは何でも3組ずつ。
持ち歩き用に1つ。学校の道具箱に1つ。家に1つ。こんな感じ。セットはオススメしません。なぜなら、必ずなくなるのですよ。何か1つでも2つでも。
そうなるともはやセットの意味をなさなくて結局別のを買うなら、バラで3組ずつ持っている方が得策です。
数字が大きく見えやすい|分度器
好みが分かれるかもしれませんが、長男はとにかく「0」に合わせられないので、分度器は、分度器の端っこが「0」になっているタイプを使っています。
ちなみに、分度器に関しては、右から角度を測るメモリもあるじゃないですか。一回り内側に。
なぜか左から測っているのに、内側のメモリを読むという現象も起こるんですね。どうみても90度以上の角度を測れと問題に書いてあるのに、答えが30度ということが起こります。
のり
スティックのりであれば何でも良いらしいです。同時に2つの作業をすることが苦手な長男は、水のりのように、押しながら塗るという2つの作業はできませんということで、学校から水のりを指定されていても、断固スティックのりを使っています。
彫刻刀
スライド式で安全。サクラの彫刻刀はケースもかわいいものがたくさんありますよ。
左利き用はこちら。
オーソドックスな彫刻刀。
5年生になると彫刻刀を図工の授業で使うんですよね。特に不器用だからこれがいいというわけではないのですが、長男はグリップ付きを選んでみました。
持ち手が握りやすいかなと思って買ってみたのですが、実際に使っている長男も使いやすいと言っていました。
その他
長男は使わなかったけど、こんなものを使っていたよ、という話を聞いたことがあるものを紹介しておきますね。
鉛筆用グリップ
グリップがないと鉛筆が持てないっていう子がいました。かわいいグリップが多くて、鉛筆を持ちたくなるし、使ってみたくなる不思議なアイテムです。
ファスナー付きファイル
忘れ物対策として教科ごとに使う、教科書・ノート・地図帳・ワーク・歌集なんかを分けて入れて管理するという方法。結構いろんな子どもが実践しているみたいです。
大きい地図帳とかちょっと入れにくいかもしれません。
クリップボードバインダー
野外の活動とかで、メモを取らないといけないんだけど、不器用な長男はメモをうまく書けなくて。
鉛筆失くしちゃう事件もあるので、紐に鉛筆をくっつけて、さらにバインダーに紐をくっつけて、絶対にメモを取れる環境を作りました。
学校でも用意されているんだけど、発達障害のママ友に聞くところによると、自分用に持っている子も、意外といるみたいですね。

振り返り|わかりやすい使いやすい文房具を使うだけで授業のできないを減らせる

たかが文房具、されど文房具。意外と発達障害の子には文房具を使うということにも難しさがあるようです。
消しゴムを練習する用紙が通級(現在の特別支援級)にあることには驚きましたが、消しゴムで字を消すというだけの作業でも困りごとになるのだと、脳の神経回路が違うということが関係してくることに気づかされました。
おそらくみなさんも自分のお気に入りの文房具があるように、発達障害だからこの文房具がいいですよ、というものはないと思います。
それぞれ、一番使いやすいものを使えばいいのですが、もし、使う文房具に困りごとがあって、何を選べばいいんかわからないという方に参考にしていただけたらうれしいです。
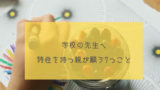

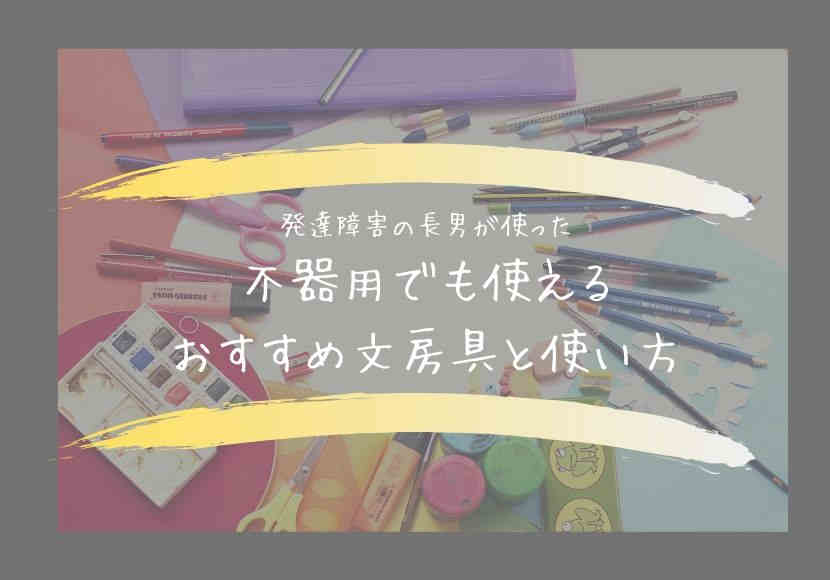






















































































































































コメント