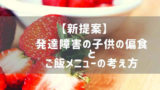発達障害の長男には、感覚過敏での困りごとがいくつかあります。幼少期から中学2年の現時点まで、どのような対処法で乗り切ってきたのか、長男を体験談からお話したいと思います。
長男の例ではありますが、発達障害の子供の感覚過敏の例や対処がわからない方の参考になればうれしいです。
【視覚・触覚・嗅覚・聴覚】発達障害の長男が困っていた&今も困っている感覚過敏の体験談

長男の感覚過敏について、実際にあった体験談を順にお話していきます。
【視覚】部屋の蛍光灯が明るく感じすぎる
長男が年長になる春休み時期に、引っ越しをしました。新居にはすでに居間の電気が2箇所ついていました。
光の調節はできないおしゃれ系が2個。リビングとダイニングと思わしき場所の上にありました。
しかし、長男が、電気が明るすぎて部屋に入れないと言いだしました。たしかに、全部の電気をつけてしまうと、かなり明るい感じではありましたね。
対処例:蛍光灯の本数を少なくする
シャンデリアっぽい形の電気で、すべて蛍光灯タイプ。全6個あったので、半分はずしました。
私たちにはちょっと薄暗い感じ。広い部屋でしたので、尚のこと暗く感じましたが、半分に減らしたことで、長男は部屋に入れるようになりました。
対策例:サングラスをかける・つばのある帽子をかぶる
蛍光灯の個数を減らしても、体調によっては辛くなる子供あり、よくテーブルの高さくらいあるアイロン台の下で遊んでいることもありました。
そんな時は子供用サングラスをかけたり、つばのある帽子を被せたりしていました。
対処例:灯りの種類を変える
居間は、家族全員が過ごす場所なので、基本蛍光灯にしていますが、長男の個人部屋はオレンジ系の電球にしています。
電球色、白色、あたりですね。シーリングライトでも白色系があるのですが、長男はペンダントライト型を選んだので、今は電球です。
また、トイレ、玄関、脱衣所、など、狭いところも全て白色電球にしています。
【視覚】学校の窓側は明るく感じすぎる
入学して気づいたのですか、窓際の席は、太陽光が辛かったようです。
外で遊ぶときは眩しい、みたいな感じはなかっかのですが、教室の机やノートへの反射が明るすぎたみたいです。
確かに、過敏さが無くても窓側席はキツイですよね。
対処例:席替えは教室の真ん中より廊下側にしてもらう
当時(小1・小2)の担任の先生が配慮してくれていて、席替えは廊下側にしてくれていたようです。
その後も、長男の配慮事項として、各担任には伝えてありますが、現在では日中はカーテンを閉めることが多くなったようで、問題ではなくなりました。
【触覚】洋服のタグが苦手ですべて裏返しで着てしまう
何歳くらいだったか忘れてしまいましたが、洋服のタグをはさみで切り始めたので嫌なんだと気づきました。
私も子供の頃は洋服のタグが気になりましたし、セーター類がチクチクして苦手でした。ハイネックもタートルネックも首が絞められる気がして嫌でした。
長男は、洋服の前後ろを反対に着る子だったんですね。さらに、裏返しも定番でした。長男が喋れるようになってからわかったことなのですが、どうもタグが嫌だったようです。
対処例:タグは基本すべて取る
幼少期からタグはすべて取っていました。はさみで切ると残骸が残って意味がないので、ニッパーで完璧に取っています。
タグを取ることで縫い目がほつれてしまう場合、バッチリ縫い直します。子供が小さいうちは危なくて手縫いでしたが、子供が大きくなってからは、パソコンの隣にミシンを置いていました。
年齢が上がるにつれ、タグを取り忘れても文句を言わなくなりました。家にいるうちは、裏返し、前後ろ逆でもいいですし、そのまま学校に行くこともありましたが、それで良いということでした。
中学2年になった今でも、前後ろ逆、裏返しはよくあるのですが、タグは取らなくてもいい、というので取っていません。
タグを取った下着の上に着れば大丈夫だよね、というのが長男との共通認識なのですが、本人的にはめんどうなようです。
最近は、タグなしのシャツやパンツもありますので、はじめからタグなしを選べばいいだけですね。
【臭覚】乾物・ポリエステルのにおいが苦手
においに関しては幼少期からダメなものははっきりしていました。
外出先、特に、道の駅や物産展のようなところで売られている、乾物。あのにおいが長男は苦手のようです。
店に入るなり、出ていくので、かなりキツイようですね。
また、小1のとき、ランドセルを背負ったまま着られる定番のレインコートを買ったら、においがダメで着られませんでした。
私も、においにはかなり敏感で、同じように何があっても絶対にダメなにおいがあり(扇子などについているお香のにおい全般)、一瞬でにおいに気づき、吐きそうになる(本当に吐く)ので、感覚はよくわかります。
対処例:乾物が売っている店には入らない
においがダメな場合は、外で待っていてもらっています。
長男が小さかった頃は、その店では買い物をしないか、誰かいれば交替で買い物をするようにしていました。
店で買う乾物は、お土産的な要素が多いので、いっそ買わなくても問題なかったです。
レインコートは着ない(着替えを持っていく)
どんなに大雨でも、レインコートは着ない。そして着替えを持っていきます。
学校の校外学習でレインコートが必要なときには100円ショップで売っているレインコートを持っていっています。
素材はポリエチレンとかですね。大丈夫なわけではなさそうですが、非常時にちょっと使うくらいならギリ大丈夫らしいです。
【聴覚】生地と触れる音が苦手
触った感じがシャカシャカしているのが苦手。アルミホイルが口に入ったような感覚になるらしいです。
- ポリエステル
- ナイロン
このあたりでできている物と触れたときの音が長男は苦手です。ただ、素材が完全にダメなわけではなく、物によりますね。
具体的には、
- エコバッグ
- リュックサックやバッグ系(水泳バッグ・裁縫セットのバッグなど)
- 冬のジャンパー(防寒具)
- レインコート
- カーペット
このあたりの物を買うとき、使うときは気を付けています。「カサカサ」「シャカシャカ」みたいな感じですね。
対処例: 苦手な素材の服は着ない
幼稚園くらいまでは、確かに上着は着たがりませんでしたが無理やり着せていました。
小3以降くらいから感覚過敏を言うようになり始め、高学年になった頃には、冬の防寒具が着られなくなっていて、フリースを重ね着していた記憶があります。
冬のジャンパーやウインドブレーカー的なものが一切着られず、素材によってはスポーツ用のジャージ、フリースや厚手のパーカーでなんとかしています。
年に何回かしか着ないのですが、スキーウエアなどは、布素材を探すのが本当に大変です。
すぐに切れなくなる子供時代は古着屋さんで安いものを買い、持ち込んでいました。レンタルだとものによっては着られない、ということもあるのが面倒だったので。
基本は綿かフリース、またはジャージにしています。
対処例:通学用リュック・バッグ類は布製を買う
中学に入るにあたって、大丈夫だと思って買った通学用リュック。
制服だと問題なく背負えるのに、ジャージになると、ジャージの素材とリュックの背中の素材がこすれる音が無理で、最終的に抱きかかえて登下校する事態が発生。
部活帰りやコロナ禍でジャージ登校が多く、当初買ったリュックは使えなくなりました。
布製のリュックを買い直したのですが、これがなかなか売っていないのですよ。それに、中学生の教材を入れて歩けるだけの大きさも十分ではない。
ジーンズショップとかに売っている、カジュアルタイプの布製リュックや、旅行用の布製リュックをかろうじて使っている感じですが、意外と大丈夫な素材でできているリュックがなくて困っています。
また、表側は布でも内側はダメな素材が多く、すべての部分を開けてみて触ってから買わないと失敗が多いので注意するようにしています。
ネットで買おうとすると、中がわからなかったり、実際の素材感や触った感覚が分かりづらく、デザインで選べないのが難点。
最近は、帆布やキャンバス系ならいけるかも、と考えています。
また、水泳バッグや手提げなどもすべて布製、またはビニール製。小学生の頃は、プールバッグはビニール製でしたが、中学に入ったらカサカサ系ばかり。
しかたがないので、100円ショップで売っている、網目っぽいものや、布バッグにしました。濡れたものはビニールに入れるので、特に問題はありませんでした。
レインコートは基本着ない(or 短時間のみの使用なら耐えてもらう)
レインコートは臭覚のところでも少し触れましたが、においも耐えられないようなので、基本着ないことにしています。
とはいえ、小学校低学年のうちしか雨の日にレインコートを着ることはなく、中学になった今は、雨でも自転車で移動したいときくらい。
学校の校外学習の持ち物として、どうしても必要なときは100円ショップとかで売っている、携帯用のレインコートにしています。ポリエチレン素材ならギリ短時間なら我慢ができるみたいです。
また、冬はフリース素材のパーカーがあれば、水をはじいてくれるので、ちょっとした雨にも対応可能。
【聴覚】畳を歩いたときの感覚と音が苦手(靴下と畳がすれる感覚と音)
部屋や旅館などにある畳。長男は、畳と足や手などがすれる音が苦手です。「ギャー」となり、その場から逃げます。
そんな長男の特性をわかっていながら、わざと畳の音を出すと(次男とか)長男はマジ切れします。
自分の家であれば、カーペットやマットなど何かを敷いてしまうか、布団を敷きっぱなしにすればいいのですが、出先ではそういうわけにもいかないですよね。
例えば、以下のような場合。
- 旅行宿泊先の和室
- 自宅以外の人の家に行く(友達・祖父母邸など)
- 外食先の座敷
家族旅行なら、洋室を予約すればいいだけですが、和室しか予約が取れなかったり、学校の集団宿泊などが和室のことがありました。
対処例:本人は畳の上では過ごさない
家族旅行であれば、すぐに布団を敷くだけですのであまり問題はありませんでしたが、学校の集団宿泊の時は、寝る直前に部屋に行って布団を敷き、以外は部屋以外で過ごしたようです。
事前に担任の先生にも伝えてありましたので、何か問題があれば先生の部屋で過ごさせるということになっていました。
また、外食先も蕎麦屋などが座敷しかない場合が多く、極力、座敷以外の蕎麦屋に行くか、蕎麦屋に行かないというようにしていました。
どうしても難しいときは、イヤホンを付け音楽を聞かせていました。周りの音が聴こえなければ大丈夫でした。
【聴覚】カーペットの素材によっては音が発生して苦手なものがある
長男の個人部屋用にカーペットを買おうと、一緒に店で選んでいたら、苦手な素材があることが判明。ネットで買わなくてよかった、と心底思いました。
素材名を確認し忘れてしまったのですが、くるんと丸くなっているタイプのカーペットですね。安いカーペットでいいかなと思って提案したら、拒否されました。
対処例:実際に本人に触って確認してもらってから購入
毛並みが長めのものは大丈夫みたいなので、単に素材だけではない気もしています。結構めんどくさいですが、実物を本人に確認してもらうのが一番安全。
正直、ここまでくると、その独特の感覚は本人にしかわからない。周りも配慮できるレベルではなくなってくるのが現実です。
子育ての困りごとが解決しない場合は発達障害の感覚過敏を疑ってみる

子供が泣き止まない、服を着ない、部屋に入らない、など、子育ての困りごとがあり、何をやっても解決しない場合は、感覚過敏を疑ってみるといいかもしれません。
喋れるようになるまで感覚過敏はわからない
コミュニケーションがちゃんと取れない就学前くらいまでは、子供の感覚過敏に気づきにくいもの。なぜなら、子供本人も何が辛いのか気づいておらず、また伝えられないから。
特に、自閉症スペクトラム症の場合、困っていることがわからず、言葉を使って人に伝えることも難しい。しかし、感覚過敏によりストレスはかかっているので、行動には出るしメンタルへの悪影響も出るわけですね。
子供の感覚過敏がわからない時期の対処法
子供の様子をよく観察する
何かしら嫌なものがあれば、避けてみましょう。躊躇していたり避けているものがないか、子供の様子をよく観察してみると、感覚過敏に気づくかもしれません。
言葉を教えコミュニケーションの練習をする
0歳児とかは無理ですが、できるだけたくさん話しかけ、言葉を教えます。特に、単語は覚えやすいですが、感覚的・感情的なものは教えないとわからないもの。
- 痛い・痛くない
- まぶしい・明るい・暗い
- 好き・嫌い
- うれしい・楽しい・怖い
- うまくいっている・困っている
など、一緒にいるときに感じているであろう子供の感覚や感情は、できるだけ単語化し、口語でいいのでたくさんの表現方法を教えておくと、知識として伝えることはできるようになると思います。
特に、「困っている」という状況は、わかりにくいようなので、積極的に困っているときに声をかけるといいと思います。
こんな様子を見つけたときは、すかさず、「困っているみたいだね、どうしたの?」と声をかけ続ければ、いつかヘルプを出すタイミングを覚えていくかもしれません。
他の人の感覚過敏対処例をどんどん実行してしまう
どんな感覚過敏に困っているかわからない場合は、感覚過敏でこういうことに困りました、こんな対処をしました、ということを次々に実行してしまうといいと思います。
- 視覚過敏を想定して、サングラスをかけさせてみる、ツバが大きめな帽子をかぶせてみる
- 聴覚過敏を想定して、イヤーマフでつけさせてみる
- 臭覚過敏を想定して、柔軟剤・芳香剤他においの強いものは、はすべて使わない
- 触覚過敏を想定して、綿の洋服にする、食べない食材は食べなくてもよいことにする
あくまでもこれは一部ですが、今はインターネットからいろんな情報収集ができますから、フル活用して、次々試してみるといいと思います。
特に、光と音、肌に当たる部分の布や偏食なんかは、感覚過敏の困りごとも多いと思うので、現状を見直してみるといいでしょう。
子供の機嫌が良くなったら、感覚過敏があるかもしれないな、と思い、その後も様子を見ていけばいいと思います。
感覚過敏とは逆で鈍麻というものもあるので注意
私はいまいち鈍麻の感覚がわからないのですが、感覚過敏とは逆で感覚鈍麻というものあるようです。
困るのは、痛みを感じる部分がにぶいと、ケガをしているのに気が付かなかったり、トイレに行く感覚がわからなかったりすることがあるようです。
何か変だな、何かおかしいな、普通こんなことになるかな、と感じることがある場合、発達相談ができるところに相談してみた方がいいと思います。
振り返り:発達障害の子供が訴える感覚過敏はできるだけ対処した方がよい

発達障害の子供が感覚過敏を訴えてきた場合は、極力対処してあげた方がいいと思います。
例えて言うならば、黒板を爪で「ギー」とやられ、耐え続けるのと同じことだと考えてみたらわかりやすいのではないでしょうか。
- 苦手な感覚は避けること
- 言葉が通じないうちは感覚過敏をわかってあげることはできない
- 訴えられた感覚は恐怖症と同類だと思い受け入れ避けてあげること
- 感覚過敏の辛さはストレスであること
- 対処できない場合は本人が耐えるしかないことを知っておく
特に理解のない配偶者や祖父母・親せきなどには、発達障害も感覚過敏も、理解してもらえないと覚悟をしておいた方がいいでしょう。
長男も、蕎麦屋でイヤホンをして音楽を聴いたままご飯を食べさせたときは、義父母にお行儀が悪いと言われ、早々に食べて外で待ったこともありましたから。
感覚過敏って、本当に本人にしてみたら、耐えられないことなのですが、理解されない場合、居場所がなくなります。自分で操作できることじゃないんですけどね。
よくわからないけど、感覚的に苦手なだけで、非難され、怒られるので、自信をなくしていきます。
私には、絶対にダメなにおいがありましたし、中学の時はトリポフォビアという丸の連続体(ハチの巣とか、茎の断面図とか、カエルの卵とか)がダメで、理科のテストが回答できない、という経験があります。
苦手な感覚を避けていても、突発的にその感覚に会ってしまったら落ち着くまで耐えるしかない。その後もうまく付き合っていくしかない。
周りからは頭がおかしい、と変人扱いされ、何を言っているの的な目で見られることの辛さを体験しているので、長男の感覚過敏も理解できる、というところはあるでしょう。
誰しも、何かしらの得意・不得意があるのですから、苦手です・嫌ですと訴えてきたときは、そうなんだと受け止め、避ける手助けをしてあげればいいと思います。
また、周りの人の配慮があれば、自己否定することなく、前向きに過ごしていけるものです。
そんなこと気にしてちゃ、生きていけないよ、と思ったり言ったりせず、いったんは話を聞いてみると、わかることがあるかもしれませんね。
成長や発達とともに、変わっていくものもありますし、ずっとダメなものもあるでしょうが、まずは健康に生きていくことが一番大事ですから。

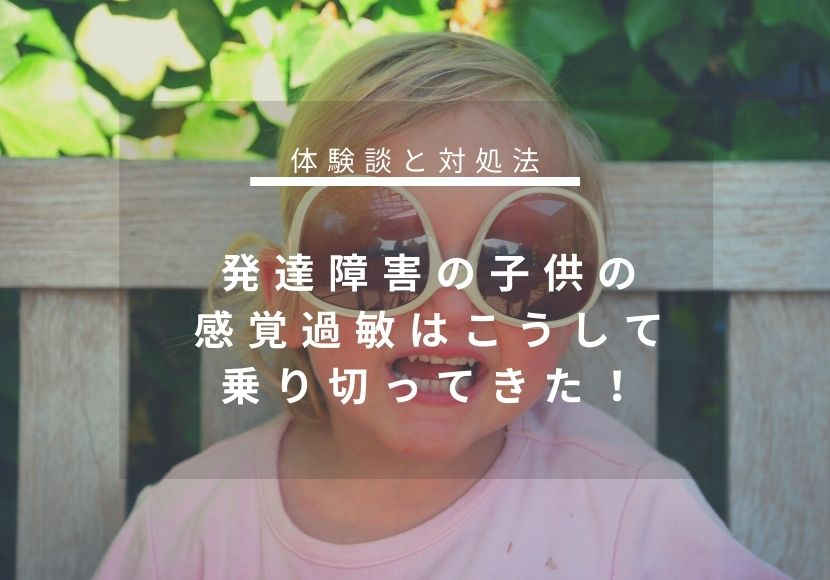













![[SKYBOW] カジュアル 帆布 バッグ アウトドア リュックサック 通学 スクールリュック キャンバスリュック 帆布リュック メンズリュック デイパック 大学生 高校生 バックパック 大容量 ユニセックス おしゃれ 3色](https://m.media-amazon.com/images/I/41Nd-idvYbL._SL160_.jpg)











![[Brodio] 【5枚入】レインコート レインウエア 自転車ポンチョレインポンチョ 雨具 袖付き 軽量レインコート 収納袋付き 通学 通勤 旅行 撥水 防雪 防塵 男女兼用](https://m.media-amazon.com/images/I/31RkudmnhxL._SL160_.jpg)