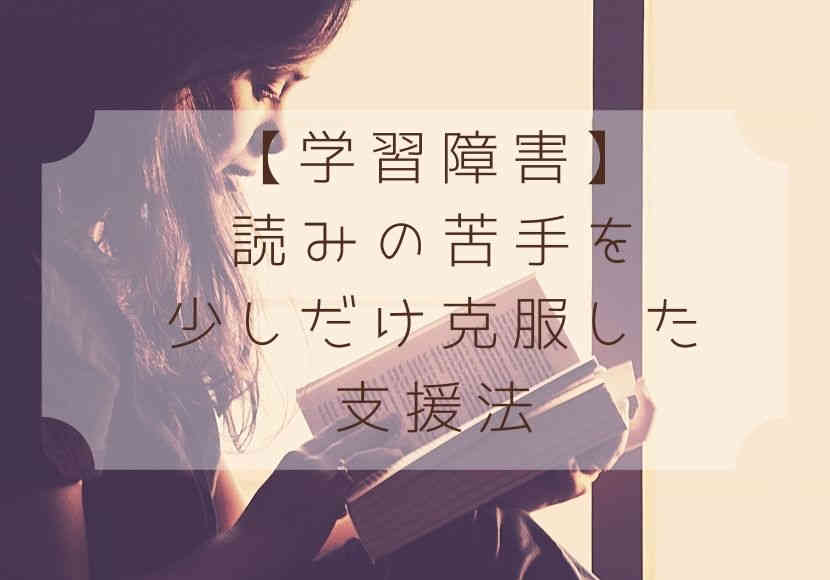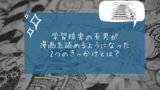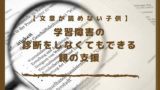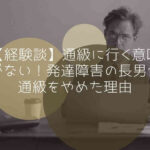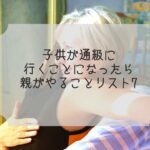文字や文章はとりあえず読めるけど、内容が理解できない学習障害の長男。
授業やテストで「読めない」ことはリスクが大きすぎると思い、通級と家庭で支援をしたところ、小6で国語のテスト100点をとれるようになりました。
今回は少しだけ「読み」の苦手を克服した支援方法を紹介します。読めるけど内容が理解できないタイプの学習障害支援の参考になればうれしいです。
学習障害の読みの支援法:効果があった順に紹介(長男の場合)
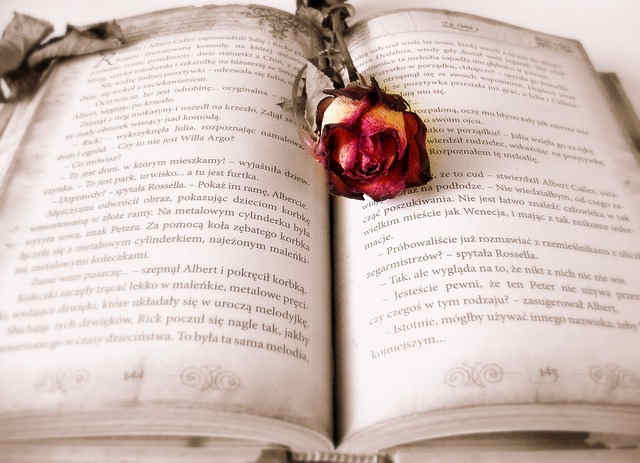
まずは効果があった支援法から紹介します。
【通級】問題と答え方を覚える:1問1答訓練
通級の個別指導時間で支援してもらった方法です。
1文章に対し、1問の問題があり、答えていく訓練。例えばこんな感じ。
問題:おじいさんはどこへ芝刈りに行きましたか?
答え:山

逆に、ここまで細分化しないとわからないものなのか、、、、と複雑な気持ちにもなりました。
しばらく1文・1問を続け、次の期には2文・2問、3文・3問というように増えていきました。
慣れてきたら、例文には表現されていないことを読み取っていく練習になりました。
問題:教室がざわつき始めた理由は何でしょう?
答え:授業中にもかかわらず副校長先生が教室にきて、田中君が急に帰り支度を始めたから。何か良くないことがあったのかもしれないというクラスメイトの心配がざわつきになった。
※花緒独自の文・問題・答えです。例文用です。
文の行間を読む、空気を読む、といった自閉傾向の特性を持つ長男のようなタイプには、なかなか難しい課題。
地道に説明を繰り返してくれた通級担任のおかげで、この手の問いにも答えられるようになりました。
余談ですが、中学になった今でも、読解問題はほぼ正解しています。一番苦手な教科だと思われていた国語ですが、5教科の中で1番点数を取っています。
この時、身についたスキルにより、その後の長男の学習意欲を大きく左右することになりました。
国語だけではなく、問題が解けるようになる→正解する、この成功体験は学習障害の子供にとってうれしい体験だと思います。
【家】映画を文章化:文章と映像をリンクさせる訓練
長男は、文字が読めて、文章もひっかかりながらですが読めるのに、内容が理解できませんでした。
文章になると、映像が浮かばないようだったので、映画を文章化して、文章と映像を交互にみて、文章と映像がリンクするようにしてみようと考えた訓練です。
こちらにやり方や結果などを詳しく紹介していますので、参考にしてください。
【療育・通級・家】ビジョントレーニング(アナログ&アプリ)
幼稚園の時に通っていた療育センターの作業療法士さんに指摘されていた目の動き。
- 目がチラッチラッと一瞬横に動く
文章を読んでいるときにチラッと目が動いてしまうと、どこを読んでいたのかわからなくなるみたいです。
特に、縦に読む国語は、完全に隣の行に移ってしまうので、話がつながらず、内容が理解できない原因にもなっていました。
療育・通級でのビジョントレーニング
主に2パターンのビジョントレーニングがありました。
- 先生、療法士さんが鉛筆を持って、一定の距離のところで前後左右にゆっくり動かし、長男が目だけで鉛筆を追う
- 数字や文字がたくさん書かれた紙の中から目的の数字や文字だけを探してチェックしていく
本だとこんな感じのタイプです。
短い時間ですが、毎回必ず実施。小6までずっと続きました。
家でのビジョントレーニング
家ではできるだけ強制にならない方がいいので、アプリなどゲーム感覚でできるものを実施していました。
これのアプリ版です。今は有料ですが、当時は無料でした。他にも3つくらい、ビジョントレーニングのアプリを入れて、その日の気分で実施していました。
宿題より先に、ビジョントレーニングをしていました。その方が宿題にもすんなり移行できましたね。
学習障害の読み支援に使ってっみた(試してみた)便利なグッズを紹介

学習障害の読みの支援に使えるかなと思って、聞いたり調べたりしたものを試してみたのですが、結果としては長男は何の道具も使いませんでした。
道具を使おうとすると、使う方に意識が向いてしまって読めない、という切ない事情があったですよね。仕方ないです。
1行分だけ穴が空いている道具(音読補助具・リーディングルーラー)
読む場行だけが空いていて、他は隠れているシートや定規形式のものです。
長男は、在籍担任が作ってくれたものを使ってみましたが、(画用紙に教科書の長さ1行分の穴をあけパウチしたもの)読みの補助にはなっても内容が理解できたわけではありませんでした。
ただ、音読の助けにはなるので、2年生までは使ったり使わなかったりで音読をしました。
現在では、こんな素敵な道具があるんですね。
色がついた下敷き・罫線が黒以外のノート
医師から聞いた話ですが、背景の色が「白」以外の方が見やすい場合があるようです。
薄い水色とか、薄い緑とか、人によって色は違うようなのですが、罫線の色も同じです。
罫線が文字の1画に見えてしまう場合があるので、罫線の色を変えると読みやすくなることもあるらしいです。
透明でカラーの下敷きなどを本に乗せて読むと読めることもあるらしい。長男は関係なかったです。
先ほどご紹介したリーディングルーラー、さまざまなカラーがあるので、読みやすくなるアイテムを探せそうですね。
シートメインならこちらが使いやすいかも。
大きな文字の本(大活字本)
まだ、字が小さいから読みにくいのかと思い、図書館で大活字本を借りてみたこともありました。
しかし、そもそも文と映像のリンクがうまくいっていなかったらしい長男だったので、文字が大きいから話の内容が理解できる、というわけではなかったらしく、5分くらいで却下しました。
図鑑(写真・イラスト)
言葉・単語のインプットに欠かせない図鑑です。写真でもイラストでもどちらでもいいのですが、できるだけいろいろなパターンを見て、認識できるようにしておくと、読みの材料になると思われます。
長男も図鑑だけは毎日眺めていましたので、言葉単体の映像まではしっかりつながっていました。
電子教科書:デイジー
異例のコロナ禍によって、学校で使う教科書がすべて電子教科書に変わろうとしていますね。
長男が小3の頃(2017年ごろ?)にもデイジー図書があり、実際に試してみました。
確かに便利ではあるのですが、教科書を読み上げてもらわなくても、学校の音読や私の音読で間に合ってしまったのです。小学生ですしね。
それよりもパソコンを立ち上げて、アクセスして、という過程が面倒だったので、結局私しか使わない、という事態に。
便利な道具はあるのに、本人のニーズや年齢に合っていないと使えないんだともどかしさと感じましたね。
オーディオブック
学年が上がってくるごとに、ある程度厚さのある本を読むことを要求されてきます。
夏休みの読書とかですね。感想文を枚数文カッチリ書かなきゃいけませんし。
というわけで6年生の時に導入したオーディオブック。もともと私がオーディオブックを使っていたので、試しに長男に聞かせてみました。
長男は、耳からの情報取得は得意なので、問題なく理解はできました。
しかし、音読ではない(自分で読んでないという意味で)という理由で結局使わず。そこまで本を読みたいという願望もないので、その後も長男は利用していません。
振り返り:読みが苦手な学習障害でも工夫することで少しだけ克服できることがある!

漫画が読めるようになったことが、どれだけうれしかったことか。それは長男本人にしかわかりませんが、日々快調に漫画を読むこと〇時間。
おかげでマニアックな知識も増え、同じ漫画を読む友達との会話もはずむようです。
映画を文章化するあたり、準備をする私の方が途中で心が折れそうになりましたが、チャレンジしてみて良かったです。
この取り組みで読めるようになった、という科学的根拠は全くありませんが、
- 成長、発達
- 療育や通級、家での地道なビジョントレーニングの取り組み
このようなことは、成果につながるきかっけになっているような気がします。
なんの根拠もなしに実験をしてみるのは私くらいしかいないかもしれませんが、何かあきらめられないポイントがあるようでしたら、小さなことでもいいのでチャレンジしてみることをおすすめします。