読み書き計算に極端な苦手さがある学習障害。でも読み書き計算が苦手ってどういうことなのかイマイチわからない、という方も多いのではないでしょうか?
今回は学習障害とはどういうものなのか?定義の確認から判断方法、診断の受け方や親にできること、学習障害である長男の体験談まで、学習障害に関するさまざまな情報をご紹介していきます。
子供が学習障害かもしれないと思っている方、単なる苦手なだけなのか?それとも学習障害なのか?誰かに相談した方がいいのかよくわからずに困っている方の参考になればうれしいです。
読み・書き・計算に極端な苦手さがある学習障害とは?|学習障害の定義

学習障害とはどのようなことを指しているのでしょうか?以下、学習障害についての文部科学省の定義です。
学習障害(LD)の定義 <Learning Disabilities>
(平成11年7月の「学習障害児に対する指導について(報告)」より抜粋)文部科学省/ 特別支援教育について
学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算 する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。
学習障害の3つのカテゴリ
学習障害には、大きく分けて3つの障害があります。
読字障害(ディスレクシア)・・・読みに困難がある障害
書字障害(ディスグラフィア)・・・書きの困難がある障害
算数障害(ディスカリキュア)・・・計算、推論に困難がある障害
学校は教科書を使って勉強することが主な活動です。学習障害の特性があると、学校生活が圧倒的に辛くなってしまいます。
学習障害の一番の問題は、周りから見てわかりづらい所にあります。見た目では学習障害であることは全くわからない。だから気づかれにくいという大きな特徴があります。
学習障害の3つのカテゴリについて、お話ししていきます。
読みに極端な苦手さがある読字障害
読字障害は主に文字認識が難しいパターンと、文字は認識できるが文章になると理解できないと言うパターンがあります。
- 文字認識が難しい
- 文字は認識できるが文章理解が難しい
文字認識が難しいパターン
- 文字が歪んで見える
- 文字が回転して見える
- 文字が反転して見える
- 文字がはっきりと見えない
このような感じで、文字そのものを認識することが難しいパターンです。
私は、このタイプの読字障害は、まず眼科健診でひっかかるのではないかと思うのですが、眼科健診との関係の情報も見つけられませんでした。
長男はこのタイプの読字障害ではないので、これ以上の詳細はわかりませんでした。
文字は認識できるが文章理解が難しいパターン
1つ1つの文字や数字は、勉強すれば認識することはできますが、文章になってしまうと意味がわからなくなってしまうタイプです。
- 眼球運動に問題がある
- 短期記憶に問題がある
- 単語と接続詞系の区別がつかない
- 単語や文章から映像が浮かばない
- 単語や文章から記憶とうまくリンクしない
文字認識ができると、なかなか文章理解でできているのかできていないのかがわかりにくく、学習障害の診断が遅れてしまいます。
また、診断したからと言って、学校側が理解し配慮してくれるのか、というのはまた別の問題です。
長男がこのタイプの読字障害なので、これまで調べてきた情報や療育で教えてもらった情報です。
長男の場合、医師や療育、通級で指摘され、訓練してもらってきたのは1の眼球運動に問題があるというところです。
目の筋肉が弱い関係で、眼球がチラッチラッと横に動いてしまうので、一定の方向で文字読み続けることができないのです。
このため、途中から隣の行を読んでしまい、話がわからなくなるということが起きていました。
2~5までは、私がいろいろ調べた結果、このような問題があると文章理解が難しくなるな、ということです。
単語から映像が浮かばない、記憶とうまくリンクしないという辺りに注目し、私が独自で実験をした結果、漫画本も読めなかった長男が漫画は読めるように激変しました。
子供の様子を見ながら、独自でアプローチすることで、苦手さがある神経を刺激することはできるんだな、と感じた出来事です。
読めない、には理由があります。脳機能の問題ではありますので、素人の親レベルでわかることなんてほぼありませんが、親だから気づくこと、出来る事もありました。
書くことに極端な苦手さがある書字障害
読字障害の子供は、書字障害も併発していることが多いそうです。
文字認識が難しければ、当然、書くことへの影響も出ますよね。
- 文字認識が難しいので書けない
- 空間把握が難しいので書けない
- 文字認識はできるが思い出せないので書けない
- 手先の運動機能が追い付いていない
- 眼球運動が問題で書けない
字を書く、ということは点の集合体である線を書けるかということになります。線を書く、字を書くということは、実は空間把握であったり、目の動き、指先の運動機能の問題とさまざまなところと関係しています。
空間把握が難しいということは、図形の問題や工作、道具を使うことにも苦手さがでてきます。
運動機能の問題であれば、箸が苦手、紐が結べない、はさみが使えないなど就学前からすでに苦手さが出ていると思います。
また、眼球運動や文字認識の問題は、目の問題と脳機能の問題が合体しており、書くということとは別の問題と関係しています。
字を書く練習(線を書いたり絵を描いたり)をしても上手くいかない場合は、書字障害を疑い、診断してみた方がいいと思います。
みんなが授業中にノートを書いたりテストを書いているのに、自分だけうまくいかないと、子供本人は自分が悪いのかもしれないと勘違いしてしまいます。
「できない」には理由があるということを、まずは大人の方に知っていただきたいです。
計算や推論に極端な苦手さがある算数障害
- 数の認知が難しい
- 数の序列がわからない
- 計算に時間がかかりすぎる
- 時計の概念がわからない
- 筆算ができない・九九が覚えられない
- 文章問題ができない
数、そのものの概念がわからない場合、その序列がわからない場合、その後の計算や時計、筆算・九九・文章題の全てにひっかかってしまいます。
1は数字で、何もない0ではなく何かが1つある状態である。この認識が難しい場合は算数障害かもしれません。
幼少期に数字を「イーチ、ニー、サーン」と数えたりしますが、この順番が覚えられなかったり、「イーチ」と「1」を教えても結びつかないという場合がこれにあたります。
耳で聞いた「イチ」と目でみる「1」が関連づかない、というところも算数障害の特性です。
眼球運動の問題との関連性
眼球運動に問題があると、筆算の桁を正しく見ることができず、結果として筆算を間違えてしまうことがあります。
筆算ができないことと、計算ができないことは別の問題だと思いますので、目の動き的に筆算ができないのか、それとも計算ができないことで筆算ができないのかは判別した方がいいと思います。
一時記憶(短期記憶)の問題との関連性
発達障害の脳は、短期記憶が弱いという特性があります。短期記憶が著しく弱い場合、計算や九九を覚えること、文章題などの数字をピックアップしておくことは難しくなると思います。
読字障害との関係からくる文章問題の苦手さ
読字障害で文章理解が難しければ、当然、文章問題は解けません。読字障害だから文章問題がわからないのか、それとも文章理解はできるけれど、数や数字的なところが問題で文章題がわからないのか、判別が必要です。
何か違うと感じたら|診断をした方がいい判断基準と診断の受け方
発達障害全般に言えることですが、子供のことで親が何かおかしいな?と感じたら、診断をした方がいいと思います。
診断を受ける判断基準|親はどこで診断するしないの判断をするのか?
診断をするメリットは、子供と接する大人が、子供を理解し、子供の脳機能に合わせた配慮やサポートができること。
つまり、子供の自己肯定感を知らない間につぶさずに済むということです。
子供の自己肯定感は、幼少期ほど親の接し方がポイントになります。ですから、子育ての悩みや困りごとは、できるだけ早めに専門機関に相談した方がいいと思います。
その延長上に医師の診断があるだけで、そもそも論で言えば、子供の特性に合わせて子育てをすることが一番の理想なわけです。
しかし、一度に大勢の子供と接する先生にはわかりにくい発達障害、学習障害は、気づかずにいると子供の自己肯定感を毎日少しずつつぶしかねないのです。
親子ともに二次障害にならないためにも、早めの診断や専門機関への相談をおすすめします。
ポイントは親の直感。「何かが違う」と必ず感じます。それが診断や相談に行くサインです。
学習障害の診断の受け方
- 学校に相談する
- 教育支援機関に相談する
- 直接病院に予約を入れる
大きく3つのパターンがあります。
学校に相談する
- 担任の先生
- スクールカウンセラー
- 特別支援教室の先生
- ピアティーチャー
- 保健の先生
学校の相談先はたくさんありますが、てっとり早いのは特別支援教室の先生でしょう。
順番的には担任→スクールカウンセラーなのでしょうが、特別支援教室の先生は発達障害の子供達を支援する先生方なので、子供の様子や特徴から診断先の紹介まで、一度でわかると思います。
ただ、あくまでも相談ですので、診断するかしないかは親次第。その後、診断の予約なども親がやります。
教育支援機関に相談する
お住まいの自治体にある教育相談のようなところです。教育委員会の管轄にあり、学校に通っている子供の相談やセラピーなどの支援をしてくれます。
就学相談なども合わせてやっている所ですので、一度相談に行けば、その後の情報も入りやすくなります。
機関によっては、心理士がいて発達検査をやってくれますので、その結果から診断を受ける受けないを決めてもいいでしょう。
さらに、学校との連携もやっているので、担任の先生へのアドバイスなども期待できます。
療育センターや児童精神科がある病院へ直接予約を入れる
ネットで予約できるところもありますが、紹介状が必要になるところもあります。
紹介状がなければ初診料(費用がかかるところがほとんど)がかかりますが、ダイレクトで予約することで一番早く診断してもらえる方法です。
しかし、時期によっては初診まで半年待ちということもありますので、その辺りは覚悟しましょう。
また、1か所の病院では納得がいかない場合、セカンドオピニオンとして他の病院にも行き、先生との相性が合う方、通いやすい方を選んでもいいと思います。
その後、療育が必要になるようなら、通いやすい方を選んだ方がいいと思います。
学習障害の症状とは?学校生活でも起こり得る例

読字障害の症状
- 絵本や教科書を読む時、1文字ずつ読んでいる
- 教科書の読み飛ばし、読み間違いが多すぎる
- 絵本や本を読むと頭が痛くなると訴える
- 絵本や本を読むと目がチカチカすると訴える
- 絵本や本を読んでも内容がわからない
- おはなしの絵本を読まずに図鑑しか見ない
子供によっては他にも症状とみられることがあると思います。
読字障害であることは、その後の知識習得に大きな差が出てきます。読めないなら代替手段を使って知識を増やす必要があります。
書字障害の症状
- 板書に時間がかかり過ぎる
- 筆算や図形が書けない
- 筆圧が異常に弱すぎる(字が薄い)
- 真っ直ぐに書けない(だんだん曲がっていく)
- 漢字が覚えられない・おしい間違いが多すぎる
- ノートなどの罫線から大きく(毎回)はみ出ている
代表的と言われている症状です。
書字障害であることは、テストや授業への参加に大きく影響がでます。
クラスのみんなが一斉に書いている時に、自分だけ追い付かないことからの焦りや、筆算や図形で毎回ものすごく間違えることで、できない自分にいらだち、追い込んでしまう可能性があります。
また、なぜ自分だけが書けないのか?自分の頭が悪いのか?もっと努力すればできるのか?という違った方向にもいきやすいので、大人の理解と配慮が子供の学校生活を大きく左右します。
指先が極端に不器用な場合は、文房具選びや使い方の工夫で乗り切ることもできますよ。
算数障害の症状
- 時間がわからないので授業の終わりや休み時間が把握出来ない
- 数字の序列がわからないので順番がわからない
- 九九が覚えられない
- 計算や筆算が難しい
- 繰り上がり・繰り下がりが理解できない
- 文章問題から何を問われているのかがわからないので解けない
日常生活は思っている以上に数字に囲まれています。
幼少期から親が数を教えることが多いので、数字の概念がわからなかったり、数を覚えられなかったり、2個ちょうだいといっても違う個数をくれたりすれば、何かおかしいと思うきっかけはあります。
ただ、それがまだ発達的に未発達なものなのか、それとも算数障害なのか、という判別は専門家でなければ難しいと思います。
きっとそのうちわかる日がくるだろうと、子供に追い打ちをかけてしまう可能性も高い障害です。
また、算数障害の特性でもある推論に関しては、自閉傾向がある場合も同じような傾向が見られるので、どちらが関係しているのかわからない場合もあります。
専門家に相談するのが一番です。
振り返り|親の直感が学習障害に気が付くカギになる!早めの診断が子供を救う

冒頭でもお話ししましたが、学習障害は気が付きにくい障害です。
親が何か違うな、何か変だな、と思っても、子供ってこんなもんなのかな、いつかできるようになるだろうと思ってしまうと、学習障害であった場合は子供が必要以上に辛い体験をすることになってしまいます。
子供の状態を親の主観で判断するのではなく、客観的に見ることができるだけで、子供の学校生活は大きく変わります。
子供の様子に気づいてあげられるのも親だからこそ。
迷ったら専門家に相談し、診断を受けてみましょう。その結果を見てからどうすればいいのかを考えても遅くはないですよ。

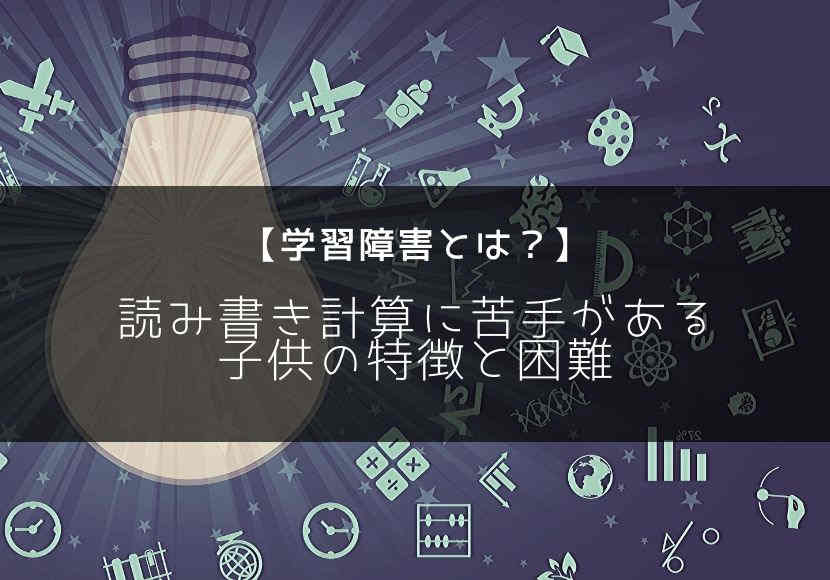


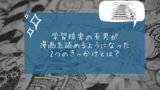


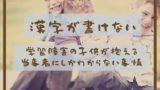
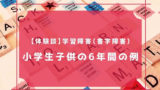
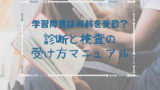


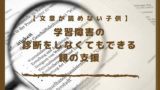
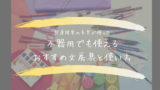


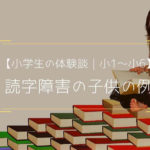

コメント