読みに困難があることの最大の問題は、学校生活のすべては読むことから始まっているということです。
全教科の教科書に始まり、板書、テストの問題、自分が書いたもの、友達が書いたもの、掲示物など、学校生活の中で、文章形態になっているものはとても多いのです。
読めばわかるでしょ。
と言われてしまうと、長男のような読字障害の子は居る場所がなくなってしまいます。
そして、周りで過ごすお友達も、読めないということの意味がわからないので、ストレートな言い方になってしまい、傷ついてしまうのです。
「誰も悪くない」あたりが、残酷だと思う学校生活です。
文字は読めても内容が理解できない読字障害の例
長男は文字は読めますが内容の把握は極端に苦手です。小学校生活の6年間で必要だった文章のタイプなどから推察し、なんとなくこんな感じだろうと予測をつけて文章と生活しています。
テスト問題などは、過去の経験から問題を予測し答えているので、初めて見るタイプの文章問題は、理解できないので答えらえれません。
そんな読字障害の長男の小学校生活は、こんな感じでしたというお話しをします。まずは就学前からです。
幼稚園年中~年長
- おはなしの絵本を読まない
- 1文字ずつしか読めない
- はなしの内容を理解していない
- ページをめくるように順番にあらすじを喋る
- 絵本を読むと(文字を読むと)頭が痛くなる
- 目の筋力が弱くチラチラ目が動いて文字が読みにくいと判明
- 療育でビジョントレーニングを始める
幼少の時から図鑑が大好きでした。特に乗り物と虫系が大好きで、昆虫図鑑をよく読んでいたのですが、絵本を全く読まないことが気になっていました。
幼稚園くらいになると、簡単に読める絵本は自分で読んだりしますよね。幼稚園でもらってくるキンダーブック的な絵本も、お話になると全く読みませんでした。
絵本は私が毎日何冊か読んであげてはいたので、読み聞かせで読んでもらった本の数はかなりの冊数だったと思いますが、それなら自分で読んでも良さそうだと思っていたんですよね。
入学前に絵本を読ませてみたところ、1文字1文字を追って読んでいて、話の内容は理解していませんでした。そして、「絵本を読むと頭が痛くなるんだ」と言っていました。
ならばと私が読み聞かせをした後、話の内容を聞いてみると、始めのページから順番にめくっているようにあらすじを喋っていました。
療育に通い始め、作業療法士さんに絵本が読めないことを話したところ、目の動きを確認してくれました。
結果、次のことが判明。
目の筋力の問題もあるようなのですが、筋力が弱いだけでもなさそうでした。その後2年くらい、ビジョントレーニングをやりました。

小学1年~2年
長男は早生まれだし、学校に入ったら読めるようになるのかなと思っていましたが、実際は教科書も読めませんでした。
- クラスのみんなは教科書を読めるのに、僕は読めない
- 音読で何回も間違ってみんなに笑われた(先生が助け舟をだしてくれたみたいです)
- みんなにできることが、僕にはできない
担任の先生も長男の様子に気づき、
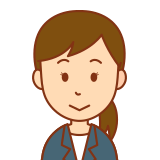
試しにテストの時に問題の長文を読んであげたら、長男君のテスト結果100点でした!!
と、実験結果を電話で報告してくれました。
読んでもらえれば理解できるけど、自分で読むと理解ができない。これが長男の最大のネックでした。
教科書関連は、自宅で予習代わりに私が読み、宿題やドリルの問題も私が読み、長男はそれを聞いて勉強を進めました。
小学3年
- 理解のない担任で「読めない」意味が理解されない日々を過ごす
- 音読などの読みの宿題は2行だけにするんだと家庭で負担を減らす
- この頃から耳で聞いたことの記憶力がすごすぎることに親(私)が気づき始める
書字障害のところでも書きましたが、この年は理解のない先生だったので、長男もいろいろと苦労しました。
「僕は読めません。」と先生に言っても、「ここを読んで書くんだよ」と返されるので、長男も若干あきらめていたようです。
私も何度か個別に面談をお願いし、担任に配慮を求めましたが、学習障害の意味がわからなかったようで、結局、私もあきらめて、自宅学習に切り替えました。
宿題で「エルマーのぼうけん」を丸々1冊読まなければいけなくて、長男も学校からエルマーの本を借りて持って帰ってきたのですが、当然長男本人は読めませんので私が読み聞かせをする形で1冊読みました。

1時間と10分もかかりました。すごく疲れたのを覚えています。
この頃から、耳で聞いた情報を記憶する能力がすごい事に私が気づきはじめました。
エルマーのおはなしに出てくる持ち物を、始めから順番に言えたこと、はなしの途中で使っていたアイテムを全て覚えていたこと。
目からの情報が取れない分、耳が発達したのかもしれない、と今でも思っています。
学校でのクイズなどは、難しい問題も1回で理解できる長男は、1番早く回答できるらしく、特技にもなっています。
小学4年~5年
- 理解ある担任に変わり無理に読まなくても良い学校生活に変わった
- 通級や療育の成果が感じられるようになってきた
- 家で私がピアノを教え始めた
- 家で私が独自の読みトレーニングを始めた
理解ある担任に変わったので、無理に読まなくてもいい生活になり、学校生活のストレスがかなりラクになりました。
小1から通っている通級でも、テスト問題の取り組みや長文の対策として、文章から情報を得ることのトレーニングをずっと続けていましたので、だんだんいろんな療育の成果が見られた時期でもありました。
家でも私が考えた独自の理論と方法で読みの実験を兼ねた訓練をしました。さらに、家でピアノを教え始めました。
この2つの方法をきっかけに、長男の読みに対する苦手意識は大きく変わっていきました。
漫画を読めるようになったことで、ネットで調べるか人に聞く以外の別の方法で情報を得ていく手段がわかってきたのです。
小学6年
- 特になし
5・6年はスーパー理解のある担任でしたので、学習障害であることの困りごとはほとんど感じられませんでした。
長男本人も「先生が素晴らしすぎて1mmも困ることはない」と断言するくらい、前向きな毎日を送っています。
担任の授業があまりにもわかりやすいので、テストの点数が良すぎて読解ができるようになってしまったのではないかと勘違いする程。
実際は、初めてみた読解問題はやはり半分くらいしかできていません。
文章問題が解けない算数障害ではない読字障害の例
文章理解が難しい長男は、算数の文章問題が理解できませんでした。
ある夏休みの宿題で出た問題と格闘すること40分。
一応算数の問題で、cmが点線で書いてあるものをなぞるだけ、という問題なのですが、点線をなぞるって何だろう・・・っと悩み続けること40分。
「点線」も「なぞる」も言葉の意味はわかるのに、文章になるとわからず、用紙に印刷されている点線のcmもわからない。
聞いてくれたら答えようと思って待っていましたが、長男は私に質問することはなく(これも問題なのですが)40分後、無事に点線をなぞってcmを書くことができました。
算数障害の特性として項目にある「文章問題が解けない」というものと、長男の例は別だと思うのですが、文章問題が解けない・できないという観点から見ると、長男もひっかかりますよね。
このように学習障害と言っても、子供によってさまざまなタイプがあるので、疑いがあるのであれば診断した方がいいと思います。
振り返り|学習障害の苦手さは早めの療育と学校の配慮で小学校時代はなんとかなる
通級や療育、家でのビジョントレーニングなどは、続けることで効果があると思います。
私はその他に、私独自で考えた読みのトレーニング方法とピアノを教えたことで、さらに効果が高まったと感じています。
やればやった分だけ、長男も要領よくこなせるようになっていきますし、現時点で長男ができることとできないことを、まずはそのまま受け入れてくれる親以外の大人の存在は、長男の小学校生活を大きく後押ししてくれました。
今では、読めない部分を友達や先生、親である私に聞いたりしながら、意欲的にいろんな活動に参加しています。
小1の時に想像していた長男の小学校生活6年間は、紆余曲折ありながらも、想像もつかなかったとても良い時代となりました。
私も学校側に一生懸命訴えてきましたが、学校側が受け入れてくれたことが本当に大きいと思います。
担任に理解されること、配慮いただくこと、受け入れてもらうことで文章理解が難しいという立ち位置にいながら、長男の居場所がありました。
担任が長男の学習障害を受け入れ、クラスメイトに配慮の方法などを説明することで、クラスメイトも長男を受け入れ、ずるいなどの文句も言わずそういうものなのだと思ってくれています。
中学校になれば、小学校のようにうまくいかないこともあるとは思いますが、小学校時代は担任次第でなんとかなるな、と感じた6年間でした。


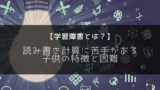



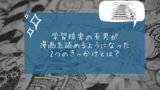

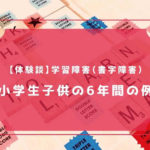

コメント