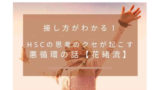感情の起伏が激しく、とにかくすぐ怒ってはスネ、怒っては泣いていた次男。
自分が思っていたことと結果が違うことで怒っている気がしてので、認知行動療法を使ったら、落ち着いてきました。
2年近く、機会あるごとに地道な接し方を続けてみたので、その方法をご紹介します。
すぐ怒るお子さんの対応に困っている方の参考になればうれしいです。
感情をコントロールするために認知行動療法で対応してみた【HSC次男用】

幼少期の次男の怒りは、本当に瞬間湯沸かし器のようでした。何が起爆剤になるのかがわからない。
本当にめんどくさくて、一時期は「勝手に怒ってれば」とあきらめモードに。
でも、やっぱりあきらめきれず、地道に認知行動療法の考え方を教えていくことで、次男の感情の出し方に変化が出てきました。
今まで
- なにかをやる→うまくいかない
- おこる→すぐやめる
- ふてくされて寝る→起きる
- もう一度やってみる→うまくいかない
- やらないという結果にする
わずか1回の再チャレンジで、どうせ僕にはできないんだ、という思考になりやめてしまう。
刺激が多くストレスが多い中で落ち着いて取り組みが出来なかったり、自分が傷つくことをあらかじめ予測し避けるためには、やらないという選択もあるのでしょう。
この、「やってみる→うまくいかない→怒る」までが次男は異常に早く、うまくやれない自分にいら立っていたみたいです。
幼少期なのに自己嫌悪??と、次男と接しながら疑問に思っていました。
そもそも長男が発達障害なので、私の子育て方針は個性を理解し、受け入れ接すること。
次男を否定するようなことは極力ない環境なのになんで??と納得がいかない時期でもありましたね。
対策後
- なにかをやる→うまくいかない
- そういうこともあるか→時間をおく
- 別のやり方を試してみる→うまくいく
- そういうことだったのかとわかる→知識や経験の上書きができる
認知行動療法の考え方を直接次男に教えることで、「うまくいかない」のは自分のせいではないと思ってもらえるようになったことが、感情コントロールに結びついていると感じています。
何でも見よう見まねである程度のことができてしまっていた次男は、初めから1回でうまくいくと勘違いしていたみたいですね。
年齢が上がってくるごとに、うまくいかないことが増え、理由も原因もわからず、いら立ってしまったのでしょう。
実践!感情コントロールができるようになった対応方法と注意点

それでは私が実際に次男にどのように対応していた方法をご紹介します。
あくまでも次男の例であるということを念頭において、HSCの子供やすぐ怒る子供の対応として参考にしていただければと思います。
事前準備
現状の状態を客観的に観察&確認
子供が怒り始めたら、まずは子供の様子を確認してみましょう。
- どんなことで怒り
- 怒ったときにどんな様子で
- 最終的に何をしているのか
など、客観的に様子を見ておきます。親の感覚であーだこーだと口をはさまず、あくまでも様子を観察。
「すぐ怒る」ことに子供自身が困っているかを聞いておく
子供自身が、自分がすぐ怒ることに対して困っていないのであれば、親がなんとかしたいと思っても難しいかもしれません。
次男の場合は、その後、自己嫌悪に陥るため、できるなら怒らずに行動したいという本人の希望があり、親としてサポートすることができたわけです。
どう考えているのか、どう思っているのか、などを子供自身に客観的に理解してもらうことが認知行動療法の始まり部分なので、子供自身が困っていることがポイントです。
事前に予告しておく
次に「すぐ怒ってしまったとき」、こんな風にしてみましょう、と事前に親が対応することを予告しておきましょう。
できれば次から紹介することをお話しておき、怒るのではなく、他にできる方法がないか一緒に考えてみよう、と予告をしておきました。
発達障害の対応も同じですが、予告しておいた方が実際に困りごとが起きたとき、今がその時だな、と思えるので効果も上がってくると思います。
大きく分けて6つの方法を実践
子供が怒り過ぎてどうにもならないときは、あまり対処できないと思い、会話ができそうな感じのときだけ、以下の対応をしました。
イライラを紙に書きだしてもらう
書けないよ、と言われることを想定しつつ、「ママのバカ」でも「うるせえ」でも何でもいいから、今怒っている原因や理由を書き出してもらいました。
全く関係ないことでもいいので、怒っている今、頭に浮かんでくることを次々書いてもらい、書き終わったらその場で丸めて捨ててもらいました。
紙は何枚になってもいいし、親に見せる必要はないので、書くだけ書いたら丸めて捨てる、ということをやってもらいました。
これは具体的に字で書くことで、自分が何に怒っているのかを自問自答してもらうようなもの。
書いて、目でみるので、若干ではありますが、客観的に目で見ることになり、怒りを認識できるのではないか、ということです。
バカ、アホ、マヌケ、でもなんでもいいので書いてもらいました。
やめる代わりに落ち着く別の方法とすり替える
それまでは、うまくいかないと怒ってやめてしまっていたところに、気持ちを切り替える別の行動を入れ込みました。
- ジュースを飲む
- お菓子を食べる
- 窓を開けて空気を入れ替える
- 外に出る
など。
テレビを見てもいいし、動画やゲームをやってもいいのでしょうが、気持ちを切り替えるというよりそのままゲームをやってしまって本質からズレる危険性があると思ってやりませんでした。
あくまでも、気持ちを切り替えるための別の行動。
発達障害の対応でも、こだわりから抜けられないときや、感情の切り替えができないときの対応として、他の好きな行動とすり替える方法を勧められていました。
これを使って、怒りでいっぱいになっている気持ちに別の空気を流し、ハッと気づかせるような意味合いでやってみました。
ジュースやお菓子を食べる、というのは本来であればあまりいい対応とは言えないのですが、次男は女子並みにお菓子が大好きなので、すり替え行動に使うにはピッタリだったのです。
1日で数回、この対応が必要になった場合ように、ジュースやお菓子だけでは糖質過多になり過ぎますから、外に出たり窓を開けて空気の入れ替えをするなども候補にあげておきました。
今の空気と別の空気になるだけでも、以外と気持ちはリセットされるようです。
目的(ゴール)を再確認
怒り過ぎて忘れてしまいがちですが、結局は何をしたかったんだっけ?ということを改めて確認しなおします。
何が言いたいかというと、何かやりたいことがあって、その途中過程でつまづいたけど、最終的に何ができればいいのか、ゴールに向かって別の道もあるのでは?ということを改めて核にしておきました。
現状との差を見つけ具体化する
子供で現状の問題点を具体化できるわけはないので、質問形式で大人の私が完全サポート。
次男にこたえてもらいつつ、次にチャレンジするならどんな方法を試してみようか、という話をしておきます。
うまくいかない場合の対策を事前に立てておく
先の予測を立てるのはHSCの得意分野だと私は思っています。
ちなみに、うまくいかない予想を立てることも得意分野でしょう。
この辺を踏まえた上で、もし、次にチャレンジしたときにうまくいかなかったら、こんな風にしてみたらどうだろ?ということを考えておきます。
ただ、怒り過ぎている場合、子供本人はこの対策を思い出せないので、声をかけて対策をやれるようにしました。
実践→大丈夫だった、できたという経験の上書き
もう1度、別の案で行動を起こすことで、体験や経験ができ、大したことなかったな、意外とできたな、と思えれば成功。
慣れないと、親子ともなかなかうまくいきませんし、毎回、対策まで実施できるとは限りませんでした。
しかし、何度もチャレンジしていくうちに、イラっとしても爆発的な怒り、というものはなくなっていきました。
すぐにやめてしまっていたのは昔の話。
当たり前のことですが、今でも「うまくいかない」ことはたくさんありますし、僕には無理だな、と言うこともあります。
しかし、以前のように「すぐ怒る」か?と言われると、ほぼ怒らなくなったと言っても過言ではないレベルまできています。
成長や発達しても認知行動療法は使えますので、この方法が次男に合っていたのはとても良いことでした。
うまくいったなと感じたポイント
- 次男本人が自分の「すぐ怒る」ことをなんとかしたいと思っていた
- 対応する親があきらめないこと
やはり、次男本人が自分の怒りグセをなんとかしたいと思っていたことが一番大きいでしょう。
親の希望だけで「すぐ怒る」クセをなんとかしたいと思っても、うまく対応しないと親の押し付けになりかねないのですからね。
さらに言えば、対応する親の方も、とにかくあきらめないことだと思いました。
本で読んだ対応や、自分がこうしようと思っていた対応ができないことも多々あります。
人間同士ですからね。親子だからってそんなに簡単にうまくいくわけではない。
そんな風に思って対応し続けることで、なんかいいかも!と思える対応はできるようになってきます。
気を付けて対応した方がいいと思った注意点
2番目の、やめる代わりに違う行動と差し替える箇所で、自傷行為にすり替えないこと、ですね。
例えば、外に出た場合、怒りに任せてダッシュをしようものなら、都会では車にぶつかってしまいますし、交通的に危ない。
また、窓を開けて空気を入れ替えたとき、窓から下をみると危険すぎます。
間違って落ちたりしたら大変。
怒りで逆上しているときなどは特に、ケガにつながらないように大人が注意した方がいいなと思いました。
振り返り:認知行動療法の考え方で「すぐ怒る」次男を卒業できた

HSCの気質上、神経質になりすぎて体験や経験が増えないことは困りごとの一つにもなるでしょう。
「怒り」という一つの感情を考えてみても、違う見方や考え方をするだけで、その後の行動が変わることは多々あると思います。
体験や経験ができれば、知識も増え、さらに別のことにも応用していける。
ちょっとしたことですが、積み重なっていくことで社会という何がおこるかわからない場に出ても対応していけるようになるのでは?というのが、私が認知行動療法の考え方を取り入れている理由です。
感情をコントロールできることは、人と生きていく上での必須項目だと思うのは、私だけではないでしょう。
幼少期のうちは、まだまだ知識も経験も足りませんから、怒ったり泣いたりすることはとても大切なこと。
しかし、あまりにも激しい癇癪にはいくら親でもメンタルがやられてしまいますからね。
実際、子供に教えられる年齢になっていなくても、認知行動療法の考え方を親が知っているだけでも、癇癪の見え方や接し方が変わってくるのではないでしょうか。
次男の場合は、今回ご紹介した方法で落ち着けるようになりました。これは、次男が小3だったことも良かった点だと思います。
会話ができれば、基本、認知行動療法的な考えは使えると思いますが、自己認識という点で言うと、成長や発達が足りていないと難しいかもしれません。
小さい子の場合は親がナントカして対応していくしかありませんが、それなりに会話ができるなら、試してみてもいいと思いますよ。