HSCだと共感能力が高すぎて、友達とうまくいかない子供っていますよね。どうしてうまくいかないのかが親にもよくわからなくて悩んでいませんか?
こんにちは!HSPの私が子供の頃、友達との距離を微妙に保っていた花緒です。子供なので意識はしていないと思いますが、ちょっと引いて付き合っていた感覚は覚えています。
今回は、HSCの子供の友達関係について、うまくいかない場合どういう対処法があるのかということを、私の経験やHSCの次男の子育て経験からお話ししていきます。
HSCの子供が友達とうまくいかなくて困っている、という方の参考になればうれしいです。
HSCの子供の友達関係

HSCの特徴はこちらの記事を参照ください。HSCのチェックリストも載せています。
共感能力が優れているHSCの子供は、一緒にいる人の感情に共感してしまいます。
共感(きょうかん)、エンパシー(empathy)は、他者と喜怒哀楽の感情を共有することを指す。もしくはその感情のこと。例えば友人がつらい表情をしている時、相手が「つらい思いをしているのだ」ということが分かるだけでなく、自分もつらい感情を持つのがこれである。通常は、人間に本能的に備わっているものである。
引用: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
誰でも少しは相手の気持ちがわかるとか、人が集まった時の空気感とか、わかる能力が有るとは思います。
人の表情や状況や言動・行動から推測することもできるでしょう。
映画やドラマに感動して泣いたり、音楽やパフォーマンスに感動したりするのは、共感能力ですよね。
HSCの子供の共感力とは【花緒論】
では、一般的な共感力とHSCの子供の共感力は、何が違うのでしょう?
と言っても、人それぞれなので、これですと断言できるものはないので、私や次男の例でお話します。
HSCの子供は人の感情や思いがわかる
一緒にいる人の感情や思いなどを読み取る共感力が優れていると思います。優れているというと、ポジティブな表現ですが、わからなくてもいい時にわかりすぎるのも困りもの。
なぜ困るのかというと、こんな感じです。
- いろんな人の感情・思いがわかる
- どうすればいいのかを察する・または考える
- その後のいろんな人の感情・思いを予測
その結果、
- こっちを助ければ、あっちが助からず
- こうすれはできるけど、反対されるかもしれない
- 自分ではこう思うけど少数意見過ぎて言えない
などいろんな思いがよぎります。一種の妄想に近いと思うのですが、自分の頭の中では、自分の思いや感情と人の思いや感情で忙しくなるんですね。
HSCやHSPの人の頭の中を言語化してみると・・
例えば、何かを解決するために対策を考える場面で、
- 自分はAだと思う。他2人がAだと思う。
- 常にいばっている人がBだと思う。
- 他全員Cだと思う。
こんな状態だったとしましょう。HSCやHSPの人の頭の中を言語化するとこんな感じ。
地球レベルで長期的に考えれば、今A案を始めた方がいいことは確かだが、面倒なのでやりたがる人はいない。
でも、いつもいばっているB案を出している人の機嫌がとても悪いので、B案にしないと怒鳴りはじめたらイヤだな・・・・
で、どうすんの?って話しなんですよね。
人の感情や空気感って、何となくわかるレベルならそこまで考えないと思うのですが、特に機嫌がいい悪いに関しては敏感な気がします。
当たり前ですがHSCの子供も自分を守りたい
機嫌が悪い→怒るんじゃないか・怒鳴るんじゃないか→場の空気が悪くなるのではないか
そんな重たい空気の中に自分は入りたくないわけです。誰でもイヤだと思いますけど、できるだけ避けたい。
だって、怒っている人の感情みたいなものも、風圧的なもので自分に飛んでくるんですよ。なんかね、別に威圧しているつもりはないのでしょうが、爆風的なものが飛んできて、手裏剣的なものがグサグサ刺さるわけです。体中に。
痛々しいのですよ。
そんなに怒鳴らなくても、怒らなくても、こうすれば丸く収まるじゃないって思うのですが、その方法を取らずに怒ったり泣いたりする人の感情だけが飛んでくる。
友達だと同情して一緒に泣いちゃうし、一緒に腹が立ってくるし、一緒に切なくも寂しくもなってしまう。要するに非常に疲れるってコトです。
いじめにも冷静に反応した過去
自分をいじめて気が済むなら、やりたいだけやれば、という感情になってしまった私です。
私があったいじめは言葉や態度(いわゆる完全無視)だけで、暴力的なものはなく、3か月もなかったかな、そんな一時的なものでした。
何されても私が全然反応しないのと、周りの友達が最終的には私の味方になってくれて、いじめた子と仲直りして終わりました。
逆に、そうでもしないと自分を保って行けない友達や人を見ていると、かわいそう(残念)な気持ちになってしまうのです。
相手にもいろいろ事情があるんだろうな、と思ってしまって。だって、生まれた時から人に悪態をついていじめて友達をおとしいれようなんて思ってるわけないですからね。
何かわかってほしい、かなえてほしい思いがあるのかもしれないとか、考えてしまい、同情してしまう。過去の話ですが。
共感力が強すぎて他の人の感情が自分の感情になってしまう
友達が好きなアニメは自分も好き、友達が持っている文房具は魅力的、友達が楽しいから自分も楽しい。
じゃあ、自分は一体何が好きなんだろう??
ということが起こります。
自分の気持ちを見ないで人の感情を自分の感情だと錯覚してしまう
錯覚しちゃうのかな、そんな中でも、本質的に興味があることや好きなものはあると思うのですが、その上に人の思いが乗っかってしまうような感じです。
人の思いを取れば、自分の好きなことなどが見えてくるのですが、人の思いがオブラートになってしまって、見えなくなってしまう。
だから、本当は自分が好きなことはこの遊びなのに、友達が好きなあの遊びばかりで遊んでいるうちに、楽しいはずなのに何か違う気がする・・・でもわからない(子供だから)というモヤモヤが生まれます。
そういうことが溜まってくると、何かをきっかけに癇癪のようなもので定期的に爆発したりすることもあります。
HSCの子供の癇癪は、そういう類かな、と今まで子供を見てきて思います。
育てやすい子・いい子と言われる子は要注意
いい子になろうとするというか、大人や親の思いに応えるために、自分がいるような気がしたり、大人や親の喜ぶ顔が見たくて、自分の気持ちに気づかないようにしている感じにも見えます。
たぶん、子供本人も気づいていないかもしれませんが、本当の思いはあるのに聞き分けがいい子は、何かあるなーと私は感じてしました。
ピアノの生徒にも、親の期待に応えるために一生懸命やりたくないピアノを頑張って、でもやりたくない自分の思いにももうフタをできなくて、という子もいましたからね。
生徒と良く話をして、親にも私から話をして、一旦レッスンを休会してもらったりして休ませましたが、お利口さんでいい子と呼ばれる子は、他の子供達から妬まれる原因になってしまうこともあります。
友達と先生などの大人との板挟みってヤツですね。
別に八方美人になりたいわけじゃない。友達の気持ちもわかるけど、先生や大人の思いもわかる。友達の味方をしたいけど、友達が間違っている時は自分の気持ちとの板挟みに合って、動けない。
正しい方を取れば友達に嫌われ、間違っている方を取ると良心が痛む。
メンタルが崩れるしかなくなります。
共感力があり過ぎて、自分が楽しめない
一緒にいる人の機嫌が気になって、自分に集中できません。
友達と一緒に遊んでいても、常に楽しいかな、つなんないって思ってないかな、ということが気になり過ぎて、遊びに集中できず、自分の楽しさにも気を向けることができないということが起こります。
授業中もクラスの友達分の感情と、先生の感情が気になって、今やるべきことに集中できないということはよくあること。
外でも見てボーっとしていないと、やってられなくなるわけです。
友達が楽しかったから自分も楽しかったのですが、本当に楽しかったとは思えなくて、もう一度自分1人で同じ遊びをしたり、出かけた場所に行ったりすることもあるくらい。
二度手間もいいところ。
HSCの子供が友達とうまくいくための3つの対策

自分の気持ちと言動・行動を同じにする
人の思いは勝手にスキャンされて自分の頭に入ってきてしまうHSCの子供。では自分は?どんな気持ち?どんな思い?ということを考えてみます。
自分の頭の中だけで考えている分には、誰にも否定されないし、嫌われません。安心して自分の気持ちを考えるように意識をしてみます。
そして、自分の気持ちと自分の行動は同じであった方がいい、ということを教えてあげましょう。
自分の気持ちと行動が違うと、自分に嘘をついて行動を取るわけですから、その穴埋めを「言い訳」などの別の行動で埋めなければいけなくなってきます。
自然と同じように、人間もバランスの生き物。どこかでバランスを取るためのツケがいつかやってきます。
そのツケは自分をむしばんでいっているということ。メンタルが崩れて、体調不良になる前に、気持ちと行動は同じにした方がいい。
その方が自分に自信が持てるし、人に振り回されなくても済みます。自分の人生は自分の時間。人に振り回されて一日が終わるよりは、自分の意志で動いた方がいろんな意味で前向きになれます。
基準は自分。その次に人がいて、一緒に生きていくためには、じゃあどうしようか?という順番です。
大げさかもしれませんが、HSCのように深く考える子供たちは、地球レベルで人間という生き物レベルで考えている子もいるので、規模を大きく話してみると伝わりやすいかなと思っています。
自分と他人は別の人間であることを知識として知る
そんなの知ってるって言われそうですが、人の感情に振り回されてしまう時点で区別できていません。
意識しないと難しいことなのですが、今自分が感じていることは誰の思い?ということを知ることです。
このような、ちょっとした翻訳作業が必要になります。
今の子供の思考回路を流れる電流の量と向きを、少し変えるか別のものとつなぎかえる必要がありますので、親がサポートしてあげたいところですね。
根ほり葉ほり聞く必要なありませんが、子供から相談を受けたら「誰の思いを背負ってしまっているのか」を一緒に考えてあげましょう。
そして、自分の思いや自分の気持ちと同じ行動を取ることで、友達との関係に嘘がなくなりますので、本当の友達とのコミュニケーションができるようになってくると思います。
自分だけの時間を作り自分の世界を作る
人の思いと感情にたくさん振り回されてしまう分、自分の世界に浸って修復する時間が必要です。
自分の部屋があれば一番いいのですが、なければ部屋の隅にでも、子供だけのプライベートスペースを作ってあげましょう。
親にも兄弟にも誰にも気を配らなくてもいい(誰も頼んでないんですけどね)、そんなところで始めて、自分の気持ちに素直になって、自分の心を休めることができるようになると思います。
好きなものに囲まれる、好きな時間を過ごせる、没頭できるものがあると尚いいですね。
習い事などで発散するという手もあります。
人が多い所が疲れるのか、習い事であれば人が多くても大丈夫なのか、子供によって違うと思いますので、興味がある子は学校と家以外のコミュニティを持ってみることも気分転換になりますよ。
振り返り|HSCの子供が友達とうまく遊べるように親はポジティブシンキングを身に付けよう

では親にできる一番のことは何でしょう?
もちろん、子供の問いに答える、子供の味方になってあげる、何があっても側で支えてあげるという安心感を与えることも必要でしょう。
私が、HSCの子供の親ができる一番のサポートは、ポジティブシンキングを身に付けることだと思っています。
HSCの子供の思考回路は結構すごいと思っていて、ネガティブな方にネガティブな方に考えていくような気がします。
そして、子供によりけりではありますが、人には「大丈夫、できるよ」と励ましておきながら、自分はできないといってやらないという傾向が見られると思います。
よくまあそこまでネガティブに考えられるね、と思うくらいなので、失敗する方の対策は子供が勝手に見つけられます。
あとは、その反対を考えればいいだけですよね。
失敗する方の対策ができたら、次にやることは、その反対。できる方の手段を考えることです。
しかし、ネガティブシンキングで「できない」と結論づけている思考回路を変えるには、ポジティブシンキングを発信していきましょう。
始めはそれでも「できない」というでしょうが、親がいつもポジティブシンキングで喋っていると、そういう方法だとできるのか、という1つの知識になると思います。
知識がたくさん集まって、ネガティブ要素よりも1つ、ポジティブ要素が上回ったら、HSCの子供でも自分から「できる」方へ向かえるんじゃないかな、と思っています。
子供に負けないくらいのポジティブシンキングを身に付けて、ネガティブ要素を上回っていきましょう。
上辺だけではない、本格的に核の部分からポジティブになるという本。うまく子育てに変換して参考にすることもできるため、Daigoさんの本はおすすめです。

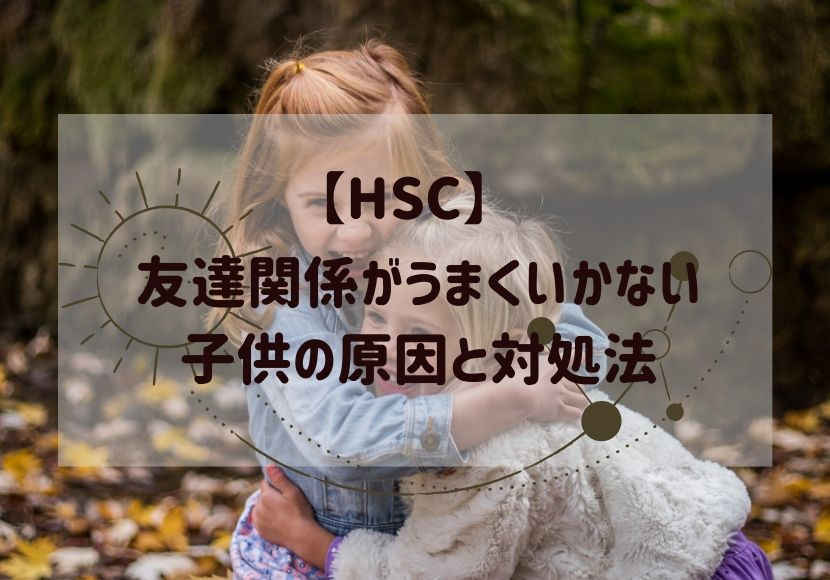
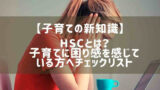

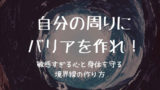


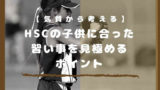




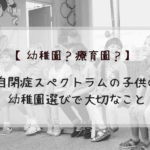

コメント