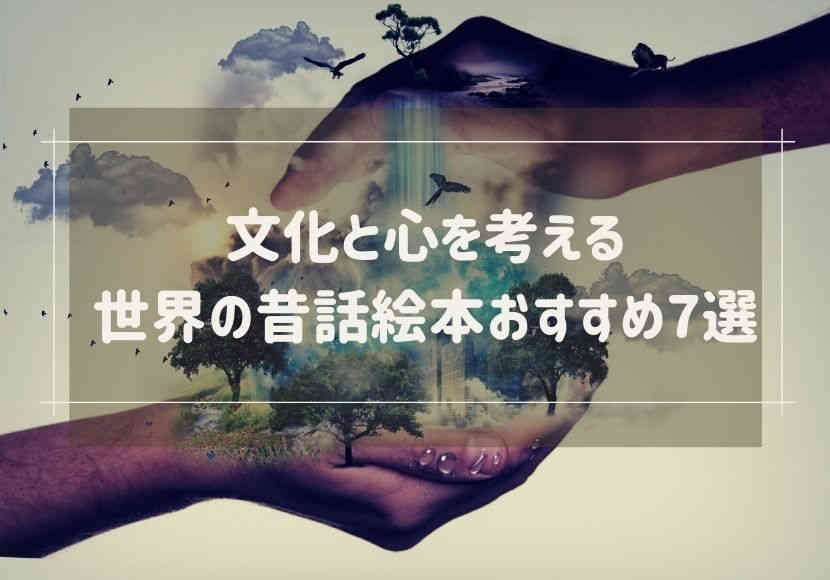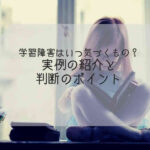長い時代を超えて語り継がれてきた昔話。世界の昔話には、日本とは違う風景や文化、人のやりとりが描かれています。
自分の周りしか知らない子供への読み聞かせには、日本+世界の昔話がおすすめ。家での読み聞かせ、幼稚園や学校での読み聞かせなどの参考になればうれしいです。
年少からわかる&難解な神話まで世界の昔話絵本7選

昔話は、どのおはなしにも、何かしらの教訓があるため、絵本選びに困らないところがメリット。
例え、淡々としていても、心に残るものかあるので、読み聞かせにもとても向いていると思います。
今回は、さまざまな世界の昔話の中から7選、ご紹介しますね。
【ウクライナ民話】びんぼうこびと/3分40秒
いくら働いても貧乏だった一家には「びんぼうこびと」が住んでおり、そのこびとを追い出したらびんぼうではなくなった、という昔話の定番なおはなし。
日本の昔ばなしっでいうところの「びんぼうがみとふくのかみ」みたいな感じではありますが、戦いらしきものは一切なく、こびとが追い出され、そのこびとが次に行った先の家が貧乏になるといった感じ。
あっさりした話、と言ってしまえばそれまでですが、ねたみなどの人間の感情も出てくるため、昔ばなしらしい展開ではあります。
おはなし自体はとてもわかりやすいので、幼稚園から小学校低学年くらいの読み聞かせ向きです。
【ジャータカものがたり】はじめてのともだち
王さまゾウのところに迷い込んできた野良犬と、王さまのゾウの友情のはなし。絵と文の感じから、保育園や幼稚園などの読み聞かせにおすすめです。
王さまのゾウさんは式典以外に出番がないので、普段はとても寂しい、という共感系。最後は「よかったね」で終わるので、年少さんからOKな昔話です。
【テキサス州のむかしばなし】青い花のじゅうたん
日照りと飢饉に苦しんでいた部族にいた少女が、親の形見でもある大切な人形を生贄に、部族を守ったおはなし。
現代の私たちの生活からは想像がつかない日照りや飢饉。日本の昔話にもあるように雨が降らない生活がもたらす人々の苦しい生活の様子が描かれています。
自分が大切にしているものを犠牲に、仲間を助けるということを、大人ではなく子供がやっているということ。
スカッとする話ではなく、どちらかというと重く心にのしかかってきますが、勇気ある少女の行動と結末は、子供の心にも響くお話となるでしょう。
【ロシアの民話】マーシャと白い鳥/5分
親の留守中に魔女の白い鳥に弟をさらわれたマーシャが、弟を助けに行く話。道中の問題を解決しつつ、魔女の元にいる弟を無事に助け出し戻ってきます。
このお話では、魔女が「ババヤガー」という表現になっているので、読み聞かせの際は一言添えた方がいいかもしれませんね。
魔女の絵は描かれているのですが、「ババヤガーってなんだ?」ってなると思います。
直接魔女に何かされるわけではないのですが(弟を連れて逃げた後は、白い鳥を使って追いかけられますが)ちょっとドキドキする感じです。
やわらかなタッチでありつつ、とても印象に残るインパクトのある絵も魅力の一つ。親の知らぬ間に起きた、とんでもない大冒険でした。
【エジプト神話】オシリスの旅/5分30秒
エジプトの神話です。エジプトの王、オシリスと妹であり妻のイシスの話。
エジプトの王であるオシリスが弟セトに騙され棺ごとナイル川に落とされて殺されてしまう。流された場所までイシスが探し、エジプトに戻ってきてもまたセトにバラバラにされ、と散々な感じ。
どんなにひどい目にあっても、他の神々の力を借りつつ、イシスが賢明にオシリスをよみがえらせようと頑張り、最後は冥界の王になるのですが。
神話なのに、兄弟で殺し合うってどうなのよ、、、と子供の頃によく思いましたが、大人になってから読んでもやっぱりどうなのよ、って思います。
ま、王さま家の権力争いの末に神になったのでしょうが、悪い王でもない人が、悪い人にやられてしまうのは後あじ悪過ぎますね。
読み聞かせとしては、文体が難しいのですよ。やわらかく優しい表現ではなく、~となる、みたいな感じがずっと続くため、高学年以下には向かないでしょう。
たぶん、飽きちゃいます。
ただ、ギリシャ神話以外の神話が絵本という短いお話でまとまっているのは、少ないと思うので貴重だと思います。
さらに、独特な絵の世界観にも注目したい作品ですので、エジプトの神様のお話はこんな感じ、というきっかけとして、家や学校などの読み聞かせで読んでみてもいいですよ。
【中国の民話】あかりの花/5分
働き者の若者のところに、あかりから出てきた嫁ができ、裕福になるとともに怠け者になる若者。
すっかり働かなくなると嫁はどこかへ行ってしまい、若者は改心します。
日本の昔ばなしの展開と同じような感じなのですが、このお話の結末は、改心した若者の元に元嫁が戻ってくるのです。
嫁はあかり(灯り)から出てきた不思議な女性で、どこからきて、どこへいなくなってしまい、どこから戻ってくるのかなど、謎が多い。
冒頭と終わりの方に出てくるゆりの花(若者の汗や涙が変化した)とも関係があるのか、ゆりの花はなんだったのか、とわからない部分もあるにしろ、しっかりと改心するあたりはさすが昔話。
改心した後、同じ幸せが戻ってくる展開はあまり見かけないので、結末もよろしく、世界のお話としての読み聞かせ向きです。
ふくろのなかにはなにがある?/7分40秒
どの国の昔話なのかがわからないのですが、キツネと人間のかけひきモノです。
キツネが捕まえたものを大きな袋に入れ、次々と人の家に袋を預けます。絶対見ないでねと言って。
ま、見ますよね。
で、見てしまうと中に入っている生き物が逃げていき、逃した責任として別の生き物をまた袋に入れ、次の家へ。の繰り返し。
見た人たちは、正直に気になったから見た、と申告するんですよね。まずそこが素晴らしいかと。
最初はハチだったのに、徐々に重く大きくなっていく袋の中身。最後はどうなるのでしょう?と子供たちも楽しみになっていくおはなしです。
振り返り:世界の昔話絵本からさまざまな文化や心に触れよう

小さな子供から大人まで、性別問わずに楽しめる世界の昔話。
読み手の読み方や子供の反応など、絵本ならではのコミュニケーションも貴重な体験ですよね。
必ずしも、読み手が伝えたいことが伝わるとは限りませんが、絵本の世界観、昔話の世界観から感じとるものはあるでしょう。
知的好奇心が旺盛な子供たちには、さまざまな世界の昔話の絵本を通して、日本とは違う文化や心に触れてほしいですね。