子供が習い事をやめたいと言い出すこと、ありますよね。習い事をいくつかやっている場合や、長く続けている場合、いずれは親子で向き合う日がくる問題です。
親としては、できれば習い事を続けてほしいと思ってしまい、なんとか子供を説得しようとしますが、イマイチ子供に響かず、悩んでしまうこともあるでしょう。
今回は、子供の習い事について、やめたいと言い出した理由を考えてみた上で、親にできる対処を3つご紹介します。
ピアノ講師の経験から、子育て経験から、現時点でわかっていることをお話しましょう。
逃げでもわがままでもない|習い事をやめたい子供の理由とは?

「習い事をやめたい」そう思うことは、逃げでもわがままでもありません。
しかし、中には子供が習い事をやめたい理由を聞かずに「ダメ」「それはわがまま」「あなたが習いたいって言ったから始めたんでしょ」「3年やるまでは続けなさい」と一方的に言う親もいます。
確かに、親の言うことも一理あるとは思います。
人の気持ちに敏感で空気を読みすぎるタイプの子供であれば(HSC)、そんな親の顔色が怖くて、習い事をやめたい本当の理由を話すことはないでしょう。
当然、子供の数だけ習い事をやめたい理由はあると思いますが、今回は私がピアノ講師をしている時に講師仲間から聞いた理由や、私が生徒本人に聞いた理由から、ぜひ親の方に知っておいていただきたい代表的な理由をご紹介します。
そもそも習い事が好きではなかったから
まだ人生経験も浅く、数も少ない子供時代は、いろんなことに興味を持ちますし、目移りもするでしょう。
- おもしろそう
- やってみたい
とても単純な思考回路で動くので、どんな体験にもチャレンジできるし、経験も増えていくきっかけになるんですね。
- 習い事の先生がこわかったらどうしよう
- 続けられなかったらどうしよう
- すぐにやめてしまったらお金が無駄になるかもしれない
- 同じグループの仲間とうまくやっていけないかもしれない
- そもそもボクにはできないかもしれない
このような、数々の「どうしよう」と「かもしれない」は基本、子供の思考回路には存在しません。
深く物事を考えるHSCの子供か、または大人の発想ですよね。
ですから、親に「この習い事やってみる?」と体験レッスンに連れて行かれたら、「やってみたい!」となるわけです。
しかし実際にやってみたら、全く興味がないものだった。ということは、子供の習い事あるあるです。
そもそも、1回の体験レッスンでわかるはずもないのです。それが子供というものです。
ですので、実際に何回か通ってみたら、全然面白くなくて、興味がないものだったから「やめたい」と言い出す可能性は十分にありますね。
思っていたよりうまく出来ない・スランプから抜けられないから
興味はあったんだけど、実際にやってみたら思っていたよりも全然うまくできない。
これも子供の習い事あるあるです。
子供の習い事が「うまくいかない」にはいくつかの原因があります。
情報が足りていない
発達段階の子供ですから、習い事に参加するための情報が足りていない場合があります。
習い事の種類によっては、基礎から順にスキルを身に付けなければいけないものがありますが、基礎から覚えていくための「言葉」であったり、先生の「伝え方や表現」が理解できなかったりすることが考えられます。
例えば、
- 日本語を日常的にたくさん聞く
- 日本語の単語を覚える
- 目で見た物と単語が結びいて記憶する
- 記憶を介して運動機能に命令を送る
- 運動神経に伝わり手や口が動く
私が考えた簡単なサンプルですが、習い事の先生から話を聞いて参加するには、日本なら日本語をたくさん聞き、理解できなければいけません。
しかし、単語や口語の表現に関しては、各家庭・子供の発達に応じて差がありますね。
先生が子供に合わせてうまく通訳ができなければ、子供は理解ができず3,4,5に結びつかず、レッスン中に目で見える、5の運動機能として見えてこない。
どこかで1つ、つまづいているだけなら、そこの情報を追加するなり、違う方法を試すなりすれば変わってくるのですが、先生も親も気づかない場合は、子供ができない思いを募らせてしまうんですね。
これは子供のせいではないのですが、親や大人はどうしても自分の知識や経験から解決法がわかるので、「なんでできないの!」「どうしてわからないの!」「こうすればいいだけじゃないの!」と言ってしまいます。
よって、最終的にわからないままの子供は興味がなくなり、できない思いを抱えたまま、「やめたい」となります。
発達が追い付いていない
子供の発達は、一概に年齢で横に線引きできるものではありません。
先程の情報量が足りていないと共通しますが、子供の中には発達障害のように神経のつながりがうまくいっていない場合や、遅れていることも考えられます。
子供をよく観察し、子供の動きや反応などから習い事の先生や親が判断できることが望ましいのですが、「できるでしょ」という思いを持っている大人も結構多いと思います。
それだけ、子供の発達に関しては判断が難しいのでしょう。
しかし、こちらも子供が悪いわけではないのですよね。
人それぞれ違う発達ですから、子供の発達に合わせて大人が配慮したり待てないようであれば、やはり「やめたい」となっても仕方がないでしょう。
グループレッスンに多い|レベルの違いから劣等感(優越感)しか感じないから
習い事の種類にもよるのですが、グループレッスンの場合、同じグループの子供達の間で、すぐに出来る子と出来ない子に差がでます。
そして、先生は出来ない子をフォローすることが多いので、すぐに出来てしまう子は時間を持て余し、習い事の時間が徐々につまらないものになり、「やめたい」となります。
逆に出来ない子は、いつも自分が先生にフォローされるので、引け目を感じてしまいます。みんなはすぐにできるのに、自分だけいつも出来ない。
そんな思いが積もりに積もって、やる気を失い、出来ない自分を責め、「やめたい」となります。
子供に習い事をやめたいと言われたら親にできる3つの対処法

次に、子供に習い事をやめたいと実際に言われた場合、親はどうすればいいのかについて3つの対処法をお話しましょう。
子供がなぜ習い事をやめたいのか理由を聞く
とにもかくにも、理由を聞きましょう。
理由も聞かずに、「ダメ」というのは、親の思いを子供に押し付けていることになってしまいます。子供は親の言う通りに動くお人形ではないので、きちんと話を聞いてあげましょう。
子供の話は傾聴スタイルで聞いた方が良い
親のいろんな思いがあれこれあるとは思いますが、まずは子供の本音を全て聞いてみましょう。
突っ込みたくなることや、棚に上げていること、誰かのせいにしてること、矛盾していることなど、気になることは多々あるでしょうが、途中で親が口を挟んでしまうと、子供の言いたいことが途中で切れてしまいます。
- やめたい理由は何か
- やめたい原因は何か
- 習い事の先生に相談できることはあるのか
- 親にできることは何か
これらの情報を子供から引き出さないことには、習い事を続けてもらいたくても説得のしようがありませんよね。
この3つを合言葉に、子供の話を傾聴し、習い事をやめたい情報を密かに収集しておきます。
習い事をする目的を親と子供で確認する
できれば、習い事を始める前にある程度決めておくといいのですが、習い事を続けていくには目的を持つ事が重要です。
- 何のために習い事をやるのか
- 習い事をすることで何ができるようになりたいのか
- 最低限どこまで頑張ってみるのか
子供と一緒に話をしながら、習い事をやる目的を考えてみます。
目的を果たせそうにない習い事だった
「やめる」というのは1つの選択肢になりますね。
目的は果たせそうなのにやめたい場合
今のやり方ではなく、子供なりの別のやり方が必要なのでしょう。
冒頭でお話した「習い事をやめたい理由」の中に原因が隠れている場合がありますので、今一度子供の発達や成長面、認知能力などを確認してみましょう。
習い事をやめる前に今できる代案はないかを考える
習い事をやめたい理由はいろいろあると思いますが、「やめる」という決断をする前に、今できることはないのか、別の方法でアプローチできるのではないか、と考えてみましょう。
現状、ベストを尽くしきったのであれば、やめるという決断をした後、後悔がなくなります。
有期限・無期限で休会し子供と習い事の距離を置く
どうしても習い事をやめたい気持ちでいっぱいの時は、いくら親や先生などの大人が介入しても配慮をしても説得をしても、子供の耳には届きません。
まして子供の心には届きません。
なぜなら、子供は「習い事をやめたい」と思っているからです。やめたい程、嫌になっている可能性もあります。
ただ、親も先生も「もったいないな」という思いを捨てきれないこともあるんですよね。
- 才能があるのに
- スランプに陥っているだけなのに
- あと少しでコツがつかめるのに
習い事には、ある一定のスキルを積まなければ本当の楽しさがわからないものもあります。
そこまで、ちょっとした辛抱が必要なこともあるのですが、今を生きる子供達。今楽しく感じられないものにモチベーションを感じられないこともあるでしょう。
そんな時は、思い切って休会して、習い事から離れてみましょう。
1ヶ月でもいいですし、3か月でもいいです。無期限にしておいてもいいですが、半年以上離れるようであれば一度やめるという決断をした方がいいかもしれません。
離れている期間に冷静になり、客観的に習い事を見ることで、やっぱりやりたいと思う事も少なくありません。
習い事が好きだから休憩期間を作る、習い事を続けていくために一旦離れるというのは、習い事を続ける秘訣でもあります。
他の先生や教室を探してみる
もし、教室の雰囲気や先生が合わない場合は、同じ習い事で違う教室を探してみましょう。
今習い事をしていたとしても、他の教室に行くことは可能です。もちろん、体験レッスンも受けられます。2つの教室に通ったって構わないのです。
本当は習い事自体は好きなのに、先生が合わずにやめたくなることは十二分に考えられます。それこそもったいない話なので、先生が合わないとわかっているのであれば、別の教室を探しましょう。
子供のストレスを減らして習い事に参加してもらった方が、親としてもうれしいですよね。
教室ではなく親が教えるパターンもある
そもそも、人と接すること自体が疲れてしまう子供もいます。発達障害やHSCの子供達は、先生の配慮なく習い事に通うことは難しいでしょう。
どうしても外で習うと、先生や教室、グループの子供達を合わずにメンタルを崩すなら、いっそ親が教えてみましょう。親ができなければ、子供と一緒にゼロから独学すればいいではありませんか。
そうやって何かを身に付けていくことを、勉強というのですから、子供には最高のお手本を見せてあげられる機会になりますよね。
当然、わからないことや大変なことにぶつかるでしょう。それでいいのではないでしょうか?
その問題や課題をどう乗り越えるのか、そのスキルを一番に子供に身に付けてほしいのですよね?だからこそ、親が一緒にやる価値が出てくるのです。
親にしかできないカスタマイズがありますので、外に出るのが辛い子供には、ぜひ親が教えてみることにチャレンジしてみてくださいね!
振り返り|習い事に通う目的を子供がわかっているなら判断は子供に任せても良いでは?

最後に、習い事に通う目的を子供と共有したのであれば、習い事をやめるのか続けるのかの最終判断は子供に任せていいと思います。
子供の年齢にもよるとは思いますが、基本的に子供の習い事ですからね。
親は環境ときっかけを与えれば良く、その後のことは子供が決めていった方が子供のためにもなるでしょう。
自分で決めたことなら、習い事をやめた理由を誰かのせいにすることはないと思います。
親の思う通りに習い事ができなかったとしても、子供の人生経験が1つ増えたと考えれば何一つ無駄ではありません。
そうやって、迷ったり、嫌になったり、乗り越えてみたりしながら子供は大人になるのでしょう。私達親は忘れてしまっているだけで、同じような思いをしてきましたよね。
子供自身、一度「習い事をやった」という経験をしているので、次にやってみようと思った時に見極める判断材料が増え、ハードルも下がります。
次はこんなことに気を付けて習い事を選ぼうと、前向きな方向へ進んでいくことも可能です。
ですので、今できることを全てやり、それでもやめるという決断をするなら、そんな子供を認めてあげましょう。
自分のことを自分で決めていくこと。それも大きな成長のひとつですから。


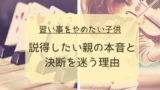

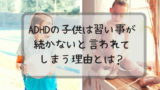

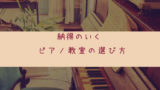
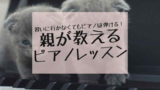
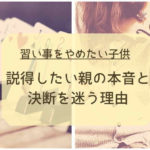
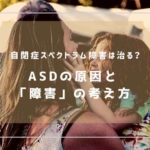
コメント