習い事をやる意味って、人それぞれ違いますよね。子供が「やってみたい」と言ったから。学校の授業で必要になるから。親自信が習っていた子供にも習わせたいなど。
習うきっかけも目的も、人それぞれ。
でも中には、習い事はやった方がいいと思うのに、どうしてもうまくいかない、という子供もいるわけです。本人もやる気はあるのに、なぜかうまくいかないということもあるのです。
子供が発達障害で習い事がうまくいかないと悩んでいる方へ、習い事をする意味を根本から考えてみましょうというお話しをします。
さらに、習い事にはどんな効果があるのか、ということを考えてみると、もう少し続けてみようかな、他の習い事に変えようかな、という基準ができると思います。
また、習い事を続けていると、レベルが上がってきますので、定期的に見直しをして、今の習い事のままでもいいのか、レベルアップを狙うのか、違う環境に移るのか、という事を考えていってもいいと思います。
子供が習い事で得られる17の効果とは?

習い事ってどんな効果があるのでしょうか?習い事の効果はさまざまな言われていると思いますが、今回は私が考えた習い事の意味を17個、ご紹介していきます。
講師経験から、自分が習い事をやってきた経験から、子育てをしている経験から、発達障害育児に携わった経験から、学校などで発達障害の子供の様子を見た経験から、考えてみました。
まずはこんなことを考えましたリスト17個です。
- 集中・没頭・好き・嫌いを経験
- 趣味・特技を作る
- あきらめない・やりとげる
- 自己肯定感が上がる
- 親以外との信頼関係
- チームワーク・切磋琢磨・ 協力・共感・力を合わせる・グルーヴの経験
- 人から評価をされる
- 特性を補う
- 体を動かす・体感を養う
- 授業に役立つ
- 気分転換になる
- 友達ができる・居場所になる
- ルール・規律を守る
- 考える力・発見する機会を持つ
- 日常生活では使わない神経を使う
- 自分を知るきっかけ
- 能力を伸ばす
ちまたの表現とはいろいろと違うかもしれませんが、基本的に勉強ができるようになるから、という発想は私にはありません。
・興味ベースで発想や工夫を活かすために知識を覚えるという逆の視点
・できないのではなくやり方を知らないだけ
一応、こんな基本方針で考えています。

ご紹介する項目の順番は思いついた順です。ランキングではありません。
集中・没頭・好き・嫌いを経験
興味があることに集中できる、没頭できる環境が習い事にはありますね。
基本的に同じ目的を持った子供が集まっていて、教えてくれる先生がいるので、興味のあること、好きな事がハマれば、習い事は最高に楽しい時間になるでしょう。
またその逆もありますね。
親の強制で通っているだけではなく、よくよく体験してみたらそんなに興味がなかった、予想とは違っていて面白くなかったということもあるでしょう。
そういう感情を自分で知ることも、経験の一つだと思います。
趣味・特技を作る
好きが高じて趣味・特技になったら、習い事ををさせた意味はおおいにありますね。親としてもうれしいところでしょう。
特技になれば、将来の仕事につながることもあるでしょうし、一芸があることで子供の人生に華を添え、身を助ける事もあるでしょう。
何よりも、趣味があるということは、日常に楽しみをプラスして持てるということです。気が向いた時だけでもいい。こんなことが好きなんだって思えるものがあるって、意外と心の支えになるものです。
あきらめない・やり遂げる体験ができる
目標や目的が設定されている習い事が多いので、目標に向かってあきらめずにやり続けた結果、得られるスキルの向上や達成感、没頭している時の充実感などを体験することができます。
発表会や作品展、試合などはその一環。
- 目標があった方が練習のモチベーションになる
- 日頃の成果を感じることができる
こういうことの積み重ねで、自分はできるんだという感覚を体験することができます。自己肯定感、というやつですね。
もちろん、その逆で、自分はできいないと言う感覚を持ってしまうこともありますが、そこは先生の力量でしょう。やり方はみんな同じじゃなくていいんです。っていうか同じはずはないですよね。
それに、目指す目標だってチーム以外はひとそれぞれでいいでしょうし。
あきらめずにやり続けることで、達成するもの、そして達成したところから先を目指そうという気持ち。
まさに、人生を生き抜く力って感じがしませんか?
自己肯定感が上がる
自己肯定感って、いろんなことが絡み合っていると思います。
自己肯定感が大事って言われても、自分1人でどうこうなるものでもないし、逆に自分で上げていくことができるものだとも思う。
私の中では自己肯定感というものはとても複雑なのですが、習い事がうまくいけば、自分でもできる!と感じられるし、先生や友達や仲間からも認められ、自分を発揮できる居場所ができる。
だから自己肯定感が上がるんじゃないかな、と思うのが私の考えです。
ということは、習い事がうまくいかなければ、当然逆の事がおこるわけですよね。そこからどうするのか。今回はその辺には触れませんが、一番重要なポイントでもあると思う。
親以外の人との交流と信頼関係
まず先生や教室の仲間、チームメイト、受付や事務の人など、習い事をするといろんな人に関わる機会が増えます。
人との関わりが難しければ無理する必要はありませんが、半強制的に交流を持つことも生き抜く力の一つ。たくさんの関係から、たくさんの人というデータを持つことができますからね。
大人になるまでの間に持たせておきたい資源的な役割になると思っています。
いろんなタイプの人がいますから、そんな人たちにもまれながら、自分の立ち位置を決めて過ごす習い事は、学校とはまた別の小さな社会。
私は会社や仕事に似ているんじゃないかなと考えています。
え?と思うかもしれませんが、個人レッスンにしろグループレッスンいしろチームにしろ、よーく考えてみたらちょっと会社っぽくないですか?
利益こそ生まないかもしれませんが、何かしらの目的を持って集まった人たちが、同じ方向を目指して行動を共にするのですから。
自分の立ち位置を考えて行動する必要があるチームは、特に社会生活みたいだなと感じます。
そして仲間を信じ、先生を信じ、スキルを上げていくことで、成果につながる。おもしろすぎるくらい仕事に似ているなと思います。
チームワーク・切磋琢磨・ 協力・共感・力を合わせる・グルーヴの経験
先程の話と似ていますが、これは主に横のつながりのはなし。
人と力を合わせる経験、先生と共感しながら演奏をする経験、同じ思いで感じるグルーヴ感。経験してみないと説明ではわからないことですが、人と感情が一体になることって、生きる糧にもなると思います。
そして、さらに大きな目標にもなると思うし、大きな安心にもつながると思う。
発達障害の子供には、個人競技のマンツーマンレッスンがいいのでは?とおすすめしましたが、先生と2人でももちろん感じることができるものです。
感覚の話なので難しい子供も多いかもしれませんが、生きているうちに1度くらいは体験しておいてもらいたいなと思います。
人から評価をされる
先生から、仲間から、親からの評価。そして自分の評価。
習い事の成果や効果、結果がでれば、周りの人から認められやすいですよね。入賞するとか、合格するとか、試合に勝つとか。
習い事をやることで、そういう目に見えるものだけじゃなくて、頑張っている姿、逃げない心、あきらめない精神など、いろんな形を評価できますよね。
評価がさらに、自己肯定感を上げるきっかけにもつながると思います。
特性を補う
特性を補うと言っても、直接的に習い事が何かを補うという意味ではありません。
- 特性の発散先として
- 特性上、難しいことをうまく体験することで習得する機会になる
例えば、学校では落ち着きがないと先生に怒られてばかりいる子供でも、スポーツの習い事では得点王だったり、大好きな習い事に没頭する時間を持つことで発散できて気持ちが落ち着いたり、体をうまく使えない子供が習い事でスポーツができるようになったり。
体操教室やスイミング、ピアノ、習字、そろばん、英語に始まり、他の習い事が実質、特性上の困り感を補う結果になることがあります。
理解があって特性を受け入れてくれる先生だったらの話ですが、これは発達障害の子供が習い事をする意味としては、とてもありがたいものですね。
体を動かす・体感を養う
特性を補うことに似ていますが、体を動かす習い事の場合は、半強制的い体を動かしますので、神経が刺激されます。
また、発達障害の子供は、体感が弱い子供が多いようで、学校にいても時間が長くなると机に伏せちゃう子もいますよね。あれは体感が弱いから、座る姿勢を保持し続けられないそうです。
療育でも体感を養う動きはよくやりますね。トランポリンやバランスボール、三輪車や自転車の練習や希望者はなわとびや鉄棒も。
体の動かし方のイメージをつかみくく、神経のつながりにアンバランスがあるので、定期的に体を動かして神経を使っておいた方がいいでしょう。
学校でいう体育みたいな感じかな。
長男は、習い事とまではいきませんが、家でトランポリンを飛んだり、バランスボールに座ることで体感トレーニングをしています。
何よりも、思い切り体を動かす事は、一番のストレス発散!筋肉を使って、成長にも貢献しましょう。
授業に役立つ
特性を補うと似たような意味ではありますが、授業に役立つ習い事をやっていると、授業で習った時にはすでに「できている」という状態なんですね。
圧倒的な優越感。
これは自分はできるという大きな自信にもつながります。 体操教室やスイミング、ピアノ、習字、そろばん、英語 。できるや上手は、クラスの子からも目を惹くため、軽く目立つんですね。
そういう優越感ってちょっとしたことですが自己肯定感にもつながっていくと思います。習い事がうまくいけば、の話ですが。
気分転換になる
大人の人が習い事に来てよく言いますね。気分転換になる~~って。
それ、だいぶわかります。
習い事の空間って、当然ですが非日常なんですよ。家と学校、公園で過ごす毎日に、ちょっといつもとは違う空間へ移動して、いつもとは違う先生と友達に囲まれて、ちょっと専門的な道具なんかを使ってみて、スキルが上がる自分を体感する。
最高の気分転換になりますよね。
うまくできれば。ですが。
それこそ、うまくできなければ、これ以上のストレスもないです。気分転換で始めた習い事にストレスがたまる悪循環。
頑張れば抜け出せますが、そこまで頑張れるかは興味と目的次第。先程も触れましたが、できるためにどうしていくのか、何をするのか、というところが一番大事で、これが達成されたら気分は晴れやか。
理想通りの気分転換になりますね。
友達ができる・居場所になる
習い事の重要ポイントでもあります、同じ趣味の友達ができる、そして学校以外の居場所になる。これは習い事をする意味としてとても大きなものを秘めています。
というのも、次男のように不登校になってしまうと必然的に友達と過ごす時間が少なくなってしまうんですね。
そして、学校という場所はもはや自分の居場所ではなくなる。
そうなった場合、習い事に行けば同じ趣味の友達がいるので、始めから話が合うんですよ。そして、仲良くなれば習い事に行くこと自体が楽しくなってくる。友達に合う事が楽しみになってくる。
そういう楽しみって、日々の張り合いとかにつながりますよね。メリハリみたいな。
1か所でいいし、友達は少なくてもいいんです。誰かいる。これが意外と大事。
ルール・規律を守る
スポーツはもちろんのこと、どの習い事にも始まる時間や終わる時間があり、やることにもルールがあり、基本的には先生の指示に従いますよね。
そういうルールや規律を守る時間を持つこと、そして従って行動できることは、社会で生きていく上で大切なことだと思います。
発達障害であろうとなかろうと、一歩外に出たらルールと規律だらけ。守らなければ車にぶつかってしんでしまいますね。
人と生きていくということは、最低限のルールと規律の中で生きていく、ということだよね、ということです。
考える力・発見する機会を持つ
言わずもがな、ですが、新しい体験や経験は、考える力や発見・発想という機会を持つことになりますよね。
親が一番望むヤツです。「考える力」ね。
でもね、習い事をやらせただけでは考える力は開花しない。親も一緒になって、考えるってなんだろうって考えないと。まずは発見するところから。発見したことから、どこまで発想を膨らませることができるのか、そらが考える力につながると思います。
習い事にいけば、発見する機会はどんどん与えられますから、親は発想を膨らますお手伝いをしてみましょう。
例えば、習い事先のエレベーターをよく見てみるとか、先生の機嫌を観察してみるとか、使っている道具に変わるものはないのかとか。
テニスだからテニスのことだけ。サッカーだからサッカーのスキルだけ、に目を向けず、もっと環境とか人とか便利な道具とか使われている科学とか。
そんなことに目を向けてもいいと思いますよ。
日常生活では使わない神経を使う
本能を満たすだけの人間の動きとは、全く違う神経を使うのが習い事ですね。
ピアノなんて弾けなくても全然生きていけますから。でも、楽譜を読める神経を使い、同時に指も動かす神経を使い、さらに自分の演奏を聴いて調整をするという神経も使う。
こういうことは、趣味で勝手にやるような人じゃない限り、習い事でもやらないと神経は使わないと思います。
だから脳トレなんでしょうね。
さらに指先、足先を使ったり、体も神経も使うことで、フル回転できますからね。錆びずに長く使い続けるためには、たまに使っていない神経にオイルを流しましょう。みたいな感じかな。
自分を知るきっかけ
習い事でうまくいくと、あ、自分ってこんなことができるんだ、自分って案外できるじゃん。と自分を知るきっかけになります。
そして、あ、自分は意外とないもできないんだな、と知るきっかけにもなります。
良くも悪くも、自分を知るきっかけになるということ。
私は、大人になるまでに、自分という人間を扱うマニュアルくらいは、自分の中で持っておいた方がいいと思っているので、習い事は大いに貢献するものだとも思っています。
というのも、社会人になって仕事を始めると、まず第1期の人達が辞めていきますよね。何かが違うと言って。
それって、自分が思っていたような仕事とは違っていたってことで、それは自分の情報収集が違っていたのか、できると思っていた以上に自分ができないと感じてしまったのか。
はたまた、できない自分ができる自分になる未来を予想できなかったのか。
どちらにしても、自分をまず知ることは、自分という体を操縦してこれからも生きるために必要なスキルです。
ならば、どんなに遅くても社会に出るまでに自分をちゃんと理解して、こうすればできるというようなマニュアルを覚えておきたいですよね。
そういう意味で考えると、習い事はモーレツに使えます。だってできることは習い事でやらないでしょ。だからです。だから、先ほどから何度か触れていますが、できない→できるにしていく過程が一番大事なんです。
能力を伸ばす
- 習い事の最大の目的は、スキルを身に付け、その能力を伸ばすこと。
- そして、生まれ持った才能だと思う能力を、プロの手で伸ばしていくこと。
習い事の意味をあれこれ考えてきましたが、この2大テーマがみなさまの一番の目標でしょう。そして、この辺の能力が伸びないと、うちの子にはこの習い事は合っていないんだわ、と考えてしまうきっかけにもなるのではないでしょうか。
一番わかりやすいものでもあるし、ある程度見えやすいものでもありますからね。
でも、習い事をやる意味って、意外と能力を伸ばすことだけじゃないなって思いませんか?
振り返り|どんな意味でもいい。どんどん習い事にチャレンジしてみよう!

発達障害の子供に習い事をやらせる意味を、多方面からいろんな切り口で17個考えてきましたが、最終的な締めとしては、どんな意味でもいいので、とにかくチャレンジしてみて経験してみましょうということです。
なんて、投げやりなって思うかもしれませんが、結局やらなきゃ何もはじまらないんです。
家でスマホ片手に検索しながら考えていても、子供の習い事の話は何も進まない。子供が興味を持った習い事から順に、体験を受けにいけばいい。
やってみたいと言ったらやらせてみればいい。先生に配慮を求める必要もありますし、送り迎えが必要になるかもしれません。
ただ、習い事をやらせてみようかな、と考えているのであれば、一度その生活を体験してみればいいのです。そこから出てくる問題が、その親子の課題となる部分でしょう。
習い事云々ではなく、その課題に親子でどう立ち向かうのか、その姿勢が子供の生きる力になっていくと私は考えています。
私はピアノ講師経験者ですからそう思うのかもしれません。でもそれもアリでしょ。迷っているならいっそ行動してから迷ってみましょう。一歩前に出てわかること、結構たくさんありますよ。

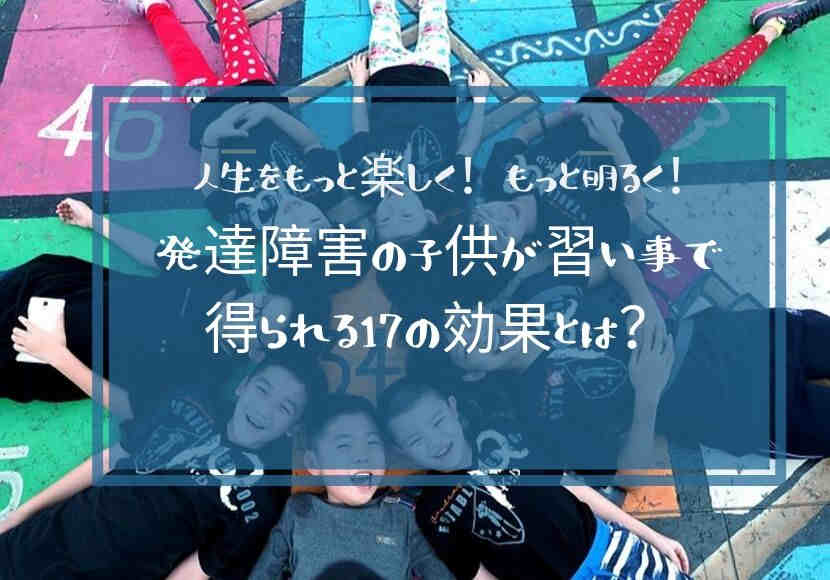
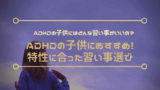
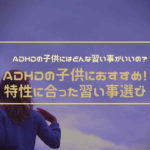

コメント