当たり前のことではありますが、私たちは死なないために生きています。「死なないように生きること」、つまり、人生の目的は「死なないこと」です。
死なないように生きるためには、どうすればいいのか?
当たり前のこと過ぎて、多くの人がその目的を忘れてしまっている気がします。人間、そんなに簡単に死なないさ、と思っているので死にそうな目に遭わない限り、基本忘れて生きる時間を過ごしています。
いやいや、不登校の話とは関係ないでしょ、と思うかもしれませんが、子供が大人にヘルプサインを出しているのに、学校に行かせたいと思っているのは、学校と人生の目的とのつながりがわからなくなっているからではないか?と思ったのです。
人生の目的を忘れてしまっているから、不登校になっている子供との接し方もわからなくなってしまうのではないか?はたまた、不登校をなんとかしたいと思っているのはなぜなのか?につながっているのではないか?と思ったのです。
では、大半の人が忘れてしまっている「死なないように生きる」とは具体的にどういうことなのでしょうか?
死なないように生きるために生命維持活動をする|食べる・寝る・運動する

優先順位が一番高いのは、食べる。次に寝る。そして運動する。大人であれは、大半の方が知っている共通認識ですよね。
そんなこと、誰でも知っている、と言いたくなるようなことですね。
生命維持の元・脳の活用のために食べる
生きるために食べること。人間は生まれた瞬間からエネルギーと栄養を補給するように本能に仕組まれていますよね。
教えていないのに生まれた瞬間から赤ちゃんは母乳を飲み、ミルクを飲みます。 食べていくためには、2つの方法が考えられます。
食べるための自給自足
現代ではあまり見かけませんが自給自足という方法があります。
農作物だけを育て自給自足をするというものではなく、完全自給自足のこと。自然の中で1人で小屋を立て、ライフラインを作り、狩猟や農業で生きていくという方法。
これだけ科学が進み、人がいる中での自給自足は、効率的な方法とは言えませんが、出来ないことはないですね。まさにサバイバル。
しかし自給自足であっても、すべてを1から作るのはさすがに大変過ぎますね。縄文時代あたりからやり直すことになりますので、ある程度のことは現金で買えるようにするでしょう。
- 材料費・機材費
- 病院代
- 水道高熱費などのライフライン代
- 税金
自給自足で賄った物を売り、多少の現金は必要になってきますね。
食べる食糧を買うためにお金を稼ぐ
現代で最も一般的な方法がお金を稼ぐこと。
- 就職する
- 起業する
- フリーランスになる
大体この3パターンでお金は稼げます。
脳と体を休めるための睡眠
人間は寝ないと生きていけないようです。
過去の先人が寝ないチャレンジをしていたようですが、やっぱり寝ないと生きていけない。
実際、睡眠不足になれば判断が落ち、運動能力にも支障をきたしてしまいますよね。ケガをしたり転んだりしますし、判断が遅れると事故にも遭います。
人間は機械ではないので、脳と体の休息は生きるために必須。危険や病気から身を守るために必ず必要なことですね。
体の循環と動ける基礎体力を維持するための運動
生きるための運動には2つ意味があると思っています。
- 血液の循環(体を動かすため・脳を動かすため)
- 必要な時にすぐに動ける基礎体力と筋力の維持
今でこそ、人間は地球上の上で優位に立って生きているような気がしていますが、いざという時に動けないと死んでしまいます。
- 動物から身を守らなければいけない場合
- 危険な場所を乗り越えていかなければいけない場合
- 犯罪や災害から命を守る場合
大げさではありますが、日々運動しておくことは、健康を維持するためにも必要ですし、脳の活力にもなってきます。
脳や体に十分血液が回っていることは、ご存知の通り生きるために必要なことですね。
食べるために必要なこと|お金を稼ぐとは?

お金を稼ぐということは、人と関わるということです。人と関わらなければ、自給自足以外に食べる方法はありません。
※自給自足も多少人との関わりと現金が必要です。
人と関わるために必要なこと
食べるためにお金を稼ぐことが必要で、お金を稼ぐためには人との関わりが必要なのであれば、人との関わるために必要なことは何なのでしょうか?
共通言語スキル
- 母国語
- 世界の共通語
共通の言葉を知ること、話せること、使えることで人と関わることができます。
共通言語の読み書きスキル
- ひらがな
- カタカナ
- 数字
- アルファベット
- ローマ字などの母国語
- 読み方・書き方の共通スキル
共通の言葉を読み書きできることで、直接的なコミュニケーション以外の間接的な関わりが可能になります。
共通認識として必要な知識
- 義務教育
- その他学校教育
最低限、お金を稼いで食べていくために、生活していくために必要であると判断されている知識は、学校教育で習得できるはずです。
一般常識と言われているもの
- 行事
- 慣習・礼儀・マナー
- 年齢の差
- コミュニケーション
- 迷惑などのモラル
住む国や地域、家庭環境によって習得の差はでますが、このようなものがあるということは大人になるまでの間に何かしら触れる機会があると思います。
冠婚葬祭や慣例行事、マナーとされているものには、触れる機会がなければ知らないことも多いので、現代ではそのような機会に触れる前に情報収集することでカバーできます。
共通で使えるツール
- お金
- 電話
- 家電
- 文房具などの手に持つ道具類
- 衣類などの身に付ける物
- 車などの移動手段物
- その他共通で使うもの
家庭か学校のどちらかで、ほとんどのツールに触れる機会があります。
一部、専門的な物もありますが、間接的でも触れる機会はあるでしょう。
お金を稼ぐために最低限必要なスキルとは?
先程挙げた例の中で、最低限必要となってくると考えられるものは次の3つ。
- 共通言語スキル
- お金の計算と管理ができるスキル
- 生きるためのスキル
共通言語スキル
共通言語を使いこなし、相手の言わんとしていることを理解し、自分の考えを伝えられなければ、人と関わってお金を稼ぐことはできません。
その手段が話す・読む・書く。
さらにコミュニケーションの取り方、礼儀やマナー。年齢によっての使い分けやモラルなどが関連してきます。
お金の計算と管理ができるスキル
稼いだお金をしっかりと計算し、生きるための費用として管理できなければお金を稼いでも足りなくなってしまいます。
共通言語である数字の認識や、義務教育で勉強する計算が大きく関わってくる項目です。
さらに、我慢をする、計画を立てる、先を見通すなどの認知能力だけでは測れない、非認知能力部分が重要な役割を担っている部分でもあります。
生きるためのスキル
- 命を守るスキル
- 稼ぐスキル
- 生活するためのスキル
ある意味、死なずに生きることにダイレクトに直結している部分ですが、生きるためのスキルを身に付けるためには、最低限共通言語の取得が必須。
さらにある程度の計算能力や非認知能力的な部分がなければ、命を守るための行動は難しいと考えます。
命を守るためには、危険・病気・犯罪・災害などがありますが、そのために必要なスキルは多方面に関わっています。
例えば、危険から命を守るためには、注意力・判断力・決断力・行動力や実行力・運動神経などが関わっており、病気から命を守るためには、掃除・洗濯・衣類の着方・手洗い歯磨き・運動などの生活習慣が関わっています。
さらに犯罪から命を守るためには防犯知識や格闘スキルが必要になりますし、災害に関しては過去の知識の情報共有、対策できるだけの資金と心構え、人との協力が必要になります。
学校教育で身に付けられるスキルとは?

義務教育でもある小学校・中学校教育ではどの程度までのスキルを身に付けることができるのでしょうか?
義務教育が終わる中学生までで死なずに生きるためのスキルを身に付けられることが理想
本来であれば、中学卒業までの間に、これらのスキルを身に付けておく必要があると思うのです。義務教育とはその後、生きていくために必要な最低限のスキルなはず。
専門的な仕事をする場合は、その後の高校や大学、専門学校や特殊学校などで必要な物を身に付けていけば良いのでしょう。
しかし、お金を稼ぐために必要な最低限のスキルは、中学卒業までの間に身に付かないことが現状です。現在の学校教育の必修科目のうち、どれだけの情報が実際に、お金を稼ぐために使われる情報なのでしょう?
義務教育として共通認識の知識を子供時代に与えるのであれば、中学卒業レベルで1人立ちできるようにしておくべきですよね。
なぜなら、高校に行かない人、行けない人もいますし、中卒で働く人も実際にいるからです。
高校や大学は最低限必要なスキルに+αするスキルを身に付けに行くもの
私の理想では義務教育でも最低限生きていけますが、中学以上に進学をすれば+αの技術をスキルとして身に付けることができるので、初任給やその後の給料に差が出てきます。
本来の学歴とは、知識を含めたスキルと経験の違いなはず。
実際に専門的なことを学んだ学生が即戦力としてお金を稼ぐこともできますが、反対に大学まで卒業したのに即戦力にならない人もいますよね。
学校側は、+αのスキルを身に付けられるようにできています。入学する子供も勉強するために学校に行き卒業しますが、実際はお金を稼げない。就職しても即戦力として使えない、すぐに辞めてしまうという現状。
ということは、学校では生きるスキルは身に付けられる人と、そうではない人がいるということになりますね。
生きる上で忘れてしまっている生きる目的と命の価値

学校で生きるスキルを身に付けられる人と見に付けられない人の差は、生きる目的を意識しているかどうかで変わってくるのではないでしょうか。
つまり死なないで生きるためには、食べていかなければいけなくて、そのためにはお金を稼がなければいけないということを忘れているから、学校で生きるスキルが身に付かないのかなと思うのです。
食べるために働く。ここは知識として知っていますし、明日死ぬかもしれない、ということも可能性があることくらいは知っています。
さらに言えば、自給自足では人間、無理があるということを忘れています。自然の中で1人で生きていくことは自分の命すらろくに守れないことでしょう。
- 自給自足では生きていくことに無理がある
- 明日死ぬかもしれない可能性がある
この2つを忘れています。つまり、幸せなのでしょうね。満たされてしまっているのです。食べ物も身の危険も忘れるくらい満たされているのでしょう。
食べるための勉強ではなく進学するための勉強になっている
現状、学校に行くということは、死なずに生きるための勉強をするのではなく、進学するために勉強をしているのかもしれません。
進学した後、何をすればいいのか、卒業した後、就職して何をすればいいのかを考えていないのです。だから、入学後も勉強に身が入らないのでしょう。
なぜなら、目的が生きるためではないからです。勉強しないと働けないよと言われてきたからです。
働かないと食べていけないよ、と言われてきたからです。
危険な目に遭わないから自分の命も大丈夫だと勘違いしている
身を持って、食べていけない=死んでしまう、を体験していないので死ぬことがわからない。核家族で人が死ぬ姿を見る機会が少なくなったから、死ぬことがわからない。
本当の自給自足がとても危険で大変であることを知らない。だから人間は群れをなして協力し合って生きていることがわからない。
自分が働かなくても親が働いているから大丈夫。自分がやらなくても誰かが動物を育て、殺して肉にしているから大丈夫。誰かがお米を育ててくれているから自分の命は大丈夫だと勘違いしているのです。
働くということはスキルの物々交換をしているということ
確かに、他の人がやってくれているのであれば、食糧の問題は大丈夫なのかもしれない。
忘れているのは、そこに対価を払う必要があるということ。お肉にしてくれている人のために、お米を作ってくれている人のために、自分は何をやってあげているのか、ということです。
結局、スキルの物々交換なのですが、間にお金という通貨を使用しているため、このつながりが見えにくくなっているのでしょうね。
助け合う、共存共栄、すべてがみな、地球上でつながっていることを忘れてしまうから、大切なことを忘れてしまうのでしょう。
死なずに生きていくために必要な常識やルール
自分が死なないためには、
- 誰かを助け食糧を確保しないといけないこと。
- そのために健康に過ごし、情報共有をしていく必要があること。
- 清潔にし、ウィルスなどの病原菌とも戦っていかなければいけないこと。
- 余計なストレスをかけてメンタルをこわさないこと。
- 犯罪を犯して人を殺さないこと。
こうやって、さまざまな常識や慣習、礼儀やマナー、モラルなどのルールができていったのでしょうね。
自分1人がゴミをポイ捨てしたって別にいいじゃないか、迷惑になっていないならいいじゃないか、警察がいないんだからいいじゃないか、ということが回り回って自分にやってくるのは、結局人はつながっているからなんですよね。
人に親切にすれば、自分にも親切が返ってくる。人のためになることをすれば自分も助けられる、というのもこのような理論の元なのでしょう。
生きる目的を忘れ命の価値がわからなくなった現代
生きる目的や命の価値に関して昔の人達は、身を持って体験していて、知恵袋となり伝えてきましたが、人とのつながりが薄くなった現代では、うっとおしいだけだと考えられがちです。
しかし、昔から伝わり続けていることの中には、死なずに生きるための過去の事例がたくさんあるわけです。人のつながりが薄くなったと感じるのは、数々の事例を改善し、簡単に人が死ななくなったからでしょう。
死なずに生きるためには、結局は人に自分のスキルを使って、食べるものを獲得しなければいけないのです。
しかし簡単に死ななくなった今、死ぬことにリアルさがなくなり、自分の命も、他人の命も、他生き物の命も、その価値がわからなくなったのかもしれません。
死なずに生きるために必要な勉強内容を更新していない学校教育
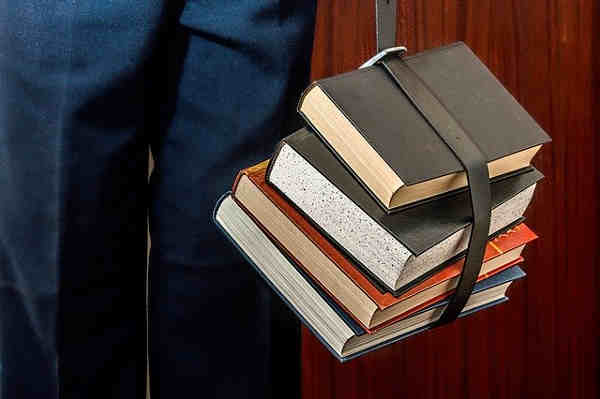
義務教育である中学卒業までの間に、生きるために必要な最低限のスキルを勉強しなければいけないのに、実際は学校での学習内容は更新されていませんよね。
だから、大学まで卒業しても即戦力として働けない、すぐに辞めてしまう、ということが起こっています。正直、大卒でも中卒でも年の差が違うだけなのでは?と言いたくなるような人もいます。
問題意識も持たないし、解決しようともしない。指示をだしても理解しようとしないで、乗り越えるために努力しようともチャレンジしようともしない。
義務教育は、これで働けると思っているのだろうか?という話なんですよね。税金ばかりを徴収していますが、そんな人たちがちゃんと税金を払えるようにしなければ、結局国が損すると私は思うのです。
現場が反映されていない学習要領で勉強する子供たち
現に大学を卒業した大人たちの中で、学校教育についてのフィードバックを求められた人はいるのでしょうか?
なぜか、現場の声が全く反映されない状態で、どこかの会議室で学習要領が決められて、その内容を子供に教育しているような気がするのです。
あれ?と思いますよね。何かがおかしい。
学校の勉強が仕事とつながらない現実を知っている親
子供はそんなこと知りませんから、親や先生に必要だといわれる勉強をして、学校に行かないと食べていけないと言われるから進学したのに、社会に出てみたら全然仕事につながってないじゃん。と思うわけです。
今まで長い時間をかけて学校を卒業したのに、覚えたスキルはどうやって使うのさ、しかもいらない情報も結構あるじゃん、と思うわけです。
そんな人たちが親になり、子供が生まれて学校に通い始めた時、「どうして学校に行かなければいけないの?」「なんで宿題をしないといけないの?」と子供に質問をされても答えられないんですよね。
だって学校の勉強は、必要なものと必要じゃないものがあって、インターネットでがっつりと勉強できる現代、学校に行かなくても勉強できてしまうんですよ。
資格だって取れるし、なんならインターネットで仕事すらできてしまう。もはやコミュニケーションスキルにも昔と同じようなものは求められていないことを親は体験で知っているのです。
学校の勉強と仕事の関係を理解していない大人たち
でもみんな学校に行っている。学校に行って就職するしか方法を知らないから、学校に行くことをすすめるが、何のために勉強していたのかを忘れている。
食べるために働くことは知っているけれど、学校と稼ぐことのつながりが見えなくなった親たちが、勉強や学校の必要性を説明できなくなっている。
だからうやむやに答えたりしますよね。
将来のために、あなたのために、生きていくために、食べていくために学校に行って勉強するんだよって答えますよね。
じゃあ、学校に行かないと食べていけないの?と問われると、学校に行かなくても生きているたくさんの人達を知っている大人は、答えにつまります。
中卒で企業して大金持ちになっている例だってたくさんありますし、学校に行かなかったエジソンが人類の生活に影響を与えていることも知っています。
あれ?何で学校で勉強するんだっけ?何で学校に行くんだっけ?と大人も混乱してしまうと思います。なぜなら、本当の理由なんて知らないし、考えたこともないから。
それでも死なずに今日まで生きてこれた大人たち
だから、学校に行くことも、勉強することも、本質的な意味を理解する必要すらなかったわけです。
だからこそ、本質を知りたい子供は納得がいかない。学校に通いながら、勉強しながら、何で自分は学校で勉強しているんだろう?
大人に聞いてもどこかしっくりこないのは、大人がわかっていないことを隠して、本心から思っていないことを言っているから。
その辺りのことに気づいてしまう子供は、先生や親、大人たちの言動と行動に矛盾を感じ始めるのでしょう。
振り返り|【結論】生きる目的から考えれば学校と勉強の必要性が見えてくる
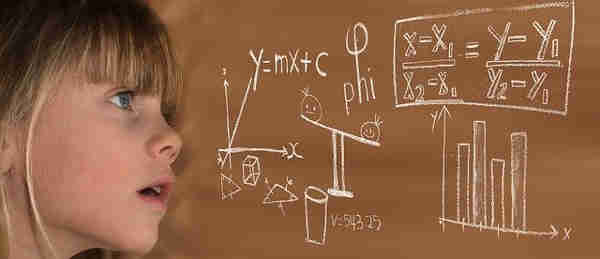
不登校になった理由やきっかけは、人それぞれ違うと思いますが、不登校になることで自分が生きる目的を知ろうとしているのではないか?と私は考えました。
学校へ行く意味、勉強する意味、自分がいじめられてしまう意味、何か納得いかない自分の気持ち、よくわからない複雑な気持ち。いろいろあるでしょう。
なぜ、自分が今、学校に行かないのか?不登校の子供たちはその辺りも含めて、物事の本質に迫ろうとしているのではないか?と私は考えています。
だとすれば、死なずに生きるためにも不登校はその子にとって必要な時間だと思いますし、子供が納得するまではいくら大人が説得しようとしても子供は動かないかな、と思ったのです。
親も先生も、子供にとっての学校がどういうものなのか、学校と勉強について、自分の頭でしっかりと考え、子供が納得がいくまで話し合う必要があると思います。
まして、先生のせいとか、親のせいとか、子供のせいとか、周りを責めている場合じゃないですよね。本質はそこじゃない。
この先、どうやって死なないように生きていくのか。まずは親が自分が死なないようにやってきたことで教えられることを考えてみるといいと思います。
生きる活動の基本でもある食べる・寝る・運動する、この3つはほぼ家庭がベースになっていることです。
親として子供に何を教えてあげられるのかを整理してみると、何か見えてくることがあるのではないでしょうか。


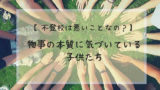
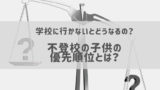
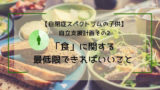
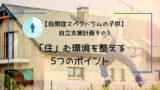
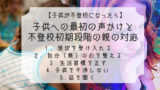

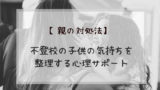
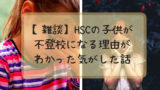
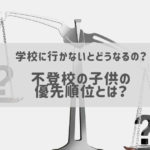

コメント