小学校で読み聞かせをやることになったけど、低学年って何を読んだらいいの?1人じゃなくて2人以上で読み聞かせる場合はどうするの?という疑問や、絵本の選び方の基準などをお話ししていきます。
まだまだカワイイ低学年!1年生・2年生におすすめ読み聞かせの絵本10冊

1年生はつい先日までは幼稚園生だったわけですから、学校に入ったからといっていきなり小学生っぽくはなりませんね。わいわい参加型の絵本ねえ、どれがいい? とか、しかけ絵本かがやいてるとかを交えつつ、読んでみるといいと思いますよ。
もう ぬげない/ヨシタケシンスケ
サイズが小さい本ではありますが、お腹を抱えて笑ってしまうレベルのおはなしです。たぶん、笑わない子供はいないと思う。たぶんね。
そんな話を淡々と読んでもいいし、いかにも面白そうに読んでもいいと思う絵本です。結構、芯のあるはなしだと私は思いますが、先に笑ってしまうから気づかないかも。
たなからぼたもち/くすのきしげのり
働くってこういうことだよね、と大人が理想に思うパターンに、子供らしい興味先行で向いていくという、一番望ましいパターンなのではないかと思う絵本です。
「働く」のに「たなからぼたもち」??と思ってしまう前に、おはなしを一度読んでみましょう。子供たちが教訓に気づくか気づかないかは別として、こういうおはなしから、いろんなことを学んでいくんだなーと思える絵本です。
ごめんねともだち/内田麟太郎
「読み聞かせ向き」というレッテルを貼るつもりは全くありませんが、読み聞かせる絵本選びに困ったら内田麟太郎さんの「ともだち」シリーズから選ぼうと決めています。(4年生までが限度)
なぜなら私が読み聞かせの絵本選びでクリアしておきたい基準を全てクリアしているからです。
この8つの基準を満たしている絵本は、読み手がどう読んだとしても、例えうまくても下手であっても、絵本の絵と内容だけで十分おもしろいのです。
いろんな「ともだち」とのおはなしがある中でも、私はこの「ごめんねともだち」が一番好き。だからこのタイトルをおすすめに載せてみました。
どうするどうするあなのなか/きむらゆういち
穴に落ちた猫とネズミがどうするのか。ネズミと猫という関係性と、ハプニングが起きたときにどう対応するのか。この2つの要素がからみ合っていてシュールなのに面白いと思います。
おはなしって結構「それだけ?」って思うことに着目していて、新たな着眼点というか発想というか、ファンタジーとかの世界だけではなく作家さんの世界が面白い。と思う。うん。
あと、絵本が縦だから、持ちにくよ。持ちにくいけどおもしろいから読んでみてくださいね。
王さまライオンのケーキ はんぶんのはんぶんばいのばいのおはなし/マシュー・マケリゴット
もしかしたら低学年の推薦図書とかになっているかもしれませんが、超タイトルが長いおはなしです。足し算とか引き算とかちょっと計算ができるようになってから読むと、子供もおはなしの意味がわかると思います。
1年生の3学期以降くらいかな。2倍とかもでてくるので、もしかしたら2年生の3学期でもいいかもしれない。
高学年では1つぶのおこめをおすすめとして紹介していますが、こういう算数が関連してくるおはなしは、数の概念がわかっていれば面白さが倍増しますね。
もし算数障害とかで数の概念の理解が難しくても、数を覚えるためではなく、1つのおはなしとして楽しめると思いますよ。
ぞろりぞろりとやさいがね/ひろかわさえこ
とても大事なゴミ問題、資源の問題を野菜が訴えている絵本です。こういう表現をすると、ちょっと難しそうと思うかもしれませんが、難しい内容ではありません。
野菜が訴える人間の生活を、素直にそのまま楽しめば良いかと思います。そして読んだ後は、みなさん冷蔵庫をチェックしましょう。
オレ、カエルやめるや/デヴ・ペティ
カエルであることがイヤになったカエルの子供が、カエルをやめると訴えつづけるおはなしです。
何に生まれてくるのかは選べませんからね。とんでもないという絵本も同じような感じですが、私たちも、人間じゃなかったら何に生まれ変わりたいか?と考えたりしますよね。
そんな感じのことを描いていますが、正直、とってもおもしろいです。そして「そうだよね」という納得もあります。読んで伝わりやすい内容の絵本かなと思っています。
ビロードのうさぎ/マージェリィ・ビアンコ
図書室の先生や他の読み聞かせの方が読んでいるかもしれませんので要確認です。絵本としても有名な絵本ですので、ご存知の方も多いかもしれませんし、すでに子供が「知っている!読んだことある」」というかもしれません。
おはなしとしては若干長めなので、幼稚園生よりは小学校低学年向けかなと思ってこちらで紹介していますが、どの学年で読んでもいいのかなとも思います。
うさぎのお人形と男の子のおはなし。トイストーリーじゃないけど、おもちゃと子供の関係に、やっぱり大人が入っちゃいけないな、と思ったおはなしでした。
ちきゅう/G.ブライアン・カラス
「僕たちは この地球という乗り物に乗って 宇宙を旅している」みたいな1文が冒頭にあるのですが、この1文を読みたいがためにクラスの読み聞かせで読みました。なんかいいじゃないですかー。地球という乗り物っていうくだりと、宇宙を旅しているという表現。
ちなみにわかりやすく漢字に変換しましたが、全部ひらがなだったんじゃないかなー。あと文章もそんな感じの文章です。ちょっと違うかもしれない。
そんな感じの冒頭で始まる科学絵本です。地球の自転や公転に関する内容が、わかりやすく絵本になっています。科学絵本の種類だと思うのですが、文章はおはなし寄りなので、読み聞かせ向き。
普通に物語みたいな感じで読めるってことです。
この絵本を読んだ後、大昔の人達が考えていた地球の絵(端に行くと落っこちちゃうヤツとか、像とか亀の上に半分だけの地球が乗っかっているヤツとか)を見せたら、子供たちが大騒ぎして大変なことになりました。
読み聞かせの極意的には補足情報をつけるのはタブーらしいですが、私は補足しちゃってます。毎回じゃないんだけど、何か補足があったらその方がインパクトがあるし、結局、私が読んだ本を図書室で借りてくれる子が多いから。
それなら読み聞かせをやっている意味があるかなと私は思っているので。あくまでも私の考えですけどね。
地球をほる/川端誠
地球を掘って地球の反対側に行くぞ!というおはなしです。おいおい、大丈夫か?と大人は思いますが、絵本の世界はそんな固定観念は関係ない世界ですからね。どんどん行っちゃいましょう。
実際、地球の裏側に着いちゃったら、日本語だけじゃなく、英語も出てきます。
地球で生きているんだよってことを、低学年のうちに読み聞かせとして読んでおきたかったので、地球関連の絵本としてピックアップしています。
振り返り|低学年の読み聞かせは何を読んでも子供たちが感動してくれる!

低学年向けの絵本と読み聞かせに関する情報をおはなししました。高学年・中学年・低学年と小学生の読み聞かせにおすすめできる絵本はとりあえず30冊紹介した形になりますかね。
それでもまだ読めそうな候補や、読んでみたいと思っている候補があるんですよねー。また別の絵本情報と一緒におすすめ絵本を紹介できればいいなと思っています。
そして、低学年の読み聞かせに初めてチャレンジする方へ。
幼稚園・中学年・高学年も参考にしていただくと、読み聞かせに必要な情報がわかると思いますので、合わせて読んでみてくださいね。
誰でも最初は初心者です。やってみようかと考えているうちにきっかけがなくなってしまうことも多々ありますので、興味があったらぜひ1度やってみてください。

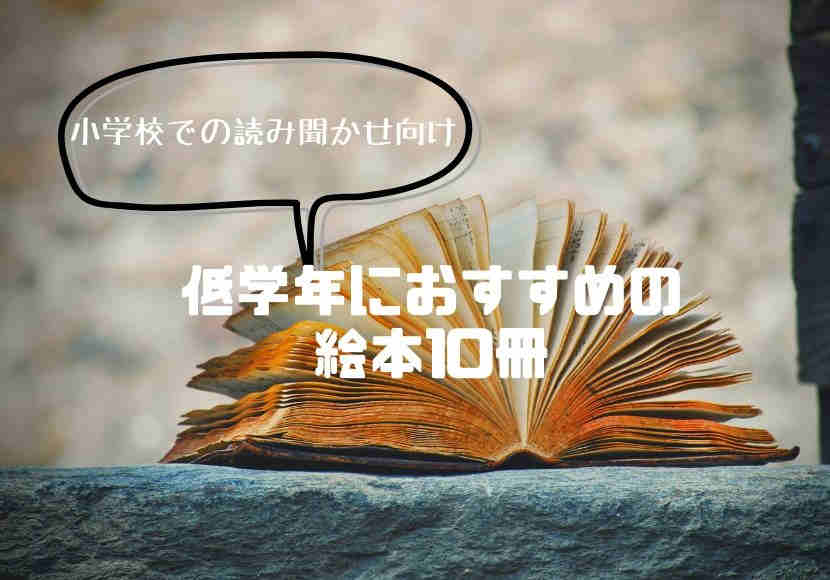










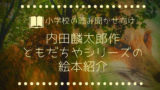

























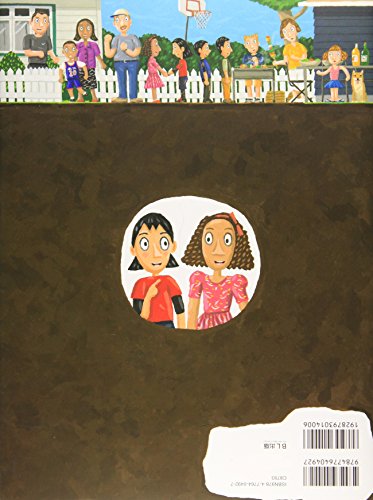



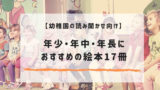

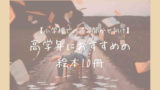
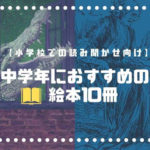

コメント