幼少期から絵本を自力で読まなかった長男が、文字は読めるけど文章理解ができないなんて全く知らず、小学校に入るまで気づいてあげられませんでした。
学習障害の長男は文章理解ができません。文章理解ができないということは、テストの問題文が理解できないということです。
読んでもらえれば100点を取れるテストを自力でやると30点になってしまう。そんな切ない学習障害の特性を持つ長男が、小学校生活のテストを乗り切るために、家と通級で何をやったのか、ということをご紹介します。
学習障害の特性に悩むお子さんの参考になればうれしいです。
学習障害と学生時代のテスト

学習障害についての定義はこちらを参考にしてください。
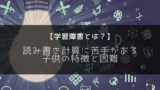
学習障害・発達障害の子どもたちを含め、どんな子どもでも勉強ができないということはないと思っています。
発達の違い、興味がない、認識の違いなどなど、きっといろんな違いがあって、今は覚えられないのかもしれないし、今は違う風に考えたいのかもしれない。
一定の時期にみんな一緒に勉強することで、テストをすることでわかることや早期発見できることはたくさんあるけれど、だからといって『できない』とくくらなくてもいいかなと思っています。
テストの点が悪いということにも、何かが隠れているのでしょう。
正直、テストの点などはどうでもいいと思っています。ただし、テストからわかることがたくさんありますよね。
勉強の理解度はもちろんのこと、知識として定着しているかとか、その知識を応用して考えられているのかとか、文章理解はもちろん、漢字の習熟度などなど、何をどこまで認知しているのかがわかりやすいことは確かです。
勉強ができるのに、テストの点が悪いのであれば、そこから何が考えられるのか。その辺を解き明かしていけば、今、何をやるべきなのかが見えてきますよね。
私であれば、問題文をどこまで理解しているのか、教科や単元によってテストの点数に違いがあるのか、単なる計算ミス・単純ミス(ADHDに多い)なのか。ちょっと考えただけでも確認項目が浮かびあがります。
そうやって1つずつお子さんの様子を確認して、1つずつ明らかになったとき、お子さんの問題なのか、別の問題なのか、はたまた問題でも何でもないのか、ということがわかってくるでしょう。
今回は、学生時代にはつき物でもあるテストに焦点を絞り、学習障害の長男がテストを乗り切るために何の対策や訓練をしてきたのかをお話ししていきたいと思います。
同じことで悩んでいる方の参考になればうれしいです。
学習障害のテスト対策|テストは問題を作った人から出されたクイズ
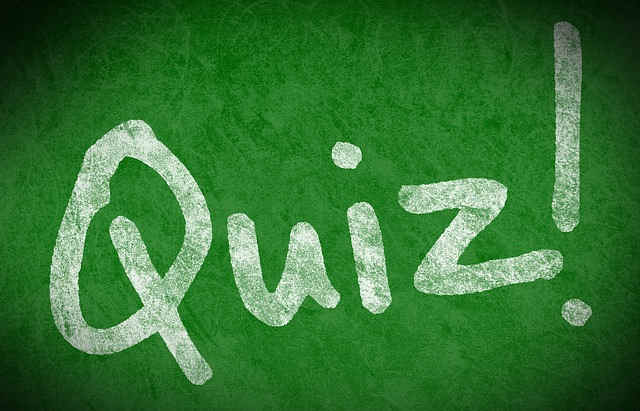
入学前から、ワークのようなものでテスト形式の答え方を教えていました。
小学3年までは長男が学習障害であることははっきりしていなかったのですが、発達障害であることはわかっていました。
学校特有の『机に座って勉強する』という行為自体、長男には興味のないことでしたから、ノートを書く、テストを受ける、という自分だけで進めていく作業は練習が必要でした。

ワークやプリント形式に書かれてある問題は、問題を作った人が出したクイズだよ。クイズの答えがわかるかな?そんな感じで練習しました。
1文1問式から練習していく
文章理解が難しい長男のために、通級の先生が地道に練習してくれること3年。始めは1文に対して1問の問題文があって、答えていく訓練から始めました。
例えば、
この問題に6月10日、と答えていく、という超地道な訓練です。
この後、2文2問になり、1文2問になり、と問題文と問題の対応数が変わっていき、本文も増えていきます。
毎週の通級で訓練して、3年後の5年生の頃には、本文には書いていない答えに対しての問題にも、回答できるようになりました。
例えば、
ボクには弟も妹もいないけど、ボクがお兄ちゃんだったら、弟にも妹にも絶対に命令なんかしない。だって先に生まれたからってえらいわけじゃないと思うから。それに命令されるとむかつくからさ。
直接答えが書いていない問題文についても、答えられるようになりました。この本文と問題自体は、今、私がサラッと思いついた問題なのですが、「ボクの気持ちを答える」という、読み手によって何を回答にするのかが変わる問題を答えるのって難しいですよね。
理想的な回答をするかしないかは別の問題なので置いておくとして、問題に回答できるというスキルを身につけるためには、本当に小さな段階から1つずつ階段を上がっていくようにやり方を覚えていくしかないと思います。
空間把握に問題あり?答えを書く場所がわからない
解答欄のカッコの大きさと回答の量があまりにも違っていたり、解答欄ではないところに答えを書いてしまったり。
そもそも論で問題を解いて答えを書く、という一見何でもないことのように思えるところで引っかかるのが発達障害。
その理由は人それぞれあると思うので、私のような素人が一概には言えないのですが、空間把握に問題がある場合、解答についての問題がおきるのではないかと思っています。
また、ADHDのように脳の中が常に高速回転している場合、
- 問題を読む
- 答えを考える
- 答案用紙に書く
この途中で、次の問題を目が読んでしまっているかもしれない。長男がこのパターンで、書字が異常に遅いので、脳の中の答えと、実際に書いている答えに時差が大幅に出てしまい、答えが違うということが起こります。
長男の場合は特に、テストなどではほぼ間違いが発生してしまい、テスト上の点数がものすごく悪くなってしまうのです。
しかし、実際に1問ずつ問題を解いて(他の問題を見えないようにして)1問ずつ答えを書けば、全問正解しています。
また、解答欄の幅や大きさから、思い切りはみ出るような答えを平気で書いていたこともしばしば。
学習障害のテスト対策|漢字は捨てる?国語テストの乗り切り方

長男が小1の頃から、完全にテストの答え方の種明かしを長男に伝授してしまっていました。そうしないとテストの意味がわからなかったので。
問題を読んで本文から答えを探す方式
長男は、絵本や長い文章を読むと、頭が痛くなるそうです。理由はわかりませんが、目がチラッチラッと横に動くため、せっかく読んでいた文章から目が反れてしまうみたい。
また目を戻すと、どこを読んでいたのかわからなくなるので、文章理解が難しい、といった具合らしい。さらに文を読んでも、状況とかの映像が浮かばないらしく、その辺も文章理解の難しさに関係しているようです。私の勝手な解釈ですが。
なので国語の長文は、長男にとっては悪夢です。いっそいきなり問題文を読んで、本文から答えを探した方が早いなと思いまして、そのようにしてきました。
「こそあど言葉」や「てにをはが」といった理論を先に教えてしまい、接続詞やセリフ、文章校正などを長男の理解度に合わせて種明かしました。ちょっとした先取り学習のようなものです。
それでも3年生くらいまではなかなかテストは難しかったですが、4年あたりから一気につながったのか、5年の時には、国語のテストで100点を取ることもありました。以降、ほぼ80点以上が多いです。
点数に開きがあるのは、テスト問題に漢字があるかないか、ですね。ちなみにテストの点数は良くても、文章の意味はわかっていません。
逆に考えれば、種明かしだけで点数は取れますね。
新種の漢字が続々見れる!新発見が面白い漢字テスト
3年生くらいまでは、何とか家で補習をすれば漢字も書けていたのですが、4年生以降は全く覚えられなくなりました。
部首と作りが逆だったり、線が1本多い少ない、点がない、気持ちは合っているが新種の漢字になっているなど、それまでとは違う問題が起こりました。
これまでと同じ勉強方法をやっていても、書くたびに漢字が間違っていきます。3回練習したら3回目は新種になっているといった感じです。
これではいくら練習をしても、漢字の習得にはならないと判断し、漢字練習を辞めました。何か、脳の中の漢字を記憶する部分があふれたような感じがしたのです。何か別の方法じゃないと覚えられないらしい。それだけはわかりました。
- 部首・作りをパズルのように組み立てる勉強
- 虫食いになっているプリントで勉強
- 1回だけ集中して書く勉強
- 習字で勉強
- 粘土で漢字を作って勉強

何をやってもダメだった・・・
一番効果があったのは、漢字テスト前に間違った感じだけを繰り返し練習し、またテストをする、という方法を、自分で決めた合格ラインになるまでひたすら繰り返す方法。
長男が自分で考えて実行した練習法なのですが、2時間くらいで100問中80点以上まで上がります。一時的なものなので、時間の経過とともに見事なまでにわからなくなっていく様は、まるで『アルジャーノンに花束を』の本みたい。
読むのはとりあえず読めるので、書きは諦めました。参考にならなくてごめんなさい。

読んでもらうことが一番の理想 !読めなくてもテストは乗り切れる
読字障害など、読むこと自体が難しい場合は、先生に問題文を読んでもらうことが一番の理想です。
私も何回かリクエストしたことがありますが、何分、教室と先生が足りないとのことで断られました。
小学校のうちから学習障害用の対応をしてもらっていないと、その後の中学高校などの受験やテストで配慮を求めることができなくなるんですよね。実績がないから。読まなくてもテスト受けれたんでしょ、ってなっちゃうから。
そういう意味も含めてリクエストしてみたのですが、うちの学校は難しかったです。しかも、テスト対策しちゃってたので、テスト受けれるじゃんってことになっちゃって。
学校側で対応してもらえないことの対策をして、対応が不要になるっていうこの切ない現実。
配慮してもらいたいけど、配慮してくれ!!ってひたすら訴える時間と労力を、自力て対策してしまいました。
長男はそれでなんとか6年まで乗り切ったけど、子どもによっては自力は難しい子もいるでしょう。また、親が対策する時間がない場合も当然ありますよね。
とりあえず、読むことに困難があっても、やりようによっては取り繕うことはできる、と思いました。

学習障害のテスト対策|計算ミスが多すぎる!算数テストの乗り切り方
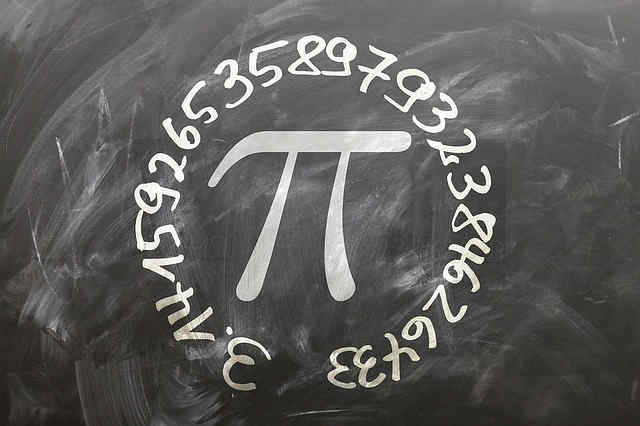
空間把握のところですでに触れてしまいましたが、長男は計算ミス、単純ミスがとてもとても多いです。今でも多い。
見直しは基本やらないみたいですね。もうすでに計算済みなのに、再度計算する意味がわからないらしい。
それはそうなんだけど、テストだからね、解答欄が間違えているとか、単純ミスとか、チェックできると思うんですけどね。過ぎたことは振り返らない主義らしいです。
長男の場合は、計算が早すぎること、目の動きの問題、書字の遅さ、と3つのアンバランスが原因で起きるミスなのですが、算数障害の場合は別の問題がでてくると思います。
長男のために考えた算数テストの対策は、次の1つだけ。
他の問題が見えなければ、頭が先に別の問題を計算してしまわないので、手が答えを書き終わるまで待てる。これでだいぶミスは減りましたが、学年とともにテストを折るのが面倒になるとやらないみたいです。
こうなったら仕方ない。本人もわかっていることなので、親が口出しするところではないですね。
数字の概念やそもそも論で計算が難しい場合、根本からの対策が必要になるでしょうね。脳のしくみなどをいろいろと調べてくると、意外とお子さんの状態から解決策が見えてくることがあります。
そのためには、お子さんが何をどこまで理解しているのかをきちんと把握するところから始めましょう。
- 目に見えているもの→脳が正しく理解しているか
- 脳の認識→記憶と照合できるか
などの超根本から始まり、記憶で止まっているのか、何かの情報と一緒だと思いだせるのか、つまづきに法則性はあるのかなど、神経回路1個ずつをつぶしていく感じで調べてみると、専門家じゃなくてもある程度の情報はわかってきます。
つまづいている場所、止まっている場所から、認知行動療法とか、作業療法とか、解決する方法も見つかってきますし、もしかしたら全然関係ないと思っていた運動神経に問題があったりすることもあります。
問題となっているところを把握することが、最初の対策です。
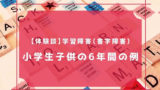
学習障害のテスト対策|好き嫌いがテストに直結!理科・社会テストの乗り切り方

私は理科も社会も全くダメでした。原因はおそらく、全く興味がなかったから。理科と社会は、興味に左右される教科といっても過言ではないと思います。
おそらく楽しみ方・面白さを知らないんでしょうね。興味がないから知らないし、知らないから興味もわかないという悪循環だと思います。
興味を無理につけることは難しいかもしれませんが、先取り学習で知識をつけることはできました。
例えば、社会で日本全国の県や県庁所在地を覚えますよね。4年?5年?その前にせめて全県の名前と県の形を覚えておくと、圧倒的優越感に浸れます。
うちは、2人とも入学前にはくもんのパズルで全県を覚えていたので、社会の授業で多いに役に立ちました。また、テレビのクイズ番組でも、県の名前が答えられない大人より自分達の方が答えられると大喜びしています。
ちょっとしたことがきっかけになって、社会のテストはできる!と思い込んだりしているみたいです。
社会や理科は、どれだけ生活に密着させておくかが興味につながるので、正直、対策することもないのですが(問題文を理解しているか、記号などの答え方くらいしかやることがない)、教科書を見て問題を作ってみたり、授業の内容から問題を作ってみるといいと思います。
ま、本人がやる気があればの問題になってしまうのですが。
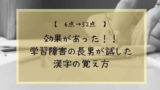
振り返り|学習障害のテスト対策で学生時代を乗り切ろう
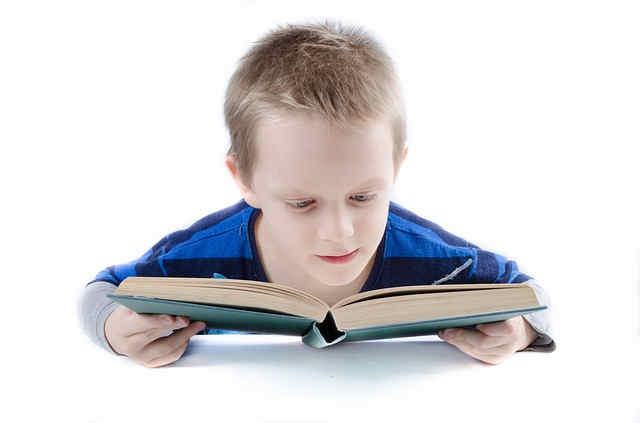
私はできるならば、親が子どもに勉強を教えることをおすすめしています。イライラして怒っちゃうならやめた方がいいのかもしれませんが、完全に子ども用カスタマイズできるのは親だけかな、とも思っています。
小学生のテスト問題なんてとても簡単なものばかりです。ちょっと復習すれば、わからない勉強はないですよ。6年生になっても親が勉強を教えれられるんですよ。それにわからなければ一緒に勉強すればいいだけ。その過程を「勉強」って呼ぶんじゃないかな。
子どもが中学受験するから問題が難しくてわからない、と言っている親が、子どもに勉強しないと将来困りますよっていくら言っても説得力ないですよね。だって親が困っている姿、見てないしね。
テストに対する考え方は、各家庭それぞれあると思いますが、私は紙切れ上の物でいくらでも何とでも書けると思っています。
知識にしろ何にしろ、本当の意味での勉強は、テストでは測れない。能力ももちろん、IQもわかることはたくさんあるけれど、大切なのはテストじゃないよね。って思っています。
ただ学生時代はテストで測られてナンボの世界。受験のために学生時代を過ごしているような物だと思っていて、親も先生も子どもも、このテストに影響されて動いているし、テストで将来や可能性を判断しているようにも思えます。
受験を越えて進学をするためのテスト対策。目標に向かって努力することや、工夫することで得られる様々なこと。費やした時間から得られるもの。集中や没頭。
テストをすることの意味は多々あるでしょう。
私はテストに重きを置いていなくて、受験もできればないところへの進学を考えているので、正直、みなさんとは違う子育てを経験することになるでしょうね。
そう言っておきながら、長男にテスト対策をしていたのには、自己肯定感を下げないための対策の1つと言ってもいいと思います。そして、やっぱり受験を受けたいと思ったときのための、ほんのわずかな底上げです。
神経回路的に難しい、やっぱりできそうにない、と思うことをみんなと同じやり方でやろうとする必要は全くありませんが、別の方法で同じことを目指すことはできるかなと思います。
この記事が「そうかもね。」と思えるきっかけになればうれしいです。
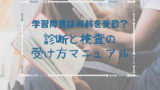

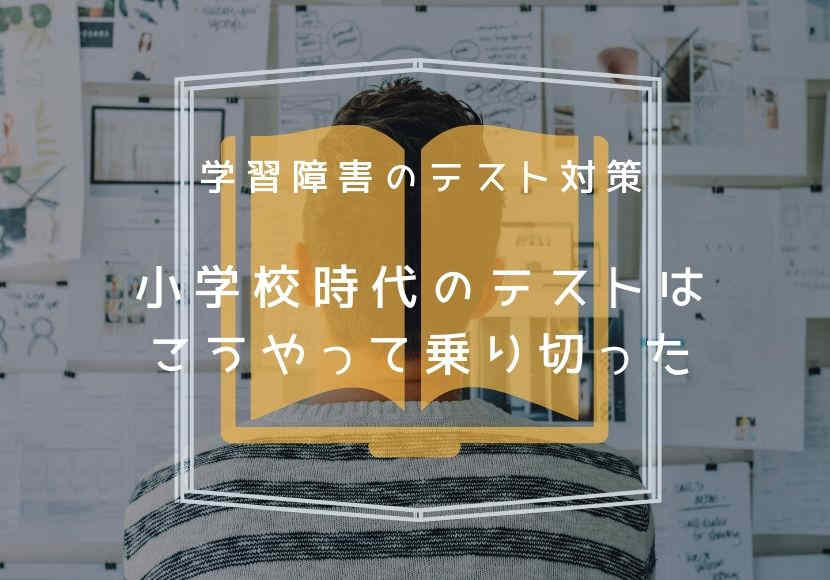
























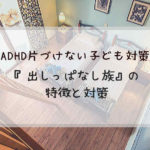
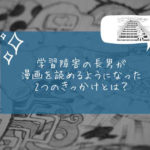
コメント