絵本の読み聞かせは子供の発達にいい影響があるからと、一生懸命、絵本を読んであげようしても、子供がページをどんどんめくってしまって、全然読めない!と困っていませんか?
私の長男も次男も2歳前まではページをめくってばかりで、絵本を読み聞かせている、とは言えない状態でした。
2歳前の子供であれば、正直、黙ってお話しを聞いているわけがない、というのが経験上言えることです。
でも、発想を変えれば絵本の読み聞かせもグンと面白くなりますよ。
絵本のページはめくらせてOK!読み聞かせることにこだわらない
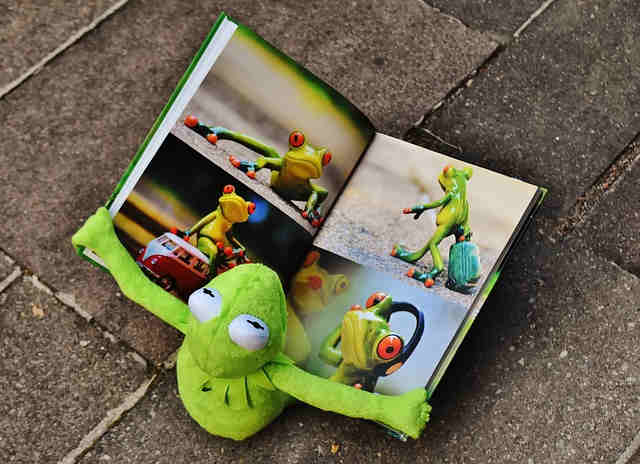
小さい子供は、まだ「絵本」というものがどういうものか知らないものです。
「開いてページをめくって閉じるまでの過程を楽しむおもちゃ」という認識になっても不思議はないでしょう。
ある意味、合っていますよね。絵本はページをめくっていくものですし、読み手をよく見て観察して、やり方はわかっていると思います。
絵本を読み聞かせてたいのは「読み手の思い」
読み手の思いとしては、絵本の内容を子供に読み聞かせたいわけですが、何も知らない子供は「ページをめくる」「絵本を閉じる」という行動になっているのでしょう。
ここで、子供の知っている絵本の使い方と、大人が知っている絵本の使い方にギャップがあるということにお気づきでしょうか。
絵本を読もうとしている大人には、読んでいる途中でページをめくってしまう子供の行動は「困りごと」と捉えてしまうのですが、よく考えてみたら子供は知らないだけだと思うのです。
絵本は読んでもらうもの、内容を楽しむものだ、ということを子供は知らないということですね。
幼少期のうちは絵本の面白さがわからないことが普通
知らないからこそ教えたい、という大人の思いを無理やり押し通そうとしても、見てわかる食べ物やおもちゃ、音のなるものとは違い、絵本は絵や言葉・ストーリーを楽しむものが多いですよね。
見えないものの楽しみ方はまだわからないのではないでしょうか?
第一段階として、まずは絵本は面白い、楽しいという世界観を持っているものだと子供に教えてみましょう。
絵本が好きであれば、発達とともに大人しくお話を聞くこともできるようになりますが、それは小2あたりだと思っておきましょう。

落ち着かない子供でも、小4あたりから少しずつ落ち着いてきます。
そんな先のこと?と思わずにまずは読み手が絵本の面白さ・楽しさを知ることから始めてみましょう。
ということで、今回は普通の読み聞かせ(という定義はありませんが)とは全く違う方法で、子供に絵本の読み聞かせをする方法をご紹介していきます。
絵本に興味を持ってもらいたい!と思っている方の参考になればうれしいです。
【絵本が読めないを一瞬で解消】新提案!面白さが伝わる絵本の読み方
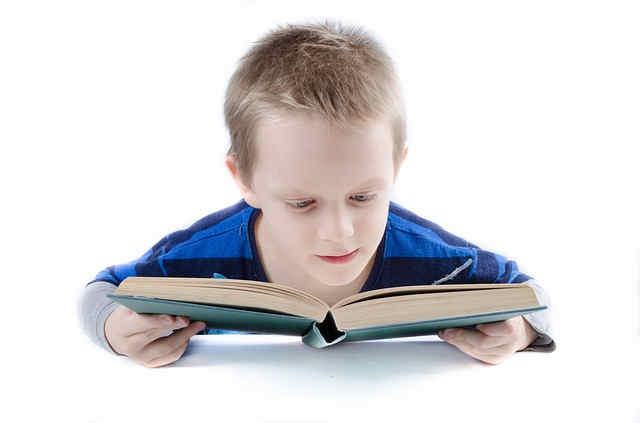
それでは普通ではない絵本の読み聞かせ方をご紹介していきます。
この読み方が正しいか間違っているか、という議論ではなく、私は自分の子供にこんな読み聞かせをしてみましたよ、という一案だと思ってくださいね。
自分が絵本を読んで役作りをする
2歳前の子供や絵本に興味のない子供に、一生懸命おはなしを聞かせようと思っても難しいと思います。まずは絵本の何が面白いのかを、読み手が読んでみつけましょう。
一番わかりやすいのがキャラクター。動物であれば泣き声や声のトーンの上げ下げで表現できますね。
- 小さい動物・小さい子供・小さいもの→高い声のトーンで
- 大きい動物・大きい大人・大きなもの→低い声のトーンで
- 忙しい・走っている・早いもの→音量少な目で早口
- ゆっくり・歩いている・遅いもの→1回で吐ききる量で1文字(の→吐く、し→吸う)
- 宇宙人・わけがわからないもの→1つの音程で、1文字ずつ(ワ・レ・ワ・レ・ハ)
- 魔女・悪魔・やまんばなど怖いもの→低い声のトーン+ふるわせて+クレッシェンド(だんだん大きく)
- いじわるなもの→スネ夫やジャイアンを真似する
- 弱いもの→のび太を真似する
- ヒーロー的なもの→ドラゴンボールやワンピースなどの主人公を真似する
- 女の子→お腹に力を入れずに裏声で
- おじいさん・おばあさん→震えた声で+「えーっと」+たまに早口
このくらいのキャラ分けができれば、幼稚園児以降の子供はほとんどが絵本に注目します。その声色の違いに注目しているわけですね。
お話しの内容よりも、まずはキャラが面白いお話しが、この世にはあるんだよ、ということを知ってもらいましょう。
子供の目だけではなく耳から効果!絵本に効果音を入れる

えー、そんなのアリ??
って言われそうですが。アリなんじゃないでしょうか。さて、効果音といっても特別なものは必要ありません。
今すぐできる効果音:言葉と声+変顔
「ジャジャーン!」とか、「パンパカパーン!」とか「ドンドン」とか、そういうカタカナを効果音としてお話しの合間にはさみます。
お話しの文章に入っている場合もありますので、その部分は意識して効果音になりきりましょう。
「変顔」というのは、変な顔をして子供を笑わせるという意味ではありませんよ。効果音の状況に合わせた表情をするということです。
例えば「パンパカパーン!」なら、何かが出てきたり、答えがわかったりするような効果音なので、ニコニコ笑顔で 「パンパカパーン!」 と言ってみる。
「ドーン」なら暗い表情で下を向きつつ、「ドーン」と言ってみる。というように、顔でも状況を説明するような感じです。
アニメのキャラクターを思い浮かべていただくとわかりやすいでしょう。
身の回りにある物で効果音:何かを叩く・こする・振る
※注意:すぐに子供が真似をしますので、危なくない物を使いましょう。
ドアをノックする音なら、机を「トントン」と叩く。足音がするなら読み手の足を使って音を出す。
というお話しの中に入り込んで入れる効果音は、発達して年齢が上がればその音から想像がつきますが、小さいうちはよくわかりませんね。
実際に叩くことで、一瞬、「ん??」と思って読み手を見ます。そうしたら、もう1度同じことをやってみせましょう。
間違いなく、すぐに真似をすると思いますが、一緒に絵本に参加できると子供の読み聞かせはいっきに上昇気流に入ります。
共感することでより「楽しい」「面白い」という実感がわくという相乗効果も期待できますよ。
文明の利器を使った効果音:音の鳴る絵本・楽器を使う
音のでるおもちゃや絵本を効果音に使うと本格的になります。楽器系のおもちゃを使ってもいいと思います。
絵本の始まりと終わりに効果音を入れてもいいですし、お話しに合わせて自由に使ってみると結構おもしろいですよ。
例えば、ももたろうの話なら、こんな感じ。
読み手:むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。(効果音:鳥の鳴き声)
読み手:おじいさんは山へ芝刈りに。おばあさんは川へ洗濯に行きました。(水の音)
お話しに合わせた効果音以外に、ページをめくる、場面が替わる、登場人物が出てくるなど、何かあるごとに音を鳴らすと、子供にとってはわかりやすいみたいです。
絵本もビックリ!1ページ1行読み
どんどんページをめくってしまう子供の場合、1ページで1行読めればいい方でしょう。ならば、思い切って1行でページをめくってしまえば良いのです。
始めから全部読もうとするから「読めない」という状況におちいりますが、始めから1行しか読まないと決めていたら、最後まで読めてしまいます。絵本も作者もビックリ。そんなに読み飛ばすの?って感じです。
お話しの内容を理解するのは、もっと成長してから、と割り切って楽しく1行を読んでいきましょう。
子供もビックリ!超早口で読む
読み聞かせの定義(というものはありませんが)から大きく外れますが、通常、絵本はゆっくり読みましょう、と言われるところを超早口で読んでいきます。
ADHDの子供は、逆に早口で読んだ方が内容が理解できるらしいです。子供によって差はあると思いますが、これは結構聞いてくれる確率が上がると思います。
ゆっくり読まないと、確かに聞き取れない単語があったり、状況を想像しながら聞くということができないのかもしれませんが、その前に子供が飽きてしまっては残念な結果になってしまいますね。
一度やってみると面白いですよ。子供がキョトンとした顔でこっちを見ています。
きっと、何を言っているのかさっぱりわからないのだと思いますが、絵本のページはどんどん移り変わるし、何かわからないけどベラベラしゃべっていて「何だろう?」と思っているうちに1冊が終わる。という衝撃の読み方です。
「え?今の何?」的な感じでOK。もう1回読んでと言われるようになったら、速度を少し遅くしたり、もう1回リクエストに応えて、さらにスピードを上げて読んであげましょう。
発達に合った絵本を選ぶ

1ページの文章が長い物、単調な絵が続く絵本など、刺激が少な目の絵本より、はっきりとわかるような絵本が面白いと思います。
○歳から、と書いてあるものを参考にして選んでみましょう。0歳から2、3歳向けの絵本を何冊か紹介しておきますね。
0歳くらいの子供におすすめの絵本
だあれだだれだ? (0歳からのあかちゃんえほん)/ 後路好章
子供と一緒にあそべる絵本。いろんな顔のバージョンを用意して、読んでみましょう。
だるまさんが/ かがくいひろし
ほとんどの赤ちゃんが大ウケする不思議な魔力を持つ絵本。「だるまさんが」と普通にスラッと読まないでくださいね。「だ・る・ま・さ・ん・がーーーーー」とたくさん期待させて、一瞬でページをめくりましょう。
ついでに、転ぶ時は読み手も一緒に転びましょう。もれなく子供も転ぶので、リピート率NO1の絵本になると思います。転びすぎて大人の方が目が回るという事態がおきます。
がたんごとんがたんごとん(福音館あかちゃんの絵本)/ 安西水丸
リズムで理解していく絵本なのかなーと思っています。男の子が何度も繰り返し読みたい絵本でランクインするくらい人気のある絵本です。
1歳くらいの子供におすすめの絵本
もこもこもこ(みるみる絵本)/ 谷川俊太郎
2歳前くらいまでの子供が楽しんでいる絵本でしょうか。大人の私には、なぜこの絵本が面白いのかが正直よくわからないのですが、子供が好きな絵本です。
この絵本は、全てのページに効果音や動きを入れることができる、スーパースペシャルな絵本です。育てにくい子どものためにある絵本用に書かれたのかと思うくらい、子供がはまります。
むしいろいろかくれんぼ(これなあに?かたぬきえほん)/ いしかわこうじ”]
単純だけどおもしろい、そしてかわいいイラストが人気のしかけ絵本です。「いないいないばあ」の逆バージョン。正解したら楽しそうな効果音で盛り上げて楽しむことができる絵本です。
2歳くらいの子供におすすめの絵本
ぞうくんのさんぽ(こどものとも絵本)/ なかのひろたか
お話しもおもしろく、キャラクターもおもしろく、オチもある。絵本定番の同じパターンを繰り返す系の絵本です。オチでは子供を抱きかかえたまま、一緒に倒れてみましょう。
「もう1回!」とリクエストされるくらい子供が喜びます。
おやすみ、はたらくくるまたち/ シェリー・ダスキー・リンカー
はたらく車が大好きな男の子から人気が高い絵本です。おやすみ前に読む絵本にちょうどいい内容とイラストの柔らかさ。好きな働く車を見て幸せな気持ちで寝てくれるか、テンションマックスになってしまうかのどちらかです。
振り返り~無理に絵本を読まなくてもいいのではないかいう仮説~

絵本を読んであげるからには、お話しの内容をちゃんと理解して、お話しの内容をちゃんと想像して、脳もフル回転して、なんて思って絵本を読むのではつまらない。
絵本に興味がないなら、無理に読まなくたっていいんです。図鑑に興味があるなら図鑑でいいじゃないですか。端から名前を読んでいけばいいのです。
うちの子供たちはクワガタ・カブトムシの図鑑の名前を1冊分通して言うのに何分かかるのか、測ったりして楽しんでいますよ。もちろん、そうやって名前や特徴を全部覚えていくのです。
お話しの世界に触れるだけが絵本の魅力ではありません。それは大人の願いですよね。大人の願いをかなえるために、子供は絵本を読んでもらうわけではないのです。
読み手の押し付けではなく、読み手が面白い、楽しいと思って読めば子供には必ず伝わります。面白いものは強制しなくても何度も「読んで」と持ってきますし、絵本を読む時間を楽しみにするようになります。
でも、絵本を楽しみにならなくてもいいと思います。だって絵本を読まなくったって死なないですから。
「子供時代は本を読まなければ」と一生懸命になりすぎて、絵本をちゃんと聞かない子供を怒ってしまっては本末転倒です。
絵本は、文字に触れる機会であったり、想像力を働かせるきっかけであったり、先人の知識を除法共有するものであったりしますが、他の方法でカバーできるのであれば問題ないのです。
まだ発達や成長が追い付いていない子供に、大人の思いを叶えさせるのではなく、子供の発達や成長に合った絵本選びや読み方をしてみましょう。
ただ、少し人生を豊かにする世界があるっていうことを知ってくれたらうれしな、程度でいいと思う。と考えてみれば、いいと思いますよ。
一緒に絵本の世界観を楽しめたら、親子のいい思い出になるってことでいいんじゃないかなと思いますよ。

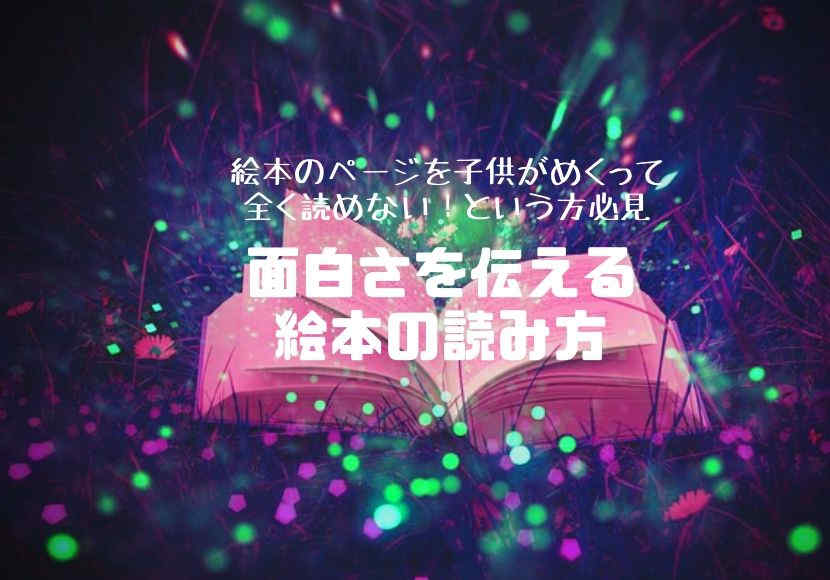
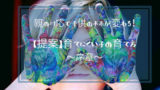
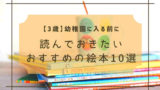
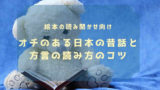


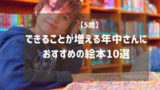
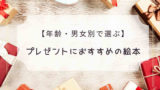







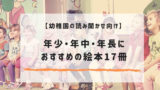
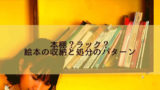

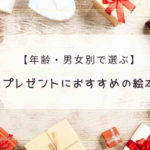
コメント