こんにちは!自分の気持ちや考えを整理すると、意外と対策が思いつくと思っている花緒です。
子供が不登校になると親はとても不安になりますよね。子供もきっと不安だと思います。でもそれ以上に、子供自身が、自分に何が起きているのかわからなくなっているかもしれません。
今回は不登校になった次男の気持ちを整理した方法、そして不登校で不安になってしまう子供の心理サポートの方法を方法をお話しします。
不登校の子供の気持ちを整理するためのフローチャート

私が次男と一緒に、自分自身を知るために不登校について感じていることを考えたフローチャートは大きく分けて3つ。
- 自他を分ける
- 自分を知る
- ここまでなら大丈夫というボーダーラインを知る
さらに、
1.「自他を分ける」については、
- 学校に行きたくないと感じている自分
- 学校に行かない自分を見る周りの目や声
この2つを別物だと切り分けて考えようとしてみる
2.「自分を知る」に関しては、
- 嫌なことは何なのかをしる
- 何がどこが嫌なのかを考える
- どうして嫌なのかを考える
3.「ここまでなら大丈夫というボーダーラインを知る」については、
OKラインがある・ない
- あるなら→先生に交渉・友達とのコミュ力強化・学校以外のコミュニティに入る
- ないなら→自分のやりたい事があるのかないのかによって対応する
このように大まかな流れを作ってみました。
次男は小3で9歳ですが、頭の回転は結構早い方で、次男にわかるように通訳気味に話せば、大人なみの思考力を持っていると私は思っています。
そんな次男と実際にはこんな感じで話しを進めてみたので、やり方を詳しくお話ししてみます。

結果としては、次男も気持ちの整理がついたようで、試してみて良かったと思っています。半年で飛躍的にメンタルが落ち着いてきています。
あくまでも私が考えた方法で、次男の性格とか特性とか気質とか、そういうものに合っていたのでいい方向へ向かえたのだと思います。
人それぞれ、いろいろと違うところがあるとと思いますので、1つの例として参考にしてくださいね。
不登校になってすぐにこの作業はやらず、1週間とか、1か月とか、少し時間を置いてからの方がいいと思います。
不登校になったばかりの時は、とりあえず休んだ方がいいと思うので。
不登校になっている子供自身が自分と他人を分けて考える練習をする

まずは自分が感じていることと、他人が感じていることが一緒になってしまわないように分けて考えるようにします。
- 学校に行きたくないと感じている自分
- 学校に行かない自分を見る周りの目や声
この2つを別物だと切り分けて考えてみます。
学校に行きたくない自分に関してはわかると思うのです。そのままですね。
で、次に、例えばいじめにあっているとか、先生に何か言われるとか、部活の空気が苦手だとか、親の期待に応えられないとか、自分以外の人の思いや感情がありますよね。
ここに関しては一旦シャットアウトします。
誰の思いも、誰かに言われたことも、何かやられたことも、一旦相手側の問題として自分から切り離します。
そうすることで、自分の感情だけが残りますよね。
嫌だった、辛かった、苦しかった、痛かったなど、いろんな子供本人の感情があると思います。
そして、そのマイナスの感情を紙に書いて身体から出してしまいます。あとは置いておくだけでいいです。箱にしまってもいいです。
後々、メンタルが回復してきたら見直す予定です。
不登校の子供自身が自分を知ることに目をむける

他の人のことは、一旦放置しておいて、自分の事に目を向けます。
自分が嫌だと感じていることは何だろう
学校に行くと、自分は何が嫌なんだろう?ということを振り返ってみます。
- 教室
- 友達
- 先生
- 専科
- 授業
- 部活など
学校生活の中で嫌なことをすべて紙に書きだしてみるといいと思います。
特に嫌なことがないと言う場合、何か不快なものがあるのであれば、同じように書いてみます。
それもなければ、特にないということでいいと思います。
時間が経てば新たに思いつくかもしれませんし、何が嫌なのかはわからないけど学校に行けないのかもしれないし、どうしても誰にも言えないし誰にも悟られたくないのかもしれませんので。
無理に聞きだそうとしたり、詮索しようとすることは逆効果になると思うので、私はやりませんでした。
次男の場合ははっきりと理由を言ったので、それ以上聞くこともありませんでした。
何が嫌なのか?どこが嫌なのか?を判明させる
次に、書き出した嫌なことの、何が嫌なのか、どこが嫌なのかをわかる範囲でいいので書きだします。
対策を考える時に使えるので、できるだけ判明しておきたいところですが、わからなければ先にいきましょう。
どうして嫌なのか?理由を考えてみる
次に理由です。
子供なりにいろんな納得がいかないことがあると思います。
でもきっと、言葉で表現するのは難しいと思います。
もし、親に話すことが嫌そうであれば、ノートや紙にこっそり書いてもらって、子供の引き出しか何かにしまっておいてもらいましょう。
理由がわからなければ解決できない、と思ってしまうかもしれませんが、親は子供の味方。まだ言えないのであれば、無理に詮索せず、時期を待ってあげてもいいと思います。
不登校の原因になっている嫌なことのボーダーラインはどこなのか?OKラインを知る

次に、不登校の原因に関係している嫌なことは、どこまでなら大丈夫で、どこ以上になったら学校に行けなくなるくらい無理なのかを考えてみます。
OKラインがある場合
例えば、クラスメイトに何か言われることが嫌で、教室には入りたくないとします。
それが、1時間なら耐えられるのか、1時間も耐えられないのか、ということですね。
フルで学校生活を送るとなると、休み時間や給食、掃除の時間、部活など、授業以外にもいろんな項目がありますから、嫌なこと以外でも疲れてしまいます。
専科の授業なら問題ないとか、保健室登校なら問題ないとか、次男のように1・2時間で早退できるなら参加できるとか、ここまでなら大丈夫かもしれないというOKラインがあるか、子供の気持ちを確認してみます。
学校・先生に交渉
OKラインがあるなら、学校や担任の先生に交渉しましょう。
学校に行くことを全行程しているわけではありませんが、全くの不登校になるよりは、少しでも何かしらの社会体験があった方がいいと私は思っています。
そういう意味で、特殊な投稿スタイルになってしまいますが、学校に相談してみるといいと思います。
その場合、あくまでも子供本人の意志を確認し、子供に学校との交渉を頼まれたら親が動いた方がいいと思います。
そうしないと、子供の気持ちを置いておいて、大人同士で解決してしまうことになると思うので。
不登校なのは子供です。子供抜きに大人同士での解決はちょっと違うかな、と思います。
友達関係ならコミュニケーション力を上げる練習をする
友達関係が上手くいっていない場合、コミュニケーションについて勉強してみるといいと思います。
これはあくまでも私の考えですが、1年生であっても、6年生であっても、中学・高校生であっても同じだと思うんです。
今、不登校になった原因が友達ならば、友達とどうやってコミュニケーションを取っていけばいいのか、親が相談にのってあげられたらいいですよね。
心理学とかを一緒に勉強すれば、自分の性格や特性のタイプなどもわかるし、相手とどうしてうまくいかないのかもわかってきます。
勉強する方法は本なりネットなりいろいろありますので、現代の文明の利器をふんだんに使って、コミュニケーション力を上げてみましょう。
うまくかわす、スルーする、反撃する、適当に対処する、大人になっても使えるスキルです。今、できる範囲、分かる範囲でいいと思います。
難しく考えず、人間という生き物を図鑑で見る的な軽い感じで、友達との付き合い方について親子で話しができたらいいですね。
学校以外のコミュニティを持ってみる
地域のイベントに参加したり、習い事を始めたりして、学校以外の子供の活動場所を作ってみます。
不定期なスポーツ教室などもいいと思います。
次男は、私がやっている地域と学校のボランティアに参加していますし、今は止めてしまいましたが、以前一緒に習っていた長男の将棋教室に毎週顔を出しています。
学校が無理でも、学校以外でのコミュニティがあると、学校ではない自分の居場所ができ、社会との接点が持てるのでおすすめです。
OKラインがない場合|自分(子供)は今、何がしたいのか?を考える
嫌なことに関して、どうしても嫌で絶対に学校には行けない場合、子供自身が何かやりたいことはないのかを考えてもらいましょう。
自分がやりたいことがわかる場合
やりたいことは何でもいいのです。
ファミリーマートのファミチキが食べたい、ゲームセンターに行きたい、1人で部屋にいたいなど、なんでも良いです。
一瞬で終わるやりたいことから、大きな夢まで、とにかくたくさん書いてみます。たくさんあればあるほどいいです。
書きだすと、書いたものを目で見るので、そこからいろんなイメージがわきやすいんじゃないかなと私は思るので、よく使っている手法です。
やりたいことはかたっぱしからやってみましょう。
もし、金銭的な余裕があるようでしたら、できるだけ叶えてあげられるといいですね。
学校に行く行かないが問題なのではなく、自分が何に向かって生きているのか、そこを感じるために、やりたいことを、何なら全部やってみる!くらいの勢いです。
自分がやりたいことがわからない場合
大人だって自分がやりたいことがわからなくなる人、たくさんいますから。子供ならなおさら、不登校になるくらい、メンタルが落ちていればやりたいことがわからなくなるものです。
何の意欲もわかない時って、頭が休まないといけないのでしょうね。全く考えられないのですよ。人間の身体は不思議ですね。
やりたいことが分からない場合は、2つの方法があります。
- 何でもいいので体験しまくる方法
- ひたすら寝て休む方法
どちらにしても、当分の間、学校はお休みです。
学校に行く前に、生きること自体が難しくなってしまうと危ないので、身を守るためにも、私と次男は学校を休む選択をしました。
やることがない場合は、世にあるいろんな体験をしてみるといいと思います。
外に出れば自然がありますし、施設に行けばいろんなものが見られますし体験もできますね。
お金はかかるかもしれませんが、子供にとっても親にとっても、いずれ必要になる時間と費用なのではないか、と私は思って、今を過ごしています。
あんまりお金がないので派手に外出できないところが残念ですが。
振り返り|子供の気持ちを整理することで不登校と向き合える

不登校って、学校が始まった当初からあって、今の今まで、いろんな研究やデータや意見があったと思います。
何一つ、同じパターンがない人間のことなので、全ての子供にカスタマイズが必要になるあたりが、不登校の大変なところ。
私はたまたま、在宅で仕事をしているのでなんとかなりますが、外で働いていたら次男の不登校生活は難しかったでしょう。
しかし、次男のパターンも1つの不登校パターンとして、誰かの参考になったらうれしいです。
子供が不登校になったからといって、腫れ物に触るように接する必要は全然ないし、親は親の人生を生きていいと思う。
ただ、親としてできることはやりたいな、と私は考えているので、あれこれ自分にできることを考えています。
学校を早退して次男とプチハイキングに行ったり、ひたすらモーターと歯車の研究をしたり、考えてみたらできることって結構ありました。
次回は、不登校だからこそできる、いろんな過ごし方の案をご紹介していきます。

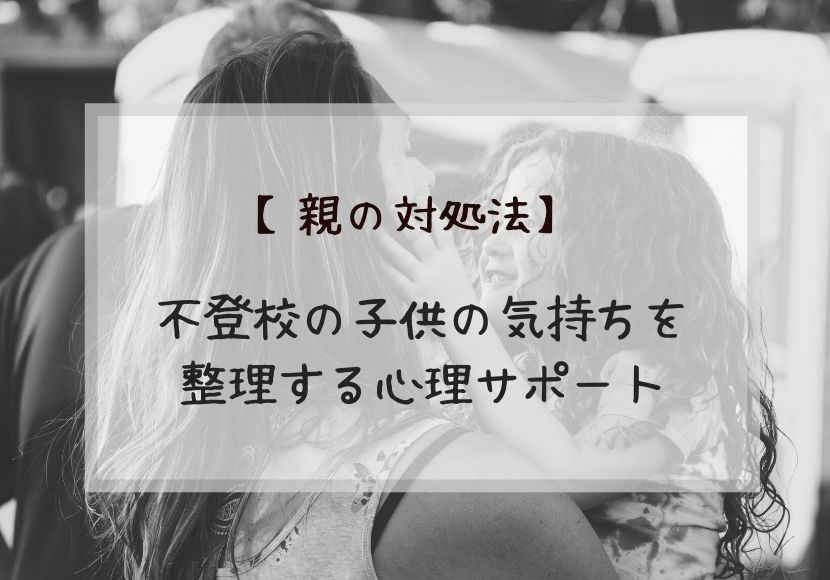
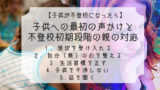
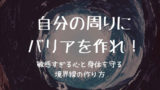
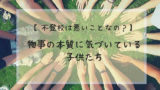
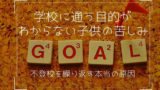
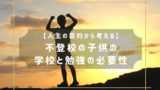
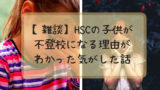
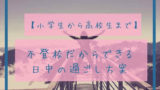
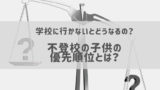
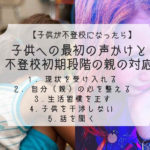

コメント